【提供者向け】未成年飲酒は店側に責任がある!刑事罰・行政罰と防止策について解説

- 「お店で未成年者の飲酒が発覚した場合、誰がどんな処罰を受けるの?」
- 「未成年の飲酒で処罰されるのを防ぐにはどうすればいい?」
飲食店や酒屋を営業する方にとって、未成年飲酒によるトラブルを防ぐのは重要な問題です。
店舗側には未成年飲酒を拒否する義務があり、怠れば重大なペナルティが科せられる可能性があります。
飲食店や酒屋を営む場合は、未成年飲酒に関してどのような法律があるかや義務について把握しておかなくてはなりません。
本記事では、未成年に酒類を提供してしまった場合にどのようなペナルティがあるかや、ペナルティを避けるための対策について解説しています。
本記事を読むことで未成年飲酒に関する法律の概要を理解し、自店でどのような対策をすれば安心かが把握できるでしょう。
未成年者(20歳未満)へ酒類を販売・提供した際に罰せられるのは店側!
未成年者(20歳未満)への酒類を提供した場合、法的責任が問われるのは未成年者ではなく提供した店側です。
この原則は、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの小売店から、居酒屋などの飲食店まで、全ての酒類取扱事業者に適用されます。
未成年者は仮に飲酒をしても、法律上の処罰を受けることはありません。
警察に補導される程度です。
一方で未成年に酒類を販売・提供した店舗側は、処罰を受ける可能性があります。
仮に未成年者が口頭で年齢を偽っていたとしても、少しでも疑わしいと感じたら身分証による確認をしなくてはなりません。
必要な確認を怠れば、処罰を受ける可能性があるので注意が必要です(誰が見ても未成年でないとわかるようであれば、口頭での確認も必要はないでしょう。)。
未成年者へ酒類を提供した店側が受けるペナルティ|刑事処分と行政処分
未成年者への酒類提供が発覚した場合、店舗側には刑事処分と行政処分両方の側面のペナルティが科される可能性があります。
以下、それぞれ詳細をみていきましょう。
刑事処分|罰金刑や懲役刑を科される可能性がある
「未成年者飲酒禁止法」では、営業者が年齢確認義務を怠り未成年者に酒類を提供した場合、50万円以下の罰金が科されます。
さらに、キャバレーやホストクラブなどの接待を伴う飲食店や、暗い照明の店舗といった特定の飲食店に対しては「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」が適用されます。
この法律に違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
|
法律の種類 |
刑事罰 |
|
未成年飲酒禁止法違反(第1条3項、第3条) |
50万円以下の罰金 |
|
風営法違反(第22条1項6号、第50条1項4号) |
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科 |
行政処分|営業停止処分などを受ける可能性がある
行政処分とは、行政機関が法令に基づいておこなう不利益処分のことで、営業停止や免許取消などが含まれます。
風営法の対象となる店舗が未成年に酒類を提供した場合、40日以上6ヵ月以下の営業停止命令を受ける可能性があります。
一方、酒屋がお酒を販売する際や飲食店でもお酒をテイクアウトで提供する際などは、酒税法上の酒類販売免許が必要です。
未成年者にお酒を販売し、未成年飲酒禁止法や風営法上の罰金刑を受けると、この免許が取り消される場合があります。
一度免許が取り消されると、3年間は同免許の再取得ができません。
|
法律名 |
処分内容 |
|
風営法(第22条6号)、同処分基準 |
飲食店営業の場合:40日以上6ヵ月以下の営業停止 |
|
酒税法(第10条7号の2、第14条2号) |
酒類販売業の免許取消し |
未成年飲酒によって店長や従業員などが書類送検された事例2選
未成年者への酒類提供で書類送検されるケースでは、店舗の運営会社だけでなく、実際に酒類を提供した従業員も処分の対象となります。
1.運営会社とその社員2名が書類送検された事例
高知県高知警察署は2020年11月、中高生に対し酒を提供したとして居酒屋の運営会社と社員2人を風営法違反容疑で書類送検しました。
本件では、来店した中高生5人のグループに対して、2時間程の間にビールなどのアルコールを合計30杯ほど提供していたとのことです。
このグループが退店後にほかの少年グループとトラブルになった際、事情を聞いた警察官が飲酒に気付き立件のきっかけとなりました。
2.運営会社とアルバイト2名が書類送検された事例
15歳から18歳の高校生8人に対してビールやカクテルを提供したとして、大手飲食店の運営会社が書類送検される事態に発展しました。
この事件は、SNSへの投稿がきっかけで発覚し、実際に提供したアルバイト2人も同容疑で書類送検されています。
酒類を提供したアルバイト従業員は「客から20歳以上と言われた」と説明しましたが、身分証明書による確認を実施していなかったことを認めています。
店舗運営側は従業員への年齢確認指導を実施していたと主張したものの、現場での確認不足が重大な違反を引き起こす結果となりました。
未成年飲酒による刑事罰などを防ぐために店側ができる3つの対策
未成年者への酒類提供を制御することは、店側にとって重要な課題といえます。
刑事罰などをふせぐためにも、以下3つの基本的な対策が重要です。
- 身分証明書による年齢確認を適切に実施する
- 注文システムによる年齢確認を取り入れる
- 未成年者の飲酒禁止をポスターなどで啓発する
1.身分証明書による年齢確認を適切に実施する
来店した客が少しでも未成年に見えたら、口頭での年齢確認だけでは十分とはいえません。
運転免許証やマイナンバーカード、学生証、保険証、在留カードなどの身分証明書による確実な年齢確認を徹底しましょう。
未成年とおぼしき若い客のグループが来店した際は、全員の身分証提示を求めることが重要です。
確認の際は「お若く見えますが、年齢確認のため身分証を提示いただけますか」といった丁寧な声かけを心がけることで、トラブルも回避しやすくなります。
もし提示を拒否された場合は、毅然とした態度で酒類提供を断るようにしましょう。
2.注文システムによる年齢確認を取り入れる
タブレット端末などのデジタル機器を活用した、年齢確認システムの導入も有効な対策です。
実際の裁判例でも、タブレット端末での年齢確認を実施していたことが、未成年者への酒類提供の故意を否定する根拠として認められた事例があります。
このような客観的な確認手段を導入することで、店舗側の適切な管理体制を示すことができます。
3.未成年者の飲酒禁止をポスターなどで啓発する
店舗の入り口や店内の目立つ場所に、未成年者への酒類提供をお断りする旨のポスターを掲示することで、店舗の方針を明確に示すことができます。
これは従業員の意識向上だけでなく、未成年者の来店自体を抑制する効果も期待できます。
啓発用ポスターは、国税庁やビール酒造組合のWebサイトなどで無料ダウンロードが可能です。
このような視覚的な注意喚起は、未成年飲酒の防止に大きな役割を果たします。
未成年への酒類提供と店側の責任に関するよくある質問
店側がもつ未成年飲酒に関する疑問について説明します。
Q.未成年への酒類提供で責任を取るのは従業員と店舗責任者のどちらか?
お店で未成年に酒類を提供した場合、原則として責任をとるのは責任者です。
お店の従業員が未成年の客に酒類を提供しても、責任者は処罰の対象となります。
しかし風営法違反の事例に関しては、責任者だけでなく従業員もまとめて処罰される事例が多いです。
Q.未成年者だと気づかずにお酒を提供した場合でも処罰されるのか?
未成年者が嘘をつくなどして、気付かずお酒を提供してしまった場合でも処罰を受ける可能性はあります。
酒類を提供する店舗には、年齢確認をおこなう義務があるためです。
たとえば顧客の容姿から未成年者と疑われるのに、口頭でしか確認をしていないと義務を果たしていないとみなされる可能性があります。
一方で身分証の提示を求めたものの、相手が身分証を偽造していて見抜けなかった場合は処罰される可能性は低いです。(そのほかの状況も考慮して判断されると考えられます。)
Q.未成年者に嘘の身分証明書などを提示された場合でも処罰されるのか?
店舗側が適切な確認をしていたにもかかわらず、偽造された身分証明書や他人の身分証明書を提示された場合、その状況によって処罰の判断が異なってきます。
たとえば顔写真付きの身分証明書との照合を適切に実施しなかったなど、確認が不十分だった場合は未成年者飲酒禁止法による処罰の対象となる可能性があります。
このような事態を防ぐためにも、身分証明書の確認は慎重におこない、とくに顔写真との照合や有効期限の確認など、細心の注意を払う必要があります。
さいごに|未成年者への飲酒提供で事件になった場合は弁護士に相談を!
未成年者への酒類提供は、店舗スタッフ個人にも深刻な法的責任が及ぶ可能性があります。
とくに風営法違反の場合、実際に提供した従業員も書類送検される事例が確認されています。
もし未成年者への酒類提供が発覚した場合は、速やかに弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談することで、具体的な状況に応じた適切な対応方針を立てることが可能です。
また、未然防止の観点からも、店舗の年齢確認マニュアルの法的な妥当性をチェックしてもらうことで、従業員の安全を守ることにもつながります。
日頃から確実な年齢確認を心がけ、トラブルを防ぐことが大切です。

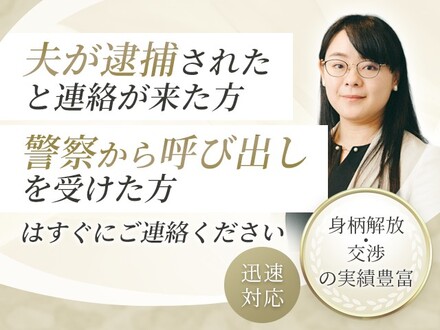
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る
【加害側の方へ】家族が逮捕されたらすぐにご相談を!早期釈放に向けて迅速に対応します【被害者側の方へ】示談交渉・損害賠償命令など、被害の状況に応じた適切なサポートいたします◆女性弁護士在籍◆初回相談0円
事務所詳細を見る
【初回相談料1時間1.1万円(逮捕されている場合等は無料)|弁護士直通TEL|夜間・休日◎】無罪を獲得した実績◎早期の身柄釈放を第一に!性犯罪/痴漢・盗撮/暴行傷害事件など元検事の弁護士に相談が◎今何をすべきか明確にご提示します
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事処分の種類と内容に関する新着コラム
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容に関する人気コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
刑事処分の種類と内容の関連コラム
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
仮釈放は早く社会復帰することが可能な重要な制度です。この記事では①仮釈放期間はどのように決定されるのか②受けるための条件③仮釈放を要求する方法④仮釈...
-
禁錮とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰で、刑務作業が義務付けられていないもののことです。この記事では懲役との違いを踏まえながら、禁錮とはどのような...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
「前科は10年で消える」という情報がありますが、前科は一度ついてしまうと生涯消えることはありません。しかし、前科による不利益は時間とともに軽減されて...
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
未成年者の飲酒は法律で明確に禁止されています。本記事では、大学での飲み会やサークル活動で飲酒を強要された場合の対処法や、未成年飲酒に関する法的リスク...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る

















































