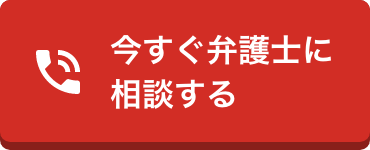【加害者限定】
【加害者限定】お急ぎの方へ

累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
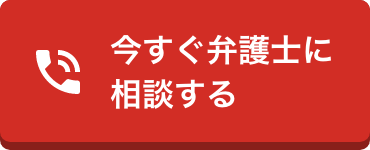
飲酒運転とは、酒気帯び運転や酒酔い運転のことです。
酒気帯び運転・酒酔い運転で逮捕された場合、一般的な刑事事件と同じような刑事手続きを受けます。
また、飲酒運転や酒気帯び運転であっても、検察に起訴されれば刑事裁判を受けることになり、罰金や懲役といった刑事罰が科されることもあります。
そこでこの記事では、酒気帯び運転・酒酔い運転の基準や罰則、逮捕後の流れなどを詳しく解説します。
なお、もし家族が逮捕されて、前科・前歴がある、人身事故を起こした、事故相手の損害が大きかったなどの場合は、ただちに弁護士に依頼しましょう。弁護士のサポートがあれば、早期釈放や不起訴処分、執行猶予判決などを目指せます。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は刑事事件に注力している弁護士のみを掲載しています。相談料無料・土日対応可の事務所も多数掲載しているので、できるだけ早急に依頼するようにしてください。
ご家族や自身が酒気帯び運転で逮捕・検挙された方へ
逮捕されると、最大で23日間の身体拘束を受け、起訴されれば懲役や罰金などの刑事罰を科される可能性があります。
検挙されて取り調べを受けた場合も、同様に起訴される可能性があります。
ご家族が飲酒運転で逮捕された方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 取り調べのアドバイスがもらえる
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 弁護活動によって不起訴・執行猶予付き判決を目指す など
刑事事件はスピードが重要です。
逮捕後72時間以内に本人と会えるのは、弁護士だけです。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
どれくらいの飲酒で違反となる?酒気帯び運転と酒酔い運転の基準
飲酒運転とは、アルコールを飲酒したのちにアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為をいいます。
道路交通法第65条では、飲酒運転に関して以下のように定められています。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
引用元:道路交通法第65条|e-Gov法令検索
飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類に分けられます。
まずは、それぞれの基準を確認しておきましょう。
酒気帯び運転の基準
酒気帯び運転の基準は、道路交通法施行令第44条の3に定められています。
これによると、血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上の場合、または呼気1Lあたり0.15mg以上の場合が酒気帯び運転とされています。
(アルコールの程度)
第四十四条の三 法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
引用元:道路交通法施行令第44条の3|e-Gov法令検索
検問などで呼気アルコール検査がおこなわれ、基準値を超えるアルコール量が検出されると、現行犯逮捕されます。
酒酔い運転の基準
酒酔い運転の基準は、法律で明確に定められているわけではありません。
しかし、体内のアルコール値に関わらず、以下のように正常な運転ができないと判断された場合には酒酔い運転になります。
- ろれつが回らず会話が成立しない
- フラフラとしていてまっすぐ歩けない
- 視線が合っていない
飲酒運転で逮捕された場合の刑事罰
飲酒運転で逮捕された場合、酒気帯び運転や酒酔い運転といった飲酒運転そのものに科される刑事罰と、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪といった飲酒運転に伴う事故に対する刑事罰があります。
また、アルコール検査を拒否した場合の刑事罰や、同乗者に対する刑事罰もあります。
飲酒運転で逮捕された場合の刑事罰について確認しましょう。
酒気帯び運転の刑事罰
酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。
前科なしの初犯の場合は、20~30万円程度の罰金刑になることもあります。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
引用元:道路交通法第117の2の2|e-Gov法令検索
酒酔い運転の刑事罰
酒気帯び運転の刑事罰は、5年以下の懲役か100万円以下の罰金となっています。
前科なしの初犯の場合は、50万円程度の罰金刑になることもあります。
しかし、酒酔い運転は危険性が高いため、初犯でも懲役刑を求刑される可能性があります。
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
引用元:道路交通法第117の2|e-Gov法令検索
もっとも、酒気帯び運転及び酒酔い運転は、初犯であって事故を起こしていないのでれば、逮捕・勾留される可能性はあまりありません。また、仮に刑事裁判になっても略式となって罰金刑となるのが一般的です。
そのため、酒気帯び運転及び酒酔い運転で弁護士のサポートを得るメリットはあまりありません。
過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)とは、自動車を運転する際に必要な注意を怠って、他人を死傷させたことに対する犯罪です。
刑事罰は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金となっています。
なお、被害者のケガが軽い場合には、情状によって起訴猶予が得られる可能性があります。
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|e-Gov法令検索
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪とは、アルコールによって正常な運転ができないにも関わらず自動車を運転するなど、危険な自動車運転によって他人を死傷させたことに対する犯罪です。
刑事罰は、相手を負傷させた場合で15年以下の懲役、死亡させた場合だと1年以上の有期懲役(最長20年)となっています。
過失運転致死傷罪よりも重く、懲役刑のみの刑事罰となっているところが特徴です。
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|e-Gov法令検索
過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に該当すると逮捕・起訴され、事故様態や事故に至った経緯、過失割合などによってどのような刑罰が決まるか変わります。
そのため、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に当てはまっているならば、弁護士に依頼することを強くおすすめします。ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は刑事トラブルに注力している弁護士のみを掲載しています。
相談料無料・土日対応可能の事務所もあるので、まずは相談から始めてみましょう。
アルコール検査を拒否した場合の刑事罰
警察による任意の職務質問は拒否することができますが、検問などでおこなわれている呼気アルコール検査は拒否すると罰則が科される可能性があります。 道路交通法には、警察官の呼気検査を拒否したり妨害したりした場合には、3ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処す旨の罰則が記載されています。
(危険防止の措置)
3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
第百十八条の二 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:道路交通法第118条の2、第67条3項|e-Gov法令検索
同乗者等に対する刑事罰
道路交通法では飲酒運転をした運転者だけでなく、自動車を提供した人、酒類を提供した人、飲酒運転した人の車に同乗している人に対しても罰則を設けています(道路交通法第65条2項、3項、4項)。
それぞれの刑事罰については以下のとおりです。
(酒気帯び運転等の禁止)
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
引用元:道路交通法第65条|e-Gov法令検索
車両の提供者
飲酒している者に対して車を貸すなどした車両提供者も刑事罰に処されます。
車両提供者の刑事罰は、運転者が酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役か50万円以下の罰金であり、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役か100万円以下の罰金となっています。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。)
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
引用元:道路交通法第117条の2の2、第117条の2|e-Gov法令検索
酒類の提供者
これから車を運転する人に対して、お酒を提供した酒類提供者にも刑事罰があります。
酒類提供者の刑事罰は、運転者が酒気帯び運転の場合で2年以下の懲役か30万円以下の罰金、酒酔い運転の場合は3年以下の懲役か50万円以下の罰金となっています。
第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第五号に該当する場合を除く。)
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
引用元:道路交通法第117条の3の2、第117条2の2| e-Gov法令検索
同乗者
飲酒運転だと知っているにも関わらず、その車に乗った同乗者にも刑事罰があります。
刑事罰は酒類提供者と同じで、運転者が酒気帯び運転の場合が2年以下の懲役か30万円以下の罰金、酒酔い運転の場合が3年以下の懲役か50万円以下の罰金です。
第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第六号に該当する場合を除く。)
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
引用元:道路交通法第117条の3の2、第117条の2の2|e-Gov法令検索
飲酒運転による行政処分
飲酒運転で逮捕されると刑事罰とは別に、道路交通法と道路交通施行令に基づいて免許取消処分や免許停止処分などの行政処分が下されます。
また、行政処分の対象者は、運転者だけでなく同乗者も該当します。
それぞれの処分内容を確認しましょう。
運転者に対する行政処分
飲酒運転をしていた運転者に対する行政処分は、酒気帯び運転か酒酔い運転かで異なります。
酒気帯び運転は、呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上~0.25mg未満の場合で違反点数13点(免許停止/停止期間90日)、0.25mg以上の場合で違反点数25点(免許取り消し/欠格期間2年)です。
また、酒酔い運転の場合は、違反点数35点(免許取り消し/欠格期間3年(違反累積なしの場合))です。
参考元:行政処分基準点数 警視庁
同乗者に対する行政処分
飲酒運転している人の車に乗っている同乗者に対しても、運転免許を取得している場合は、運転者と同様の行政処分がくだされます。
酒気帯び運転の場合は、呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上~0.25mg未満の場合で違反点数13点、0.25mg以上の場合で違反点数25点です。
また、酒酔い運転の場合は、違反点数35点となっています。
飲酒運転で逮捕されずに在宅事件になるケース
在宅事件とは、警察や検察に身柄拘束されていない状態で、捜査や裁判などを受ける刑事事件のことをいいます。
飲酒運転の場合でも全ての事件で逮捕・勾留されるわけではなく、事故が発生していない場合などでは、在宅事件となるケースも高いです。
また、飲酒運転で逮捕された場合でも悪質性が低く、加害者による証拠隠蔽や逃亡の可能性が低いと判断されれば、勾留されずに釈放となるケースもあり得るでしょう。
一方で、前科・前歴がある場合や、過失運転致死傷罪などに該当する人身事故を起こしている場合、執行猶予中にも関わらず事件を起こした場合、正当な理由なく呼気検査を拒否した場合などは、逮捕・勾留されやすい傾向があります。
飲酒運転で逮捕された後の流れ
飲酒運転で逮捕された場合は、一般的な刑事事件と同じように逮捕後に事件送致・勾留・起訴・裁判の順番に処理されます。
それぞれの段階で、どのようなことがおこなわれるのか、誰に助けを求められるのかなどを確認しましょう。

1.事件発生~逮捕
飲酒運転は、そのときの体内のアルコール濃度が重要な証拠になります。
そのため、検問や交通事故時の呼気検査で基準値以上のアルコール濃度が検出された際に現行犯逮捕となるケースが通常です。
だからといって、交通事故を起こしたのに警察に連絡しないのは全くおすすめできません。例えばひき逃げは過失運転致死傷罪・救護義務違反・報告義務違反等で、より重い犯罪になってしまいます。
なお、飲酒運転で事故を起こしたのであれば、逮捕された段階で弁護士に依頼しておくとベターです。逮捕直後から事故被害者と示談ができれば、起訴・不起訴の判断において有利になる可能性があるからです。
2.逮捕~送致
飲酒運転で逮捕されると、まず警察署で事件に関する取り調べがおこなわれます。
また、警察は逮捕後48時間以内に検察に事件を送致するかどうかの判断をおこないます。
このとき、被疑者は当番弁護士制度を利用して、1度だけ無料で弁護士と面会することが可能です。
警察官・検察官・裁判官などに当番弁護士制度を利用したい旨を伝えると面会手続きをおこなってくれるので覚えておきましょう。
なお、逮捕後に取り調べを受ける段階で、家族の人が弁護士に依頼するのも有効な手です。前述した当番弁護士は1度しか面会できません。一方、私選弁護士であれば面会の回数に制限はありません。
特に、警察の取り調べで作成される供述調書は、裁判になったときに重要な証拠となります。できれば取り調べ前に弁護士からアドバイスをもらい、適切に対処できるようにしておきたいところです。
参考元:日本弁護士連合会:逮捕されたとき
3.送致~起訴
警察から検察へ事件送致がされると、検察は24時間以内に勾留請求するかどうかの判断をします。
そして、裁判所から勾留許可がおりてしまうと、原則10日間(最大20日)にわたり身柄拘束が続くことになるのです。
この間も警察や検察による捜査はおこなわれて、検察は起訴するか不起訴にするかの判断をおこないます。
なお、単純な飲酒運転の場合は罰金刑を科すための略式起訴となるのが通常です。
一方、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪であれば20日間の勾留をうけ、そのまま起訴されることも考えられます。
弁護士のサポートがあれば、勾留しないよう働きかけるほか、勾留が決定されても準抗告や勾留取消請求などで早期の釈放を目指します。
4.起訴~裁判
前科・前歴がある場合などは略式起訴ではなく公判請求となり、一定期間を経たのちに刑事裁判となるケースが一般的です。
刑事裁判では執行猶予付き判決になる場合もありますが、執行猶予中に事件を起こした場合は実刑判決となる可能性が高いでしょう。
なお、あくまで一般論ですので、処分内容は個別の事件や犯罪によって異なります。
弁護士に依頼していれば、まずは不起訴を目指します。被害者との示談、身元引受人の確保などを通じて、不起訴に向けた環境を整えます。
一方、刑事裁判となっても、代理人となって被告人に有利な事実の主張・立証などを通じ、不起訴処分や減刑を目指します。
このように、飲酒運転で事故を起こした場合には、早期から弁護士へ依頼することが重要です。刑事事件ナビは刑事事件に注力している弁護士のみを掲載しています。相談料無料・土日相談可の事務所も多数掲載しているので、まずは相談から始めましょう。
最後に
飲酒運転で逮捕された場合は、一般的な刑事事件と同じように逮捕・事件送致・勾留・起訴・裁判の順番で処理されます。
しかし、場合によっては、身柄拘束されずに在宅捜査になったり、不起訴処分になったりするケースもあります。
また、悪質性が高いと判断された場合でも、早めに弁護士に依頼することで、早期釈放や不起訴処分などの獲得を目指すことができます。
特に被害者がいる場合は、被害者との間で示談成立ができるかが減刑のポイントにもなります。
被害者やその家族は、基本的に加害者と直接面会してくれませんが、弁護士であれば被害者と示談交渉することができる場合もあります。
他にも取り調べに関するアドバイスなども受けられますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
ご家族や自身が酒気帯び運転で逮捕・検挙された方へ
逮捕されると、最大で23日間の身体拘束を受け、起訴されれば懲役や罰金などの刑事罰を科される可能性があります。
検挙されて取り調べを受けた場合も、同様に起訴される可能性があります。
ご家族が飲酒運転で逮捕された方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 取り調べのアドバイスがもらえる
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 弁護活動によって不起訴・執行猶予付き判決を目指す など
刑事事件はスピードが重要です。
逮捕後72時間以内に本人と会えるのは、弁護士だけです。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。