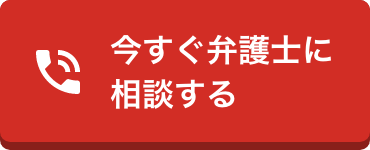【加害者限定】
【加害者限定】お急ぎの方へ

累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
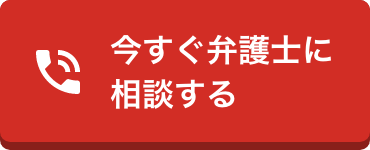
犯罪を犯して有罪になると、刑事罰を受けるだけでなく「前科」がつくことになります。
前科がつくと、「前科調書」に記載されて記録が残ります。前科調書は、刑事裁判で被告人の前科を証明するために検察官が証拠として提出する書面です。
ただし、前科がつくデメリットはこれだけではありません。私生活においても仕事上においても、さまざまな不利益を受ける可能性があるのです。
そこでこの記事では、まず前科について簡単に解説したあと、前科がつくデメリットや前科を回避する方法について解説します。
なお、すでに刑事事件の加害者になっており、「このまま手続きが進むと前科がつく可能性がある」人はただちに弁護士へ依頼してください。
刑罰の軽重も重要ですが、それ以前に前科を回避する方が大切です。そのためには、早期から弁護士のサポートを受ける必要があります。
前科がつくのを避けたい方へ
前科がつくデメリットには、次のようなものがあります。
- 解雇・懲戒される恐れがある
- 履歴書等で『賞罰欄』があれば、前科の記入を求められる
- 出国・入国制限がかかる可能性がある
不起訴処分を得られれば、前科はつきません。
たとえ在宅事件であったとしても、起訴され有罪になれば、前科がつきます。
前科がつくのを避けたい方は、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力している弁護士を探せるサイトです。
初回相談無料・即日対応可の事務所も多数掲載しているので、まずは相談して今後の見通しを確認しましょう。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|
そもそも前科とは?前科がつく条件と前歴との違い
前科とは、法律上の定義はありませんが、一般的には、刑事裁判で有罪判決を受け、刑の言い渡しを受けた経歴をいいます。
ここでは、簡単に前科とはどういうものなのかについて、また、前科と似たような意味合いを持つ『前歴』との違いについて、簡単に解説します。
どんなときに前科がつくのか
前科は、刑事裁判で有罪判決により刑が言い渡されたときにつきます。刑罰には、懲役、禁錮、罰金等がありますが、いずれの刑罰でも有罪判決であれば前科がつきます。
また、これらの刑が執行猶予となった場合であっても、前科として罪を犯した事実が経歴に残ります。
一方、逮捕されても不起訴処分であれば前科はつきませんし、起訴されたとしても裁判で無罪判決を受ければ前科がつくことはありません。
前科と前歴の違い
刑事裁判で有罪判決を受け、刑の言い渡しを受けた経歴を前科と言うのに対し、『前歴』とは、前科も含めたより広い概念で、警察や検察などの捜査機関により、被疑者として捜査対象となった事実を指します。
これは、不起訴処分になった場合も含まれます(逮捕・勾留された場合であっても、不起訴処分であれば同様です)。そのため、前歴は、罪を犯したということを示すものではありません。
前科と前歴では、扱いが大きく異なるため、刑事事件で被疑者になった場合には、早急に対応することが必要です。
前科がつくデメリット8つ|仕事や人間関係、それぞれのデメリットは?
 前科がつくことで、社会生活において様々なデメリットが考えられます。
前科がつくことで、社会生活において様々なデメリットが考えられます。
- 仕事におけるデメリット
- 家庭におけるデメリット
- その他社会生活でのデメリット
- 再犯時のデメリット
4つの項目ごとに、デメリットについて詳しく解説します。
仕事におけるデメリット
①解雇されるおそれがある
会社の就業規則等に、有罪判決を受けることが「解雇事由」として明記されている場合、解雇される可能性が高いといえます。
また、就業規則に前科についての規定がなくても、会社の名誉や評判を著しく傷つけた場合や、犯罪の性質上、会社や他の社員等との関係で職場環境を強く害する場合は、解雇の正当な理由となり得ます。
なお、解雇されない場合であっても、懲戒処分を受けるということも十分考えられます。
②就職活動や転職活動で申告が求められる場合がある
法的に前科の有無というプライバシー性の高い事項を申告する義務はありませんので、これを秘匿することは自由です。
しかし、履歴書の賞罰欄にて前科の記載が求められたり、面接において前科の有無を確認されたり、採用において前科の存在が考慮されることは十分考えられます。
もちろん、後述するように前科を欠格事由とする職業では必然的に前科の申告が必要です。
真実を告知する義務は法的にありませんが、就業規則等で「採用時における虚偽の告知は、解雇事由に該当する」などと定められている場合、採用時に前科の有無を偽ったことを理由として、就職後に解雇されるおそれがあります。
また、前科を秘匿した上で採用され、採用後に前科の事実が発覚した場合、解雇を免れたとしても、経歴詐称として事実上の不利益を受ける可能性は否定できません。
もっとも、正直に申告したことで、採用されないというリスクはあります。
③就くことのできない職業がある
前科がつくと、一定の期間、就業できない職業や、取得できない国家資格があります。具体例は以下のとおりです。
|
弁護士、弁理士、教員
その他国家資格を必要とする職業
|
禁錮以上の前科の存在は欠格事由となりますので、一定期間内は就業できません。
|
|
金融に関する仕事
|
一般的に、金融機関の職業の身元調査は、厳格厳密に行われていると言われており、前科の存在が不利に働くおそれがあります。
|
|
警備員
|
警備業法により、禁錮以上の前科を有する者は刑の終了から5年間警備員の仕事につくことができません。
|
家庭におけるデメリット
④離婚事由になり得る
前科があることがただちに離婚事由に該当するわけではありません。
ただし、前科の対象となった犯罪行為の性質や、それに伴う刑事処分を踏まえて、離婚事由の『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』(民法第770条第1項第5号)に該当する可能性はあります。
その他社会生活に関するデメリット
⑤インターネット上に残る場合がある
前述の通り、前科はプライバシー性の高い事項であることから、公的機関が前科の情報を公開することはありません。
しかし、ニュース記事等の情報がインターネット上に残り続けることで、他人に前科の存在が知られるおそれがあります。
⑥海外旅行の際、渡航先で前科の申告を求められる場合がある
国によっては前科の申告を求められることもあります。そのため、当該国家の入国許可基準によっては、入国が許可されない可能性があります。
再犯時のデメリット
⑦検察庁や警察に記録が残る
検察庁は犯罪履歴の管理を行っており、前科を記録として残しています。もっとも、この記録は一般公開されることはありません。
⑧再犯後の刑事裁判で判決が重くなるおそれがある
前科のある人が再び刑事裁判を受けることになった場合、前科がない人間に比べて重い刑事処分を受ける可能性が高くなります。
前科の有無は情状面で考慮されるため、前科の存在はその後別の罪を犯した場合の刑事裁判において不利に働く可能性は極めて高いです。また、前科の種類と再犯の時期によっては、以下の通り「累犯」として刑が加重されます。
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする
引用元:刑法第57条
前科がついてしまった後、いかに再犯を防止するのかについては、本人だけでなく周囲のサポートを含め、具体的な対策が必要でしょう。
起訴までの対処で前科を回避できる可能性が上ります。
日本の刑事手続きでは起訴されると99%近くが有罪となって前科がつきます。つまり、前科を回避するには起訴前に対処をして不起訴処分を目指さなければなりません。
そのためには、弁護士のサポートが必要不可欠です。弁護士に依頼すると不起訴処分のために次のような活動をおこないます。
- 被害者との示談
-
家族などの監督があり再発防止に努める旨の意見書を検察官に提出する
- 有利な証拠を集めて不起訴処分にすべき旨の意見書を検察官に提出する など
これらの弁護活動は早めに手を打っておく必要があります。逮捕されると起訴まで原則23日しかないからです。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力している弁護士を探せるサイトです。相談料無料・即日対応可の事務所も多数ありますので、ただちに依頼先を決めてください。
前科がつくデメリットとしてよく誤解されるもの
ここまで前科がついた場合のデメリットについて解説してきましたが、一方で、デメリットであると誤解されているものについてもご説明します。
戸籍や住民票などで一般公開されるようなことはない
前科情報は警察と検察に加えて本籍地の市区町村に『犯罪人名簿』という形で残されます。
このことから、「戸籍や住民票に前科情報が載るのでは?」と心配されている方がいるかもしれませんが、戸籍や住民票などに前科情報が載ることはありません。
何度かお伝えしているように、前科情報はプライバシー性が非常に高いため、厳重に管理されています。
選挙権は失わない
選挙権を失う条件の「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」と前科の有無を混同して考えている方もいるかもしれませんが、前科によって永久的に選挙権を失うことはありません。
罪を犯して有罪判決を受けた方でも、すでに刑の執行が終わっていれば問題なく選挙を行えます。
※ただし、政治資金規正法や公職選挙法等違反の前科がある場合には、選挙権が停止される場合があります。
国からの保護を受ける権利を失わない
たとえ前科があっても、国から認定されれば保護制度を活用できます。
借入やローンの審査にも影響はない
消費者金融などの金融機関は、信用情報機関の情報を元に審査を行っていますが、この信用情報機関には前科の情報が載せられることはありませんので、借入やローンを行うことができます。
ただし、服役中にローンの支払いが滞りブラックリストに入ってしまっている、社会復帰後の就職難で収入が少ないとの理由で審査が通らないことはあり得るでしょう。
【重要】前科がついてしまうのを回避する方法
 はじめにお伝えしたように、起訴されて有罪判決を受けることではじめて前科がつくことになります。
はじめにお伝えしたように、起訴されて有罪判決を受けることではじめて前科がつくことになります。
しかし、たとえ逮捕されたとしても早急に対応することで、前科を回避することができるかもしれません。
ここでは、前科を回避する3つの方法について見ていきましょう。
とにかく早急に対応する
犯罪を起こしてしまった場合や罪を疑われた場合、まずは早急に対応することを一番に考えてください。逮捕される前であれば逮捕前の対応ができますし、起訴前であれば不起訴処分の獲得を目指すことも可能です。
具体的にどのような対応をとるべきかは、事件内容や状況によって異なります。具体的には次のようなものがありますが、弁護士に依頼すれば適切に判断してサポートをしてもらえます。
- 前科がない・被害が小さい場合は刑罰を与えるほどでない主張をする
- 証拠を集めて無罪であることを示す
- 加害者の境遇や犯罪の様態を考慮した結果、起訴猶予が妥当であると主張する など
まずは弁護士に直接相談して、最適な対処法のアドバイスをもらってください。
被害者と示談を行う
具体的な方法の1つとして、被害者との示談が挙げられます。示談とは、被害者に謝罪と示談金の支払いを行い、許しを請うことです。
示談で和解できれば被害届を取り下げて捜査終了となる場合もありますし、示談成立の事実が検察官に評価されて不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
起訴される前に示談交渉を円滑に進めることができれば、有罪判決を回避できる可能性も高くなるでしょう。
ただし、被害者との示談は加害者や加害者の家族が自らおこなうことは通常ありません。弁護士に依頼しておこないます。
加害者自身もしくは加害者の家族が示談をしようとしても、被害者が感情的になり示談がまとまらない可能性が高いからです。また、弁護士でなければ、適切な示談内容を取りまとめることは難しいでしょう。
示談のためにも弁護士への依頼は必要です。
きちんと反省して再犯を防ぐ
事件内容や程度にもよりますが、被疑者本人が罪の反省をしっかり行い、再犯のおそれが低いと評価されれば、前科がつかずに不起訴で身柄開放される可能性もあります。
罪を犯した事実があるにもかかわらず闇雲に罪を否定したり、証拠隠滅を行ったり、開き直った態度を見せていると、悪質性が評価され、起訴されるということも十分おこり得ます。
警察・検察に反省を示すには、取調べで反省の態度が伝わるようにしたり、反省文を提出したりなどが具体例です。ただし、取調べも反省文の作成も事前に弁護士からアドバイスを受けた方が反省が伝わりやすいはずです。
反省を示して不起訴処分を獲得するためにも、弁護士への依頼は有効です。
不起訴処分を目指すには、弁護士への依頼が有効です。
不起訴処分を目指すには、逮捕直後からの弁護活動が重要です。弁護士に依頼すれば次のようなサポートを得られるので、前科がつく可能性を減らせます。
- 被害者と示談をする
- 反省の念を客観的に示す
- 取調べのアドバイスをする
- 犯行をしていない証拠を示す など
起訴されるまでの期間は、原則として逮捕から最長23日間しかありません。時間の制限がありますから、できるだけ早く依頼することが重要です。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力している弁護士を探せるサイトです。相談料無料・即日対応可の事務所も多数ありますので、まずは相談して今後の見通しを確認しましょう。
すでについてしまった前科を消すことはできない
ここまで主に、まだ前科がついていない人の対処法をお伝えしました。では、すでに前科がついてしまっている人はどのような対処をすればよいでしょうか。
「前科を消したい」と考える方もいるでしょうが、結論をお伝えすると一度ついた前科を消すことはできません。警察と検察には前科の情報が一生残ってしまうこととなります。
しかし、何度もお伝えしているように、ここでの前科情報は簡単に外部に知られるようなことはありません。
最も大きなデメリットは、再び犯罪を起こしたときに前科の存在が評価されてより厳しい刑を受け得ることでしょう。
そのため、すでに前科がついている方が一番気を付けるべきことは、再び罪を犯さないような生活を送っていくことです。
もしも性犯罪や薬物犯罪のように再犯率が高い犯罪の前科があるのであれば、再犯を防ぐための更生施設を利用することも検討してみてください。
まとめ
前科がつくと、少なからず私生活に悪影響があることがわかりました。
この記事で紹介したデメリットは以下のとおりです。
- 解雇・懲戒されるおそれがある
- 就職活動で申告を求められる場合もがある
- 就くことのできない職業がある
- 離婚事由になり得る
- ニュースがインターネット上に残る場合がある
- 海外旅行等の際入国審査に影響がある国もある
- 検察庁や警察に記録が残る
- 再犯後の刑事裁判で刑が重くなるおそれがある
前科がつくことを避けるには、早めに刑事事件が得意な弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。多くの弁護士に無料で相談できますので、まずは一人で悩まずに相談してみてください。
前科がつくのを避けたい方へ
前科がつくデメリットには、次のようなものがあります。
- 解雇・懲戒される恐れがある
- 履歴書等で『賞罰欄』があれば、前科の記入を求められる
- 出国・入国制限がかかる可能性がある
不起訴処分を得られれば、前科はつきません。
たとえ在宅事件であったとしても、起訴され有罪になれば、前科がつきます。
前科がつくのを避けたい方は、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力している弁護士を探せるサイトです。
初回相談無料・即日対応可の事務所も多数掲載しているので、まずは相談して今後の見通しを確認しましょう。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|