人を殺してしまったら何罪になる?人の死と関係する犯罪と罪に問われないケース

人を殺してしまったときには、殺人罪や過失致死罪、傷害致死罪などの犯罪が成立します。
もしも、殺人を犯してしまい悩んでいるなら、自身の罪を認め、早めに自首をするのが一番です。
いずれにせよ、殺人をしてしまったという事実から逃げることはできません。
どうしても自首をするのが難しい場合は、早めに弁護士へ相談して対応についてアドバイスをもらいましょう。
本記事では、人を殺してしまったときに適用される可能性がある犯罪類型や法定刑、私選弁護人に相談・依頼をするメリットなどについてわかりやすく解説します。
人を殺してしまい、居ても立っても居られずに悩んでいる方は、本記事を読んで行動に移してください。
人を殺してしまったら何罪?殺意の有無などによって成立する犯罪は変わる
まずは、人を殺してしまったときに問われる罪について詳しく解説します。
人を殺してしまったときに適用される犯罪類型の考え方
人を殺してしまった場合にどのような犯罪が適用されるかは、客観的構成要件要素と主観的構成要件要素の2つの側面から判断されます。
人を殺してしまったケースでは、「人を殺害した」という客観的構成要件要素は確定している状況です。
そのため、人を殺してしまったときにどのような罪状で刑事訴追されるかは、「殺意の有無」によって異なると考えられます。
人を殺してしまったときの主観の種類
一般的に「殺意」とは、人を殺そうという意思のことです。
法律的には「殺意=人を殺す故意」と表現されます。
人を殺す故意の内容は、以下のように区分されます。
- 意図:「人を殺すこと」の実現を意図する場合
- 確定的故意:「人を殺すこと」を確定的なものとして認識・予見している場合
- 未必の故意:「人を殺すこと」の確定的な認識・予見はないが、その蓋然性を認識・予見している一定の場合
このような内心の状況で人を殺してしまったときには、殺人罪が成立します。
一方、行為者の内心が以下の状況のときには、殺人罪の故意は認められません。
- 認識ある過失:「人を殺すこと」についていったんは行為者の意識にのぼったものの、結局としてそれを否定した場合
- 認識なき過失:「人を殺すこと」自体が行為者の意識にのぼらなかった場合
これらの主観で人を殺してしまったときには、殺人罪以外の犯罪類型で処罰されることになるでしょう。
殺意などの行為者の主観を認定する方法
殺人を犯してしまった際に問われる罪は、殺意の有無によって判断されるケースが多いものの、実際に「人を殺してしまったその瞬間に行為者がどのような主観でいたのか」を立証するのは簡単ではありません。
なぜなら、行為当時の当事者の主観を直接的に知ることはできないからです。
そのため、実際の刑事手続きでは、犯人の供述や第三者の証言、行為当時の客観的事実などを考慮し、犯人が犯行時にどのような主観だったのかを認定することになります。
たとえば、「被害者を殺害するつもりでナイフを胸に刺した」という被疑者本人の自白があれば、殺意があったことを認定しやすいです。
また、「凶器の種類」や「創部の箇所」も殺意の認定に役立つ客観的証拠です。
たとえば、何キロもあるダンベルで被害者を殴りつけたケースなら、凶器自体の殺傷能力が高いので、「行為時点で被害者に対する殺意があったのだろう」という事実認定に傾きやすくなります。
一方、すぐに折れるカッターナイフで被害者の「肘」を傷つけようとした事案では、カッター自体に殺傷能力はないうえ、創部の箇所も致命傷を負いにくいことから、「行為時点で殺意があったとは考えにくい」と事実認定される可能性が高いです。
そのほか、「殺害行為に至った経緯」や「犯行の動機」もポイントになるでしょう。
たとえば、犯人が以前から「被害者を殺したい」などを発言していたことが第三者の証言から明らかになっているのなら、実際に事件を起こしたときに殺意があったと事実認定されやすくなります。
このように、殺意などの加害者側の内心を認定するときには、加害者本人の証言だけではなく、事件をめぐる客観的証拠が重要になります。
人を殺してしまった場合に成立する可能性がある主な犯罪と刑罰
ここでは、人を殺してしまったときに適用される可能性がある犯罪類型の構成要件や法定刑について解説します。
1.殺人罪|死刑または無期もしくは5年以上の懲役
殺人罪とは、「人を殺したとき」に成立する犯罪類型のことです。
殺人罪の法定刑は、「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」と定められています。
また、殺人罪は、未遂罪・予備罪も処罰対象です。
殺人罪の構成要件は以下3つです。
- 人
- 殺す
- 故意
第1に、殺人罪の客体は「人」です。
人の始期は、「胎児が母体から露出して直接的な侵害の可能性が生まれたとき(一部露出説)」と考えるのが判例通説です。
そして、人の終期は、自発呼吸が不可逆的に停止したこと、心臓が不可逆的に停止したこと、瞳孔反射の消滅の3つが総合的に考慮して規範的に判断されます。
第2に、殺人罪の実行行為は「人を殺すこと」です。人を殺害する現実的危険性のある行為であれば手段の如何は問われません。
第3に、殺人罪は故意犯なので、「殺意」が必要です。
明確に「被害者を殺害しよう」という殺意を抱いていた場合だけではなく、「当該行為に及ぶと被害者が死亡するかもしれない」という未必の故意の場合にも成立します。
2.過失致死罪|50万円以下の罰金
過失致死罪とは、「過失により人を死亡させたとき」に成立する犯罪類型のことです。
過失致死罪の法定刑は「50万円以下の罰金刑」と定められています。
また、親告罪である過失致傷罪とは異なり、刑事告訴がなくても立件されます。
たとえば、人を殺してしまったものの、人を殺す故意がなく、殺害行為当時の主観が「認識ある過失」や「認識なき過失」に該当すると認定される状況の場合、殺人罪は適用されず、過失致死罪で処断されることになります。
3.重過失致死罪|5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
重過失致死罪とは、「重大な過失により人を死亡させたとき」に成立する犯罪類型のことです。
重過失致死罪の法定刑は「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」と定められています。
まず、重過失致死罪と殺人罪の違いは、行為者の主観です。
殺人の故意が認定される事案では殺人罪が適用され、殺人の故意が存在せずに過失にとどまるケースでは重過失致死罪の適用が問題になります。
次に、過失致死罪と重過失致死の違いも重要です。
なぜなら、過失致死罪であれば「50万円以下の罰金刑」の範囲、つまり、懲役刑・禁錮刑が下されるリスクをゼロにできるのに対して、重過失致死罪が適用されると、懲役刑回避に向けた防御活動が必要になるからです。
重過失致死罪における「重過失」とは、「過失の程度が重いこと」を意味します。
つまり、過失致死罪と重過失致死罪は、「行為者の過失の程度」で区別されるということです。
殺人の故意を否定して過失致死罪・重過失致死罪の適用を受けるのか、重過失致死罪の適用を回避して過失致死罪で処罰されるのかは、「行為当時の行為者の主観がどのように認定されるのか」によって異なります。
できるだけ有利な罪状での処断を目指すのなら、被疑者・被告人側にとって有利な証拠を収集するだけではなく、収集された証拠を丁寧に積み上げて立証する工夫が必要です。
そのため、万が一人を殺してしまった場合は、必ず刑事実務を得意とする私選弁護人を選任するようにしてください。
4.傷害致死罪|3年以上の有期懲役
傷害致死罪とは、「身体を傷害し、よって人を死亡させたとき」に成立する犯罪類型のことです。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」と定められています。
傷害致死罪が適用されるのは、「傷害罪で処罰の対象になる傷害を受けた被害者が死亡したとき」です。
傷害とは、「生活機能の毀損、健康状態の不良変更(人の生理機能の侵害)をもたらす行為」と理解するのが判例です。
たとえば、頭部をめがけて拳で殴りかかる行為、エアガンを被害者の腹部めがけて打つ行為だけでなく、被害者をノイローゼに追い込む程度の執拗な嫌がらせ電話のような「暴行によらない傷害」も含まれます。
傷害致死罪と殺人罪を区別するのは、当事者の主観です。
つまり、傷害行為に及んだ加害者が、行為当時に殺意を抱いておらず、ただ単純に「被害者に怪我を負わせること」だけを認識していたと認定できる状況であれば、傷害致死罪が適用されることになります。
殺人罪では執行猶予を勝ち取るのは難しいですが、傷害致死罪なら執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
殺人罪で立件された場合は、傷害致死罪の適用を目指した防御活動を展開する事例が多く、刑事裁判実務に詳しい私選弁護人のサポートが不可欠といえるでしょう。
5.業務上過失致死罪|5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
業務上過失致死罪とは、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させたとき」に成立する犯罪類型のことです。
業務上過失致死罪の法定刑は「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」と定められています。
業務上過失致死罪は、過失致死罪の加重類型です。
過失によって人を死亡させた事実が「業務上」発生したときに成立します。
たとえば、熊を駆除するために猟銃を使用しようとしたものの、誤発射により無関係の一般市民に弾が命中してしまい、被害者が死亡した場合、過失致死罪ではなく、業務上過失致死罪が適用される可能性が高いです。
6.過失運転致死罪|7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
過失運転致死罪とは、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させたとき」に成立する犯罪類型のことです。
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」と定められており、過失運転致傷罪のように情状による免除の制度は定められていません。
また、無免許の状態で過失運転致死罪が適用される交通事故を起こしたときには、法定刑が「10年以下の懲役」に引き上げられます。
たとえば、運転中にスマートフォンを操作していたために横断歩道を渡っていた歩行者に気付かずこの人を轢いて死亡させてしまったときには、過失運転致死罪が成立します。
なお、交通事故を起こしたときの状況次第では、過失運転致死罪ではなく、危険運転致死罪、過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪などが適用されて、より重い刑事罰を下される可能性があります。
人を殺してしまっても罪に問われない主なケース
人を殺してしまったとしても、事案の状況次第では刑事責任を問われないパターンもあり得ます。
ここでは、人を殺してしまっても罪に問われない代表例を解説します。
1.正当防衛が認められた場合
正当防衛が成立する事案なら、人を殺してしまっても殺人罪などの容疑で刑事責任を科されることはありません。
正当防衛とは、「急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為」のことです。
正当防衛に該当する場合、違法性が阻却されるので、刑事責任は問われず無罪と扱われます。
正当防衛の要件は、以下のとおりです。
- 急迫不正の侵害
- 自己または他人の権利を守るための防衛行為
- 防衛の意思
- やむを得ずにした行為であること
なお、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するために防衛行為に及んだものの、防衛の程度を超えていると判断される場合には、「過剰防衛」に該当すると判断される可能性があります。
過剰防衛と判断されると、場合により刑が減軽または免除されます。
たとえば、相手から殴りかかられたときに、護身用に所持していたナイフで反撃をして相手を刺殺したケースでは、防衛行為が過剰であるため、過剰防衛の成否が問題になるでしょう。
場合によっては、過剰防衛自体も否定されて、殺人罪や傷害致死罪がそのまま適用される可能性もあります。
2.緊急避難が認められた場合
自己または他人の生命、身体、自由または、財産に対する現在の危難を避けるために、やむを得ずにした行為が、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合には、緊急避難が成立します。
人を殺してしまったとしても、緊急避難が成立する場面では、違法性が阻却されるので刑事責任は発生しません。
緊急避難の要件は以下のとおりです。
- 自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難
- 避難行為(現在の危難を避けるための行為であること)
- 危難の意思
- やむを得ずにした行為
- 害の均衡(保護法益が侵害法益と同程度か、それよりも優越すること)
たとえば、通り魔にナイフで襲われそうになっている友人を助けるために、通り魔を羽交い絞めにして動けないようにしたところ、首元が締まって通り魔を殺してしまったときには、緊急避難が成立する可能性が高いです。
なお、避難行為が害の均衡の程度を超えたときには「過剰避難」に該当し、場合により刑が減軽または免除されます。
3.正当行為が認められた場合
人を殺してしまったとしても、正当行為に該当するときには違法性が阻却されるので刑事責任は問われません。
正当行為とは、法令行為と正当業務行為のことです。
たとえば、医療行為として手術をしている最中に患者が死んでしまった場合、手術について患者本人の同意があり、医学的適応性・医術的正当性が認められる場合は、正当行為に該当します。
なお、正当業務行為にあたるかどうかは、事案ごとの具体的な事情を総合的に考慮して判断される点に注意が必要です。
4.心神喪失が認められた場合
人を殺してしまったとしても、殺害行為当時に心神喪失状態にあったときには、刑事責任は問われません。
心神喪失とは、刑事責任能力が欠如する状態のことです。
行為者に有責に行為する能力が備わっていないときには、その行為者を法的に非難することができず、刑事責任が阻却されます。
心神喪失状態にあったかどうかを判断するときには、生物学的要件(精神の障害)と心理学的要件(弁識・制御能力)の2つの基準が考慮されます。
実務上、心神喪失とは「精神の障害によって行為の違法性を弁識し、その弁識に従って行動を制御する能力を欠く状態のこと」と定義されており、弁識能力か制御能力のどちらか一方でも欠けていれば、心神喪失にあったことを理由に刑事責任が阻却されます。
また、心神喪失にあったかどうかは、病歴や犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様、犯行後の行動、犯行以後の病状などを総合的に考慮して判断されます。
つまり、医師によって統合失調症の診断が下されたとしても、それだけを理由に心神喪失状態であったことが認定されるわけだはないのです。
なお、精神上の障害により、弁識能力または制御能力が著しく限定されている状態であれば、「心神耗弱(しんしんこうじゃく)」であることを理由に、刑事責任が減軽されます。
5.年齢が14歳未満だった場合
人を殺してしまった加害者が14歳未満の未成年であるときには、刑事責任は問われません。
これは、14歳未満の年少者は、犯罪予防の見地から刑事処罰を加えるのではなく、その他福祉的措置などによって矯正・更生を目指すべきだと政策的に考えられているからです。
なお、14歳以上20歳未満の加害者が人を殺してしまったときには、少年法が適用されて、少年院送致や検察官送致などの手続きを経てさまざまな処分が下される可能性が高いです。
人を殺してしまった場合は弁護士のサポートが必要不可欠
人を殺してしまった場合には、刑事事件を得意とする私選弁護人のサポートが不可欠です。
ここでは、刑事訴追されたあとの弁護方針ごとに、私選弁護人を選任するメリットをわかりやすく解説します。
罪を認める場合の弁護方針
人を殺してしまったことを認める場合には、以下の目標を掲げて防御活動を展開することになります。
- 早期に自白をしたり犯罪に関係する証拠を提出したりすることで、身柄拘束期間の短縮化を目指す(在宅事件化)
- 被害者との示談が成立していること、殺人に至った動機にやむにやまれぬ事情があったこと(家族間での介護疲れ、生活苦など)などを主張することで、実刑判決の回避や刑期の短縮化を目指す
早期の示談成立や有利な情状証拠を収集するには、刑事弁護を得意とする弁護士のサポートが不可欠でしょう。
なお、人を殺してしまった場合はどんな理由であれその責任から逃れることはできません。
人を殺してしまったという自覚がある場合は、罪を認めて償うことを第一に考えるようにしてください。
罪を認めない場合の弁護方針
人を殺してしまった事実を否認する場合や、心神喪失や正当防衛、故意がなかったことを主張する場合には、逮捕・勾留による長期の身柄拘束を避けることはできません。
そのため、被疑者・被告人側に有利な刑事処分や認定を引き出すためには、捜査活動の初期段階から防御方針を明確化し、自らの主張を根拠付ける証拠を収集する必要があります。
とくに、殺人罪で立件された事案において公訴事実に反する主張をするケースでは、適切な防御活動を展開しなければ、長期の実刑判決が下される可能性が高いです。
いずれにせよ、速めのタイミングで刑事事件弁護に強い弁護士に相談しましょう。
さいごに|何かしらの事件を起こした際にはすぐに弁護士相談を
人を殺してしまったときには、まずは自分の罪を認めて弁護士へ相談し、自首することを考えてください。
特別な事情がない限り、殺人という罪から逃れることはできません。
人を殺してしまったことについて防御活動をしたい場合は、当番弁護士や国選弁護人ではなく、刑事事件を得意とする弁護士の力を借りましょう。
弁護士であれば、たとえ殺人を犯してしまった人であっても、味方となってくれます。
なお、ベンナビ刑事事件では、殺人事件などの弁護実績が豊富な専門家を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。


【初回面談30分無料】【元検事の弁護士が在籍】刑事事件の対応実績豊富な弁護士が、依頼者様に寄り添います。早期釈放を通じた社会復帰のことも考えた対応を大切に、最後までサポート。ぜひお早めにご相談ください。
事務所詳細を見る
【秘密厳守】不同意わいせつ/性犯罪/痴漢/盗撮・のぞき/レイプ・強姦/児童ポルノ・児童買春「警察から呼び出しを受けた/通報されてしまった」知らない間に捜査は進んでいます!解決を目指すなら、お早めにご相談を!
事務所詳細を見る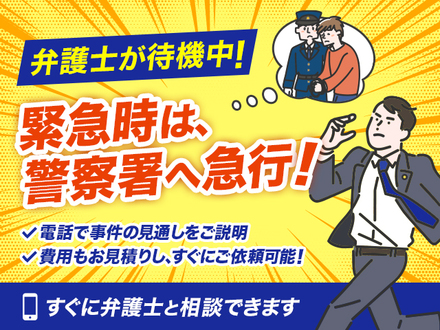
【八王子駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



殺人事件を起こしたらに関する新着コラム
-
未成年者が殺人事件を起こしたときには、少年法が適用されます。本記事では、未成年者が殺人事件を起こしたときの手続きの流れや親の法的責任、弁護士に相談・...
-
本記事では、人を殺してしまったときに適用される可能性がある犯罪類型や法定刑、私選弁護人に相談・依頼をするメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
殺人で逮捕され、刑事裁判にて有罪判決が下されると、死刑や無期懲役などの罰則が科せられる可能性があります。ただし、中には正当防衛として扱われるケースや...
-
殺人未遂で逮捕・起訴される構成要件と量刑が決まるポイント、減刑となる基準などを解説します。刑法第203条で殺人未遂罪が成立する最も重要な条件は、『殺...
-
過失致死(かしつちし)とは、殺害の意志がない状態(過失)で相手を死亡させてしまうことを言います。
-
殺人未遂罪でも刑罰が軽くなれば、執行猶予を受けられる可能性があります。執行猶予を獲得するためには、殺意がないことの証明が最も重要になるでしょう。
-
殺人未遂罪による公訴時効は25年ですが、事件について起訴をされると時効が停止します。今回は殺人未遂事件における時効期間と時効停止の基準について解説し...
-
殺人未遂罪による量刑の相場は3年~15年が一般的だとされていますが、未遂罪による減免が考慮されるため比較的軽い量刑になる可能性も高くなります。
-
殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪で、刑法第199条では「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
殺人事件を起こしたらに関する人気コラム
-
過失致死(かしつちし)とは、殺害の意志がない状態(過失)で相手を死亡させてしまうことを言います。
-
殺人未遂で逮捕・起訴される構成要件と量刑が決まるポイント、減刑となる基準などを解説します。刑法第203条で殺人未遂罪が成立する最も重要な条件は、『殺...
-
殺人未遂罪による量刑の相場は3年~15年が一般的だとされていますが、未遂罪による減免が考慮されるため比較的軽い量刑になる可能性も高くなります。
-
殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪で、刑法第199条では「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
-
殺人未遂罪による公訴時効は25年ですが、事件について起訴をされると時効が停止します。今回は殺人未遂事件における時効期間と時効停止の基準について解説し...
-
殺人未遂罪でも刑罰が軽くなれば、執行猶予を受けられる可能性があります。執行猶予を獲得するためには、殺意がないことの証明が最も重要になるでしょう。
-
殺人で逮捕され、刑事裁判にて有罪判決が下されると、死刑や無期懲役などの罰則が科せられる可能性があります。ただし、中には正当防衛として扱われるケースや...
-
未成年者が殺人事件を起こしたときには、少年法が適用されます。本記事では、未成年者が殺人事件を起こしたときの手続きの流れや親の法的責任、弁護士に相談・...
-
本記事では、人を殺してしまったときに適用される可能性がある犯罪類型や法定刑、私選弁護人に相談・依頼をするメリットなどについてわかりやすく解説します。
殺人事件を起こしたらの関連コラム
-
殺人未遂罪による公訴時効は25年ですが、事件について起訴をされると時効が停止します。今回は殺人未遂事件における時効期間と時効停止の基準について解説し...
-
殺人未遂で逮捕・起訴される構成要件と量刑が決まるポイント、減刑となる基準などを解説します。刑法第203条で殺人未遂罪が成立する最も重要な条件は、『殺...
-
殺人未遂罪でも刑罰が軽くなれば、執行猶予を受けられる可能性があります。執行猶予を獲得するためには、殺意がないことの証明が最も重要になるでしょう。
-
殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪で、刑法第199条では「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
-
過失致死(かしつちし)とは、殺害の意志がない状態(過失)で相手を死亡させてしまうことを言います。
-
殺人で逮捕され、刑事裁判にて有罪判決が下されると、死刑や無期懲役などの罰則が科せられる可能性があります。ただし、中には正当防衛として扱われるケースや...
-
殺人未遂罪による量刑の相場は3年~15年が一般的だとされていますが、未遂罪による減免が考慮されるため比較的軽い量刑になる可能性も高くなります。
-
本記事では、人を殺してしまったときに適用される可能性がある犯罪類型や法定刑、私選弁護人に相談・依頼をするメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
未成年者が殺人事件を起こしたときには、少年法が適用されます。本記事では、未成年者が殺人事件を起こしたときの手続きの流れや親の法的責任、弁護士に相談・...
殺人事件を起こしたらコラム一覧へ戻る








































