前科は消える?前科がつく不利益や不利益がほぼ解消されるまでの期間についても解説


- 「前科は10年経てば消える」
- 「執行猶予がついていれば前科にならない」
前科について調べているときに、このような情報を目にしたことはありませんか?
しかし、これらは誤った認識です。
前科は一度ついてしまうと、基本的に生涯消えることはありません。
とはいえ、前科による不利益は、一定期間が経過することで実質的に軽減されていきます。
また、起訴される前であれば、前科がつかないよう対応できる可能性もあるでしょう。
本記事では、前科はいつまで残り続けるのかや、前科によってどのような不利益を受けるのかについて詳しく解説します。
また、前科による不利益がどのように軽減されていくのかや、そもそも前科がつかないようにするためにできることも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
刑事事件に直面したとき、誰もが不安を感じるものです。
正確な知識を得ることが、適切な対応への第一歩となります。
前科がついてしまうと消えることはない
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、判決が確定したことによって「その罪を犯した事実が確定した」という記録のことです。
「執行猶予がついた場合は前科にならない」「10年経てば前科は消える」といった誤った情報が広まっていますが、実際には執行猶予付きの判決や罰金刑であっても、有罪判決が確定すれば前科となります。
前科の記録は、検察庁と本籍地の市区町村で管理されており、本人が亡くなるまで消えることはありません。
これらの記録は、選挙権の確認や資格審査、再犯時の量刑判断などで必要になるため、厳重に保管されています。
前科は極めて重要な個人情報として法律で保護されており、正当な理由がある場合を除いて、一般の人が閲覧することはできません。
前科がつくことによって受ける主な不利益
前科がつくと、社会生活のさまざまな場面で影響を受けることになります。
具体的には、前科がつくことで以下のような不利益が生じるでしょう。
- 解雇や退学になる可能性がある
- 就職・転職で不利になることがある
- 職業・資格の制限を受ける
- 海外渡航の制限を受けるおそれがある
- 選挙に参加できなくなる
- 婚姻関係に不利益を及ぼす可能性がある
- 犯罪行為をおこなった事実を、周囲に知られる可能性が高まる
- 次に犯罪行為をおこなった際に、罪が重くなる可能性がある
それぞれについて、詳しく解説します。
解雇や退学になる可能性がある
在職中の会社員に前科がついた場合、会社の就業規則によって処分が決定されます。
有罪判決を受けたことが解雇事由として規定されている場合や、犯罪行為によって会社の信用が著しく失墜した場合は、解雇される可能性が高いでしょう。
また、学生の場合も学則に基づいて退学処分となる可能性もゼロではありません。
ただし、解雇や退学の判断は、犯罪の内容や情状、本人の反省の態度、これまでの勤務態度や学業成績なども考慮して総合的に判断されるのが一般的です。
就職・転職で不利になることがある
履歴書に賞罰欄が設けられている場合、前科の事実を記入する必要があります。
とくに国家資格を要する職業では、前科の記載が必須のため、登録・採用にも大きく影響するでしょう。
なお、前科を記載しなかった場合、後に発覚すると経歴詐称として解雇される可能性があります。
一般企業の場合は必ずしも申告の必要はありませんが、質問された際は虚偽の申告をしないようにしましょう。
職業・資格の制限を受ける
前科がつくと医師や看護師、弁護士や公認会計士、公務員など、多くの職業で資格制限を受けます。
在職中の場合は失職し、新規に就職を目指す場合は受験資格が得られないなど、自由に職業を選べなくなる点に注意しましょう。
裁判官、検察官、弁護士、国家公務員、地方公務員、医師、歯科医師、助産師、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、取締役、監査役、執行役、警備員、保育士、建築士など
海外渡航の制限を受けるおそれがある
前科があると、パスポートの発給やビザの取得が制限される場合があります。
たとえパスポートが発給されても、入国審査が厳しい国への渡航は困難になる可能性があるでしょう。
とくに、執行猶予中や仮釈放中は行動が制限され、海外渡航が認められません。
さらに、渡航先の国によってはビザの発給が拒否されたり、入国審査で入国を拒否されたりすることもあります。
選挙に参加できなくなる
禁錮以上の刑に処された場合、その執行を終えるまでは選挙権が停止されます。
また、収賄罪で有罪となった場合は、一定期間は選挙区への投票や出馬ができません。
なお、執行猶予中も同様の制限を受けます。
婚姻関係に不利益を及ぼす可能性がある
有罪判決を受けた事実は、民法に定める法定離婚事由の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
そのため、前科を理由に配偶者から離婚を求められた場合、応じざるを得ない状況になりかねません。
また、婚姻を予定している場合でも、前科の存在が結婚の障害となる可能性があります。
犯罪行為をおこなった事実を、周囲に知られる可能性が高まる
刑事事件の被疑者・容疑者として逮捕・起訴された場合、報道機関による報道の対象となることもあるでしょう。
とくに重大な事件の場合、テレビやインターネットニュースで大々的に報じられやすい傾向にあります。
これらの情報は、SNSなどで拡散される可能性があり、インターネット上に長期間残り続けます。
時間が経過しても、インターネット上に残った情報は完全には消えないため、知られたくない人に知られるという不安が長期間つきまといます。
次に犯罪行為をおこなった際に、罪が重くなる可能性がある
警察や検察庁は前科の記録を保持しており、再犯かどうかはすぐに判明します。
再犯の場合、初犯よりも重い刑罰を科されやすく、罪が重くなる可能性があります。
とくに、最初の刑の執行から5年以内に新たな犯罪を犯した場合は累犯として扱われ、さらに厳しい刑罰を受けることになるので注意が必要です。
「刑の言い渡しの効力」が消滅すれば、前科の不利益はほぼ解消される
前科そのものは本人が亡くなるまで消えることはありません。
しかし、一定の条件を満たすと「刑の言い渡しの効力」が消滅し、多くの不利益が解消されます。
具体的には、資格制限の解除や海外渡航の制限緩和など、社会生活上の制約が大幅に軽減されます。
「刑の言い渡しの効力が消滅する」とは?
刑の言い渡しの効力が消滅すると、法律上はその刑を受けていなかったものとして扱われます。
これにより、職業や資格の制限が解除され、新たに資格を取得することも可能になります。
ただし、すでに失った資格が自動的に復活するわけではないため、再度取得するための手続きが必要です。
また、刑の効力が消滅しても、前科の事実そのものは消えないため、その事実を知る人々の認識は変わりません。
刑の言い渡しの効力が消滅するまでの期間
刑の言い渡しの効力が消滅するまでの期間は、受けた刑罰の種類や執行猶予の有無によって異なります。
それぞれの場合について詳しく説明します。
執行猶予がついた懲役・禁錮刑の場合|執行猶予期間の経過後
執行猶予を取り消されることなく猶予期間を満了すると、刑の言い渡しの効力は自動的に消滅します。
たとえば、3年間の執行猶予が付いた場合、3年間何事もなく過ごせば刑の言い渡し効力は消滅します。
執行猶予がつかない懲役・禁錮刑の場合|刑期終了から10年後
実刑判決を受けた場合、その刑の執行を終えてから10年間、新たに罰金以上の刑に処せられることなく経過することで刑の言い渡しの効力が消滅します。
なお、この「10年間」という期間は、満期出所の場合は出所日の翌日から、仮釈放の場合は仮釈放期間満了日の翌日から計算されます。
罰金刑の場合|罰金の納付から5年後
罰金刑の場合、罰金を完納してから5年間、新たに罰金以上の刑に処せられることなく経過すれば、刑の言い渡しの効力は消滅します。
この「5年間」という期間は、罰金を納付した日から起算されます。
前科をつけないためには不起訴処分の獲得が重要
一度でも前科がつくとその記録は生涯残り続けます。
そのため、もし今現在、刑事事件の被疑者として前科がつく可能性がある状況にいる場合は、前科がつかないように対策することが非常に重要です。
そのためには、検察官による起訴を回避し、不起訴処分を獲得することが最も効果的な方法となります。
なお、不起訴処分を獲得するためには、以下の対応を検討してください。
できるだけ早期に弁護士に相談する
事件が起きた直後から弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができます。
初期対応を誤ると、その後の対応が難しくなる可能性があります。
被害者との示談を成立させる
被害者との示談が成立し、被害弁償をおこなったうえで許しを得られれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
示談交渉は弁護士に依頼することで、スムーズに進めることができます。
取り調べに適切に対応する
捜査段階での取り調べにおいて、不適切な発言や態度は不利に働く可能性があります。
弁護士のアドバイスを受けながら、適切に対応することが重要です。
再犯防止への意欲を示す
反省の態度を示し、二度と同じ過ちを繰り返さない意思を明確にすることも、不起訴処分を獲得するための重要な要素となります。
ただし、これらの対応をおこなっても、必ずしも不起訴処分が確約されるわけではありません。
犯罪の内容や状況によっては、起訴されることもあります。
もし何らかの事件に巻き込まれてしまった場合は、できるだけ早期に弁護士への相談を検討しましょう。
前科の消滅に関してよくある質問
最後に、前科の消滅でよくある質問について説明します。
同じような疑問を持っている方は、ここで解消しておきましょう。
略式起訴での罰金刑なら前科は消える?
略式起訴で罰金刑を受けた場合でも、前科が消えることはありません。
略式起訴とは、軽微な事件について正式な公判手続きを経ず、書面審理のみで罰金刑などを科す簡易な手続きです。
しかし、略式起訴で罰金刑を受けた場合でも、確定判決による前科として記録が残ります。
ただし、罰金の納付から5年以上が経過し、新たな罰金刑が確定しなければ、「刑の言い渡しの効力」が消滅します。
前科の有無は誰でも調べられる?
一般の人が他人の前科を調べることはできません。
前科の記録は、以下の場所に保管されています。
- 裁判所の記録
- 警察・検察などの捜査機関の記録
- 本籍地の市区町村が保管する犯罪人名簿
これらの記録は、高度に秘匿性の高い個人情報として厳重に管理されています。
アクセスできるのは、裁判所が量刑判断の資料とする場合や、捜査機関が犯罪捜査のために必要な場合と限定されています。
もしも一般人が前科歴を知る場合、マスコミや報道、新聞やネットニュース、それらの情報が転載された掲示板等となるでしょう。
恩赦で前科は消える?
恩赦とは、国家が特別な恩恵として、犯罪者に対して刑事上の責任を免除したり、刑の効力を失わせたりする制度です。
しかし、恩赦を受けても前科自体が消えることはありません。
なお、恩赦には以下のような種類があります。
- 大赦:有罪判決を無効にする
- 特赦:判決の言渡しの効力を失わせる
- 減軽:確定した刑の重さを軽くする
- 復権:制限された資格を回復する
- 刑の執行の免除:刑の執行を免除する
令和元年に実施された「即位恩赦」では、復権と刑の執行の免除がおこなわれましたが、いずれの場合も前科の記録自体を消し去る効果はありませんでした。
前歴や逮捕歴は消える?
前歴や逮捕歴は、本人が死亡するまで消えることはありません。
逮捕歴とは、刑事事件の被疑者として警察に逮捕された記録のことを指します。
一方、前歴は逮捕に限らず、被疑者として捜査対象になった場合につく記録のことで、逮捕歴を包含するより広い概念です。
これらの記録は、捜査対象となった時点で残り、たとえ不起訴処分や無罪判決となっても消えることはありません。
前科については、刑法で定められた期間経過で刑の言い渡しが失効しますが、前歴・逮捕歴にはそのような制度はなく、生涯残り続けることになります。
前科は10年で消えると聞いたけど本当?
前科は10年で消えるという認識は誤りです。
前科自体は生涯にわたって記録として残り続けます。
そもそも「前科は10年で消える」という誤解は、「刑の言い渡しの効力の消滅」と前科の記録を混同していることから生じています。
刑の言い渡しの効力は、禁錮以上の刑では刑の執行を終えてから10年、罰金刑では納付から5年が経過すると消滅します。
この効力の消滅により、それまで制限されていた資格の取得が可能になるなど、法的な制約がなくなるのです。
しかし、「刑の言い渡しの効力の消滅」によって前科の記録そのものが消えることはありません。
前科の記録は捜査機関に保管され続け、再び犯罪を犯して起訴された場合には、量刑を判断する重要な材料として考慮されます。
つまり、「刑の言い渡しの効力が消滅する」ということと、「前科の記録が消える」ということは、全く異なる事柄なのです。
さいごに|前科がつくおそれがあるならまずは弁護士に相談を!
前科は一度ついてしまうと生涯消えることはありません。
刑の言い渡しの効力が消滅しても、前科の記録自体は残り続け、さまざまな場面で影響を及ぼす可能性があります。
しかし、逮捕されたとしても、必ずしも前科がつくとは限りません。
早期の段階で弁護士に相談し、適切な対応をとることで、不起訴処分となる可能性もあります。
とくに初犯の場合は、被害弁償や示談の成立により、前科がつかないよう対応できることもあるでしょう。
もし前科がつくような事態に直面したときは、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

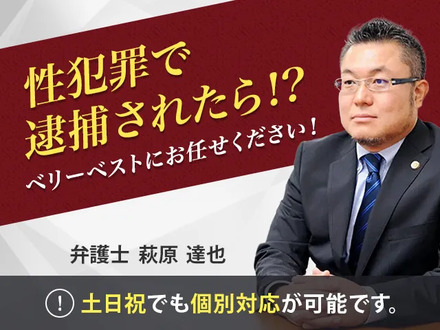
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る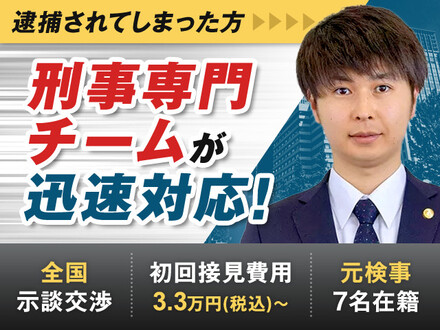
【町田駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る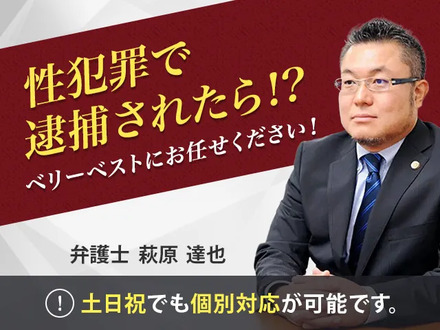
【六本木一丁目駅近】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事処分の種類と内容に関する新着コラム
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容に関する人気コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
刑事処分の種類と内容の関連コラム
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
情状酌量とは、裁判所で刑を確定する際に、被告人が犯罪を犯すまでの背景をくみとった上で、刑を軽くすることを指します。「情状酌量の余地なし」と判断される...
-
実刑(じっけい)とは、執行猶予が付かずに懲役刑や禁錮刑で刑務所に収監されるという判決を受けてしまうことです。実刑判決を受けてしまうと、その後、数カ月...
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年者への酒類提供は、店舗だけでなく提供した従業員個人も刑事罰や行政処分の対象となる可能性があります。本記事では、具体的な罰則内容や、裁判例を交え...
-
「不起訴はいつわかるのか」という疑問を抱いている方向けに、この記事では不起訴がわかるタイミングについてくわしく解説しています。身柄事件の場合、最大で...
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
-
未成年者の飲酒は法律で禁止されており、20歳未満はお酒を飲むことはできません。2022年4月から成人年齢は18歳になりましたが、飲酒は20歳からです...
-
未成年者の飲酒は法律で明確に禁止されています。本記事では、大学での飲み会やサークル活動で飲酒を強要された場合の対処法や、未成年飲酒に関する法的リスク...
-
偽計業務妨害罪は身近にある犯罪であり、実際に自身の行為が該当するのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、偽計業務妨害...
刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る




















































