【未成年者向け】飲酒にまつわるトラブルと法律|飲酒を強要された場合の対処法も紹介

大学の飲み会やサークルの集まりで、飲酒をすすめられ、断りづらい状況に直面する学生は後を絶ちません。
とくに入学後間もない大学1年生は、新しい環境に馴染もうとする中で、飲酒を強要されることも少なくないでしょう。
未成年者の飲酒は法律で明確に禁止されている行為です。
しかし、具体的な法的リスクや、SNSでの写真投稿による二次被害、さらには断り方や対処法まで、正確な情報を得られていない学生が多いのが現状です。
本記事では、未成年の飲酒に関する法的リスクと具体的な対処法について解説します。
飲酒を断る際の実践的なアプローチから、トラブルが発生した場合の適切な対応まで説明していきます。
未成年者(20歳未満)の飲酒は法律で禁止されている!
未成年者(20歳未満)の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法(正式名称:二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律)」によって禁止されています。
同法の第一条では、以下のように規定されています。
第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
この法律は主に「未成年者に飲酒をさせた者」を処罰するための法律です。
未成年者本人が飲酒をしても刑罰を受けることはありませんが、以下にあてはまる方は刑罰の対象となる可能性があります。
- 未成年者と知りながら酒類を提供した者
- 監護者が飲酒を容認した場合
- その場にいながら制止しなかった大人
なお、2022年4月の成人年齢引き下げにより18歳が成人となりましたが、飲酒に関しては依然として「20歳未満禁止」が継続しています。
これは、若年層の飲酒が心身に与える悪影響を考慮した結果です。
契約や選挙権といった「自己決定権」とは異なり、健康被害の観点から20歳という年齢制限が維持されているのです。
未成年者(20歳未満)の飲酒などがバレたらどうなる?
未成年者が飲酒していたことなどがバレた場合はどうなるでしょうか。
以下、想定される状況をみていきましょう。
未成年者が飲酒していた場合|罰則はないが警察の補導対象になる
未成年者飲酒禁止法は、未成年者をアルコールの悪影響から保護することを目的としているため、飲酒をした本人への罰則規定は設けられていません。
ただし警察による補導の対象となり、以下のような措置が取られる可能性があります。
- 警察署での事情聴取(飲酒の経緯や場所など)
- 保護者への通知
- 学校への連絡
学校へ連絡された場合、退学などの重い処分を受けるかもしれません。
また酒に酔ってケンカなどをして相手にけがをさせてしまった場合、未成年者でも暴行罪や傷害罪で逮捕される可能性があります。
親など監督者といた場合|監督者に責任が問われる
親権者や監督代行者が一緒にいた場合、未成年者が飲酒していた場合に制止しなくてはならないと法律で定められています。
第一条二項 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
この規定に違反した場合、1,000円以上1万円未満の金銭納付(科料)が科せられます。
一見軽い処分に思えるかもしれませんが、これは前科として記録に残る刑事罰です。
なお監督代行者とは、親権者に代わり未成年者を日ごろから監督する義務を負っている方のことで、具体的には以下の方があげられます。
- 両親に代わって弟や妹の面倒をみている同居中の兄や姉
- 親戚や知り合いの子どもを預かり、面倒をみている同居中の方
- 住み込みで従業員を雇用している雇用主の方
- 学生寮の者間など
大学の先輩や会社の上司は監督者には該当しませんが、部活動の監督や顧問が合宿先で未成年の飲酒を黙認した場合などは、監督者としての責任を問われる可能性があります。
このように、立場や状況によって監督責任の範囲は異なってきます。
未成年者がお酒を所持していた場合|警察に没収されることになる
未成年者飲酒禁止法第二条において、未成年者の酒類所持は規制されています。
満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
この法律により、未成年者が飲用目的で所持する酒類および関連器具は、行政処分により没収される可能性があります。
ほかの未成年者に飲酒を迫った場合|強要罪などが成立する可能性がある
未成年者に飲酒を強要する行為は、犯罪行為として扱われます。
具体的には、刑法第223条の強要罪が適用される可能性があり、暴行や脅迫を伴う場合は、それらの罪も加えて問われることになります。
未成年者(20歳未満)が飲酒トラブルに巻き込まれた際の4つの対処法
飲酒の誘いは、友人との集まりや祝い事の席など、さまざまなシーンで起こり得ます。
未成年者が飲酒トラブルに巻き込まれないよう、以下の対処法を知っておくことが大切です。
- お酒を飲まない理由をしっかりと伝える
- 両親や教師など身の回りの大人に相談する
- 地域の少年サポートセンターなどに相談する
- 深刻なトラブルに発展している場合は早めに弁護士に相談する
1.お酒を飲まない理由をしっかりと伝える
お酒を勧められた際は、「20歳未満には飲酒させてはいけない」という法律の存在を相手に伝えることが効果的です。
また、「部活動に支障が出る」「親との約束がある」など、自分が大切にしている理由を述べることで、相手の理解を得やすくなります。
それでも強要が続く場合は、その場を離れることも適切な選択です。
2.両親や教師など身の回りの大人に相談する
ひとりで抱え込まず、両親や教師など、信頼できる大人に相談しましょう。
経験豊富な大人からの助言により、適切な対処方法が見つかることがあります。
3.地域の少年サポートセンターに相談する
各都道府県に設置されている少年サポートセンターでは、未成年者の悩みに関する相談を受け付けています。
飲酒トラブルを保護者にも相談しづらいという場合は、こちらの窓口も活用してみてください。
専門の相談員が対応してくれるため、心理的なサポートも期待できます。
お近くの少年サポートセンターは、Googleなどの検索サイトで以下のようなキーワードにて検索すれば見つけられるでしょう。
「●●県(お住まいの都道府県名)少年サポートセンター」
4.深刻なトラブルに発展している場合は早めに弁護士に相談する
飲酒を強要され急性アルコール中毒になったり、飲酒が原因で器物損壊などの事件を起こしたりした場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
加害者への損害賠償請求や、示談交渉など、法的な対応が必要な場合は、弁護士のアドバイスを受けることが重要です。
【未成年者向け】飲酒に関するよくある質問 未成年者がもつ飲酒に関する疑問について説明します。
Q.どうして未成年者は飲酒をしてはいけないの?
20歳未満の時期は、脳や身体が著しい発達段階にあります。
この時期のアルコール摂取は、成人と比べてより深刻な影響を及ぼす可能性が高いです。
アルコールを分解する能力も未熟なため、少量の飲酒でも重大な健康被害をもたらす恐れがあるとされています。
【20歳未満がお酒を飲んではいけない主な理由】
- 脳の発達が阻害され、記憶力や学習能力の低下を引き起こす
- 肝臓などの内臓器官に重大な障害を与える可能性がある
- 成長に必要な性ホルモンの分泌バランスが崩れる可能性がある
- 若年での飲酒習慣は、将来のアルコール依存症リスクを高める
Q.飲酒が原因で停学・退学になる可能性はあるの?
未成年の飲酒は、学則違反として厳しい処分の対象となることも少なくありません。
学校によっては、未成年飲酒に対して停学処分を設けており、飲酒が原因で事故や重大なトラブルを起こした場合は、退学処分となることもあります。
このような処分は学業に重大な影響を与えるだけでなく、将来の就職活動にも支障をきたす可能性があります。
Q.ノンアルコール飲料なら未成年者でも飲んでもいいの?
ノンアルコール飲料は、アルコール度数が1%未満の商品を指し、法律上は未成年者が飲んでも違法とはなりません。
未成年がノンアルコール飲料を飲んでも、身体的な悪影響も特にないです。
しかし未成年が飲酒に関心を持つ原因になったり、将来的に依存症を引き起こすリスクを高めたりする可能性があります。
そのため酒類業界は、未成年者に対するノンアルコール飲料の販売を自主規制しているのです。
以上のことから、未成年者がノンアルコール飲料を飲むことは推奨されません。
さいごに|未成年の飲酒は絶対NG!20歳を超えてから飲むようにしよう
未成年の方が、一時の雰囲気や周囲からの圧力で「仕方なく」飲酒をしてしまうケースは少なくありません。
しかし、それによって取り返しのつかない結果を招く可能性があります。
SNSでの拡散による社会的信用の失墜、学業への影響、そして何より、成長期の身体に重大な健康被害をもたらすリスクがあります。
「みんなが飲んでいるから」「断るのが申し訳ない」という気持ちは理解できますが、自分の将来を危険にさらしてまで同調する必要はありません。
飲酒を強要されたときは、きっぱりと断る勇気を持ちましょう。
困ったときやトラブルに巻き込まれたときは、本記事で紹介した相談窓口や弁護士を活用してください。
アルコールは20歳になってから、適切な判断のもとで楽しみましょう。

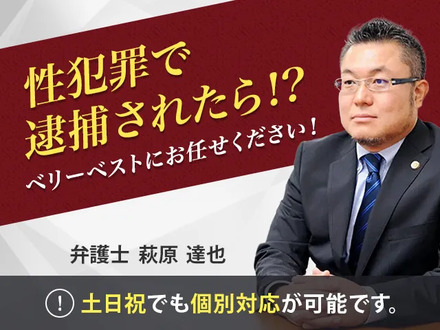
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る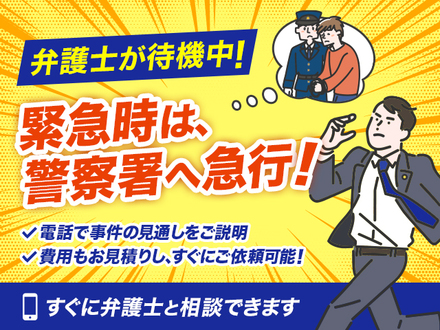
【八王子駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る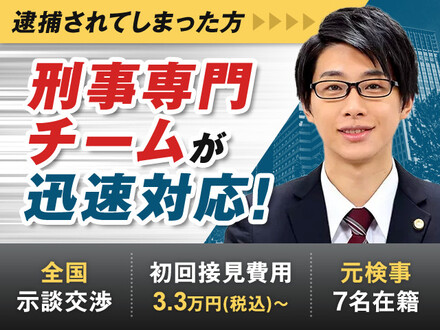
【北千住駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事処分の種類と内容に関する新着コラム
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容に関する人気コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
刑事処分の種類と内容の関連コラム
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
-
禁錮とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰で、刑務作業が義務付けられていないもののことです。この記事では懲役との違いを踏まえながら、禁錮とはどのような...
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
刑事罰には「執行猶予」という猶予期間が設けられるケースがありますが、刑事罰の最高刑である死刑においても執行猶予が付くことはあるのでしょうか? 本記...
-
少年が事件を起こした場合、少年院に入るかどうかが今後の人生を左右する分かれ目になります。本記事では、12歳未満の少年が少年院に収容される可能性につい...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
「前科は10年で消える」という情報がありますが、前科は一度ついてしまうと生涯消えることはありません。しかし、前科による不利益は時間とともに軽減されて...
刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る

















































