未成年が殺人を犯すとどうなる?刑罰の有無や年齢による手続きの違いを解説

未成年者が殺人事件を起こしたときには、少年法が適用されます。
殺人事件のような深刻な事件を起こしたケースでは、少年審判を経て検察官送致の決定が下されて、刑事裁判にかけられるリスクが高いです。
刑事裁判にかけられると懲役刑などの重い刑事罰が科されて、少年の社会復帰・更生が困難になりかねません。
本記事では、未成年者が殺人事件を起こしたときの手続きの流れや親の法的責任、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。
万が一、自分の子どもが殺人事件を起こしてしまった場合は、今すぐ弁護士へ相談して自首することを検討してください。
子どもの将来を考えると、隠したり、不誠実な対応をしてもいいことはありません。
未成年者が殺人をした場合は少年法が適用される
少年法は、20歳に満たない少年が刑事事件や刑罰法令に抵触する事件を起こしたときに適用される法律です。
20歳未満の未成年者が殺人事件を起こした場合は、少年法のルールに基づいて処分が決定されます。
成人が刑事事件を起こした場合、刑事訴訟法が適用されたうえで、厳格に刑罰法令が適用されます。
成人は自分のおこなった行為に対して自ら責任を負うべきですし、刑事責任を追及されても仕方ないからです。
一方、未成年者である少年は年齢的に未成熟なうえ、素行には普段の家庭環境・交友関係・学校などの社会環境などが強く影響しています。
このような状況で、成人と同じ刑事手続きを適用したとしても、矯正・更生・教育を達成できず、再犯に及んだり社会復帰が困難になったりしかねません。
そのため、少年が刑事事件や刑罰法令に抵触事件を起こしたときには、少年法を適用し、性格の矯正や環境の調整なども視野に入れた適切な処分が下されるのです。
未成年者の殺人に対する刑事裁判の有無は犯行時の年齢で変わる
未成年者が殺人事件を起こしたときにどのような手続きが適用されるかは、犯行当時の少年の年齢によって異なります。
具体的にどのような手続きがされるのか、犯行当時の年齢ごとに見ていきましょう。
14歳未満の場合|刑事裁判の対象にならない
刑法第41条は、刑事責任年齢を14歳と規定しています。
つまり、14歳未満については、刑罰法令に抵触する行為に及んだとしても、刑事罰を下されないということです。
殺人事件を起こした未成年者が14歳未満の少年なら、刑事訴訟法を前提とした逮捕・勾留という強制処分が下されないだけではなく、刑事裁判にかけられることもありません。
ただし、14歳未満の少年は刑事責任能力が否定されるだけで、おこなった犯罪行為に対して何の措置も下されないわけではない点に注意が必要です。
14歳未満の少年には児童福祉法が適用されたうえで福祉的な措置が下されるほか、少年審判を経たうえで少年院送致などの処分が下されます。
14~15歳の場合|刑事裁判の対象になりうる
14歳以上の少年については刑事責任能力が認められるので、少年法が適用されたうえで、事案の状況を踏まえて適切な処分が下されます。
殺人事件を起こした少年が14歳~15歳の場合には、家庭裁判所で少年審判を受けなければいけません。
家庭裁判所の判断次第では、事件が検察官に送致されて(逆送事件)、通常の刑事手続きを経て刑事裁判で最終的な判決内容が決定されます。
一方、少年審判において保護処分などが下されたときには、刑事裁判などの通常の刑事手続きを経ることなく、更生の道を歩むことになります。
16歳以上の場合|原則として刑事裁判の対象になる
殺人事件を起こした少年が16歳以上の場合には、少年法が規定する「原則逆送事件」に該当するため、原則として刑事裁判を受けなければいけません。
本来、未成年者が非行に及んだ場合、家庭裁判所が少年審判においてどのような処分を下すのかを決定できます。
ただし、16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させたときや、18歳以上の特定少年が死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁錮に該当する事件を起こしたときには、類型的に事件の悪質性が高く、更生・社会復帰を目標に掲げている少年審判の性格には馴染みません。
そこで、少年が一定の重大犯罪を起こしたときには、「原則逆送事件」として扱い、事件を受け取った家庭裁判所は、原則として検察官送致の決定をしなければいけないとされています。
ただし、家庭裁判所の調査の結果、犯行の動機や態様、犯行後の情況や少年の性格、年齢、行状および環境その他の事情を考慮して、刑事処分以外の措置が相当と判断されるときには、検察官送致ではなく少年院送致などの保護処分を下すことも例外的に可能です。
そして、16歳以上の少年が殺人事件を起こしたケースも原則逆送事件に該当するため、殺人事件を起こした未成年者は刑事裁判にかけられることになります。
14歳以上の未成年者が殺人をした場合の流れ
14歳以上の未成年者が殺人事件を起こしたときの手続きの流れを解説します。
1.逮捕
殺人事件のような重大犯罪の場合、捜査機関に発覚すると逮捕される可能性が高いです。
警察に逮捕された場合、警察署で48時間以内の取り調べが実施されます。
警察段階の取り調べにおける供述内容や供述姿勢は被疑者側が自由に決定できますが、取り調べ自体を拒否することはできません。
また、逮捕されているときには外出や外部との連絡も不可能です。
なお、理屈上は逃亡や証拠隠滅のおそれが存在しない事案は在宅事件と扱われるはずですが、殺人事件のような重大犯罪については、逮捕されることが多いです。
例外的に在宅事件として処理されるケースでは、身柄拘束をされることなく任意の事情聴取が実施されます。
2.検察へ送致
警察段階の取り調べが終了すると、被疑者の身柄は検察官に送致されます。
逮捕中の被疑者に対して実施される検察段階の取り調べには「24時間以内」という制限時間が設けられています。
警察段階の取り調べと合わせて合計72時間内に、検察官は少年が起こした殺人事件の取り調べを済ませます。
3.勾留・観護措置
未成年者が起こした殺人事件について、検察官がさらに捜査をする必要があると判断した場合、検察官が勾留請求をする可能性があります。
勾留請求が認められた場合、身柄拘束期間は10日以内の期間で延長されます。
なお、拘束期間はさらに10日間延長可能なので、合計で20日にわたって勾留される可能性があります。
ただし、少年の被疑事件については、やむを得ない場合でない限り、検察官は勾留請求をすることはできません。
そこで、未成年者が起こした殺人事件について、検察官がさらに捜査をする必要があると判断する場合は、検察官は裁判官に対して「勾留に代わる措置」を請求できるとされています。
ここでいう「勾留に代わる措置」とは、「家庭裁判所調査官の観護に付すること」や「少年鑑別所に送致すること」の2つです。
「家庭裁判所調査官の観護に付すること」が下されたときには、未成年者の身柄はすぐに釈放されます。
一方、「少年鑑別所への送致」が決定されたケースでは、原則として2週間(必要があるときには4週間まで、鑑定などの必要性があるときには8週間まで)、少年鑑別所に身柄が収容されます。
未成年が殺人事件を起こした事案については、少年鑑別所に送致される可能性が高いでしょう。
4.家庭裁判所へ送致
検察官が未成年者が起こした殺人事件についての捜査を終了し、犯罪の嫌疑があると判断したときや、家庭裁判所の審判に付すべき理由があると思料されるときには、事件が家庭裁判所に送致されます。
そして、未成年者が14歳~15歳の場合には、家庭裁判所における少年審判において、諸般の事情を総合的に考慮したうえで処分内容が決定されます。
少年審判における処分内容の種類は以下のとおりです。
- 保護処分決定(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
- 検察官送致
- 知事または児童相談所長送致
- 不処分
- 審判不開始
未成年者が起こした事件が殺人のような重大犯罪の場合については、最低でも保護処分決定が下される可能性が高いでしょう。
一方で、殺人事件を起こした未成年者が16歳以上なら、「16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させたとき」は原則逆送事件に該当するため、事件は原則として検察官に送致され、成人と同じ刑事手続きで処分内容が決定されます。
5.検察へ送致(逆送)
少年審判において検察官送致の決定が下されたときには、未成年者が起こした殺人事件は家庭裁判所から検察官に引き継がれます。
逆送の判断が下された事案については、検察官は原則として少年事件を起訴する必要があります。
6.起訴
家庭裁判所から少年事件を引き継いだ検察官が起訴処分を下します。
起訴処分とは、被疑事件を公開の刑事裁判にかける旨の訴訟行為のことです。
少年審判を経て逆送された少年事件については、原則として起訴処分を下す必要があるとされています。
7.刑事裁判
未成年者が起こした殺人事件について起訴処分が下された場合、成人が事件を起こしたときと同じように刑事裁判が開廷されます。
なお、少年事件の判決では、死刑と無期刑が緩和される点に注意が必要です。
たとえば、殺人事件を起こした未成年者が18歳未満なら、死刑をもって処断するべき事案については「無期刑」が科されます。
また、本来無期刑が下される事案では、10年以上20年以下の範囲での有期懲役または有期禁錮の判決を下すことも可能です。
14歳未満の未成年者が殺人をした場合の流れ
殺人事件を起こした未成年者が14歳未満だったときの手続きの流れについて解説します。
1.補導・触法調査
14歳未満は刑事責任能力が認められないので、逮捕・勾留などの強制処分を下されたり刑事裁判にかけられたりすることはありません。
ただし、「14歳未満だからどのような非行に及んでも何の措置も採られない」というわけではない点に注意が必要です。
まず、14歳未満の触法少年が事件を起こしたときには、少年警察活動規則に基づいて「補導」がおこなわれて、触法調査が実施されます。
触法調査では、刑事訴訟法に基づく逮捕・勾留とは異なり、強制的に身柄が拘束されることはありません。
あくまでも任意をベースに、触法少年に対して氏名・年齢・家族関係・交友関係・事件を起こした経緯や理由などが質問されます。
なお、被疑者が14歳未満であると判明する前に現行犯逮捕されたようなケースでは、取り調べの過程で触法少年であることが判明した時点で釈放されます。
2.児童相談所へ送致
警察が触法少年に対する触法調査を終えると、捜査機関が児童相談所長に少年事件について通告をおこないます。
児童相談所では、14歳未満の未成年者に対してさまざま質問を実施したうえで、以下のいずれかの措置が下されます。
- 児童またはその保護者に訓戒を加える
- 児童またはその保護者に誓約書を提出させる
- 児童福祉司、知的障害者福祉司、児童委員などによる指導を受けさせる(児童相談所や自宅などで)
- 小規模住居型児童養育事業者や里親に委託する
- 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所させる
- 家庭裁判所に送致する
3.家庭裁判所へ送致
14歳未満の未成年者が起こした事件が殺人事件のような重大犯罪である場合、福祉的措置が下される可能性は極めて低いでしょう。
そのため、児童相談所は家庭裁判所送致の判断を下して、事件・身柄は家庭裁判所に引き継がれます。
4.少年審判
14歳未満の未成年者が起こした殺人事件を送致された家庭裁判所は、観護措置を下したうえで、少年審判を開くべきか否かを判断します。
少年審判の開始が決定された場合は、触法少年および保護者、付添人が出廷したうえで、保護処分などの最終的な処分内容が決定されます。
なお、14歳未満の触法少年には刑事責任能力が存在しないため、検察官送致決定が下されることはありません。
未成年の殺人に関するよくある質問
さいごに、未成年者の殺人事件についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
Q.未成年が殺人をすると実名報道される?
成人が刑事事件を起こしたとき、実名報道されるか否かについては報道機関の裁量次第です。
事件の悪質性や社会的注目度などの事情が総合的に考慮されたうえで、報道各社の判断でニュースになるかが決まります。
一方、少年事件の実名報道については以下の規定が置かれている点に注意が必要です。
第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
引用元:少年法|e-Gov法令検索
なお、特定少年(18歳以上の未成年者)が公訴提起されたときには、少年を特定できるような情報・写真を報道することが可能です。
Q.殺人に及んだ未成年者の親に責任は生じる?
まず、未成年者が殺人事件を起こしたとしても、親自身が刑事責任を問われる可能性は極めて低いです。
親が未成年者を教唆・幇助していたり、間接正犯が成立するような特殊な事情が存在したりする場合に限って、例外的に刑事責任を問われるリスクが生じます。
一方、殺人事件を起こした未成年者の親の民事責任については注意をしなければいけません。
というのも、民法上は不法行為に基づく損害賠償責任について以下のルールが定められているからです。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。引用元:民法|e-Gov法令検索
つまり、殺人事件を起こした未成年者が自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えておらず、民法上の賠償責任が認められないときには、未成年者の監督義務者が損害賠償責任を負うということです。
また、殺人事件を起こした未成年者が事理弁識能力を備えており、少年本人が不法行為に基づく損害賠償責任を負担する場合であったとしても、親自身について民法第709条の一般不法行為責任が成立するときには、損害賠償請求に応じなければいけません。
Q.未成年が殺人事件を起こした場合は前科が付くのか?
前科とは、刑罰を受けた経歴のことです。
この定義に基づくと、未成年者が殺人事件を起こした場合において、検察官送致を経て刑事裁判で有罪判決が確定したときには、前科が付くことになります。
一方、少年審判で少年院送致などの保護処分決定が下されたときには、前科は付きません。
Q.未成年が殺人事件を起こしたときでも弁護士に相談したほうがよいのか?
未成年者が殺人事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼をしたほうがよいでしょう。
刑事事件や少年事件を得意とする弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。
- 警察や検察で実施される取り調べや触法調査での回答方法についてアドバイスを期待できる
- 逮捕・勾留されたときでもできるだけ早期の身柄釈放を目指して捜査機関に働きかけをしてくれる
- 少年院送致や懲役刑などの重い処分・判決を回避するために、少年審判や刑事裁判で役立つ情状証拠をそろえてくれる
- 被害者との間で早期に示談交渉を開始してくれる
- 社会復帰や更生を実現しやすい環境の整備方法についてアドバイスを提供してくれる
未成年者であったとしても、殺人事件のような重大犯罪を起こすと、重い処分・判決が下される可能性が高いです。
弁護士が介入するタイミングが早いほど少年にとって有利な状況を作りやすくなるでしょう。
なお、自分の子どもが殺人事件を起こしてしまったことがわかったら、罪に対する防御活動よりもまずは自首することを検討してください。
結果的に審理や裁判で有利に働く可能性もあるため、自首についても弁護士へ相談してみましょう。
さいごに|未成年者の殺人事件は少年事件が得意な弁護士に相談を
未成年者が殺人事件を起こした場合、少年院送致のような重い保護処分に留まらず、検察官送致を経て刑事裁判で有罪判決が下される可能性が高いです。
殺人は非常に重い罪であるため、責任から逃れることはできません。
万が一、お子さんが殺人事件に関与してしまった場合はすぐに弁護士へ相談し、自首することを検討してください。
ベンナビ刑事事件では、少年事件を数多く取り扱う弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる私選弁護人・弁護士までお問い合わせください。


【初回面談30分無料】【元検事の弁護士が在籍】刑事事件の対応実績豊富な弁護士が、依頼者様に寄り添います。早期釈放を通じた社会復帰のことも考えた対応を大切に、最後までサポート。ぜひお早めにご相談ください。
事務所詳細を見る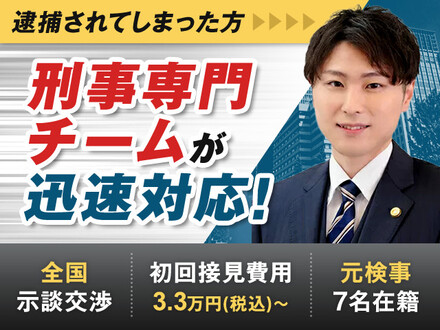
【銀座駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る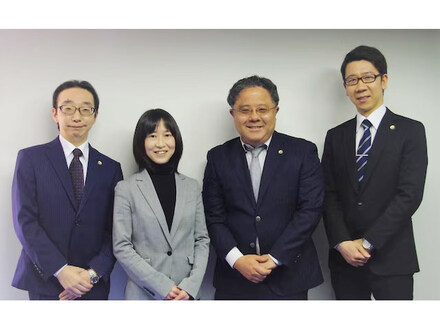
【警察から連絡がきた/被害届を出された方/刑事告訴を受けた方へ】痴漢・盗撮/万引き/人身事故・交通違反/暴行など幅広いお悩みに豊富な実績◆少年事件もお任せください◆迅速対応で刑事処分回避に向けてサポート【女性弁護士も在籍】東京・大阪に事務所あり
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



殺人事件を起こしたらに関する新着コラム
-
未成年者が殺人事件を起こしたときには、少年法が適用されます。本記事では、未成年者が殺人事件を起こしたときの手続きの流れや親の法的責任、弁護士に相談・...
-
本記事では、人を殺してしまったときに適用される可能性がある犯罪類型や法定刑、私選弁護人に相談・依頼をするメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
殺人で逮捕され、刑事裁判にて有罪判決が下されると、死刑や無期懲役などの罰則が科せられる可能性があります。ただし、中には正当防衛として扱われるケースや...
-
殺人未遂で逮捕・起訴される構成要件と量刑が決まるポイント、減刑となる基準などを解説します。刑法第203条で殺人未遂罪が成立する最も重要な条件は、『殺...
-
過失致死(かしつちし)とは、殺害の意志がない状態(過失)で相手を死亡させてしまうことを言います。
-
殺人未遂罪でも刑罰が軽くなれば、執行猶予を受けられる可能性があります。執行猶予を獲得するためには、殺意がないことの証明が最も重要になるでしょう。
-
殺人未遂罪による公訴時効は25年ですが、事件について起訴をされると時効が停止します。今回は殺人未遂事件における時効期間と時効停止の基準について解説し...
-
殺人未遂罪による量刑の相場は3年~15年が一般的だとされていますが、未遂罪による減免が考慮されるため比較的軽い量刑になる可能性も高くなります。
-
殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪で、刑法第199条では「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
殺人事件を起こしたらに関する人気コラム
-
過失致死(かしつちし)とは、殺害の意志がない状態(過失)で相手を死亡させてしまうことを言います。
-
殺人未遂で逮捕・起訴される構成要件と量刑が決まるポイント、減刑となる基準などを解説します。刑法第203条で殺人未遂罪が成立する最も重要な条件は、『殺...
-
殺人未遂罪による量刑の相場は3年~15年が一般的だとされていますが、未遂罪による減免が考慮されるため比較的軽い量刑になる可能性も高くなります。
-
殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪で、刑法第199条では「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
-
殺人未遂罪による公訴時効は25年ですが、事件について起訴をされると時効が停止します。今回は殺人未遂事件における時効期間と時効停止の基準について解説し...
-
殺人未遂罪でも刑罰が軽くなれば、執行猶予を受けられる可能性があります。執行猶予を獲得するためには、殺意がないことの証明が最も重要になるでしょう。
-
殺人で逮捕され、刑事裁判にて有罪判決が下されると、死刑や無期懲役などの罰則が科せられる可能性があります。ただし、中には正当防衛として扱われるケースや...
-
未成年者が殺人事件を起こしたときには、少年法が適用されます。本記事では、未成年者が殺人事件を起こしたときの手続きの流れや親の法的責任、弁護士に相談・...
-
本記事では、人を殺してしまったときに適用される可能性がある犯罪類型や法定刑、私選弁護人に相談・依頼をするメリットなどについてわかりやすく解説します。
殺人事件を起こしたらの関連コラム
-
殺人で逮捕され、刑事裁判にて有罪判決が下されると、死刑や無期懲役などの罰則が科せられる可能性があります。ただし、中には正当防衛として扱われるケースや...
-
殺人未遂罪でも刑罰が軽くなれば、執行猶予を受けられる可能性があります。執行猶予を獲得するためには、殺意がないことの証明が最も重要になるでしょう。
-
本記事では、人を殺してしまったときに適用される可能性がある犯罪類型や法定刑、私選弁護人に相談・依頼をするメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
殺人未遂罪による公訴時効は25年ですが、事件について起訴をされると時効が停止します。今回は殺人未遂事件における時効期間と時効停止の基準について解説し...
-
過失致死(かしつちし)とは、殺害の意志がない状態(過失)で相手を死亡させてしまうことを言います。
-
未成年者が殺人事件を起こしたときには、少年法が適用されます。本記事では、未成年者が殺人事件を起こしたときの手続きの流れや親の法的責任、弁護士に相談・...
-
殺人未遂で逮捕・起訴される構成要件と量刑が決まるポイント、減刑となる基準などを解説します。刑法第203条で殺人未遂罪が成立する最も重要な条件は、『殺...
-
殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪で、刑法第199条では「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
-
殺人未遂罪による量刑の相場は3年~15年が一般的だとされていますが、未遂罪による減免が考慮されるため比較的軽い量刑になる可能性も高くなります。
殺人事件を起こしたらコラム一覧へ戻る






































