控訴と上告の違いをわかりやすく解説!どんなときにできる?刑事・民事でどう違う?

控訴と上告は、どちらも判決に納得がいかない場合の不服申立て手段です。
ただ、両者の違いを正確に説明できる人は少ないのではないでしょうか。
本記事では、控訴と上告の違いをわかりやすく解説し、それぞれどんな場面で使われるのかを説明します。
また、抗告などの似たような手続きとの違いについても触れているので、ぜひ参考にしてくだい。
控訴と上告の違い
控訴と上告とでは、主に次の2点が大きく異なります。
- 何回目の裁判に対する不服申立てなのか
- 認められる理由
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
何回目の裁判に対する不服申立てかが違う
控訴と上告の1つ目の違いは、「何回目の裁判に対する不服申立てなのか」という点です。
日本の裁判制度では、誤った判断が下されるリスクを減らすために三審制が採用されています。
三審制において、訴訟の審理は「第一審→第二審→第三審」の最大3段階でおこなわれ、第一審・第二審の段階では判決に対する不服申立てが可能です。
そして、第一審に対する不服申立てを控訴、第二審に対する不服申立てを上告と呼びます。
つまり、控訴は「第一審→第二審」に進む手続きで、上告は「第二審→第三審」に進む手続きといえるでしょう。
認められる理由が違う
控訴と上告の2つ目の違いは、「どのような理由で認められるのか」という点です。
控訴は比較的幅広い理由で認められるのに対して、上告は裁判の判断や手続きに重大なミスがあった場合などに限り認められます。
控訴と上告の共通点
控訴と上告はそれぞれ異なる制度ですが、主に次の3点が共通しています。
- 申立てできる人
- 申立てができる期限
- 申立てから判決までの流れ
各共通点について、以下で詳しく解説します。
申立てできる人
控訴と上告のひとつ目の共通点は、「申立てできる人」です。
控訴も上告も、判決に不服のある当事者であれば申立てることができます。
具体的には、以下のような人物を指します。
- 民事事件:原告、被告または訴訟に利害関係のある第三者
- 刑事事件:被告人または検察官
申立てができる期限
控訴と上告の2つ目の共通点は、「申立てができる期限」です。
いずれも、申立て期限は起算日から起算して2週間(14日間)に設定されています。
申立てから判決までの流れ
控訴と上告の3つ目の共通点は、「申立てから判決までの流れ」です。
控訴や上告を申立てたあとは、以下のような流れで手続きが進みます。
- 控訴申立書または上告申立書の提出
- 控訴趣意書または上告趣意書の提出期限の指定
- 控訴趣意書または上告趣意書の提出
- 控訴審または上告審での審理
- 判決の言い渡し
控訴と上告の刑事事件と民事事件における違い
控訴や上告の手続きや要件は、取り扱う事件が民事事件か刑事事件かで異なります。
民事事件と刑事事件における控訴と上告の違いについて、以下で詳しくみていきましょう。
刑事と民事における控訴の違い
刑事事件と民事事件の控訴手続きで異なるのは、主に次の4点です。
- 申立先
- 控訴期間の起算日
- 控訴理由
- 弁論ができる人
以下、違いを表にまとめました。
|
違い |
刑事事件 |
民事事件 |
|---|---|---|
|
申立先 |
高等裁判所 |
第一審が地方裁判所の場合 →高等裁判所 第一審が簡易裁判所の場合 →地方裁判所 |
|
控訴期間の起算日 |
判決の言渡し日の翌日 |
判決書または判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書の送達を受けた日の翌日 |
|
控訴理由 |
① 以下の事由があるとき ② 以下の事由があるとき ③ ①②のほか、訴訟手続きに法令の違反があって、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるとき ④ 法令の適用に誤りがあって、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるとき ⑤ 刑の量定が不当であるとき ⑥ 事実の誤認があって、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであるとき ⑦ 以下の事由があるとき |
限定されていない |
|
弁論ができる人 |
・検察官 ・弁護人 (※被告人本人の弁論は不可) |
・両当事者 ・代理人弁護士 |
それぞれのポイントについて、詳しくみていきましょう。
刑事の場合は必ず高等裁判所
刑事事件における控訴は、必ず高等裁判所に対しておこなわれます。
民事事件と異なり、第一審が簡易裁判所であっても、控訴の提起先は必ず高等裁判所となるのです。
控訴審を担当する高等裁判所は第一審を担当した裁判所の所在地に応じて決まります。
どの高等裁判所が管轄するかは、裁判所の公式Webサイトで確認できます。
控訴期間は、民事事件でも刑事事件でも14日間(2週間)ですが、それぞれ起算日が以下のように異なります。
- 民事事件:判決書の送達を受けた日、または判決が言い渡された口頭弁論期日の調書が送達された日の翌日
- 刑事事件:判決の言い渡しがあった日の翌日
民事事件では、控訴期間は判決の送達日から起算されます。
そのため、控訴を検討している場合、検討期間を少しでも長く確保するために、法廷で判決内容だけを聞いてあえて判決文を受け取らないという対応が取られることもあるのです。
なお、民事事件では、控訴期間の最終日が土日祝日や年末年始にあたる場合、翌営業日に期限が延長されます。
しかし、刑事事件では控訴期間は14日間固定で、延長は認められません。
民事の場合、控訴理由に限定はない
刑事事件と異なり、民事事件における控訴理由は限定されていません。
そのため、第一審判決を取消または変更したい場合、どのような理由であっても基本的には控訴が認められます。
刑事事件では、被告人本人が弁論することはない
刑事事件の控訴審では、被告人本人が直接弁論をおこなえません。
検察官と弁護人がそれぞれの立場から弁論をおこない、裁判所は弁論の内容を基に判決を下します。
民事と刑事における上告の違い
刑事事件と民事事件の上告手続きで異なるのは、主に次の3点です。
- 申立先
- 上告期間の起算日
- 上告理由
以下、違いを表にまとめました。
|
違い |
刑事事件 |
民事事件 |
|---|---|---|
|
申立先 |
最高裁判所 |
・第二審が高等裁判所の場合 →最高裁判所 ・ 第二審が地方裁判所の場合 →高等裁判所 |
|
上告期間の起算日 |
判決の言渡し日の翌日 |
判決書または判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書の送達を受けた日の翌日 |
|
上告理由 |
①判決憲法の違反があるとき、または憲法の解釈に誤りがあるとき ②最高裁判所の判例と相反する判断をしたとき ③最高裁判所の判例がない場合に、大審院もしくは上告裁判所たる高等裁判所の判例、または刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたとき |
①判決憲法の違反があるとき、または憲法の解釈に誤りがあるとき ②法律に従って判決裁判所を構成しなかったとき ③法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したとき ④日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したとき ⑤専属管轄に関する規定に違反したとき ⑥法定代理権、訴訟代理権、代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたとき ⑦口頭弁論の公開の規定に違反したとき ⑧判決に理由を付せず、理由に食い違いがあるとき ⑨(高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき |
控訴や上告と関連する言葉との違い
ここからは、控訴や上告などと似た以下の用語について解説します。
- 上訴
- 抗告
- 跳躍上告
上訴とは|控訴も上告も含まれる
上訴とは、裁判の判決に納得がいかない場合に、裁判が確定する前に上級の裁判所に不服を申立て、判決の変更や取り消しを求めることを総称した手続きをいいます。
控訴や上告は、上訴の一種です。
また、次に紹介する抗告も、上訴に含まれます。
抗告とは|判決ではなく決定に対する不服申立て
控訴や上告は、いずれも「判決」に対する不服申立てですが、抗告は「決定」に対する不服申立てをいいます。
決定とは、判決と異なり口頭弁論を開かずにおこなわれる裁判で決まった事柄のことです。
たとえば、第一審の裁判所が下した勾留や保釈、押収などが該当します。
なお、勾留・保釈・押収に対しては「準抗告」ができる場合もあります。
準抗告は、起訴前や第一回公判の前に裁判官がおこなった判断や、捜査機関による接見・押収などの処分に対する異議申立てをいいます。
跳躍上告とは|控訴を飛ばして最高裁に訴えること
跳躍上告とは、刑事事件において第一審の裁判所が下した判決に対し、控訴を経ずに直接最高裁判所へ上告する手続きをいいます。
通常、第一審の判決に不服がある場合は、まず控訴をおこない、第二審で審理を受けたあとに上告するのが一般的な流れです。
しかし、跳躍上告では例外的に控訴を省略し、いきなり最高裁判所の判断を仰ぐことができます。
跳躍上告が認められる背景には、法律の適用や運用における混乱を防ぐという目的があります。
憲法違反に関する問題や法律解釈の相違が生じた場合、そのまま控訴審を経て通常の手続きを踏んでいては、最終的な判断が確定するまでに時間がかかり、その間に不統一な解釈や混乱が生じる可能性があります。
そのため、法の安定性を保ちつつ、できるだけ早く最高裁判所の最終判断を示すために、控訴審を飛び越えて直接最高裁判所が判断を下す仕組みが設けられているのです。
跳躍上告が認められるのは、以下のような場合に限られます。
単に「判決内容に不満がある」という理由だけでは跳躍上告は認められません。
- 法律・命令・規則・処分が憲法に違反すると判断された場合
- 地方公共団体の条例や規則が法律に違反すると判断された場合
なお、民事事件においては、同様の制度を「飛躍上告」と呼びます。
刑事事件における跳躍上告と目的は同じで、重要な法律問題について迅速に最高裁判所の判断を仰ぐための制度です。
さいごに
控訴と上告も、いずれも裁判の判決に不服を申立てる手続きです。
ただし、控訴は第一審判決に対する不服申立てで、上告は第二審判決に対する不服申立てという点で異なります。
また、控訴は幅広い理由で認められますが、上告は裁判の判断や手続きに重大なミスがあった場合にしか認められません。
そのほかにも、刑事事件と民事事件とでは、申立先や申立て理由、申立て期間の起算日などが異なります。
両者の共通点や違いを把握して、万が一の際に適切な対応を取れるようになりましょう。


【初回相談料1時間1.1万円(逮捕されている場合等は無料)|弁護士直通TEL|夜間・休日◎】無罪を獲得した実績◎早期の身柄釈放を第一に!性犯罪/痴漢・盗撮/暴行傷害事件など元検事の弁護士に相談が◎今何をすべきか明確にご提示します
事務所詳細を見る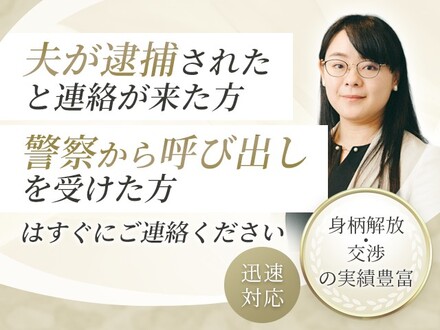
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る
検事の経験を持つ弁護士が窃盗・万引き/少年事件/性犯罪など幅広い刑事事件に対応◆『警察の呼び出しを受けている』『ご家族が逮捕された』はすぐご相談を◆フットワークの軽さを活かした迅速対応【即日接見も◎】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事処分の種類と内容に関する新着コラム
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容に関する人気コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
刑事処分の種類と内容の関連コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
釈放は、簡単に言えば「人身の拘束が解かれて自由の身になれること」ですが、刑事事件では保釈や仮釈放など似たような制度があります。この記事では釈放を目指...
-
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ...
-
「前科は10年で消える」という情報がありますが、前科は一度ついてしまうと生涯消えることはありません。しかし、前科による不利益は時間とともに軽減されて...
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
前科がつくことによるデメリットは、仕事や結婚など社会生活に影響を及ぼす点です。この記事では、前科の意味を説明した上で、前科がつくことによる具体的なデ...
-
禁錮とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰で、刑務作業が義務付けられていないもののことです。この記事では懲役との違いを踏まえながら、禁錮とはどのような...
-
本記事では、財産刑と呼ばれる罰金と科料について知りたい方に向けて、罰金と科料の違いや対象となる犯罪、罰金や科料に関して実務上のポイント、罰金や科料の...
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
未成年者の飲酒は法律で禁止されており、20歳未満はお酒を飲むことはできません。2022年4月から成人年齢は18歳になりましたが、飲酒は20歳からです...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る





















































