未成年者の飲酒に関連する法律とは?成年年齢は18歳でもお酒は20歳のまま!

2022年4月の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒に関する年齢制限は20歳未満のまま維持されています。
しかし、「成人とされる年齢」と「飲酒が許可される年齢」の違いを正しく理解できていない人も少なくありません。
とくに大学生活をはじめとする飲酒を伴う交流の機会が増える中で、18歳、19歳の飲酒に関する法的な取り扱いについて正確な理解が求められています。
そこで本記事では、未成年飲酒に関する法規制について詳しく解説します。
ノンアルコールは許されるのかなど、未成年が飲酒を禁止されている「酒類」の定義にも触れているので、最後まで目を通してみてください。
未成年者の飲酒に関連する3つの法律とそれぞれの内容
未成年者の飲酒は主に3つの法律によって規制されています。
未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、そして酒税法です。
それぞれ異なる側面から未成年者の飲酒を規制し、違反した場合の罰則を定めているので詳しくみていきましょう。
1.未成年者飲酒禁止法|未成年者の飲酒の禁止と営業者等の罰則について規定している
未成年者飲酒禁止法は、20歳未満の者の飲酒を全面的に禁止する法律です。
正式な名称は「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」であり、未成年者自身の飲酒行為の禁止に加え、親権者による監督責任や、営業者による提供制限まで幅広く規定されています。
ただし、未成年の飲酒に対する罰則は定められていません。
未成年が飲酒した場合は、基本的に周囲の大人や店舗側が罰せられることになります。
営業者には年齢確認の義務が課せられており、未成年者の飲酒を防止するための具体的な措置として、禁止表示の掲示やスタッフへの教育が求められています。
これらの規定に違反した場合、50万円以下の罰金が科され、接客担当者や店舗経営者が処罰の対象となります。
|
内容 |
罰則 |
|
20歳未満の人は飲酒してはならない |
罰則規定なし(制止・指導の対象) |
|
親・監督代行者は未成年者の飲酒を知った場合に制止しなければならない |
科料(1,000円以上1万円未満の軽微な金銭制裁) |
|
営業者は20歳未満の人が飲酒することを知りながら酒類を提供してはならない |
50万円以下の罰金 |
|
営業者は20歳未満の人の飲酒防止のために年齢確認などの措置を講じなければならない |
50万円以下の罰金 |
2.風営法|居酒屋などの店舗で未成年者に酒類を提供してはならない旨を規定している
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では、接待飲食等営業をおこなう店舗における未成年者への酒類提供を規制しています。
風営法の対象となるのは、居酒屋・バー・キャバクラ・スナックなどです。
規制対象の店舗が未成年に酒類を提供した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処される可能性があります。
3.酒税法|上記の法律に違反し罰金刑を受けた店の免許は取り消される旨を規定している
酒税法では、未成年者飲酒禁止法や風営法に違反した場合の行政処分について定めています。
具体的には、20歳未満の者が飲用することを知って酒類を販売もしくは提供し、これらの法律により罰金刑に処された場合、税務署長は酒類販売業者の免許を取り消すことができると規定しています。
酒税法によって規定されている「酒類」の定義|ノンアルコールは飲める?
未成年の飲酒は法規制があると理解しつつも、ノンアルコールなら問題ないのではないかと考える人もいるでしょう。
ここでは、未成年の飲酒が法律で禁止されている「酒類」の定義を解説します。
1.アルコール分1%以上の飲料は酒類であるため飲めない
酒税法では、アルコール分1%以上の飲料を「酒類」と定めています。
水などで薄めることでアルコール分1%以上となる飲料や、粉末状で溶解するとアルコール分1%以上となるものも含まれます。
なお、医薬品や工業用アルコールなど、特定用途のものは除外されています。
2.ノンアルコール飲料は法律上飲めるものの推奨されてはいない
ノンアルコール飲料は法律上の規制対象ではありませんが、そもそも未成年者の購入を想定していません。
酒類の広告審査委員会の自主基準では、ノンアルコール飲料を「満20歳以上の者の飲用を想定・推奨している」と定義しています。
アルコールの味に慣れてしまうことで、飲酒への興味が誘発され、将来的に依存症を引き起こす可能性があるためです。
実際、小売業者に対しては、ノンアルコール飲料についても酒類と同様に区分して陳列し、年齢確認したうえで販売するよう指導されています。
法律で飲酒が禁止されている年齢は20歳未満!18歳・19歳の飲酒はNG
2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒に関する年齢制限は変更されていません。
つまり、18歳で成人となっても、20歳になるまでは飲酒することができません。
ここからは、飲酒が禁止される年齢について詳しくみていきましょう。
1.2022年の民法改正により18歳以上が成人になった
2022年4月1日の民法改正により、成人年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
これにより、18歳から親の同意なく契約を結んだり、クレジットカードを作ったりすることが可能になりました。
しかし、これまで20歳で線引きされていたものが、一律に18歳へと引き下がったわけではありません。
健康面や非行防止などの観点から、一部の年齢制限は20歳のまま維持されています。
2.未成年者飲酒禁止法も改正されて20歳未満の飲酒禁止が明確になった
成人年齢の引き下げに合わせ、未成年者飲酒禁止法は「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」と変更され、条文内にある「満二十年ニ至ラザル者」の表現も「二十歳未満ノ者」に改められました。
成人年齢の引き下げ後も、20歳未満の者の飲酒を法律で規制していることを明確にするためです。
しかし、飲酒できる年齢について正しく理解されていないケースも散見されるため、関係機関は酒類小売業界などに対して周知徹底を図り、年齢確認の実施など、20歳未満の者の飲酒防止に向けた取り組みを要請しています。
未成年者の飲酒が法律で禁止されている代表的な3つの理由
未成年者の飲酒は、法律によって厳しく規制されていますが、これは単なる慣習ではありません。
科学的な根拠に基づいた重要な理由があります。
未成年者の飲酒が禁止されている主な3つの理由は以下のとおりです。
- 身体の成長に悪影響を及ぼす可能性がある
- アルコール依存症を引き起こすリスクが高まる
- 交通事故やトラブルなどを引き起こしやすくなる
1.身体の成長に悪影響を及ぼす可能性がある
成長期にある未成年者の身体は、アルコールに対して敏感に反応します。
なかでも最も深刻なのが、脳の発達への影響です。
飲酒によって学習能力や集中力が低下するだけでなく、脳の正常な発達が妨げられる可能性があります。
また、未成年者の肝臓は、アルコールを分解する能力が十分に発達していません。
そのため、体内に入ったアルコールの処理が追いつかず、さまざまな臓器に大きな負担がかかってしまいます。
大人と比べても、その影響ははるかに大きいといえます。
さらに、性ホルモンへの影響も大きいです。
成長期は性ホルモンの分泌が活発な時期であり、アルコールによってそのバランスが乱れると、生殖機能の正常な発達が妨げられる可能性があります。
成年者の飲酒は、心身の健全な発達を脅かす危険性をはらんでいるのです。
2.アルコール依存症を引き起こすリスクが高まる
早期からの飲酒開始は、アルコール依存症のリスクを著しく高めます。
とくに15歳以下で飲酒を始めた場合、20歳以降に開始した場合と比べて依存症になる確率が3倍以上に上昇するとされています。
アルコール依存症になると、震えや不眠、集中力低下などの身体症状が現れ、日常生活に支障をきたしかねません。
また、社会生活や人間関係にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
3.交通事故やトラブルなどを引き起こしやすくなる
アルコールには、思考力や自制心といった脳の働きを鈍らせ、運動機能を低下させる作用があります。
その結果、転落事故や水難事故、交通事故など、命に関わる重大な事故を引き起こす危険性が高まります。
とくに未成年者は、アルコールに対する感受性が強いといわれています。
少量の飲酒でも判断力が著しく低下し、感情が高ぶりやすくなるため、暴力行為に及んだり、危険な性行為によって予期せぬ妊娠や性感染症のリスクが高まったりします。
このように、未成年者の飲酒は重大な事故や取り返しのつかない問題行動につながる可能性が極めて高いのです。
さいごに|未成年者の飲酒は「しない」「させない」を徹底しよう!
本記事では、未成年者の飲酒に関する法的規制と、その規制がある理由について詳しく解説してきました。
2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒は20歳まで法律で禁止されています。
これは、未成年者の心身の健康を守り、重大な事故やトラブルを防ぐための重要な法規制です。
飲酒に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合は、ひとりで抱え込まず、弁護士に相談することをおすすめします。

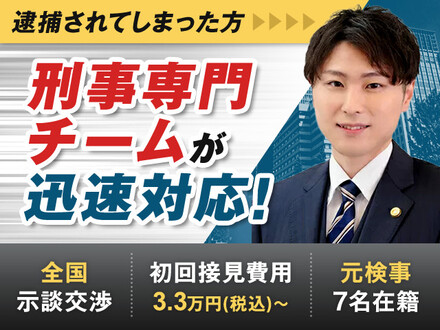
【銀座駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る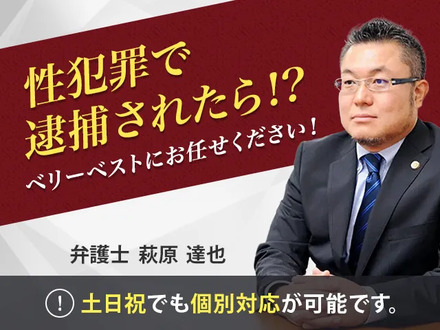
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る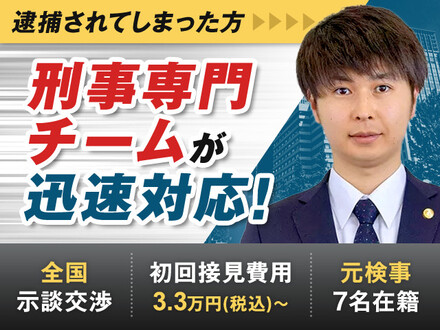
【町田駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事処分の種類と内容に関する新着コラム
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容に関する人気コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
刑事処分の種類と内容の関連コラム
-
「前科は10年で消える」という情報がありますが、前科は一度ついてしまうと生涯消えることはありません。しかし、前科による不利益は時間とともに軽減されて...
-
未成年者への酒類提供は、店舗だけでなく提供した従業員個人も刑事罰や行政処分の対象となる可能性があります。本記事では、具体的な罰則内容や、裁判例を交え...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
「不起訴はいつわかるのか」という疑問を抱いている方向けに、この記事では不起訴がわかるタイミングについてくわしく解説しています。身柄事件の場合、最大で...
-
情状酌量とは、裁判所で刑を確定する際に、被告人が犯罪を犯すまでの背景をくみとった上で、刑を軽くすることを指します。「情状酌量の余地なし」と判断される...
-
大人であっても保護観察処分になることはあります。しかし、大人の保護観察処分が具体的にどのようなものなのかイメージできない人も多いはずです。本記事では...
-
偽計業務妨害罪は身近にある犯罪であり、実際に自身の行為が該当するのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、偽計業務妨害...
-
刑事罰には「執行猶予」という猶予期間が設けられるケースがありますが、刑事罰の最高刑である死刑においても執行猶予が付くことはあるのでしょうか? 本記...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る




















































