処断刑とは?刑罰の決め方と量刑のポイントをわかりやすく解説

- 「処断刑ってそもそも何?」
- 「法定刑や量刑などとはどう違うの?」
刑罰について調べていると、「量刑」や「法定刑」などさまざまな言葉が登場するので、違いがわからずに困惑している方もいるのではないでしょうか。
実際に、刑事事件の判決ではさまざまな「刑」が用いられるため、それぞれの違いや決まり方をおさえて、しっかりと理解しておくことが重要です。
本記事では、処断刑の定義や関連用語との違いを詳しく解説します。
刑罰の決まり方を体系的に理解するのに役立ててください。
処断刑とは|法定刑にもとづき、必要に応じ刑の加重・減軽をして導き出した刑
処断刑とは、法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をして決定される刑罰をいいます。
法定刑とは、特定の罪を犯した場合の刑罰です。
たとえば、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
この法定刑に、法律上または裁判上の加重・減軽事由を考慮して、処断刑が決まります。
処断刑と量刑・法定刑・宣告刑の違い
処断刑を理解するにあたっては、量刑・法定刑・宣告刑などの関連用語の理解が欠かせません。
それぞれの意味を以下にまとめているので、違いをしっかりと理解しましょう。
| 量刑とは | 被告人に対してどの程度の刑罰が適切かを決める作業 |
| 法定刑とは | 特定の犯罪に対して定められている刑の範囲 |
| 処断刑とは | 法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽を考慮して決められる刑罰 |
| 宣告刑とは | 裁判官が最終的に言い渡す刑罰 |
処断刑の決まり方・計算方法
ここでは、処断刑を決める際に考慮される、4つの加重・減軽事由について解説します。
1.再犯加重が考慮される
処断刑を決めるにあたっては、再犯加重が考慮される場合があります。
再犯加重とは、過去に懲役刑の実刑を受けた人が、刑の執行を終えたあと5年以内に新たな罪を犯した場合に適用されるものです。
再犯加重に該当すれば、懲役刑が2倍に引き上げられます。
たとえば、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、再犯加重が考慮される場合、懲役刑が「30年以下」に引き上げられるのです。
2.法律で定められた減刑が考慮される
以下のように法律上刑を軽くするべき特別な事情がある場合、刑の減軽が認められます。
- 犯行時に心神耗弱(判断能力の著しい低下)の状態であった場合
- 従犯(補助的な立場で犯罪に関与した者)であった場合
刑の減軽が認められると、有期懲役刑と罰金刑の上限がそれぞれ2分の1に引き下げられます。
たとえば、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、刑の減軽が認められる場合、懲役刑が「7年6ヵ月以下」、罰金刑が「25万円以下」となります。
3.併合罪によって加重される
複数の罪を犯した場合、それぞれの罪を個別に処罰するのではなく、ひとつの刑として扱うことがあります。
これを「併合罪」といいます。
併合罪が適用されると、懲役刑の上限は、基本的に最も重い罪の刑の1.5倍に引き上げられます。
なお、罰金刑の上限は、各罪の罰金額の合計になります。
たとえば、窃盗罪と傷害罪の両方を犯した場合、それぞれ以下の法定刑に基づいてより重い傷害罪の法定刑が基準となり、懲役刑の上限は「22年6ヵ月」、罰金刑の上限は100万円となります。
- 窃盗罪:10年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 傷害罪:15年以下の懲役または50万円以下の罰金
4.情状酌量による減刑が検討される
酌量減軽とは、罪を犯した事情を考慮し、情状を汲むべき事由がある場合に、刑を軽くすることができる制度です。
「裁判上の減軽」とも呼ばれます。
裁判官が刑を減軽するかどうかを判断する際には、さまざまな事情が考慮されます。
たとえば、被害者と示談が成立し、被害者自身が加害者を処罰しなくてもよいと考えている状態は、情状酌量すべき事由の代表例です。
刑の減軽が認められると、有機懲役刑と罰金刑の上限がそれぞれ2分の1に引き下げられます。
たとえば、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、裁判上の減軽が認められる場合、「7年6ヵ月以下の懲役または25万円以下の罰金」となります。
量刑の(宣告刑を決定するまでの)プロセス
刑事裁判において、被告人に科される刑罰は裁判官が一定の裁量をもって決定します。
しかし、全ての判断を裁判官が自由にできるのではなく、法律に基づいた段階的なプロセスを経なければなりません。
ここでは、量刑が決まるまでの基本的な流れを詳しく解説します。
1.被告人の行為が法律のどの条文にあたるかを決定する
裁判官はまず、被告人が起訴された犯罪について、事件の事実関係をもとに、刑法や特別刑法のどの条文に該当するかを判断します。
たとえば、傷害罪は被告人が「人の身体を傷害した」といえる場合に成立します。
一方、単なる暴行にとどまる場合には暴行罪に、傷害を与えて死亡させてしまうと傷害致死罪に区分されます。
2.条文に書かれた法定刑にもとづき刑の種類を決める
次に、該当する条文に定められた法定刑の枠組みにもとづき、具体的な刑の種類を決めます。
たとえば、傷害罪の法定刑は、15年以下の「懲役」または50万円以下の「罰金」です。
被告人の行為の悪質性や被害の大きさなどを考慮して、懲役刑にするのか、それとも罰金刑にするのかを判断します。
3.条文に書かれた法定刑にもとづき処断刑を決める
刑の種類を決めたあと、法定刑に法律上・裁判上の加重・減軽事由を考慮して、処断刑を決定します。
4.処断刑の範囲内で宣告刑を決める
処断刑は、懲役については「1ヵ月以上15年以下」、罰金については「1万円以上50万円以下」など、一定程度の幅が定められていることが多いです。
この処断刑の範囲内で、裁判官が宣告刑を決定します。
宣告刑については、法定刑や処断刑のような、厳密な法律上の基準が定められているわけではありません。
最終的には、裁判官が個々の事情を考慮しながら適切な刑を判断することになります。
量刑において加味される事情
裁判官は、処断刑の範囲内でさまざまな事情を加味して量刑をおこない、宣告刑を決定します。
量刑の判断に影響を与える事情は多岐にわたりますが、ここではとくに重要なものを紹介します。
被害の大きさ
犯罪によってどの程度の被害が生じたかは、量刑に大きく影響します。
傷害事件であれば、単なる打撲なのか、それとも重傷を負わせたのか、後遺症は残るのかといった点が考慮されます。
犯行や動機の悪質性
犯行の悪質性も量刑に大きな影響を与えます。
被害者と言い争いの末に突発的に殴ってしまったケースと、事前に刃物を準備し計画的に傷害を加えたケースでは、後者のほうが悪質と判断され、重い刑が科される可能性が高くなるでしょう。
また、単なる感情的なけんかの延長で暴力を振るった場合と、相手を長期間にわたって暴行を加え続けた場合では、後者のほうがより厳しく処罰されます。
前科の有無
被告人に過去の前科があるかどうかも、量刑に影響します。
初犯であれば執行猶予がつく可能性もありますが、過去に傷害罪で有罪判決を受けている場合や、短期間のうちに犯罪を繰り返した場合には、刑が重くなるでしょう。
示談が成立しているか
被害者との示談が成立していれば、量刑が減軽される可能性があります。
示談とは、加害者と被害者が話し合い、金銭の支払いなどの条件で和解することです。
示談が成立すると、被害者が加害者を許し、処罰を望まないという意思表示となることが多いため、裁判官はこれを考慮し、刑を軽減することがあります。
自首や自白があったか
自首や自白があれば、量刑が減軽される可能性があります。
自首とは、捜査機関に犯罪が発覚する前に、自ら犯罪事実を申告することです。
自首が認められれば、刑を軽くできる旨が刑法で規定されています。
また、逮捕後に素直に罪を自白した場合も、裁判官の心証が良くなり、刑の減軽につながることがあります。
被告人は反省しているか
被告人がどの程度反省しているかどうかも、量刑の決定に影響します。
被告人が謝罪の手紙を書いたり、被害者に直接謝罪したりしていた場合、刑の減軽につながる可能性があるでしょう。
一方で、反省の態度が見られない場合は、刑が重くなる可能性があります。
被告人の性格や年齢、周囲の環境
被告人の性格や年齢、周囲の環境も、量刑の決定に影響します。
被告人の年齢が若い場合、社会復帰や更生の可能性が高いと見なされ、量刑の決定において有利な要素として考慮されることがあるでしょう。
また、定職についているなど、生活基盤が安定していると認められれば、再犯を犯す可能性が低いと評価され、刑が軽くなる可能性があります。
余罪はないか
余罪で起訴されていない場合、実質的に余罪を処罰する目的で量刑を加重することはできません。
しかし、余罪を通じて被告人の性格や経歴、または犯罪の動機や目的、方法などの事情を推測することは可能です。
たとえば、初犯であっても余罪があることが確認されれば、刑が重くなる可能性があります。
被害者に落ち度はなかったか
被害者の行動が事件の発端になった場合や、被害者側にも一定の責任があると判断される場合、量刑が軽減されることがあります。
たとえば、被害者が先に手を出していた場合や、執拗に挑発していた場合には、刑が軽くなりやすいです。
被害者の処罰感情
被害者の処罰感情も、量刑の決定に影響します。
被害者が重い刑を望んでいる場合は、刑が重くなりやすく、一方で、被害者が加害者を許していた場合は、刑が軽くなりやすい傾向があります。
社会の処罰感情・社会的な影響
事件の内容が社会的に大きな影響を与えた場合や、国民の関心が高い場合、量刑が加重される可能性があります。
たとえば、児童に対する傷害事件であれば、児童本人だけでなく、その保護者や学校関係者、地域の住民にも大きな不安を与えるため、刑が重くなる傾向があるのです。
さいごに|刑を軽くするには弁護士へ相談を
犯罪が発生した場合、まずはどの犯罪類型に該当するか検討されます。
そして、該当する犯罪の「法定刑」に、再犯加重や情状酌量などの影響を考慮して「処断刑」が決まります。
そのあと、被害の大きさや犯行の悪質性、被害者の反省の程度などの要素が「量刑」に影響を与えます。
そして、量刑を踏まえたうえで、最終的には裁判官が「宣告刑」を決定されるのです。
このように、処断刑・量刑・法定刑・宣告刑は似ていますが、はっきりと違いがあります。
正しく理解したうえで、刑罰が決定されるプロセスとともに覚えておきましょう。
なお、なるべく刑を軽くする場合には、被告人に有利となる事情を裁判官に適切に説明する必要があります。
個人が主張するのは難しいので、万が一起訴されてしまった場合、刑事事件に得意な弁護士に相談するようにしましょう。


【初回相談料1時間1.1万円(逮捕されている場合等は無料)|弁護士直通TEL|夜間・休日◎】無罪を獲得した実績◎早期の身柄釈放を第一に!性犯罪/痴漢・盗撮/暴行傷害事件など元検事の弁護士に相談が◎今何をすべきか明確にご提示します
事務所詳細を見る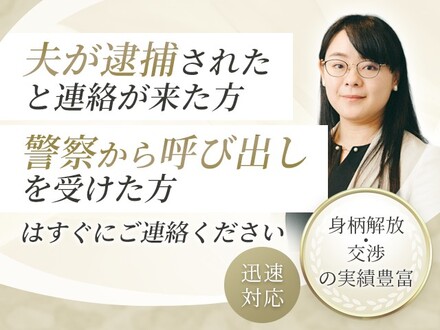
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る
検事の経験を持つ弁護士が窃盗・万引き/少年事件/性犯罪など幅広い刑事事件に対応◆『警察の呼び出しを受けている』『ご家族が逮捕された』はすぐご相談を◆フットワークの軽さを活かした迅速対応【即日接見も◎】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事処分の種類と内容に関する新着コラム
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容に関する人気コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
刑事処分の種類と内容の関連コラム
-
禁錮とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰で、刑務作業が義務付けられていないもののことです。この記事では懲役との違いを踏まえながら、禁錮とはどのような...
-
未成年者の飲酒は法律で明確に禁止されています。本記事では、大学での飲み会やサークル活動で飲酒を強要された場合の対処法や、未成年飲酒に関する法的リスク...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
仮釈放は早く社会復帰することが可能な重要な制度です。この記事では①仮釈放期間はどのように決定されるのか②受けるための条件③仮釈放を要求する方法④仮釈...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ...
-
実刑(じっけい)とは、執行猶予が付かずに懲役刑や禁錮刑で刑務所に収監されるという判決を受けてしまうことです。実刑判決を受けてしまうと、その後、数カ月...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
本記事では、財産刑と呼ばれる罰金と科料について知りたい方に向けて、罰金と科料の違いや対象となる犯罪、罰金や科料に関して実務上のポイント、罰金や科料の...
刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る




















































