「然るべき対応をとる」は脅迫になる?脅迫罪が成立する条件を解説


「『然るべき対応をとります』と発言をしたら、逆に相手から『その発言は脅迫に該当するから警察に通報します』と言い返されて不安になった」というケースは多く存在します。
とくに、SNSが普及した昨今においては、インターネット上でもこのようなやり取りが見られ、無関係な第三者が警察に通報するという事態も発生しています。
そこで本記事では、正当な権利行使と脅迫罪の成否、脅迫罪に問われかねない発信をしたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
「然るべき対応をとる」は脅迫にあたる?
まずは、「しかるべき対応をとる」と相手に伝える行為が脅迫罪に該当するのかについて解説します。
そもそも「脅迫罪」とは?
刑法第222条では、脅迫罪について以下のように定めています。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。引用元:刑法|e-Gov法令検索
脅迫罪は、意思活動(行動)の自由を制約する犯罪類型です。
「被害者本人またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫したとき」に成立します。
まず、害悪の告知の方法に制限はありません。
口頭はもちろん、電話やメール、LINEやDM、SNSの投稿などで相手に伝えた場合でも、脅迫罪が成立する可能性が高いです。
次に、加害の対象は刑法第222条に限られた対象に限られます。
たとえば、親しい関係性にある人に対して害を加える内容の告知であったとしても、「親族」に含まれない場合、脅迫罪は成立しません。
一方、「被害者が飼っているペット」に対する害悪の告知は、「財産に対する害悪の告知」に該当するため、脅迫罪が成立します。
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
「ただ脅し文句を伝えるだけだから重い刑事処分が下されることはないだろう」と油断をしてはいけません。
脅迫罪は、懲役刑が定められている犯罪類型なので、捜査の初期段階から丁寧に防御活動を展開しなければ、初犯でも実刑が下されるリスクがあります。
正当な権利の行使を告知する意図であれば脅迫にはあたらない
告知の内容が正当な権利の行使に関するものであれば、脅迫には当たりません。
たとえば、万引き犯を捕まえた店員が「警察に通報して被害届を提出する」と口頭で伝えた場合、告知者が正当な権利の行使を告知しているだけのため、脅迫罪には該当しない可能性が高いです。
また、痴漢にあった被害者が加害者に対して「然るべき対応をとらせていただきます」と伝える行為も脅迫罪には当たらないでしょう。
ただし、店員が万引き犯に対して「ここで今すぐ裸にならなければ警察に通報する」と発言した場合、条件として提示されている内容が、正当な権利行使とは評価できないため、脅迫罪が成立する可能性があります。
そのほか、まったく訴えるつもりはないのに「然るべき対応をとらせていただきます」や「警察や弁護士に相談します」と伝える行為は、ただ相手を不安にさせることが目的であるため、脅迫罪で刑事訴追されるおそれがあります。
「然るべき対応をとる」以外に脅迫罪が成立し得る言葉の例
脅迫罪が成立する言葉に該当するかどうかは、「一般的に人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知か」という基準で判定されます。
そのため、実際に相手方が畏怖したことまでは必要とされません。
この前提を踏まえると、脅迫罪が成立する可能性が高い言葉として、以下のものが挙げられます。
- 殺すぞ
- 殴るぞ、しばくぞ、刺すぞ
- 村八分にするぞ
- 覚えとけよ(文脈次第)
- 子どもを誘拐するぞ、このまま帰れると思ったら大間違いだぞ
- 性交中の動画をSNSで拡散するぞ、不倫していることを家族にばらすぞ
- ペットを殺すぞ、店に火をつけるぞ など
一方「呪うぞ」や「一生許さないぞ」という抽象的な表現だけでは一般人を畏怖させる程度の表現とはいえず、脅迫罪が成立する可能性は低いでしょう。
なお、この基準を満たすかどうかは、単なる言葉の字面だけで判断されるのではなく、当人同士の関係性や文脈などの事情が総合的に考慮されます。
「然るべき対応をとる」は強要罪や恐喝罪にあたる可能性もある
「然るべき対応をとる」という言葉は、文脈や状況次第では、脅迫罪以外に強要罪や恐喝罪に問われるリスクがあります。
それぞれの構成要件や罰則について、以下で詳しく見ていきましょう。
強要罪|脅迫や暴力で義務でないことを無理やりさせるなどした場合
脅迫罪と類似する犯罪類型として、強要罪が挙げられます。
強要罪は、「生命や身体などに害を加える旨を告知して脅迫することによって、人に義務のないことをおこなわせたり権利の行使を妨害したりしたとき」に成立します。
脅迫罪の法定刑が「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」であるのに対して、強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
脅迫罪では「生命や身体などに害を加える旨を告知して脅迫する行為」自体が処罰対象とされているのに対し、強要罪では、脅迫行為が人に義務のないことをおこなわせたり、権利の行使を妨害したりするための手段と位置づけられています。
たとえば、接客中にトラブルが起きた従業員に対して、客側が「今すぐ土下座をしなければSNSで悪口を書くぞ」と伝えて、従業員を土下座させた場合には、義務のないことを無理矢理させたと認定できるので、強要罪が成立します。
また、債権者から個人的にお金を借りていた人が、借金を契約通りに返済できなくなったときに「法的措置をとってきたら、お前の家族にどんなことが起こるか覚悟をしておけよ」と伝えて借金の踏み倒しに成功した場合には、債権者の正当な権利の行使を妨害したと考えられるので、強要罪が成立する可能性が高いです。
恐喝罪|脅迫や暴力で金銭を脅し取るなどした場合
脅迫罪と似た犯罪類型として「恐喝罪」が挙げられます。
恐喝罪は、以下のようなケースで成立します。
- 人を恐喝して財物を交付させたとき
- 人を恐喝して財産上不法の利益を得たとき
- 人を恐喝して他人に財産上不法の利益を得させたとき
まず、恐喝罪の実行行為である「恐喝」とは、「暴行または脅迫によって被害者を畏怖させること」です。
脅迫罪と同様に、相手を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知が必要で、相手を単に困惑させるにとどまる場合には「脅迫(恐喝)」には該当しません。
次に、恐喝罪が成立するには、畏怖に基づく財産の交付行為までが求められます。
たとえば、痴漢の被害者が「今すぐにATMで50万円を支払ってくれなければ警察に110番通報する」と伝えた結果、加害者側がこれに応じた場合は、口調や行為態様など次第ですが、恐喝罪が成立するおそれがあるでしょう。
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役刑」と定められており、脅迫罪よりもかなり重い刑罰が科される可能性があります。
「然るべき対応をとる」(訴えるぞ)で裁判になった有名な判例
「然るべき対応をとる」という発言について、脅迫罪の成否が問題になった裁判例を紹介します(大審院大正3年12月1日)。
まずは、本件に先行して起こった詐欺事件について押さえましょう。
そもそもの原因である詐欺事件においては、詐欺被害者Aらが、詐欺行為に及んだ疑惑のあるBを刑事告訴したものの、取り調べの結果Bには不起訴処分が下されました。
その後、詐欺罪での刑事告訴を不満に思ったBが、Aらに対して「自分を告訴したのは虚偽告訴罪に該当する違法行為だ、Aらに懲役刑が科されなければおかしい」や「嘘の刑事告訴で名誉が毀損された。Aらを虚偽告訴罪で刑事告訴する」と記載された書面を送付しました。
本件は、この書面を送付した事実が脅迫罪に該当するかが争われた事案です。
第一審及び原判決では、「告訴をするかどうかは告訴権者の自由なので、告訴権がある以上、脅迫罪は成立しない」という理由で、Bには無罪判決が言い渡されました。
検察官はこれを不服として上告します。
これに対する大審院の判決をわかりやすくまとめると、「虚偽の告訴をされた者が、直ちに虚偽告訴罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、虚偽告訴者を畏怖させる目的で告訴する旨の通知をしたときには、脅迫罪が成立する可能性がある」というものでした。
正当な権利行為が脅迫罪を構成するか否かを判断するときには、「正当な権利行使だから常に合法的におこなうことができる」という理屈は通用せず、権利行為に至った目的や本人の意図が考慮されるといえるでしょう。
脅迫してしまった場合にやるべきこと
「然るべき対応をとる」などの強い文言を相手方に告知してしまい、脅迫罪の容疑で刑事訴追されるのではないかと不安を感じているときの対処法を2点紹介します。
被害者との示談を成立させる
脅迫行為に及んでしまったときには、できるだけ早いタイミングで被害者との示談成立を目指すのが重要です。
示談とは、紛争当事者間での話し合いによって民事的解決で合意をすることです。
たとえば、被害者側がまだ警察に相談をしていない段階で示談が成立すれば、和解契約の締結をもって紛争は解決したと扱われるので、脅迫事件が警察に発覚するリスクを最大限軽減できます。
また、既に警察が捜査活動をスタートしていたり、脅迫罪の容疑で逮捕・勾留されていたりしても、「逮捕するかどうか」や「起訴処分を下すかどうか」、「どのような判決を下すべきか」を判断するときには、被害者側の処罰感情が考慮されるのが実情です。
そのため、処分や判決が決定する前に示談を成立させることができれば、「被害者の処罰感情は軽減された」ことを理由に、軽い刑事処分を獲得できる可能性が高まるでしょう。
ただし、脅迫罪は非親告罪なので、脅迫行為の態様が極めて悪質な場合には、示談が成立していたとしても刑事責任を問われかねない点に注意が必要です。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
突発的・衝動的に「然るべき対応をとる」と相手に伝えてしまったときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件を得意とする弁護士に相談してください。
刑事事件の経験豊富な弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるでしょう。
- 「然るべき対応をとる」という発言をした経緯を踏まえて、脅迫罪で立件されるおそれがあるかどうかを判断してくれる
- 刑事訴追されるリスクがあると判断されるときには、すぐに被害者との間で示談交渉を開始して刑事事件化の防止を目指してくれる
- 逮捕されたとしても、早期の身柄釈放・勾留阻止・在宅事件への切り替えを目指してくれる
- 不起訴処分獲得を目指した防御活動を展開してくれる
- 取り調べでの供述方針を明確化してくれる
- 執行猶予付き判決獲得に役立つ情状証拠などを収集してくれる
弁護士が介入するタイミングが早いほど、有利な刑事処分を獲得できる可能性は高まります。
現段階で捜査機関側から連絡がなかったとしても、「然るべき対応をとる」などの発言・発信をしてしまったときには、速やかに刑事事件を得意とする弁護士の意見を求めるべきでしょう。
脅迫罪についてよくある質問
さいごに、脅迫罪についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
訴えると言って実際に訴えない場合は脅迫罪になりますか?
「然るべき対応をとります」「弁護士に相談します」「警察に被害届を提出するぞ」などの告知をするだけで脅迫罪になるわけではありません。
これらの発言・発信はあくまでも正当な権利行為に分類されるからです。
しかし、まったく訴えるつもりがないのに「訴えるぞ」と告知する行為は、ただ単に相手を怖がらせる目的だったと認定されるリスクがあります。
「ただ畏怖させることが目的だった」と評価されると、脅迫罪の容疑で刑事責任を問われる可能性が生じます。
「然るべき対応をとる」と告知をしたのにその後まったく何の動きも見せないのはハイリスクな行為だと理解しておきましょう。
「脅迫罪では警察が動かない」というのは本当ですか?
「脅迫罪では警察は動かない」というのは間違いです。
脅迫罪は刑法に規定される犯罪であり、捜査機関は被害申告を受けた以上、犯罪行為が存在するのかについて捜査活動を実施する義務があります。
ではなぜ「脅迫罪では警察が動くことはない」という間違った考えが広がっているのでしょうか。
その理由として考えられるのは以下のような事情があるからです。
- 民事不介入の原則があるので、「脅された」「脅したわけではない」という情報だけでは当事者間の私的紛争に過ぎず、警察が介入しにくいから
- 脅迫的な言葉を発信されたケースでは客観的証拠を収集しにくいから
- 殺人罪や強盗罪などの重大犯罪に比べると事件性が低いので、捜査リソースが充てられにくいから
もちろん、「殺すぞ」とSNS上で発信されたような事案なら、客観的証拠が存在しますし、事件性も高いと判断される可能性が高いです。
さいごに|脅迫事件に発展するおそれがある場合は弁護士に相談を!
衝動的に「然るべき対応をとるぞ」などと告知をしてしまったときには、念のために刑事事件を得意とする弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
どれだけ「然るべき対応をとります」という発言に至った経緯に正当な理由があったとしても、告知をされた側が警察に相談すれば、脅迫事件として刑事手続きに巻き込まれるリスクが生じかねないからです。
ベンナビ刑事事件では、脅迫事件などを得意とする弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。


【初回相談無料】即日接見OK!刑事事件はスピードが非常に重要です。当事務所では、ご依頼を受けてからなるべく迅速に接見に伺い、素早い弁護活動を心がけています。休日のご相談やオンライン相談にも対応◎
事務所詳細を見る
【即日接見◎│初回面談0円】「警察から連絡が来た方」「ご家族が逮捕された方」はお早めにご連絡ください◆痴漢・盗撮・強制わいせつ/暴行・傷害など示談交渉は当事務所にお任せを◆早期解決に向けて全力でサポート!※匿名でのご相談はお受けできません。
事務所詳細を見る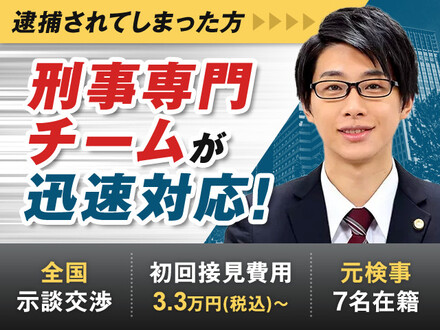
【北千住駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



その他の犯罪を起こしたらに関する新着コラム
-
本記事では、このような恐喝未遂のことを知りたい方に向けて、恐喝未遂罪の定義や構成要件、恐喝未遂罪で警察に逮捕された事例、恐喝未遂罪で逮捕されたあとの...
-
本記事では、ミスティーノの違法性や問われる可能性がある罪、万が一利用してしまった場合の対処法について解説します。
-
本記事では、住居侵入罪において初犯でも逮捕・起訴されるかどうか、実際に起訴を回避するためにできる対応策について、わかりやすく解説します。
-
テレグラムでのやり取りが警察にバレる可能性について詳しく解説します。テレグラムの特徴や関連する犯罪事例、警察のデータ解析能力などを具体的に説明します...
-
本記事では、オンラインカジノが違法となっている理由や、近年の取り締まり強化の流れ、時効などについて詳しく解説します。オンラインカジノを利用してしまっ...
-
本記事では、一般人でもオンラインカジノ利用によって逮捕されることはあるのか、逮捕された場合のデメリットなどを解説します。また、実際に逮捕されてしまっ...
-
本記事では、迷惑防止条例違反について知りたい方に向けて、迷惑防止条例違反の定義や意味、迷惑防止条例違反に該当する主な犯罪、迷惑防止条例に規定されてい...
-
本記事では、オンラインカジノの利用を検討している方に向けて、オンカジ関連で成立する可能性がある3つの犯罪、日本国内でオンカジの利用や勧誘をして逮捕さ...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
本記事では、正当な権利行使と脅迫罪の成否、脅迫罪に問われかねない発信をしたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
その他の犯罪を起こしたらに関する人気コラム
-
違法ダウンロード(いほうだうんろーど)とは、インターネット上に違法にアップロードされたコンテンツ(画像や動画等)をダウンロードする行為のことです。こ...
-
迷惑電話や執拗なクレームは、威力業務妨害に問われる危険があります。自分では正当な理由があると思っていても、刑罰が科せられる可能性があります。この記事...
-
脅迫罪とは被害者に害悪の告知をする犯罪で、【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金】の法定刑が定められています。脅迫に聞こえるような脅し文句や言葉...
-
映画や小説などのフィクションでよく見るサイコパスは、現実に存在します。この記事では、犯罪心理学者にサイコパスの特徴や、その基準を伺いました。イメージ...
-
本記事では、名誉毀損が成立する条件、名誉毀損が成立する具体例、トラブルに発展した時の対処法について解説します。
-
本記事では、住居侵入罪の具体的な定義や刑罰、そして構成要件を詳しく解説。「初犯でも懲役刑になるのか」「正当な理由ってどこまで?」といった疑問にも回答...
-
公文書偽造(こうぶんしょぎぞう)とは、国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪です。【法定刑は1年以上10年以下】と意...
-
不法投棄(ふほうとうき)とは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた処分場以外に、廃棄物を投棄することです。
-
死刑になる犯罪は全部で18種類あり、殺人罪などのイメージしやすいものから、海賊行為を規定したイメージしにくいものまで多くあります。裁判で死刑が下され...
-
護身目的でもナイフなどを携帯できないことをご存知ですか?この記事では銃刀法違反で逮捕されかねないケースと銃刀法違反の罰則、逮捕されてしまったときにと...
その他の犯罪を起こしたらの関連コラム
-
不正アクセス禁止法とは、インターネット通信等における不正なアクセスとその助長行為を規制する法律です。実際に、何がこの違法行為に当たり、どのようなケー...
-
罪を犯してしまったものの、証拠がないから大丈夫だろうと安心している方もいるかもしれません。本記事では、警察がどのような状況で動くのか、証拠の種類や重...
-
本記事では、住居侵入罪において初犯でも逮捕・起訴されるかどうか、実際に起訴を回避するためにできる対応策について、わかりやすく解説します。
-
サイバー犯罪とは、主にコンピュータを使ってネットワーク上で行われる犯罪の総称を言います。近年では、犯罪件数や規模が増加しているということで、警察庁で...
-
死体遺棄とは、死体を埋葬せずに捨て置く犯罪行為で、犯した場合は死体遺棄罪で罰せられます。遺骨の遺棄は罰則対象となりますが、散骨については明確に罰する...
-
客引き行為は風営法や各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていて、違反して逮捕された場合にどのように対応すれば良いのか、また、起訴・前科を付けないために...
-
強要罪は「暴行や脅迫を用いて相手に義務のないことをおこなわせる犯罪」です。身近に起こり得る犯罪で、刑罰は懲役3年以下の懲役刑しかありません。本記事で...
-
不退去罪(ふたいきょざい)とは、住居などから出ていくように要求を受けたにもかかわらず、退去せずにそのまま居座り続けることで罪が成立する犯罪です。
-
逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)とは、人を不法に逮捕・監禁する行為を言います。法定刑は3カ月以上7年以下の懲役が設けられています。人の自由を奪う...
-
給付金の不正受給をしてしまったら、返還方法を含めて弁護士に相談しましょう。無料相談できる窓口もたくさんあります。不正受給は発覚すれば詐欺罪に問われる...
-
商標法違反(しょうひょうほういはん)とは、他者の商標(商品やサービスを区別するマーク)と同一の商標を使い、商標権者の権利を侵害したり、不当利得を得た...
-
不法投棄(ふほうとうき)とは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた処分場以外に、廃棄物を投棄することです。
その他の犯罪を起こしたらコラム一覧へ戻る























































