心神喪失で無罪になるのはなぜ?責任能力の考え方や無罪に納得できない理由などを解説

刑事事件では「犯人が犯行時に心神喪失状態であっため無罪」となるケースも存在します。
しかし「事件を起こしたことに変わりはないのに、なぜ無罪なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
そこで本記事では、心神喪失状態で起こした事件について、なぜ無罪になるのかについて詳しく解説します。
また、心神喪失で無罪になったあとの手続きの流れや、心神喪失を主張するときに弁護士へ相談するメリットなどについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
心神喪失者が無罪になるのはなぜ?刑事責任能力が認められないから
まずは、心神喪失者が無罪になる仕組みについて、刑事責任の基本ルールから遡って解説します。
大前提|刑事責任を科されるのは3つの要件を満たしたとき
そもそも刑事責任が科されるのは、以下3つの要件を満たしたときに限られます。
- 構成要件に該当する行為に及んだこと
- 違法性阻却事由がないこと(正当防衛など)
- 責任阻却事由がないこと
なかでも、犯行時に精神疾患を患っていたり、若年者であったりしたときには、3つ目の要件である責任能力の有無が問題になります。
たとえば、犯行当時の犯人の年齢が10歳なら刑事未成年者であることを理由に責任能力がないと判断され、刑事責任を問われることはありません。
また、犯行当時に犯人が統合失調症などの深刻な症状に悩まされていたり、覚せい剤の影響で幻覚を見ていたりする場合には、心神喪失・心神耗弱への該当性が問題になり、刑事責任が減免される可能性があります。
つまり、犯行に及んだ被疑者・被告人の属性や精神状況が、「責任能力の有無」という観点で考慮されるということです。
心神喪失は責任阻却事由の要件で問題になる
刑事事件の要件における「責任阻却事由の有無」の項目で問題になるのが、行為者の責任能力です。
責任能力とは、「刑事責任非難に値する能力」を意味します。
また、責任能力が欠如する状態であることを「心神喪失」と呼ばれます。
そして、刑法第39条第1項では、心神喪失者の行為は罰しないと定められています。
なぜなら、心神喪失者には刑事責任能力が存在しないため、刑事責任を科すための要件を満たさないからです。
心神喪失の内容・定義
刑法に規定されているのは、「心神喪失者の行為は罰しない」というルールのみです。
どのような状態の行為者が心神喪失に該当するのかについて、刑法には一切規定がありません。
そこで、最高裁判所は、心神喪失を「精神の障害により、行為の違法性を弁識し(事理弁識能力)、その弁識にしたがって行動を制御する能力(行為制御能力)を欠く状態のこと」と定義しています。
つまり、事理弁識能力または行動制御能力のどちらか一方を欠く状態になると、心神喪失に該当することを理由に刑事責任を科されずに済むのです。
事理弁識能力と行動制御能力のそれぞれの定義は、以下のとおりです。
- 事理弁識能力:自分の行為の違法性を判断する能力(やろうとしていることが悪いことだと理解する能力)
- 行動制御能力:行為の違法性を弁識したときに当該行為を制御する能力(悪いことだと理解したときに問題の行為をやめることができる能力)
なお、心神喪失と似た概念として「心神耗弱」が挙げられます。
心神耗弱とは、精神の障害によって事理弁識能力・行動制御能力が著しく限定されている状態のことです。
心神喪失のように無罪になることはありませんが、刑の減軽という効果を得られます。
心神喪失の判断要素
心神喪失の状態であったかどうかを判断するときには、病歴や犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様、犯行後の行動、犯行以後の病状など、さまざまな事情が考慮されます。
たとえば、被疑者・被告人が精神鑑定を受けた結果、心神喪失の状況にあったという鑑定書が出されたとしても、ほかの事情を考慮した結果、心神喪失とは判断されないケースもあるのです。
実際、統合失調症を罹患していたとしてもそれだけを理由に心神喪失になるわけではなく、心神耗弱にとどまるという判断がされることもあります。
以上を踏まえると、心神喪失は画一的な基準や医学的所見によって判断されるものではなく、あくまでも裁判所の評価、法律判断によるものだといえるでしょう。
なぜ心神喪失者のように刑事責任能力がない人だと無罪になるのか?
では、心神喪失者が刑事責任能力がないことを理由に無罪になるのはなぜでしょうか。
ここでは、その理由について解説します。
1.犯罪に及んだときに物事の善悪を判断できないから
心神喪失状態にあるということは、事理弁識能力・行動制御能力のどちらかひとつを欠いている状態です。
事理弁識能力を欠いているということは、自分がしようとしている行為が違法か適法か、物事の善悪自体を判断できないことを意味します。
物事の良い悪いを判断できない人物に刑事罰を科すのは、刑法が採用している「責任主義」に反するといえるでしょう。
2.処罰を与えても本人がその意味を理解できないから
心神喪失者に対して刑事処罰を下したとしても、なぜ自分が刑事罰を科されるかを理解することができません。
心神喪失者は物事の善悪を判断できない場合やあるほか、善悪自体は判断できたとしても自分の意思で違法行為をやめることができないからです。
そもそも、刑事罰は犯人に対して、再犯の予防・抑止、更生を促すために科されるものです。
しかし、刑事罰を科される意味そのものを理解できない状態なら、仮に刑事罰を科したところで、再犯予防などの効果を期待することができません。
そのため、心神喪失者に対しては刑事責任を追及しないというルールが徹底されているのです。
心神喪失を理由に無罪判決が出されることに納得できないのはなぜか?
被害者やその家族にとっては、心神喪失であることだけを理由に無罪になることに納得できない人もいるでしょう。
ここでは、心神喪失を理由に無罪判決が下されることに納得できない理由を紹介します。
1.理由がどうあれ犯罪をしているから
心神喪失を理由に無罪になったとしても、犯罪行為に及んでいること自体は事実です。
本来は重い刑事責任を問われるのに、「加害者本人に斟酌するべき事情がある」というだけで、どれだけ重い罪を犯しても無罪になる、という点にアンバランスさを抱く人は多いでしょう。
2.被害者やその家族が報われないから
殺人罪や窃盗罪などの犯罪には、被害者や被害者家族が存在します。
「何の罪もない犯罪被害者が生命・身体・経済的に不利益を被っているのに、心神喪失者は何の刑事責任も果たしていない」という点に不信感が募る人は多いのでしょう。
3.心神喪失を理由に処罰を逃げているように感じるから
心神喪失が問題になるケースでは、覚せい剤中毒者や飲酒で酩酊状態になった加害者についても問題になることが多いです。
このような人物が「自分は犯行当時に心神喪失状態にあったから」と主張すると、覚せい剤や飲酒などを言い訳にして刑事罰を逃れようとしているような狡さを感じてしまいます。
心神喪失で無罪になった後の流れ
一定の重大犯罪事件を起こしたものの心神喪失などを理由に刑事処分・有罪判決を免れた人に対しては、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することが目指されています。
この制度のことを「医療観察法制度」と呼びます。
医療観察法制度が適用されると、以下の流れで心神喪失者に対する対応が決定されます。
- 検察官が地方裁判所に対して対象者を鑑定入院させる旨の決定を求めて申し立てをする
- 明らかに必要がないと認められる場合を除いて、地方裁判所が対象者を鑑定入院させる
- 鑑定入院期間中に、意思が鑑定をおこなって意見書を作成する
- 審判期日において、地方裁判所が対象者に対する医療措置の内容などを決定する
なお、医療観察法制度が適用されるのは、以下の犯罪類型に該当する行為に及んだ場合に限られます。
- 現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪、これらの未遂罪
- 不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、監護者わいせつ及び監護者性交等罪、これらの未遂罪
- 殺人罪、自殺関与罪、同意殺人罪、これらの未遂罪
- 傷害罪
- 強盗罪、事後強盗罪、これらの未遂罪
また、医療観察法制度は、心神喪失・心神耗弱を理由に刑事裁判で無罪や刑の減軽を受けた人だけではなく、「対象行為をおこなったことが認定されたものの、心神喪失・心神耗弱であることが認められるために不起訴処分が下された者」にも適用されます。
このように、心神喪失で無罪や不起訴になったとしても、対象者に対して一定の医療的措置が下されるのです。
心神喪失を理由に無罪を狙うときに弁護士へ相談するメリット
心神喪失を理由に無罪を目指すときには、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談・依頼をすることをおすすめします。
刑事弁護実績やノウハウが豊富な専門家の力を借りることによって、以下のメリットを得られるからです。
- 犯行時に統合失調症などの影響があったことを立証するために役立つ診断書・鑑定書を独自に用意してくれる
- 被害者との間で早期に示談交渉をして刑事事件化の回避を目指してくれる
- 逮捕・勾留による長期の身柄拘束の阻止を目指してくれる
- 捜査段階から心神喪失を主張して、微罪処分や不起訴処分獲得を目指してくれる
- 診断書・鑑定書以外に、個別具体的な事実を積み上げて犯行時に心神喪失状態であったことを公判廷で主張・立証してくれる
- 心神喪失者をケア・バックアップする環境が整っていることを裁判官にアピールして無罪判決獲得の可能性を高めてくれる
- 事案の状況から心神喪失の認定が難しいケースなら、心神耗弱を求めるなど、柔軟な弁護活動を期待できる
刑事裁判において心神喪失の判断を引き出すのは簡単ではありません。
なぜなら、捜査機関側が用意する鑑定書などの客観的証拠に対抗するために、被疑者・被告人側でもさまざまな証拠を準備しなければいけないからです。
特に、心神喪失が争点になるケースでは、当番弁護士や国選弁護人などの制度を利用するのではなく、刑事事件を得意とする私選弁護人に相談・依頼すべきでしょう。
さいごに|心神喪失者が無罪なのは人権侵害を防止する意味合いもある!
心神喪失者は刑法第39条第1項の規定に基づいて無罪と扱われます。
現行刑法では責任主義が採用されており、事理弁識能力・行動制御能力を欠く人物に対して刑事責任を追及するべきではないと考えられているからです。
しかし、実際に刑事訴追されたケースで心神喪失の判断を勝ち取るのは簡単ではありません。
刑事裁判では、診断書や医師の意見書だけではなく、犯行当時の事情を総合的に考慮し、心神喪失に該当するか否かが判断されるからです。
刑事手続きで心神喪失を争点にする場合には、刑事裁判経験豊富な弁護士のサポートが不可欠といえます。
ベンナビ刑事事件では、法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で法律事務所を検索できるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士まで問い合わせてください。

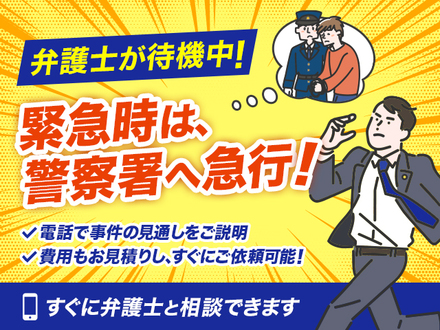
【八王子駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る
【新宿駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る
【即日接見◎│初回面談0円】「警察から連絡が来た方」「ご家族が逮捕された方」はお早めにご連絡ください◆痴漢・盗撮・強制わいせつ/暴行・傷害など示談交渉は当事務所にお任せを◆早期解決に向けて全力でサポート!※匿名でのご相談はお受けできません。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
-
この記事では、痴漢で解雇されるシチュエーションや、解雇するかどうかを判断するときに考慮されるポイント、弁護士に早期相談・依頼するメリットなどについて...
-
ニュースでよく聞く「検挙」という言葉の正確な意味を理解している人は、実はそこまで多くはありません。検挙という言葉がよく使われるシーンや、似た用語との...
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
自分が逮捕されるかもしれない、あるいは家族や友人が逮捕されてしまったというとき、相談の時間や経済的な余裕がない場合は、まずは無料のメール相談を活用す...
-
本記事では執行猶予期間中の方に向けて、執行猶予の取り消しについての定義・意味、執行猶予が取り消しになる2つのパターン、再犯をして執行猶予が取り消しに...
-
指名手配とは、一定の事件で逮捕状が発布されている被疑者について全国の警察で協力して捜査を行うためのシステムで、逮捕状が出ているものの被疑者が逃亡する...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
ニュースやドラマでよく聞く「検察」について、警察との違いを知りたいけれどよくわからないという方は少なくありません。 本記事では、逮捕前後の流れを含...
-
冤罪事件の補償金については、金額が安すぎるという声も多く見られています。本記事では、冤罪被害者への補償金の現状や、その金額が「安い」と批判される理由...
-
殺害された人が生前殺されることを承諾していた場合、犯行に及んだ人物は殺人罪ではなく、承諾殺人罪の容疑で刑事訴追されます。本記事では、承諾殺人の構成要...
-
緊急避難とは、刑法で定められた違法性阻却事由の一つです。正当防衛も違法性阻却事由という点では同じですが、緊急避難と正当防衛は成立要件が異なります。具...
-
偽計業務妨害罪は身近にある犯罪であり、実際に自身の行為が該当するのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、偽計業務妨害...
-
名誉毀損の可能性がある行為をしてしまったら、刑法第230条を理解することが非常に重要です。 本記事では、刑法第230条について、どのようなときに名...
-
摘発(てきはつ)とは、「犯罪の存在を公表すること」です。犯罪があったことを社会に向けて明らかにする行為を指すため、犯人が特定されている場合には「検挙...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る























































