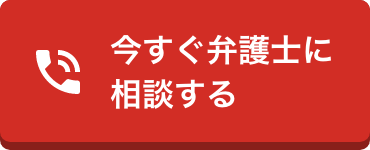【加害者限定】
【加害者限定】お急ぎの方へ

累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
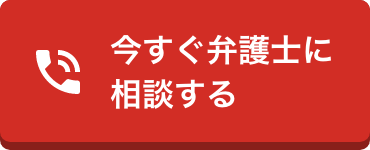
刑事裁判とは、犯罪を起こした疑いのある人が本当に犯罪を行ったのか(有罪か無罪か)、もし行ったとしたのならどの程度の刑罰を与えるのかを決める手続きのことです。

引用元:警察庁|刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等
刑事裁判については、テレビなどで、法廷で犯人が犯罪の動機を供述したり、証人が事件の証言を行ったりするシーンを見たことがある方もいると思います。司法にあまり関わりのない多くの人は刑事裁判と民事裁判を混同しがちですが、全くの別物です。
この記事では、刑事裁判はどのようなものなのか、どのような理由で行われるのか、そして、ご家族が刑事裁判を受けることになった方に向けて、減刑を勝ち取るためにできることをご説明します。
ご家族や自身の早期釈放を望んでいる方へ
刑事事件で起訴されると刑事裁判手続を経て判決を下されることになります。
日本は刑事裁判の有罪率が高く、無罪判決を得ることは至難の業です。
ただ起訴前に不起訴処分になれば、罪に問われず前科も付きません。
ご家族や自身が刑事事件の当事者になった方は、早急に弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼をするメリットは次の通りです。
- 取り調べの受け方のアドバイスをもらえる
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 被害者との示談交渉を任せられる など
刑事事件は早い段階での弁護活動が非常に重要です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|
この記事に記載の情報は2024年03月22日時点のものです
刑事裁判における2つの種類
刑事裁判には、「略式裁判」「正式裁判」の2種類があります。
略式裁判
略式裁判は簡易的な手続きで行われる裁判です。ドラマなどでみる刑事裁判のように、法廷で弁護人と検察官が主張を闘わせるような裁判とは少し異なります。
略式裁判の場合、法廷で検察官と弁護人が意見を出し合うようなことはしないのが特徴です。略式裁判を行うためには一定の要件を満たす必要があります。
-
- 簡易裁判所の管轄する刑事事件である
-
100万円以下の罰金または科料を科すことのできる刑事事件である
- 被疑者が略式手続きに同意している
以上の要件を満たした場合は、刑事裁判を略式手続きで行えます。
正式裁判
刑事事件の基本的な裁判形態が正式裁判になります。
正式裁判とは略式裁判のように手続きを簡易化せず、法廷で弁護人と検察官が証拠を出し合いその上で裁判官が判決を下す形態の裁判です。テレビなどでよく見る裁判を想像するとわかりやすいのではないでしょうか。
わかりやすい刑事裁判の流れ
刑事事件が正式裁判で行われる場合、以下のような流れで進みます。

弁護人や検察官、裁判官、被告人などの登場人物がどのようなやり取りを行うのかも含めて解説します。
冒頭手続き
刑事事件の裁判で最初に行われるのが「冒頭手続き」です。冒頭手続きでは、
- 被告人は本人で合っているか(本人確認)
- 検察官はどのような見解で被告人を起訴したのか
- 被告人は起訴事実についてどう考えているか
などを明らかにし、整理します。
刑事裁判の最初に行われる情報確認的な意味合いだと理解すれば、わかりやすいのではないでしょうか。
人定質問
人定質問は裁判官が被告人に対して行う本人確認です。人違いはあってはならないことですので、まずは被告人本人なのか確認するところから入ります。
裁判官が被告人に聞くのは住所や本籍地、職業などです。
起訴状の朗読
「なぜ起訴されたのか」「何のために裁判をするのか」を明らかにします。
検察官が起訴状を読み上げることで裁判官、弁護人、被告人にあらためて起訴内容を伝えます。起訴状の内容に不明確、不明瞭な部分があれば裁判官が検察官に釈明を求めることもあります。
なお、被害者の氏名は「被害者」などと伏せる場合もあります。プライバシーに配慮するため、性犯罪の刑事裁判ではよく行われます。
秘権の告知
裁判官が被告人に黙秘権について告知します。黙秘権の告知は裁判官によって言葉遣いが若干異なりますが、以下のような説明がされます。
-
-
被告人は終始沈黙できること
- 個別の質問に対して陳述を拒めること
- 陳述もできること
-
被告人が陳述すると被告人にとって不利な証拠にも有利な証拠にもなること
罪状の認否確認
その後、被告人に対して、検察の起訴状についてどう考えているか、意見を聞きます。黙秘権の告知の後に裁判官が被告人に「起訴状の内容についてどうですか?」と確認するという流れです。
被告人は起訴状の内容を認めるなら「認めます」、認めないなら違っている部分について簡潔に説明します。罪状認否で被告人がどのように答えるかは、被告人と弁護人が打ち合わせして決めておくのが基本です。
被告人の認否の後、弁護人にも意見を求められます。
証拠調べ
刑事裁判の冒頭手続きの次に行うのは証拠調べです。
証拠調べではまず検察官が冒頭陳述を行います。被告人の経歴や犯罪に至る経緯などを説明します。
裁判員裁判では弁護人も冒頭陳述を行い、被告人の主張の基礎となる事実や裁判員に注目してもらいたい証拠などを説明します。その後、検察官、弁護人双方から証拠調べ請求を行います。
検察官の立証
検察官は犯罪の事実について立証責任を負います。冒頭陳述の後、まずは検察官が証拠調べ請求を行います。
証拠は書面、物(凶器など)、証人などです。
裁判官は、検察官が請求した証拠について弁護人の意見(同意・不同意など)を聞いたうえで、採用する証拠を決定します。
弁護人の立証
続いて弁護士の立証です。証拠については検察官と同じく、書面や物、証人などを請求します。
なお、証人の尋問の後に、被告人質問を行うという流れが多いです。
弁論手続き
証拠取調べが終わると弁論手続きに移ります。
検察の論告・求刑
検察官が証拠取調べによって被告人の罪が立証されていることや、被告人に科される罰について意見を述べます。手続きによっては、被害者も意見を述べることも可能です。
弁護人の最終弁論
次いで弁護人も意見を述べます。
被告人最終意見陳述
検察官や弁護人が論告や弁論をした後に被告人にも意見を述べる機会が与えられます。被告人は刑事裁判の一連の流れを踏まえて「自分は無実です」「反省しています」など、あらためて自分の意見を述べるのです。
結審・判決
被告人が意見を言い終えたら裁判官が審理終了を宣言します。後は判決の日付を決めて、その日に判決の言い渡しを行うという流れです。
結審から判決までの期間は特に争いのない情状酌量のケースで数週間から1ヶ月程です。
また、日本では「原則として審理を3回受けられる」という三審制度を採用しています。第一審の判決に不服があれば控訴により第二審で争うことも可能です。第二審の判決にも不服があれば、上告できます。
控訴や上告があると刑事裁判が終わるまでさらに期間を要することになります。
三審制度と裁判所の種類
日本では3回まで裁判を受け直すことのできる三審制が起用されています。第一審の判決に不服を持ち上級の裁判所に新たな判決を求めることを控訴、第二審の判決に不服を持ち第三審を求めることを上告と言います。
裁判所の種類は5種類あり、事件の内容や、裁判の進み具合で裁判所が変わってきます。
| 裁判の種類 |
内容 |
|
簡易裁判
|
軽微な事件を裁判する場合はこちらで行われ、全国に438箇所あります。
|
|
地方裁判所
|
通常の事件での裁判はこちらで行われ、全国に50箇所あります。通称、地裁と呼ばれます。
|
|
高等裁判所
|
地方裁判所、家庭裁判所の判決内容に不満があり控訴した場合にこちらで行われます。全国の主要都市の8箇所あります。
|
|
最高裁判所
|
高等裁判所の判決でも不服で、上告した場合にこちらで裁判を行うことになります。東京の1箇所にしかありません。
|
|
家庭裁判所
|
少年犯罪の場合こちらで行われます。
|
参考:裁判所の種類及び数
刑事裁判と民事裁判の違い
日本の裁判には刑事裁判の他に民事裁判があります。
刑事事件の判決で被告人に刑罰が与えられても、それだけで被害者に賠償金が支払われるわけではありません。刑事裁判手続とは別に賠償金を求める必要があり、このときに利用されるのが民事裁判手続です。
たとえば交通事故に遭ったとき、車によって人をはねた場合、加害者に科される刑罰については刑事裁判手続で判断され、一方で加害者が被害者に対して支払うべき慰謝料や治療費等の賠償金については、被害者・加害者間で民事裁判手続で争うことになります。このように、刑事裁判と民事裁判は同じ裁判でも性質や目的、使われる場面が異なります。
刑事裁判と民事裁判の違いを以下の表にまとめました。
| |
刑事裁判
|
民事裁判
|
|
起訴・提訴する人
|
検察官
|
私人
|
|
根拠となる法律
|
刑法、刑事訴訟法等
|
民法、民事訴訟法等
|
|
解決方法
|
判決のみ
|
和解による解決も可能
|
起訴・提訴する人
民事裁判は基本的に私人間の紛争を解決するための裁判です。民事裁判は個人や法人が訴えを提起します。
対して刑事裁判は検察官が起訴します。刑事事件は罪を犯したと疑わる人に対して、有罪無罪や処罰に内容を決めるためのもので、私人による起訴はできません。
また、民事事件は、裁判をするか否かは私人が決めることです。刑事事件は、告訴がなければ提起できない親告罪を除き、被害者の意向に関わらず検察官が起訴・不起訴を決めて手続きを進めるという違いがあります。
根拠となる法律
刑事裁判で用いられる法律は、罪と刑罰を定めた「刑法」が基本になります。この他に「覚せい剤取締法」や「銃刀法」、「大麻取締法」など、犯罪を定めた法律も用いられます。
刑事裁判の手続きについては刑事訴訟法が定めています。
対して民事裁判では「民法」が基本になります。この他に商法等民事事件に関わる法律も用いられます。
手続きについては民事訴訟法が定めています。
解決方法
刑事裁判手続きでは、基本的には判決により手続きが終了します。民事裁判手続きでは判決の他に和解により解決することも多々あります。
和解とは、民事裁判の当事者がお互い譲歩して、解決金の支払いなどによって解決する方法です。
刑事裁判でよくある質問
刑事裁判のよくある質問について順番に説明します。
刑事裁判に費用はかかりますか
刑事裁判そのものは費用がかかることは原則としてありません(ただし、訴訟費用を被告人に負担させる場合もあります)。もっとも、自らが依頼して弁護士を付けたのであれば弁護士費用(60~100万円程度)がかかります。
弁護人はどうやって選任されますか
弁護人を選任する方法は2つあります。
ひとつは、被告人や被告人の家族が自分たちで弁護士を選ぶ方法です。この方法で選ばれた弁護人を私選弁護人と言います。
もうひとつは、資力などの事情から被告人本人が弁護士を選べないため、国が弁護人を選ぶ方法です。この方法で選ばれた弁護人を国選弁護人と言います。
刑事裁判で有罪になる確率はどれくらいですか
刑事裁判の有罪率は99.9%と言われています。もちろん年によって犯罪件数や有罪率は異なりますが、極めて高い有罪率であることは間違いないでしょう。
ただし、不起訴となる事件もあることを忘れてはいけません。起訴されてしまえば有罪率は極めて高いため、被疑者段階で不起訴を獲得するための活動は重要と言えるでしょう。
裁判員制度ってなんですか
裁判員制度とは2009年に始まった制度で、国民の中から裁判員を選び、裁判官と一緒に事件を審理し、事実を認定し、判決を決めていく制度です。国民と司法との壁を取り払い、国民の意見も取り入れた公平な判決ができるようにという目的があります。
裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。
「無罪推定の原則」とはどういうことですか
無罪推定の原則とは「被告人の有罪が確定するまで罪を犯していない人として扱われなければならない」という原則です。世界人権宣言や国際人権規約にも定められた刑事裁判の原則で、憲法によっても保障されています。
この意味は、疑いだけで自由や財産、尊厳を奪ってはならないということです。近年は報道に対して無罪推定の原則が守られていないのではないかという批判があります。
刑事裁判までにしておきたいこと
刑事裁判の有罪率が非常に高いのはすでにお伝えした通りです。そのため、刑事裁判で無罪にできないか考えておられる方で、まだ起訴されていない・逮捕されて間もない方は、ぜひ早めに弁護士に刑事弁護を依頼することをおすすめします。
起訴前に不起訴になれば罪には問われず前科も付きません。逮捕後迅速に対応することができれば、仕事や家庭環境などその後の生活においても大きな影響を及ぼすこともありません。
刑事弁護に関しては次の関連記事に詳しい記載があります。ぜひご参考にしてみてください。
まとめ
刑事事件で起訴されると刑事裁判手続を経て判決を下されることになります。日本は刑事裁判の有罪率が高く、無罪判決を得ることは至難の業です。
ただし、無罪は難しくても不起訴処分を獲得することは可能です。そのためにも、家族や本人は早めに刑事事件に注力する弁護士へ相談することをおすすめします。
ご家族や自身の早期釈放を望んでいる方へ
刑事事件で起訴されると刑事裁判手続を経て判決を下されることになります。
日本は刑事裁判の有罪率が高く、無罪判決を得ることは至難の業です。
ただ起訴前に不起訴処分になれば、罪に問われず前科も付きません。
ご家族や自身が刑事事件の当事者になった方は、早急に弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼をするメリットは次の通りです。
- 取り調べの受け方のアドバイスをもらえる
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 被害者との示談交渉を任せられる など
刑事事件は早い段階での弁護活動が非常に重要です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|