おはよう逮捕とは?早朝に警察が逮捕に来る理由やほかの時間帯の逮捕の可能性など

「おはよう逮捕」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、警察が早朝に容疑者の自宅へ訪れ、そのまま逮捕することを指す俗称です。
刑事ドラマなどでも見かける場面ですが、実際になぜ早朝に逮捕がおこなわれるのか、法律的な理由や捜査上のメリットを正しく理解している方は少ないかもしれません。
さらに、逮捕は早朝だけでなく昼間や夜間にもおこなわれる可能性があり、その時間帯ごとに意味や事情が異なります。
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
おはよう逮捕とは?早朝におこなわれる通常逮捕のこと
おはよう逮捕とは、被疑者が在宅している可能性が高い早朝のタイミングに実施される通常逮捕処分を意味します。
通常逮捕とは、裁判官が事前に発付した逮捕状を被疑者に呈示することで実行される強制処分のことです。
おはよう逮捕が実施される理由は、被疑者の身柄を確実に拘束するためです。
日中や休日のように被疑者が在宅していない時間帯に捜査員が自宅を訪れたとしても、被疑者が自宅におらず、逮捕処分が空振りになりかねません。
そのため、早朝という確実に在宅しているであろう時間帯を狙って逮捕を実施するのです。
なお、おはよう逮捕は、一般的に以下のような流れで実施されます。
- 早朝に自宅のインターフォンが鳴る
- インターフォンに応答すると、「○○警察署の者です」などと回答がある
- 玄関を開けると、その場で逮捕状が読み上げ・呈示されて、逮捕される
居留守を使ってもおはよう逮捕を免れることはできない
おはよう逮捕をする目的で警察官にインターフォンを鳴らした場面では、被疑者側が以下のような反応をする可能性があります。
- 早朝に自宅のインターフォンが鳴らされること自体に違和感があって無視する
- 眠っていてインターフォンが鳴ったことに気付かない
- インターフォン越しに映った人たちに見覚えがないので居留守を使う
- 警察がやってくる心当たりがあり、逮捕されるのではないかと不安を抱え、そのまま居留守を使ってやり過ごそうとする など
警察は、おはよう逮捕を実行する前に被疑者の行動パターンを調べ、おはよう逮捕実行時に自宅に所在することを把握しているのが一般的です。
そのため、居留守を使ったとしても、最終的に逮捕されることは免れられないでしょう。
また、おはよう逮捕がおこなわれる際には、警察官は逮捕状とは別に、捜索差押許可状を請求・取得していることが多いです。
つまり、錠前を外して自宅などに立ち入ることが許されているので、居留守を使っても無駄なのです。
仮に居留守を使って警察官の訪問をやり過ごせたとしても、逮捕状の有効期限は原則7日以内なので、どこかのタイミングで警察に見つかって逮捕される可能性が高いでしょう。
以上を踏まえると、居留守を使っておはよう逮捕に対抗するのは現実的な方法とはいえません。
おはよう逮捕についてもっと知りたい人向けの補足情報
おはよう逮捕の詳細について解説します。
1.時間帯|6時~9時ごろが多い
おはよう逮捕がおこなわれるのは、午前6時〜午前9時、日の出以降の時間帯が多いとされています。
もちろん、被疑者が就寝中の深夜や日の出前などの時間を狙っておはよう逮捕が実行されるケースも少なくありません。
ただし、日没後〜日の出前に通常逮捕をおこなうには、裁判所から逮捕状の夜間執行について事前に許可が必要です。
そして、裁判所から夜間執行に関する特別な許可を得るのは捜査機関にとって面倒なことなので、余程の特殊事情がない限り、日の出後の午前6時〜午前9時頃を狙っておこなわれます。
2.曜日|平日(月曜~水曜)が多い
おはよう逮捕が実施される曜日について法律上のルールは存在しません。
そのため、平日、休日、年末年始など、どのタイミングでもおはよう逮捕が実施される可能性はあります。
ただし、実際の捜査実務では、平日の月曜日〜水曜日におはよう逮捕がおこなわれることが多いとされています。
なぜなら、おはよう逮捕がおこなわれたあとは、警察署で48時間以内の取り調べを実施したうえで、事件や被疑者の身柄を検察官に送致しなければいけないからです。
そして、平日のほうが在庁している検察官が多く、平日の送検のほうが好まれる傾向にあるため、おはよう逮捕や警察段階の取り調べも週の前半で済まされるのです。
3.事件|通常逮捕の対象となる事件
おはよう逮捕がおこなわれるのは、通常逮捕の対象になる刑事事件だけです。
そもそも、刑事事件を起こしたとしても、常に警察に逮捕されるわけではありません。
裁判官が逮捕状を発付するのは、以下の要件を満たしたときに限られます。
- 逮捕の理由:被疑者が犯罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること。単なる疑いや被害者からの被害申告があるだけでは足りず、客観的な証拠が必要。
- 逮捕の必要性:逃亡または証拠隠滅のおそれがあること。
そのため、警察から事前に任意の出頭要請を受けて、その都度事情聴取に応じており、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されるような状況であれば、実際に犯行に及んだ事実に疑いがないような状況であったとしても、おはよう逮捕が実施されることはありません。
しかし、任意の出頭要請を無視・拒否したり、事前に実施される事情聴取で黙秘・否認をしたりすると、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されて、おはよう逮捕される危険性が高まります。
おはよう逮捕以外にも日中や夕方の通常逮捕はありえるのか?
捜査実務上、被疑者を通常逮捕する場面では「おはよう逮捕」がおこなわれることが多いです。
では、おはよう逮捕以外の方法で通常逮捕されることはないのでしょうか。
早朝以外の逮捕の可能性について、以下で詳しく解説します。
1.日中の通常逮捕はあまり多くはない
日中に通常逮捕がおこなわれるケースは多くはありません。
たとえば、刑事事件の被疑者が社会人の場合、日中は勤務先に所在している可能性が高いです。
もちろん、警察が勤務先を訪問して被疑者を逮捕することも可能ですが、勤務先で逮捕をすると無関係な会社の人たちに迷惑がかかるおそれがあるため、余程の特殊事情がない限り、勤務先などでは通常逮捕はおこなわないように配慮がなされています。
被害者が無職や在宅ワークなどで常時在宅しているなどのケースを除き、通常逮捕は日中におこなわれる可能性が低いと考えられるでしょう。
2.帰宅後を狙った通常逮捕はありえる
通常逮捕は、被疑者が自宅などに所在する可能性が高いタイミングを狙っておこなわれます。
そのため、おはよう逮捕と並んで、帰宅後逮捕も頻繁に実施されています。
被疑者が社会人や学生などで、帰宅後のほうが身柄を拘束できる可能性が高い場合には、帰宅後に警察官が自宅を訪問して通常逮捕をおこないます。
3.深夜の通常逮捕は基本的には少ない
刑事訴訟法第116条第1項では、夜間の令状執行について以下のような制限を定めています。
第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
日没後、日の出前の深夜に通常逮捕をおこなうには、深夜執行について裁判所の事前許可がある場合に限られています。
そのため、深夜に通常逮捕がおこなわれるケースは稀だといえるでしょう。
おはよう逮捕に関するよくある質問
さいごに、おはよう逮捕についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
Q.おはよう逮捕と通常逮捕に違いはあるのか?
おはよう逮捕は、通常逮捕の一類型です。
通常逮捕のうち、午前6時〜午前9時頃を目安に実行されるものを、特におはよう逮捕と呼称しているだけに過ぎません。
おはよう逮捕と通常逮捕には違いはありませんし、おはよう逮捕の要件や手続きについては、刑事訴訟法などの通常逮捕のルールに沿って判断されます。
Q.早朝に自宅へ逮捕に来ないよう交渉できるか?
おはよう逮捕が実施されるタイミングを被疑者側でコントロールすることはできません。
「早朝自宅を訪問されると家族や近隣住民に迷惑がかかるから」「早朝は家事などで忙しいから」などの理由があったとしても、捜査機関側がおはよう逮捕に踏み出すと判断した場合には、躊躇なく身柄が押さえられます。
ただし、おはよう逮捕をされないように事前にリスクヘッジをするのは不可能ではありません。
たとえば、出頭要請に素直に応じる、任意の事情聴取で正直に犯行を自供する、捜査機関から提出を求められた証拠物を素直に提出するなど、逃亡または証拠隠滅のおそれがないと判断される状況を作り出せば、おはよう逮捕を回避し、在宅事件として刑事手続きが進められるでしょう。
Q.おはよう逮捕されたあとはどうなる?
おはよう逮捕をされると、そのまま警察署に連行されて、警察官からの取り調べを受けなければいけません。
逮捕後は警察や検察で取り調べを受け、必要に応じて勾留がおこなわれます。
起訴されない場合でも、最長23日間は身柄を拘束される可能性がある点に注意が必要です。
そして、身柄拘束期間は、当然外部との連絡は取れません。
そのため、学校や職場を無断で休むことになり、日常生活に支障をきたすおそれもあります。
おはよう逮捕からの早期釈放を目指すためには、弁護士へ相談して保釈のために働きかけてもらうことが大切です。
さいごに|一般的に通常逮捕は「おはよう逮捕」になることが多い!
刑事事件を起こして通常逮捕の判断が下される場合には、おはよう逮捕の方法で身柄が拘束されることが多いです。
ただ、早朝に警察官がやってきて逮捕や捜索差し押さえが実行されると、家族や近隣住民にも迷惑がかかりますし、何より、被疑者の日常生活にさまざまな悪影響が生じかねない点に注意が必要です。
そのため、刑事事件を起こしておはよう逮捕のリスクに晒されている場合には、任意の事情聴取に丁寧に対応したり、自首をして在宅事件処理の可能性を高めたりするなどの工夫が必要だと考えられます。
ベンナビ刑事事件では、おはよう逮捕への対策などを得意とする弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回の相談料無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、おはよう逮捕のリスクに晒されて不安を抱えているなら、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。

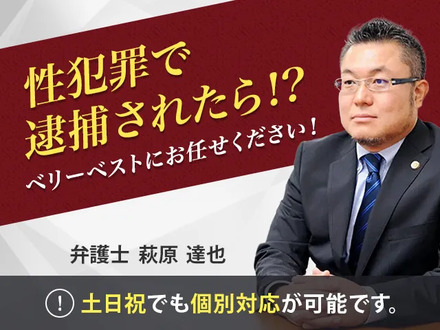
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る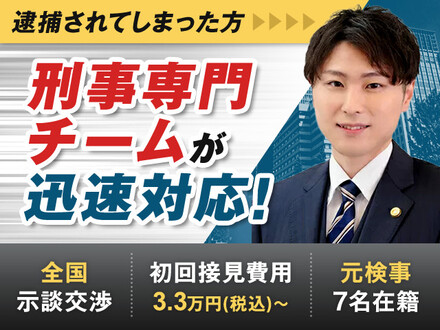
【銀座駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る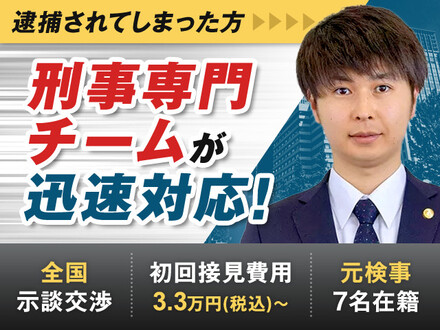
【町田駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事処分の種類と内容に関する新着コラム
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容に関する人気コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
刑事処分の種類と内容の関連コラム
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
実刑(じっけい)とは、執行猶予が付かずに懲役刑や禁錮刑で刑務所に収監されるという判決を受けてしまうことです。実刑判決を受けてしまうと、その後、数カ月...
-
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ...
-
精神鑑定の結果心神喪失状態にあると判定されると、無罪になる可能性があります。本記事では、刑事事件を 起こした人物が精神鑑定を経て無罪になる理由、無...
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
偽計業務妨害罪は身近にある犯罪であり、実際に自身の行為が該当するのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、偽計業務妨害...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
本記事では、立ちションと罰金の関係が気になる方に向けて、立ちションだけなら罰金になる可能性はないこと、立ちションと一緒に成立する可能性がある犯罪4選...
刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る


















































