逮捕されるのは何歳から?未成年が逮捕される可能性や回避方法を解説

未成年が犯罪行為をおこなった場合、「子どもだから逮捕はされない」と思う方は多いのではないでしょうか。
しかし、実は一定の年齢を超えると、未成年でも法律上逮捕されることがあります。
とはいえ、未成年の場合は成人とは異なり、少年法によって守られている部分も多いため「何歳から」「どのような場合に」逮捕されるのかを正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、逮捕される年齢の基準や、未成年が逮捕されるケース、逮捕を回避するためのポイントをわかりやすく解説します。
お子さんの行動に不安を感じている方や、万が一トラブルが起きた場合の対応を知っておきたい方は、ぜひ最後まで参考にしてください。
逮捕されるのは何歳から?未成年でも逮捕される?
未成年が罪を犯した場合の取り扱いは、年齢によって大きく異なります。
法律では明確に年齢の境界線が設けられており、その基準となるのが「14歳」です。
14歳以上か未満かによって、逮捕の可能性からその後の手続きまで全く違う流れとなります。
以下では、14歳以上と14歳未満のそれぞれのケースについて、逮捕の可能性や適用される法律を見ていきましょう。
未成年でも14歳以上であれば逮捕される可能性がある
日本の法律では、14歳以上の未成年は「犯罪少年」として扱われ、成人と同様に逮捕される可能性があります。
また、14歳以上になると警察による逮捕・取り調べ・勾留など、成人とほぼ同じ刑事手続きがおこなわれる場合があります。
ただし、未成年者は少年法の対象となるため、裁判所では「刑罰」ではなく「保護処分(少年院送致や保護観察など)」を通じて更生を目的とした対応が取られるのが通常です。
なお、2022年4月1日以降、成人年齢が18歳となったことで、「18歳・19歳の場合は成年・未成年どちらで扱われるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
犯罪行為をおこなったのが18歳・19歳の場合、「特定少年」として扱われ、少年法の適用を受けつつも成人に近い扱いとなります。
具体的には、2022年4月の少年法改正により、原則逆送対象事件の拡大や実名報道の解禁など、より厳格な運用がなされるようになりました。
さらに、重大な犯罪を犯した場合には、家庭裁判所から検察官送致(逆送)され、成人と同じ刑事裁判を受ける可能性もあります。
14歳未満は逮捕されず刑事責任にも問われない
犯罪行為をおこなったのが14歳未満の場合、逮捕されることはありません。
刑法第41条では、犯罪における責任年齢について以下のとおり定められているからです。
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
14歳未満の加害者は「触法少年」として扱われ、たとえ重大な犯罪を犯しても逮捕や勾留といった強制的な身柄拘束はおこなわれません。
これは刑事責任能力がないものとみなされるためです。
ただし、全く何も措置が取られないわけではありません。
被害者が死亡するなど重大な事件の場合は、児童相談所による一時保護措置が取られ、事実上身柄を拘束される可能性があります。
また、家庭裁判所での少年審判が開かれ、児童自立支援施設への送致や保護観察といった保護処分が決定される場合もあり、適切な指導・教育を受けることになります。
未成年が逮捕されたあとの流れ
14歳以上の未成年が逮捕された場合、以下の流れで手続きが進みます。
- 警察の取り調べ
- 検察官による取り調べ
- 勾留・観護措置による身柄拘束
- 家庭裁判所への送致
- 少年審判後、処分の決定
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
1.【最大48時間】警察で取り調べを受ける
逮捕された未成年は警察署の留置場に身柄が拘束され、最長で48時間にわたって警察官による取り調べを受けます。
警察は事件の概要や動機、経緯などについて聞き取りをおこない、終了後は検察官に送致されます。
ただし、罰金以下の刑にあたる軽微な犯罪の場合は、警察から直接家庭裁判所に送致されるケースもあります。
なお、特定少年(18歳・19歳)が逮捕された場合は、罰金以下の刑にあたる犯罪行為であっても検察官に送致されます。
2.【最大24時間】検察へ送致され検察官の取り調べを受ける
警察から送致を受けた検察官は、引き続き取り調べをおこないます。
検察官による取り調べは最長24時間です。
検察官は取り調べを通じて、以下のいずれかを判断します。
- 家庭裁判所に送致する
- さらなる取り調べのため、裁判所に勾留を請求する
検察官が勾留を請求し、裁判所が認めた場合は、引き続き身柄拘束が続くことになります。
3.【最大20日間】勾留・観護措置による身柄拘束が続く
裁判所が勾留を認めた場合、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長を含めて最長20日間の勾留が可能です。
警察での取り調べ期間(最大3日間)を加えると、合計で最長23日間拘束されることになります。
ただし、少年事件で勾留が認められるのは「やむを得ない場合」に限られており、少年法第43条1項に基づいて、より適切な環境で身柄を確保するための「勾留に代わる観護措置」が取られるケースもあります。
勾留に代わる観護措置の特徴は、以下のとおりです。
- 収容場所: 少年鑑別所
- 期間: 10日間(延長不可)
- 目的: 少年の生活状況や性格を観察し、適切な処遇を検討するため
つまり、未成年が逮捕された場合も、成人と同様に長期間拘束される可能性はあるものの、少年法によって「更生を目的とした手続き」が優先される点が大きな違いといえます。
4.家庭裁判所へ送致される
未成年が関わる事件は、捜査が終了すると全て家庭裁判所に送られるのが原則です。
これは「全件送致主義」と呼ばれる仕組みで、成人事件のように検察官が起訴・不起訴を判断することはありません。
警察の捜査が終わると、事件は必ず家庭裁判所に送致され、少年法に基づく手続きに移ります。
家庭裁判所では、事件を受け取ったあとに「少年審判をおこなうかどうか」を判断するため、家庭裁判所調査官が少年本人や家庭環境の調査を開始します。
さらに、より専門的な観察が必要と判断された場合は、送致から24時間以内に少年鑑別所での「観護措置」が取られます。
その後、調査結果をもとに家庭裁判所が以下のいずれかを決定します。
- 少年審判の開始: 少年の処遇(保護観察や少年院送致など)を判断するために審判を開く
- 審判不開始: 軽微な事件で、反省が見られ再非行の恐れがない場合など、審判を開く必要がないと判断されたときに事件終了
つまり、少年事件では「起訴・不起訴」ではなく、「審判をおこなうかどうか」が重要な分かれ目となるのです。
5.少年審判を受け処分が決定される
家庭裁判所調査官による調査完了後、審判開始が決定されると少年審判が実施されます。
少年審判は家庭裁判所で開催され、少年本人、裁判官、裁判所書記官、調査官、事務官、保護者、付添人(弁護士等)が出席します。
成人の刑事裁判と似た流れですが、非公開で実施され、検察官は基本的に立ち会いません。
裁判官は、少年の年齢、事件の重大性、本人の反省状況、家庭環境、再犯可能性などを総合的に評価し、最も適切な処分を決定します。
処分決定により一連の少年事件の手続きが完了となります。
少年審判で決定される処分の種類
少年審判で下される処分には、以下4つの種類があります。
- 保護処分
- 知事・児童相談所長送致
- 検察官送致
- 不処分
それぞれの処分内容について、詳しく見ていきましょう。
保護処分
保護処分は、少年の更生と社会復帰を目的とした処分で、以下の3つに分類されます。
- 保護観察処分
少年が家庭で生活しながら社会内での更生を図る処分です。
保護観察官や保護司による指導・監督のもと、遵守事項を守りながら月数回の面会を通じて近況報告をおこないます。 - 児童自立支援施設・児童養護施設送致
主に低年齢の児童を対象とした開放的な施設での処分です。
施設内の学校に通学し、他児童との共同作業やクラブ活動を通じて自立支援を受けます。 - 少年院送致
再非行のおそれが大きく社会内更生が困難と判断された場合の処分です。
教科教育や職業訓練を受けながら規律正しい集団生活を送り、社会適応能力を身につけます。
知事・児童相談所長送致
知事・児童相談所長送致とは、18歳未満の少年について、児童福祉法による措置に委ねるため都道府県知事または児童相談所長に送致する処分です。
非行の度合いは高くないものの、家庭環境に問題があり継続的な保護・指導が必要な少年が対象となります。
送致後は、児童福祉司による指導措置や児童自立支援施設への入所措置などが決定されます。
この処分は少年法ではなく児童福祉法の枠組みで対応することで、より適切な環境での保護と指導を実現することを目的としています。
検察官送致
検察官送致は、刑事処分が相当と認められる場合に検察官へ送致する処分です。
死刑や拘禁刑にあたる罪で刑事処分が適当と判断された場合や、16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件では、原則として検察官送致となります。
なお、2022年の少年法改正により、18歳・19歳の特定少年については、死刑、無期または短期1年以上の拘禁刑にあたる事件で原則逆送が適用されようになりました。
送致を受けた検察官は原則として起訴し、少年は成人と同様の刑事裁判を受けることになります。
不処分
不処分は、少年に対して特別な処分をおこなわない決定です。
少年が非行をおこなったと認められない場合や、非行があっても教育的働きかけにより非行のおそれが取り除かれた場合に選択されます。
この処分により少年の身柄は釈放され、特に制約を受けることなく日常生活に復帰できます。
未成年が逮捕されたらどうなる?考えられる主なリスク
ここからは、未成年が逮捕された場合のリスクについて、詳しく説明します。
退学になる可能性がある
未成年が逮捕された場合、学校から退学処分を受ける可能性があります。
学校教育法施行規則26条3項では、「性行不良で改善の見込がないと認められる者」や「学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者」に対して退学処分が可能とされています。
逮捕の事実がこれらの事由に該当すると判断されれば、退学処分もあり得るでしょう。
また、正式な退学処分を避けるために自主退学を促されるケースもあります。
ただし、公立の小・中学校は義務教育のため退学処分はありません。
14歳以上は前科がついて進学・就職で不利になるなどの影響が生じる可能性がある
14歳以上の未成年が重大事件で検察官送致され、有罪判決を受けると前科がつきます。
そうなると、将来にわたって以下のような影響が生じる可能性があります。
- 就職活動で前科の申告を求められる場合がある
- 採用時の経歴調査で不利になる可能性がある
- 弁護士、教員、警備員など特定の職業に就けない
- インターネット上に情報が残るリスクが高い
- 海外留学や旅行時に入国制限される可能性がある
- 結婚や家庭生活に影響を与える場合がある
- 前科があることで重い処分を受けるおそれがある
- 社会復帰がより困難になる可能性がある
これらの影響は長期間にわたって続く可能性があり、人生設計全体に大きな影響を与えることがあります。
18歳以上は実名で報道されるおそれがある
18歳、19歳の特定少年については、令和4年の少年法改正により実名報道の規制が一部緩和されました。
そのため、逮捕されたのが18歳・19歳の場合は実名報道がされ、テレビやネットで名前が出回ってしまう可能性があります。
実名報道による私生活への影響は計り知れません。
少年本人はもちろん、親や家族にまで悪影響を及ぼすリスクがあるでしょう。
ただし、全ての事件で実名報道されるわけではなく、報道機関の判断に委ねられています。
未成年が逮捕されないためにできること
未成年であっても逮捕される可能性がある以上、事前に適切な対応を取ることが重要です。
以下では、逮捕のリスクを軽減するために取るべき行動について解説します。
まずは親に相談する
逮捕されるかもしれない不安があるときは、まず親に相談することが最も重要です。
未成年で犯罪に当たる行為をした場合、自力での解決は困難であり、必ず周囲の大人の協力が必要となります。
自分のした行為を親に打ち明けることは勇気がいりますが、逮捕されれば結果的に親に知られることになってしまいます。
そのため、早い段階で親に相談し、今後の対応を一緒に考えてもらうほうが賢明です。
親の協力があることで、適切な対応策を検討でき、逮捕のリスクを軽減できる可能性が高まります。
自首することも選択肢に入れておく
逮捕を回避したい場合、自首することも重要な選択肢の一つです。
犯罪の捜査では、容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、逮捕せずに在宅のまま事件の捜査を進めることがあります。
自首は自ら警察署に出向いて犯行を告白する行為であり、逃亡とは正反対の行動です。
とくに親の監督下で生活する未成年の場合、自首により逃亡のおそれがないと判断され、逮捕される可能性が低くなると考えられます。
刑事事件の対応が得意な弁護士に相談する
逮捕のリスクを軽減するためには、刑事弁護に強い弁護士への相談が効果的です。
未成年の刑事事件は少年法の適用により、成人とは異なる特殊な手続きが適用されます。
また、逮捕の可能性も年齢によって変わるなど、高度な法的知識が必要です。
刑事弁護に豊富な経験を持つ弁護士であれば、少年事件特有のポイントを理解しており、個別の事情に応じた適切なアドバイスを提供できます。
早期の相談により、最適な対応策を検討し、逮捕回避の可能性を高めることができるでしょう。
弁護士による活動で解決した未成年者の逮捕事例
ここでは、未成年が犯罪行為によって逮捕されてしまったものの、弁護士の関与によって軽い処分で済んだ事例を紹介します。
弁護士に相談すべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
友達にそそのかされオレオレ詐欺に加担してしまった少年の逮捕事例
地元の友達から誘われて詐欺グループに加担してしまった少年が現行犯逮捕された事案です。
弁護士は、複数回の面談を通じて少年から反省と謝罪の気持ちを引き出し、全ての被害者との示談交渉を成功させました。
また、家庭裁判所調査官との話し合いにより少年の変化と更生への取り組みを示した結果、家庭裁判所で不処分の決定を獲得しています。
女の子にわいせつ行為をおこない逮捕された中学生の逮捕事例
中学生がショッピングモールで女の子にわいせつ行為をおこない逮捕された事案です。
弁護士は少年本人との面会を重ねながら事件の原因を究明し、家庭環境や学校関係に問題がないことを確認しました。
また、早期の身柄開放を実現し、カウンセリングの紹介や再犯防止に向けた家族との面談を繰り返し実施した結果、通常の一般保護観察よりも軽い一般短期保護観察での解決となりました。
強盗致傷の嫌疑をかけられ逮捕された少年の逮捕事例
複数の少年が1人の少年からバイクと現金を奪ったとされる事件で、依頼人は「その場にいただけで何もしていない」と主張していた否認事件です。
弁護士は依頼人の言い分を詳細に聞き取り、現場確認や周辺への聞き込み調査を実施しました。
その後、依頼人の主張をまとめた書面を検察官に提出した結果、家庭裁判所に送致されることなく釈放され、学校生活に復帰することができました。
未成年の逮捕に関してよくある質問
さいごに、未成年者の逮捕に関して保護者や本人からよく寄せられる疑問について解説します。
未成年が逮捕されると親に連絡がいく?
未成年者が逮捕された場合、警察から親に連絡がいくことがほとんどです。
なぜなら、未成年の釈放時における身元引受人が保護者になるケースが多いからです。
逮捕後は、勾留も含めて起訴・不起訴の判断が下されるまで最大23日間にわたって自宅に帰れなくなります。
この期間中に未成年者の行方不明事件として警察に相談される可能性があることから、逮捕の連絡を入れることが実務上の運用となっています。
未成年が逮捕された場合も逮捕歴は残る?
未成年であっても、14歳以上であれば逮捕歴がつくことはあります。
年齢に関係なく、逮捕という手続きを経た以上は記録として保管されることになるのです。
さいごに|未成年も逮捕される可能性はある!まずは弁護士に相談を!
14歳以上の未成年は成人と同様に逮捕される可能性があります。
「未成年だから大丈夫」という考えは通用せず、逮捕後は最大23日間の身柄拘束を受け、その後の人生に深刻な影響を与えるリスクがあります。
もし犯罪に当たる行為をしてしまい、逮捕の不安を抱えている場合は、一人で悩まずに早急に対応することが重要です。
まずは信頼できる親や保護者に相談し、その上で刑事弁護に精通した弁護士のサポートを求めることをおすすめします。
適切な初期対応により逮捕を回避できる可能性もあり、仮に逮捕されても軽い処分で済む場合があります。
未来への影響を最小限に抑えるためにも、弁護士の力を借りながら最善の解決策を見つけてください。

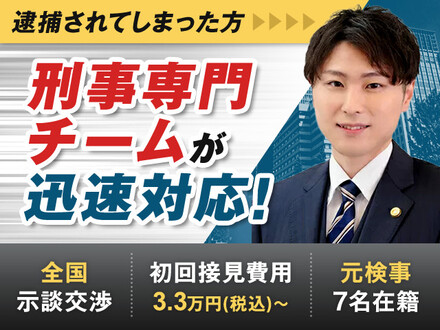
【銀座駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る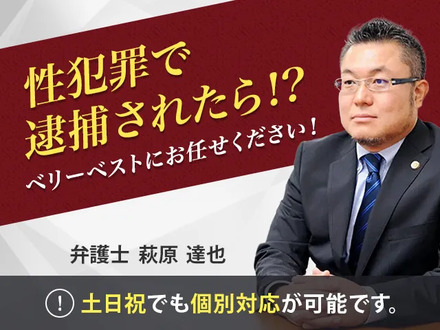
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る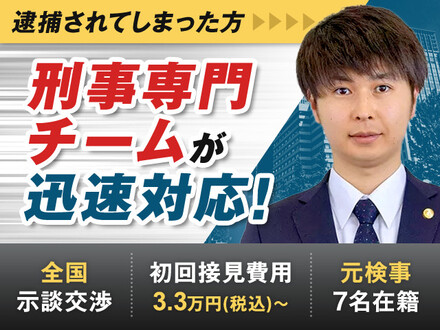
【町田駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事処分の種類と内容に関する新着コラム
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容に関する人気コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
刑事処分の種類と内容の関連コラム
-
本記事では、立ちションと罰金の関係が気になる方に向けて、立ちションだけなら罰金になる可能性はないこと、立ちションと一緒に成立する可能性がある犯罪4選...
-
未成年者への酒類提供は、店舗だけでなく提供した従業員個人も刑事罰や行政処分の対象となる可能性があります。本記事では、具体的な罰則内容や、裁判例を交え...
-
偽計業務妨害罪は身近にある犯罪であり、実際に自身の行為が該当するのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、偽計業務妨害...
-
殺害された人が生前殺されることを承諾していた場合、犯行に及んだ人物は殺人罪ではなく、承諾殺人罪の容疑で刑事訴追されます。本記事では、承諾殺人の構成要...
-
業務をしているとき、過失によって事故を起こしてしまったら、業務上過失致死傷罪に問われます。業務上過失致死傷罪に該当するのは、どのような事故のときなの...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
精神鑑定の結果心神喪失状態にあると判定されると、無罪になる可能性があります。本記事では、刑事事件を 起こした人物が精神鑑定を経て無罪になる理由、無...
-
未成年者の飲酒は法律で禁止されており、20歳未満はお酒を飲むことはできません。2022年4月から成人年齢は18歳になりましたが、飲酒は20歳からです...
-
仮釈放は早く社会復帰することが可能な重要な制度です。この記事では①仮釈放期間はどのように決定されるのか②受けるための条件③仮釈放を要求する方法④仮釈...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
刑事罰には「執行猶予」という猶予期間が設けられるケースがありますが、刑事罰の最高刑である死刑においても執行猶予が付くことはあるのでしょうか? 本記...
-
禁錮とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰で、刑務作業が義務付けられていないもののことです。この記事では懲役との違いを踏まえながら、禁錮とはどのような...
刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る























































