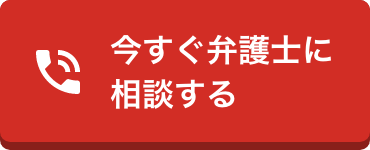偽証罪は証人が嘘を付く罪|罪の定義と類似の罪


偽証罪(ぎしょうざい)とは、法律のより宣誓した証人が虚偽の陳述を行うことに対する犯罪です。法定刑は、3ヶ月以上10年以下の懲役という重い罰則が設けられている犯罪です。
裁判所で宣誓した証人が嘘の証言を行うと、偽証罪に問われることになります。実際に、偽証罪が身近に起きるようなことはほとんどないのですが、偽証罪の定義や関連の罪などについて解説していきたいと思います。
偽証罪の定義
それでは、偽証罪とはどのような罪になるのかをこちらで解説していきたいと思います。
偽証罪については刑法169条に明記
偽証罪については刑法169条に、
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。
と、記載があります。
主体は宣誓した証人のみ
偽証罪の対象となる人物は、「法律による宣誓をした証人のみ」です。法律による宣誓については後述しますが、刑事裁判や民事裁判で証言を求められた証人のみですので、刑事裁判の被告人や、民事裁判での原告・被告がうその証言をしたからと言って、偽証罪に問われることはありません。
もちろん、被告人や原告・被告がうその証言をしたことが発覚したのであれば、刑事裁判においては裁判官からの印象は悪くなり、判決による刑罰にも影響してくるでしょう。
また、民事裁判の場合に、原告・被告がうその証言をした場合、民事訴訟法により10万円以下の過料が科されることがあります。
法律による宣誓とは
偽証罪の「法律による宣誓」とは、刑事事件の場合は「刑事訴訟法」、民事事件の場合は「民意訴訟法」による宣誓のことを言います。つまり、裁判で宣誓を行った証人がうその証言を行った場合に偽証罪が成立するのです。
「知らない」とうそをついた時は?
証言をする際に、よく「記憶にない」などの証言がされることがあります。実際に記憶がないのであれば問題ないのですが、裁判の原告・被告・被告人をかばうために知らないと証言の拒否をしたり、虚偽の証言をすると、宣誓証言拒否罪や偽証罪に該当することもあります。
偽証罪の罰則
偽証罪の罰則は、【3ヶ月以上10カ月以下の懲役】です。
偽証罪に類似した罪と罰則
偽証罪には似たような罪がいくつかありますので、こちらでご紹介いたします。
宣誓証言拒否罪
裁判では、証言を拒絶できる「証言拒絶権」というものがあります。しかし、正当な理由なく宣誓や証言を拒んだ場合は、宣誓証言拒否罪に該当します。
宣誓証言拒否罪の罰則は、【10万円以下の罰金または拘留】です。情状によっては、罰金と拘留の併科がされることもあります。
正当な理由の宣言・証言の拒否(証言拒絶権)
正当な理由、すなわち宣言拒絶権として認められている内容は以下のとおりです。
【民事訴訟の場合】
・自己や自己の一定範囲の親族等(配偶者・4親等内の血族・3親等内の姻族(これらの関係にあった者)、後見人、被後見人)が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項や、これらの者の名誉を害すべき事項(民事訴訟法196条)
・公務員の職務上の秘密(民事訴訟法197条1項1号)
・医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教・祈祷・祭祀の職にある者(これらの職にあった者)が職務上知り得た事項で黙秘すべきもの(民事訴訟法197条1項2号)
・技術又は職業上の秘密に関する事項(民事訴訟法197条1項3号)
引用元:証言拒絶権-Wikipedia
【刑事訴訟の場合】
・自己や自己の一定範囲の親族等(配偶者・3親等内の血族・2親等内の姻族(これらの関係にあった者)、後見人・後見監督人・保佐人、被後見人・被保佐人)が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある証言(刑事訴訟法146条、147条)
・医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が業務上知り得た事実で他人の秘密に関するもの(刑事訴訟法149条)
引用元:証言拒絶権-Wikipedia
虚偽告訴罪
同じく、うそをつくことが犯罪になるものとして、「虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)」というものがあります。端的にお伝えすると、相手に刑事処分を受けさせるために嘘の刑事告訴を行なった場合に成立する罪です。
法定刑は、【3ヶ月以上10年以下の懲役】と、偽証罪と同じです。
関連記事:虚偽告訴罪(誣告罪)とは|痴漢をはじめとする冤罪の防御策
虚偽鑑定等罪
虚偽鑑定等罪とは、法律により宣言した鑑定人・通訳人・翻訳人などがうその鑑定や通訳、翻訳を行った際に成立する犯罪です。法定刑は、【3ヶ月以上10年以下の懲役】と、偽証罪と同じ法定刑が設けられています。
まとめ
いかがでしょうか。このように、裁判での証人に対する犯罪も存在しています。
特に刑事事件では、刑事裁判で法廷に立つ身近な方のために情状証人となる方もいるでしょうが、被告人の都合の良いようにうその証言をしたような場合、罪に問われることもありますので注意が必要です。
もしも、証人として法廷に立つようなことがある場合は、一度弁護士にアドバイスを受けることをおすすめします。
関連記事:情状証人の役割とは|選ばれる人や責任・証言時の注意点を解説



【スピード重視】【電話/メール/LINEのお問い合わせ24時間受付中】盗撮/風俗店トラブル/不同意わいせつ/痴漢/暴行/傷害/窃盗/援助交際など、幅広い刑事事件に迅速対応いたします!経験豊富な弁護士にお任せください!
事務所詳細を見る
【刑事少年事件専門・24時間365日受付・無料相談・全国に支店】年間相談数3000件超、年間解決事例数約500件、釈放保釈多数の圧倒的実績で社会復帰を強力に弁護する刑事特化のリーディングファーム
事務所詳細を見る
【全国対応】警察から捜査されている/家族が逮捕されてしまった場合は、今すぐご相談を!前科回避・示談交渉・早期釈放など、迅速かつスムーズに対応いたします《逮捕前のサポートプランあり》詳細は写真をタップ!
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



詐欺事件を起こしたらに関する新着コラム
-
本記事では、闇バイトに関与してしまった場合に弁護士に相談すべき理由と、その具体的な対応方法について詳しく解説します。
-
結婚詐欺で逮捕されると、詐欺罪で10年以下の懲役刑になる可能性があります。この記事では、結婚詐欺で逮捕された後の流れや前科を回避する方法などを加害者...
-
給付金詐欺とは、一般的に国や自治体の支援金や補助金を嘘の申請によって不正に受け取る詐欺行為を指します。例えば、2020年は新型コロナウイルスの対策と...
-
保険金詐欺とは、保険金が受け取れる条件を満たすために虚偽の申し出をしたり、わざと事故などを起こしたりして不正に保険金をだまし取る詐欺行為のことです。
-
本記事では、詐欺の共犯が成立する条件や逮捕されたときの流れを解説します。
-
詐欺事件を起こしてしまったら早急に弁護士に相談しましょう。刑事手続きにはタイムリミットがあり、早期釈放や減刑獲得のためにはスピーディな対応が重要です...
-
詐欺罪はニュースなどでも頻繁に取り上げられ、身近に存在することを実感する犯罪のひとつです。詐欺の構成要件は4つに分類されますが、複雑なものではなく身...
-
詐欺罪の初犯は執行猶予がつくのか、初犯でも実刑となるのか。この記事では、詐欺罪の初犯について、量刑相場や、不起訴処分または執行猶予を獲得するためのポ...
-
本記事では、詐欺事件での示談のメリット・示談金の相場・示談の流れや方法・示談金が支払えない場合の対応・弁護士に依頼するメリットなどをわかりやすく解説...
-
詐欺の受け子で逮捕された場合、たとえ初犯でも実刑判決となる可能性があります。少しでも状況の改善を望む方は、早い段階で弁護活動を受けるのが有効でしょう...
詐欺事件を起こしたらに関する人気コラム
-
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と定められています。本記事では、詐欺罪が成立する要件や弁護士に無料相談できる窓口、詐欺罪の刑事手続で知っておきたいこ...
-
詐欺罪とは、刑法246条に規定された人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役が法定刑で定められています。他人を騙して金品をだ...
-
結婚詐欺は、男性・女性問わずたくさんの人が被害に遭っています。信じていた人が実は結婚詐欺師だったということもよくある事例ですので、ぜひこの記事をご覧...
-
詐欺罪はニュースなどでも頻繁に取り上げられ、身近に存在することを実感する犯罪のひとつです。詐欺の構成要件は4つに分類されますが、複雑なものではなく身...
-
偽証罪(ぎしょうざい)とは、法律のより宣誓した証人が虚偽の陳述を行うことに対する犯罪です。法定刑は、3ヶ月以上10年以下の懲役という重い罰則が設けら...
-
寸借詐欺(すんしゃくさぎ)とは、「財布を落とした」「交通費を忘れた」などとうそをつき、相手の善意に付け込んで、金銭をだまし取る行為のことをいいます。...
-
本記事では、詐欺の共犯が成立する条件や逮捕されたときの流れを解説します。
-
詐欺罪の初犯は執行猶予がつくのか、初犯でも実刑となるのか。この記事では、詐欺罪の初犯について、量刑相場や、不起訴処分または執行猶予を獲得するためのポ...
-
経歴詐称とは、一般的に学歴や職歴を偽ることです。簡単に言うと自分の経歴についてうそをつくことですが、場合によっては、うそでは済まされないこともありま...
-
詐欺の受け子で逮捕された場合、たとえ初犯でも実刑判決となる可能性があります。少しでも状況の改善を望む方は、早い段階で弁護活動を受けるのが有効でしょう...
詐欺事件を起こしたらの関連コラム
-
保険金詐欺とは、保険金が受け取れる条件を満たすために虚偽の申し出をしたり、わざと事故などを起こしたりして不正に保険金をだまし取る詐欺行為のことです。
-
偽証罪(ぎしょうざい)とは、法律のより宣誓した証人が虚偽の陳述を行うことに対する犯罪です。法定刑は、3ヶ月以上10年以下の懲役という重い罰則が設けら...
-
結婚詐欺は、男性・女性問わずたくさんの人が被害に遭っています。信じていた人が実は結婚詐欺師だったということもよくある事例ですので、ぜひこの記事をご覧...
-
詐欺罪とは、刑法246条に規定された人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役が法定刑で定められています。他人を騙して金品をだ...
-
寸借詐欺(すんしゃくさぎ)とは、「財布を落とした」「交通費を忘れた」などとうそをつき、相手の善意に付け込んで、金銭をだまし取る行為のことをいいます。...
-
本記事では、詐欺事件での示談のメリット・示談金の相場・示談の流れや方法・示談金が支払えない場合の対応・弁護士に依頼するメリットなどをわかりやすく解説...
-
経歴詐称とは、一般的に学歴や職歴を偽ることです。簡単に言うと自分の経歴についてうそをつくことですが、場合によっては、うそでは済まされないこともありま...
-
オークション詐欺で逮捕された場合には詐欺罪が適用され、10年以下の懲役刑を科される可能性があります。この記事では、オークション詐欺になる行為とその刑...
-
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と定められています。本記事では、詐欺罪が成立する要件や弁護士に無料相談できる窓口、詐欺罪の刑事手続で知っておきたいこ...
-
本記事では、詐欺の共犯が成立する条件や逮捕されたときの流れを解説します。
-
サクラも詐欺罪で逮捕される場合があることをご存知ですか?サクラでも詐欺の共犯又は従犯と評価される可能性もあり、逮捕の可能性があります。今回はこのよう...
-
詐欺罪の初犯は執行猶予がつくのか、初犯でも実刑となるのか。この記事では、詐欺罪の初犯について、量刑相場や、不起訴処分または執行猶予を獲得するためのポ...
詐欺事件を起こしたらコラム一覧へ戻る