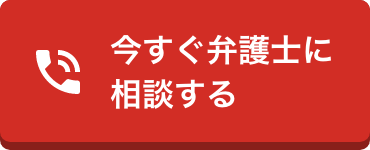【加害者限定】
【加害者限定】お急ぎの方へ

累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
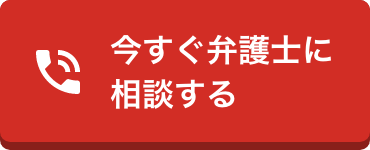
詐欺罪とは「他人のお金をだまし取ったりする犯罪」のことを指しますが、詐欺罪が成立するには定められた構成要件を満たしている必要があります。
例えば、予期せぬ事情によって借りていたお金を返せなくなったケースや、はじめから嘘をついていることがバレていたケースなどでは、構成要件を満たしておらず詐欺罪が成立しないこともあります。
なお、詐欺というと熟達した犯罪者や緻密な知能犯罪者を想像しがちですが、なかには一般人が詐欺だと知らずに詐欺事件に関わってしまい、共犯者として逮捕されることもあります。
2020年版の犯罪白書によると、2019年の詐欺事件の検挙件数は1万5,902件にのぼり、これは窃盗・暴行・傷害に次いで4番目の多さです。「遠い世界の話だと思っていたが、家族が詐欺容疑で逮捕された」ということがあるかもしれません。
この記事では、詐欺罪が成立する条件や罰則、逮捕後の流れや減刑獲得のポイントなどを解説します。
ご家族や自身が詐欺罪で逮捕された方へ
詐欺罪で逮捕されると、10年以下の懲役を科される可能性があります。
そういった事態を防ぎ、不起訴や執行猶予付き判決を獲得するためには、ただちに弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士ならば、下記のような弁護活動を効果的におこなえます。
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 被害者と示談・損害賠償を行い宥恕文言(処罰を望まないこと)を得る
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
逮捕後72時間以内に接見できるのは弁護士のみです。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)では、初回相談無料・土日対応可・即日対応可の事務所を掲載しています。
対応を間違い後悔しないためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|
刑法第246条|詐欺罪の構成要件と罰則

まずは刑法第246条に規定されている、詐欺罪の条文を確認しましょう。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:第246条|刑法
一般的にイメージされるような、人をだまして金品などの財産を奪う行為は「1項」に該当します。ここでいう財物とは、現金や貴金属類といった価値が高い物品はもちろん、不動産や有価証券なども含まれます。
「2項」が示す「財産上不法の利益を得ること」とは、支払いの義務を免れる行為だと解釈すればよいでしょう。例えば、タクシーの無賃乗車、ホテルの無銭宿泊、レストランの無銭飲食などが該当します。
詐欺罪に問われる4つの構成要件
詐欺罪が成立するのは、欺罔・錯誤・交付行為・財産移転といった4つの構成要件が、全てそろっている場合です。
これら4つの構成要件のうち一つでも欠ければ、詐欺罪が成立しないか、または未遂となります。
欺罔(ぎもう)
詐欺罪の構成要件のうち、特徴的で重要なのが「欺罔(ぎもう)」です。難しい用語ですが、簡単にいえば「人をだますために嘘をつくこと」を指していると考えればよいでしょう。
嘘の口実によって、詐欺の手口は以下のように分類されます。
- 仕事をしていないのに「月末の給料でお金を返す」と嘘をいう(借用詐欺)
- 結婚するつもりがないのに「借金を肩代わりしてくれれば結婚できる」と嘘をいう(結婚詐欺)
- 他人の物件なのに「代金を先払いしてくれればマンションを譲る」と嘘をいう(不動産詐欺)
なお、以下のように嘘でなく真実を伝えていた場合には、詐欺罪は成立しません。
- 月末の給料でお金を返すつもりだったが、ほかの支払いが多く返済にまわせなかった
- 結婚の意思はあったが、周囲に強く反対されて叶わなかった
- 実際に自分の物件を譲る意思はあったが、差押えられて売却できなくなった
上記のように、予期せず約束が果たせない事態に陥った場合は、詐欺罪ではなく民事上の「債務不履行」にあたるものと考えられます。
この場合、被害者は加害者に対する刑罰を求めることはできませんが、裁判によって損害賠償を求めることは可能です。
錯誤
欺罔の次の段階にあるのが「錯誤」です。
錯誤とは、発言した者が内心で思っていることと意思表示の内容が一致しておらず、そのことについて相手が気づいていないことです。嘘を伝えられた相手が、「真実ではないことを真実だと信じていること」だと考えればよいでしょう。
例えば、「月末の給料で返済する」という嘘を伝えられて、「月末にはちゃんと返済してもらえる」と信じ込んでしまう状態が典型例です。
なお、「最初から嘘だとわかっていた」という場合には、被害者が錯誤に陥っているとはいえないので詐欺罪は成立せず、犯罪不成立または詐欺未遂となる可能性があるでしょう。
振り込め詐欺に対する捜査手法として用いられるような「だまされたフリ作戦」なども、かつて「被害者が錯誤の状態にないので詐欺罪としては無罪だ」と争われた経緯があります。
交付行為
「交付」とは、欺罔によって相手に錯誤を生じさせ、「相手が財産を自ら差し出す行為」を指します。
欺罔・錯誤が存在していても「渡すお金がなかった」というケースや、お金を用意して銀行の窓口で振り込みをしようとしたところ職員が詐欺に気づいて引き止めたケースなどでは、交付がないため詐欺未遂になります。
あくまでも交付は「自ら差し出させる」というもので、無断で持ち去ったり強引に奪ったりした場合には、窃盗罪や強盗罪といった別の犯罪に問われます。
財産移転
交付した財産が、加害者や第三者の手に渡った状態が「財産移転」です。
金品が加害者の手に渡った状態はもちろん、加害者が管理する銀行口座に振り込まれた状態なども、「財産が移転した」とみなされます。
詐欺罪の罰則
詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役」です(刑法第246条)。最短で1か月、最長で10年の間、刑務所で服役することになります。
他の犯罪では、「◯年以下の懲役または◯◯万円以下の罰金」などと規定されているものもありますが、詐欺罪の場合は罰金刑がありません。
詐欺で捕まって有罪判決が下された場合、執行猶予がつかない限り、確実に懲役刑が科されます。
未遂でも罰せられる
刑法第250条では「この章の罪の未遂は罰する」と規定しています。この場合の「章」とは、刑法にある「第37章 詐欺及び恐喝の罪」を指します。
詐欺罪のほかには、電子計算機使用詐欺罪・背任罪・準詐欺罪・恐喝罪なども、未遂で処罰される可能性があります。
詐欺未遂については、刑法第43条の「刑を減軽できる」または「自己の意思によって中止した場合は減軽・免除」という規定が適用される可能性もあるでしょう。
しかし、例えば「被害者が詐欺を見破ったりして予定外に失敗した」などのケースでは、減軽が適用されないおそれがあります。
騙し取った資産は没収
詐欺によってだまし取った資産は、刑法第19条の規定によって没収されることがあります。ただし、没収された資産は被害者に返還されるのではなく、国庫に帰属します。
したがって、没収されたとしても被害は回復されず、被害者からの返還・賠償請求を避けられるわけではありません。
詐欺罪に問われた場合の流れ

詐欺事件の容疑者として罪に問われた場合、どのような流れで刑事手続きを受けるのでしょうか?ここでは、刑事手続きの流れについて解説します。
警察による逮捕と取調べ
詐欺事件となれば、警察による取調べがおこなわれます。逮捕後48時間を限度に、身柄を拘束されて強制の取調べを受けることになります。
ケースによっては、身柄拘束を受けずに任意事件として捜査手続きが進められることもありますが、その場合は警察署などに呼び出されて、任意の取調べを受けることになります。
検察による取調べ
警察による取調べの後は、逮捕後48時間以内に検察庁に事件が送られて(送致)、検察官の取調べを受けます。
検察官による取調べの結果、「さらに身柄を拘束して捜査する必要がある」と判断されると、身柄拘束の延長である勾留を受け、最長20日間の取調べを受けます。
基本的に、勾留中は警察に身柄が戻されますが、その間に数回の検察官による取調べがおこなわれるのが通常の流れです。任意事件の場合も、検察庁に事件が送られた後は、検察官による取調べを受けることになります。
起訴された場合は刑事裁判になる
検察官は、被疑者を取調べて「刑事裁判をおこなって罪を問う必要がある」と判断すると、裁判所に起訴します。
起訴された段階で被疑者は「被告人」という扱いになり、刑事裁判が開かれて有罪・無罪の判決が下されます。
通常、刑事裁判は1か月に1回程度の頻度で開かれ、一時的な身柄解放である「保釈」が認められない限り、数か月にわたって身柄拘束が続くことになるでしょう。
不起訴の場合は事件終了となる
検察官が、被疑者を取調べて「刑事裁判をおこなう必要はない」と判断すると、不起訴処分となって事件終了となります。この場合、刑事裁判は開かれませんので、刑罰が下されることも前科がつくこともありません。
検察官が不起訴処分を下す主なケースは、次のとおりです。
|
罪とならず
|
構成要件を欠いている場合、心神喪失などの理由で犯罪が成立しない場合
|
|
嫌疑なし
|
別の真犯人が判明したりして容疑が晴れた場合
|
|
嫌疑不十分
|
犯罪を証明するために必要な証拠が足りない場合
|
|
起訴猶予
|
証拠は十分揃っており起訴すれば有罪になるものの、あえて起訴しない場合
|
ここで注目すべきは「起訴猶予」でしょう。
起訴猶予とは、刑事裁判で有罪になることがほぼ確実な状況であっても、さまざまな状況を考慮して検察官の裁量で起訴を見送るという処分を指します。
確実な基準ではありませんが、おおむね次のような事情があれば、詐欺をはたらいた事実があったとしても起訴猶予になりやすいでしょう。
- 被害額を全額弁済しており実害がない
- 被害額がわずかである
- 被害者との示談が成立している
起訴されれば99%以上の確率で有罪になる

ドラマなどでは、大逆転のきっかけになる証拠を提示して、劇的な無罪判決が下されるシーンが描かれることもありますが、現実の刑事裁判で無罪判決が下されるケースは極めて稀です。
日本の司法制度では、起訴された事件は99.9%の確率で有罪になっているので、無罪獲得を期待するべきではありません。
もちろん、無実の罪で疑いをかけられているのであれば証拠を集めて対抗するべきですが、詐欺をはたらいた事実がある場合、無罪判決を得られる可能性はほぼ0%でしょう。
詐欺事件を起こしてしまった場合は、無罪獲得ではなく不起訴処分の獲得を目指すほうが賢明でしょう。不起訴になれば、刑罰が下されることもなく即日で釈放されます。
不起訴を目指すには弁護士が必須
検察官から不起訴処分を獲得する確率を高めるには、弁護士にサポートを依頼するのが有効です。
刑事事件に注力している弁護士であれば、不起訴処分の獲得に向けて以下のような弁護活動が期待できます。
自首をして捜査に協力する
不起訴処分の獲得に向けて有効なのが「自首」です。
捜査機関が犯罪の発生を認知していない段階や、まだ被疑者が特定されていない段階で被疑者が自ら名乗り出れば、自首が成立します。
自首が成立すると、刑法第42条の定めによって刑罰が減軽される可能性があり、詐欺グループの情報を捜査機関に提供するなど、積極的に捜査協力したりすれば不起訴処分の獲得も期待できます。
ただし、自首が成立するかどうかを適切に判断するには法律知識が必要であり、素人だけでは自首が不成立となり減刑事由として認めてもらえない恐れがあります。
弁護士であれば、自首と認められる状況なのかを法的視点から判断してくれるうえ、自首の際の同伴を依頼することも可能です。
示談や贖罪寄付を行う
起訴・不起訴を判断する際、検察官が重視する判断材料のひとつが「被害者との示談」です。例えば、被害者との示談が成立して被害届や告訴が取り下げられている場合には、不起訴処分の獲得が期待できます。
ただし、被害者の中には「加害者と直接会いたくない」という方もおり、交渉を始めることすらできないケースもあります。弁護士であれば示談交渉を代行でき、被害者も弁護士相手であれば交渉に応じてくれる可能性があります。
なお、被害者が示談に応じてくれない場合は、反省の意を込めた「贖罪寄付」をおこなうという選択肢もあります。
ただし、基本的に贖罪寄付は、弁護士の所属団体である弁護士会や日弁連などを通じておこなうものですので、この場合も弁護士によるサポートが必要不可欠です。
起訴されたとしても執行猶予を目指せる
たとえ検察官が起訴したとしても、すぐに刑務所に収監されるわけではありません。執行猶予つきの判決が得られれば、前科はつくものの、身柄拘束が解かれて日常生活に復帰できます。
執行猶予期間中、再び詐欺事件を起こしたり別の犯罪を犯したりしなければ、刑の執行は免除されます。不起訴処分が下されなかった場合には、執行猶予の獲得を目指すのがベターです。
ただし、素人がやみくもに「執行猶予にしてください」と主張するだけでは足りず、実刑判決となってしまう恐れがあります。
弁護士であれば、反省文の作成サポートや再犯防止に向けた環境整備など、ケースごとに対応を考えて「執行猶予が相当である」と主張してくれますので、執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
意外と身近にある詐欺行為

詐欺については「いわゆる詐欺師のようなプロが犯行におよぶもの」というイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
意外にも、身近なところから詐欺事件に巻き込まれてしまうおそれもあります。
知らぬ間に詐欺に加担してしまう落とし穴
例えば、電話などを使って不特定多数の者からお金を奪う「特殊詐欺」の場合、役割を細かく分担して行われることがあります。その際、それぞれの担当者を集めるため、以下のような募集があるようです。
- 稼ぎのよいアルバイトがある
- 指定された場所に行くだけの簡単なアルバイトです
- ATMで現金を引き出してくるだけです
- リストに従って電話やメールをするだけの仕事です
このような誘い文句に乗ってしまうと、高確率で詐欺の一端を担うことになるでしょう。
例えば、振り込め詐欺の電話をかける役割の「かけ子」、被害者からキャッシュカードなどを受け取る「受け子」、だまし取ったキャッシュカードから現金を引き出す「出し子」として、詐欺に加担してしまうおそれがあります。
特に、お金のない未成年者・若いフリーター・仕事を引退した高齢者は「簡単に稼げる」などのうたい文句に乗せられやすいでしょう。
たとえ詐欺だと知らなくても、このような詐欺に加担してしまうと、警察に逮捕されて共犯者として刑罰が科せられてしまうおそれがあります。
まとめ
詐欺罪は、欺罔・錯誤・交付行為・財産移転といった4つの構成要件をすべて満たしている場合、成立する犯罪です。刑罰は懲役刑しかなく、執行猶予がつかずに有罪判決となった場合、刑務所に収監されることになります。
取り調べなどの刑事手続きには時間制限があり、逮捕後はスピーディに手続きが進行します。自首・示談交渉・贖罪寄付・再犯防止に向けた環境整備など、減刑獲得のためにできることはさまざまありますが、素人が対応するには限界があります。
弁護士であれば、そもそも詐欺罪が成立するのかどうかを法的視点から判断してくれるほか、依頼者の代理人として示談交渉などに対応してもらうことも可能です。初回相談無料の事務所もありますので、まずは話を聞いてみましょう。
ご家族や自身が詐欺罪で逮捕された方へ
詐欺罪で逮捕されると、10年以下の懲役を科される可能性があります。
そういった事態を防ぎ、不起訴や執行猶予付き判決を獲得するためには、ただちに弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士ならば、下記のような弁護活動を効果的におこなえます。
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 被害者と示談・損害賠償を行い宥恕文言(処罰を望まないこと)を得る
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
逮捕後72時間以内に接見できるのは弁護士のみです。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)では、初回相談無料・土日対応可・即日対応可の事務所を掲載しています。
対応を間違い後悔しないためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|