虚偽告訴罪とは?構成要件や事例について解説

虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、相手に刑事罰や懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発をおこなった場合に成立する犯罪です。
この罪に問われると、3ヵ月以上10年以下の懲役刑に処されます。
特に、痴漢冤罪や社会生活に対する報復を目的とした虚偽の告訴によって、無実の方が被害に遭うケースがあります。
本記事では、虚偽告訴罪の構成要件や適用される罰則、起こりやすい事件とその事例について解説します。
虚偽告訴罪について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
|
刑事事件はスピードが命です! もしもご家族や身近な方が逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。 刑事事件ではスピードが重要です。 【ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)】では、刑事事件が得意な弁護士を掲載しています。 相談料無料の法律事務所も多いので、まずはお住まいの地域から弁護士を探してみて、相談してみることをおすすめします。 |
虚偽告訴罪とは
虚偽告訴罪とは、虚偽の告訴をしたときに問われる罪です。
嘘の犯罪事実を申告することで、無実の方に犯罪に対する処罰を求めます。
以下で、詳しく見ていきましょう。
「虚偽」の「告訴」をした際に成立する犯罪
虚偽告訴罪とは、「虚偽」の「告訴」をおこなった場合に成立する犯罪です。
ここでいう「虚偽」とは事実に反すること、すなわち嘘をつくことを指し、「告訴」とは警察などの捜査機関に対して犯罪の発生を申告することを意味します。
虚偽告訴罪については、刑法第172条で次のように定められています。
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
引用元:刑法 第172条
要するに、刑事罰または懲戒処分を受けさせようという目的を持って、虚偽の申告をした場合に虚偽告訴罪が成立するというわけです。
虚偽の告訴を受けた警察は、通常の事件と同じように捜査を開始し、被疑者を特定します。
そして、被疑者に事情を聴くなどの対応をおこないます。
場合によっては逮捕や勾留に至り、身柄が長期間拘束されることもあります。
このように、虚偽の告訴は捜査機関の労力を無駄にするだけではなく、無実の方の人生に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
したがって、実際には発生していない事件について嘘をついて犯罪を申告する行為は、刑法上の犯罪として処罰の対象となるのです。
法定刑は3ヵ月以上10年以下の懲役
前述のとおり、刑法第172条には罰則として「3ヵ月以上10年以下の懲役」と定められています。
このことからもわかるとおり、虚偽告訴罪には罰金刑がなく、懲役刑のみが科される重い犯罪です。
ただし、刑法第173条には次のような規定があります。
(自白による刑の減免)
第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
引用元:刑法 第173条
つまり、事件の裁判が確定する前や懲戒処分がおこなわれる前に、自ら虚偽の告訴であったことを捜査機関に打ち明ければ、刑罰の減刑または免除が認められる可能性があるということです。
虚偽告訴罪の構成要件
虚偽告訴罪が成立するためには、以下の3つの構成要件を全て満たしている必要があります。
- 刑事・懲戒処分を受けさせる目的がある
- 虚偽の告訴・告発がある
- 故意が認められること
1.刑事・懲戒処分を受けさせる目的がある
虚偽告訴罪が成立するためには、相手に刑事罰や懲戒処分などの制裁を与える意図や目的があることが前提となります。
この目的については、刑事罰や懲戒処分を受けさせる積極的な意図までは不要であり、刑事罰や懲戒処分を受けるかもしれないといった程度の認識で足りることとされています。
2.虚偽の告訴・告発がある
虚偽告訴罪が成立するためには、事実に反する内容であること、すなわち虚偽の告訴・告発がおこなわれていることが必要です。
そのため、申告した内容が事実に基づいている場合には、この要件は満たされません。
たとえば、「会社のお金を同僚が横領している」と嘘のつもりで警察に告発したとしても、警察の捜査によって、実際に横領があったと判明した場合、申告内容は結果的に真実だったことになります。
このように、本人が虚偽のつもりで申告したとしても、実際に事実に基づいていれば、虚偽告訴罪は成立しません。
3.故意が認められること
虚偽告訴罪が成立するためには、「故意」が認められることが必要です。
ここでいう「故意」とは、虚偽であるとわかっていながら、あえて申告する意思を意味します。
たとえば、うわさ話を聞いて本人がそれを本当だと思い込んで告発したが、後になって事実ではなかったと判明したという場合には、「虚偽である」という認識、つまり「故意」がなかったことになります。
このようなケースでは、虚偽告訴罪は成立しません。
思い込みによる告訴・告発は虚偽告訴罪になるのか
結論からいうと、思い込みによる告訴や告発は、原則として虚偽告訴罪には該当しません。
なぜなら、虚偽告訴罪が成立するためには、申告内容が虚偽であることを認識しながら申告することが必要だからです。
そのため、例え後から「事実ではなかった」と判明したとしても、申告した時点で「あの人が犯人だ」と本当に信じていたのであれば、虚偽であるという認識がなかったことになり、虚偽告訴罪は成立しません。
ただし、「あの人は本当は犯人ではないかもしれない」といったように、犯人かどうか確証がない状態で申告した場合には注意が必要です。
このようなケースでは、たとえ明確に嘘をついていなくても、「虚偽である可能性があると知りつつ申告した」と判断され、「末必の故意」として虚偽告訴罪に問われる可能性があるからです。
被害申告する際には、十分に注意しましょう。
虚偽告訴罪が起こりやすい事件とその事例
虚偽告訴罪は、あまり耳なじみのない罪名であり、具体的なイメージが湧きにくいというのも事実です。
ここでは、虚偽告訴罪が起こりやすい事件と、その具体的な事例について紹介します。
痴漢冤罪
虚偽告訴罪で一番起こりやすいのが、痴漢冤罪です。
満員電車の中で、女性が「この人は痴漢です!」と訴えて、男性が警察に連行されたものの、実際には痴漢行為をしていなかったという事例が典型です。
このようなケースには、主に2つのパターンがあります。
1つ目は、単なる誤認による冤罪です。
たまたま被害者の近くに立っていたという理由で、実際には何もしていないのに痴漢と間違えられたというケースです。
2つ目は、故意に事実をでっち上げたケースです。
たとえば、示談金や慰謝料の獲得を目的として、実在しない犯人を仕立て上げて告発する場合です。
このように、金銭的利益を目的として虚偽の申告をおこなった場合には、虚偽告訴罪が成立する可能性があります。
社会生活でのトラブル・報復
社会生活の中でトラブルが生じて、相手に強い怒りや恨みを抱いた際、「相手を陥れてやろう」「逮捕されるようなことを警察にいってやろう」といった報復的な動機から、事実に反する申告をおこなうケースがあります。
たとえば、社内で上司に叱られたことに腹を立てて、「パワハラを受けた」「暴力を振るわれた」といった事実に基づかない内容で告発をおこなって、懲戒処分を狙うケースです。
このような行為は、退職のタイミングや人事異動の時期に起こりやすいとされています。
相手に対する報復を目的として虚偽の申告をおこなった場合には、虚偽告訴罪が成立する可能性があります。
恋愛・男女関係のもつれ
恋愛や交際関係が破綻した際に、感情的な対立や恨みから虚偽の告訴に至るケースも少なくありません。
特に、浮気や別れ話をきっかけとして、事実に反する申告をおこなう事例が見られます。
たとえば、交際中に浮気が発覚し、それに対する報復として「無理やり性行為をさせられた」などと虚偽の被害申告をして警察に告訴するケースです。
このような申告を受けて警察が動けば、無実の相手が逮捕・勾留されるなど、重大な不利益を被るおそれがあります。
そして、もし申告者がそれが虚偽であることを知りながら申告した場合には、虚偽親告罪が成立し、刑罰の対象となる可能性があります。
虚偽告訴罪に類似した犯罪
虚偽告訴罪には、いくつかの類似した犯罪があります。
ここでは、それらの類似した犯罪について解説します。
名誉毀損罪
名誉棄損罪は、逮捕させるつもりはないものの、虚偽の情報を第三者に言いふらす行為に該当する犯罪です。
この罪については、刑法第230条で次のように規定されています。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 第230条
特徴としては、発言の内容が「事実であるかどうか」は直接関係ありません。
つまり、内容がたとえ事実であっても、相手の社会的評価を不当に低下させた場合には、名誉毀損罪の構成要件に当てはまります。
なお、罰則については、「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」とされています。
偽証罪
偽証罪とは、裁判で宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に問われる罪です。
これは、裁判の場における「真実の解明」を著しく妨げる重大な行為として、刑法第169条により以下のように規定されています。
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
引用元:刑法 第169条
偽証罪の罰則は、3ヵ月以上10年以下の懲役刑です。
裁判で虚偽の証言をした場合には、偽証罪が成立するでしょう。
虚偽申告の罪(軽犯罪法違反)
虚偽申告の罪とは、存在しない犯罪や災害を公務員に対して申告した場合に問われる罪です。
たとえば、「火事が起きている」「強盗が入った」「誘拐された」といった虚偽の通報や申告をおこなうと、軽犯罪法違反に該当します。
軽犯罪法第1条16号には、以下のように規定されています。
(軽犯罪法)
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
引用元:軽犯罪法 第1条 第16号
このような場合、拘留または科料の刑罰を科される可能性があります。
いたずら目的でおこなわれることが多い一方で、内容や影響が重大な場合には、捜査機関の業務を妨害したとして、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
詐欺罪・詐欺未遂罪
詐欺罪および詐欺未遂罪は、他人を欺いて金品などの財産的利益を不法に得た場合、またはそのような行為をおこなうとしたが、結果として得られなかった場合に成立する犯罪です。
詐欺行為に着手した時点で、たとえ未遂に終わったとしても「詐欺未遂罪」として処罰の対象となります。
刑法第246条では、次のように定められています。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法 第246条
詐欺の典型例のひとつに「美人局」があります。
これは、女性が男性と性的関係を持つ、またはそのような状況に誘導したあとに、「実は未成年である」「妊娠した」などと主張し、相手に不安や罪悪感を抱かせることで、示談金などの名目で金品を要求し、財産を不法に取得しようとします。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされており、罰金刑の規定は存在しません。
そのため、重い犯罪と位置付けられています。
恐喝罪・恐喝未遂罪
恐喝罪および恐喝未遂罪は、相手に対して暴力や脅迫などにより不安や恐怖を与えて、金品などの財産的利益を不法に得る行為に対して成立する犯罪です。
また、そのような行為に着手したものの、結果として財産の交付に至らなかった場合には、恐喝未遂罪が成立します。
刑法第249条では、次のように定められています。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
たとえば、実際には存在しない犯罪をでっち上げて、「このままだと問題が大きくなる」などと告げることで、相手に恐怖心を与えて、金銭を支払わせるような行為が、恐喝罪です。
恐喝罪の罰則は、10年以下の懲役と定められており、罰金刑の規定はありません。
この点は詐欺罪と同様で、重い犯罪と位置付けられています。
逮捕されてから虚偽告訴罪で訴えることはできるのか
冤罪で逮捕されてしまった場合、状況によっては虚偽告訴罪で相手を訴えることは可能です。
しかし、その際には必ず弁護士に依頼することを強くおすすめします。
なぜなら、弁護士を立てずに個人で訴えを起こそうとしても、「やった・やってない」の水掛け論になってしまう可能性が非常に高いからです。
さらに、捜査機関から見れば、加害者とみなされた立場であるため、弁護士なしで動くことで、かえって不利な状況を招き、刑罰が重くなってしまうリスクすらあります。
このように、冤罪を主張してひとりで戦うことは非常に困難で、精神的・法律的なハードルが高いといえます。
自分を守るためには、少なくとも弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることが不可欠です。
虚偽告訴罪に問われた場合の流れ虚偽告訴罪に問われた場合、どのように刑事手続きが進んでいくのでしょうか。
ここでは、虚偽告訴をしたとされる本人の立場から、罪に問われた後に起こり得る一般的な流れを見ていきましょう。
基本的には、以下のような段階を経て進んでいきます。
- 事情聴取
- 逮捕・勾留
- 起訴・不起訴の判断
- 刑事裁判
- 判決の確定
事情聴取
まずは、警察や検察から任意の呼び出しを受けて、事情聴取がおこなわれます。
この段階ではまだ逮捕されませんが、虚偽告訴の疑いがある行為や発言について、詳しく質問を受けます。
逮捕・勾留
事情聴取の結果、警察が「虚偽の申告があった」と判断し、かつ証拠隠蔽や逃亡のおそれがあると認められた場合には、逮捕される可能性があります。
逮捕された場合、まずは48時間以内に警察での身柄拘束と取調べがおこなわれます。
一方で、証拠隠蔽や逃亡のおそれが低いと判断された場合には、逮捕されず「在宅捜査」となることもあります。
警察での逮捕後の取調べが終了すると、事件は検察官に送致されます。
検察官は送致から24時間以内に、勾留が必要かどうかを判断します。
必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求をおこないます。
裁判官が請求を認めた場合、被疑者はまず10日間の勾留請求を受けることになります。
さらに、捜査の必要性があると認められた場合には、最大10日間の延長が可能であり、合計で最大20日間の勾留となるケースもあります。
起訴・不起訴の判断
被疑者が勾留された場合、検察官は勾留期間中にその事件を起訴するかどうかを判断します。
起訴された場合には、刑事裁判に進むことになり、原則として裁判までの間は身柄拘束が続きます。
一方で、不起訴処分となった場合には、速やかに釈放されます。
刑事裁判
検察官によって起訴されると、事件は刑事裁判へと進みます。
裁判では、被告人が本当に罪を犯したのか、つまり「虚偽であることを認識しながら告訴をおこなったかどうか」が主な争点となります。
審理では、事実関係や被告人の故意であるかどうかが慎重に検討されます。
そして、審理の結果を受けて、裁判所は有罪か無罪かの判決を下します。
有罪になった場合には、懲役の長さなどの刑罰の内容も合わせて言い渡されます。
判決の確定
刑事裁判の審理を経て、有罪か無罪かの判決が下され、その判決が確定します。
虚偽告訴罪の法定刑は、「3ヵ月以上10年以下の懲役」と定められており、罰金刑はなく、懲役刑のみとなっています。
そのため、判決が確定し、執行猶予が付かなかった場合には、刑務所に収監されることになります。
一方で、執行猶予付きの判決が下された場合には、実際に刑務所に入ることなく刑の執行が猶予されます。
虚偽告訴罪に関するよくある質問
最後に、虚偽告訴罪についてよくある質問を紹介します。
虚偽告訴罪はどこから成立しますか?
虚偽告訴罪は、相手に刑事または懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の内容を故意に申告したときに成立します。
つまり、「事実に反する内容であること」「それを虚偽であると知っていたこと」「処罰させようという意図があったこと」という、これら3つの要件が全てそろったときに、虚偽告訴罪に問われることになります。
一方で、勘違いや思い込みによる申告であれば、虚偽であるとの認識がなかったと判断されるため、原則として罪には問われません。
虚偽の告訴は罪になりますか?
はい、虚偽の告訴は罪になります。
相手を陥れる目的で、実際には起きていない犯罪を申告する行為は、刑法上の「虚偽告訴罪」に該当します。
虚偽であるとわかっていながら、相手に処罰を受けさせようとする目的で申告した場合には、重い刑事罰が科される可能性があります。
軽い気持ちで虚偽の告訴をしてしまうと、懲役刑につながることもあるため、十分に注意しましょう。
虚偽告訴罪の慰謝料相場はいくらですか?
虚偽告訴罪における慰謝料の相場は、事案ごとの状況によって大きく異なります。
一般的に、名誉毀損や不法行為に基づく慰謝料請求では、10万円〜50万円程度が認められる傾向にあります。
ただし、虚偽の告訴によって被害者が逮捕・勾留されていたり、社会的信用を大きく損なうようなケースでは、被害の深刻さに応じて100万円を超える高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
犯罪行為は当然のことながら許されないものであり、捜査機関も事件の解決に向けて真剣に動きます。
しかし、そうした捜査機関の働きを利用して他人を陥れる行為は、捜査機関を混乱させるだけでなく、無実の方の人生そのものを傷つける重大な犯罪です。
このような行為を処罰するために「虚偽告訴罪」があります。
もしも虚偽の告訴によって被害を受けたと感じる方は、まずは「ベンナビ刑事事件」を活用して、お住まいの地域に対応する弁護士へ無料相談してみてください。

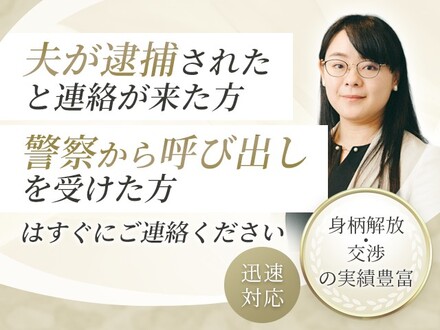
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る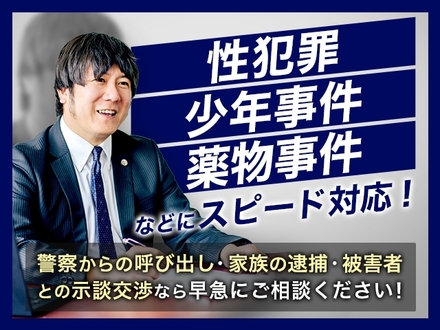
性犯罪/薬物事件/少年事件などに注力!刑事事件はスピード勝負です。逮捕直後および警察から連絡が来た時点からご相談ください。依頼者様がご納得できるよう、丁寧かつわかりやすい説明を心がけています。
事務所詳細を見る
【早期釈放/不起訴実績多数】加害者側・被害者側双方で、示談交渉対応多数◆痴漢・盗撮/暴行傷害/事故/窃盗など迷う前に電話◆早めの相談で選択肢を広げることが可能◎◆【即日接見で安心をお届け】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



その他の犯罪を起こしたらに関する新着コラム
-
本記事では、このような恐喝未遂のことを知りたい方に向けて、恐喝未遂罪の定義や構成要件、恐喝未遂罪で警察に逮捕された事例、恐喝未遂罪で逮捕されたあとの...
-
本記事では、ミスティーノの違法性や問われる可能性がある罪、万が一利用してしまった場合の対処法について解説します。
-
本記事では、住居侵入罪において初犯でも逮捕・起訴されるかどうか、実際に起訴を回避するためにできる対応策について、わかりやすく解説します。
-
テレグラムでのやり取りが警察にバレる可能性について詳しく解説します。テレグラムの特徴や関連する犯罪事例、警察のデータ解析能力などを具体的に説明します...
-
本記事では、オンラインカジノが違法となっている理由や、近年の取り締まり強化の流れ、時効などについて詳しく解説します。オンラインカジノを利用してしまっ...
-
本記事では、一般人でもオンラインカジノ利用によって逮捕されることはあるのか、逮捕された場合のデメリットなどを解説します。また、実際に逮捕されてしまっ...
-
本記事では、迷惑防止条例違反について知りたい方に向けて、迷惑防止条例違反の定義や意味、迷惑防止条例違反に該当する主な犯罪、迷惑防止条例に規定されてい...
-
本記事では、オンラインカジノの利用を検討している方に向けて、オンカジ関連で成立する可能性がある3つの犯罪、日本国内でオンカジの利用や勧誘をして逮捕さ...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
本記事では、正当な権利行使と脅迫罪の成否、脅迫罪に問われかねない発信をしたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
その他の犯罪を起こしたらに関する人気コラム
-
違法ダウンロード(いほうだうんろーど)とは、インターネット上に違法にアップロードされたコンテンツ(画像や動画等)をダウンロードする行為のことです。こ...
-
迷惑電話や執拗なクレームは、威力業務妨害に問われる危険があります。自分では正当な理由があると思っていても、刑罰が科せられる可能性があります。この記事...
-
脅迫罪とは被害者に害悪の告知をする犯罪で、【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金】の法定刑が定められています。脅迫に聞こえるような脅し文句や言葉...
-
映画や小説などのフィクションでよく見るサイコパスは、現実に存在します。この記事では、犯罪心理学者にサイコパスの特徴や、その基準を伺いました。イメージ...
-
本記事では、名誉毀損が成立する条件、名誉毀損が成立する具体例、トラブルに発展した時の対処法について解説します。
-
本記事では、住居侵入罪の具体的な定義や刑罰、そして構成要件を詳しく解説。「初犯でも懲役刑になるのか」「正当な理由ってどこまで?」といった疑問にも回答...
-
公文書偽造(こうぶんしょぎぞう)とは、国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪です。【法定刑は1年以上10年以下】と意...
-
不法投棄(ふほうとうき)とは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた処分場以外に、廃棄物を投棄することです。
-
死刑になる犯罪は全部で18種類あり、殺人罪などのイメージしやすいものから、海賊行為を規定したイメージしにくいものまで多くあります。裁判で死刑が下され...
-
護身目的でもナイフなどを携帯できないことをご存知ですか?この記事では銃刀法違反で逮捕されかねないケースと銃刀法違反の罰則、逮捕されてしまったときにと...
その他の犯罪を起こしたらの関連コラム
-
保護責任者遺棄罪(ほごせきにんしゃいきざい)とは、扶助が必要な人物を置き去りにする犯罪です。扶助が必要な人物の保護をしなかったという、いわゆる「何も...
-
ヤミ金で逮捕された場合、重い罰則を科される可能性があります。この記事では、ヤミ金で逮捕された場合の対処法から、ヤミ金で問われる罪、重い罰則、逮捕後ど...
-
本記事では、一般人でもオンラインカジノ利用によって逮捕されることはあるのか、逮捕された場合のデメリットなどを解説します。また、実際に逮捕されてしまっ...
-
本記事では、住居侵入罪において初犯でも逮捕・起訴されるかどうか、実際に起訴を回避するためにできる対応策について、わかりやすく解説します。
-
本記事では、ミスティーノの違法性や問われる可能性がある罪、万が一利用してしまった場合の対処法について解説します。
-
本記事では、オンラインカジノが違法となっている理由や、近年の取り締まり強化の流れ、時効などについて詳しく解説します。オンラインカジノを利用してしまっ...
-
賭博罪(とばくざい)は、金銭や宝石などの財物を賭けてギャンブルや賭け事をした際に成立する罪です。この記事では、賭博罪の構成要件、該当する行為、罰則、...
-
死刑になる犯罪は全部で18種類あり、殺人罪などのイメージしやすいものから、海賊行為を規定したイメージしにくいものまで多くあります。裁判で死刑が下され...
-
テロ等準備罪は、テロ集団などの組織的犯罪による被害を未然に防ぐために新設された法案です。採決時は野党から猛反発を受けましたが、2017年6月15日に...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
サイバー犯罪とは、主にコンピュータを使ってネットワーク上で行われる犯罪の総称を言います。近年では、犯罪件数や規模が増加しているということで、警察庁で...
-
客引き行為は風営法や各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていて、違反して逮捕された場合にどのように対応すれば良いのか、また、起訴・前科を付けないために...
その他の犯罪を起こしたらコラム一覧へ戻る



















































