12歳未満の少年でも少年院に送致される?少年事件の流れや弁護士に依頼するメリット

14歳未満には刑事責任能力が認められないとされているため、12歳未満の子どもが事件を起こしたとしても、懲役や罰金刑などの処罰を受けることはありません。
ただし、12歳未満の年齢で刑法などに触れるような犯罪行為に及んだ場合、刑事事件手続きは適用されませんが、少年事件手続きの対象になる点に注意が必要です。
12歳未満の少年が少年審判にかけられると、裁判官の判断次第では、少年院送致の保護処分が下されるリスクが生じます。
そこで、本記事では、12歳未満の少年が事件を起こしたときに少年院送致されるまでの流れや、少年事件について弁護士に相談・依頼をするメリットなどについて解説します。
12歳未満の少年でも少年院に送致される可能性はある
事件の内容次第ですが、12歳未満の少年でも少年院に送致される可能性はあります。
少年院に収容される年齢は、おおむね12歳~20歳です。
明確な年齢制限があるわけではなく、割合としては低いものの、12歳未満が収容されるケースは実際に存在します。
少年院に収容されている人の年齢分布は、以下のとおりです。
【少年院への12歳以下の収容者数】
|
年次 |
12歳以下の収容者数 |
|---|---|
|
2021年 |
22人(男18人・女4人) |
|
2022年 |
23人(男20人・女3人) |
|
2023年 |
21人(男20人・女1人) |
「12歳未満だから少年院に送致されることはないだろう」と油断をして早期の防御活動を怠ると重い保護処分が下されるリスクが高まるので、できるだけ早く弁護士の力を借りるようにしてください。
12歳未満の少年の少年院送致に関する基本情報
まずは、12歳未満の少年の少年院送致に関する基本情報を整理しておきましょう。
特に必要が認められる場合でなければ送致されることはない
12歳未満の少年が事件を起こした場合であったとしても、家庭裁判所が少年審判を開始した場合には、決定をもって少年院送致の保護処分を下すことができます。
ただし、14歳未満の少年に対して少年院送致の保護処分を決定できるのは、「特に必要と認められる場合」です。
例えば、深刻な被害が発生している場合や、少年の更生をサポートする体制が全く整っていない場合、事件を起こしたことに対して少年自身が全く反省しておらず再犯の可能性が高い場合などが挙げられます。
つまり、12歳未満の少年について審判が開始されたときには、「少年院送致をする特別な理由がないこと」を丁寧に主張立証することが重要だと考えられます。
収容先の少年院は第一種少年院または第三種少年院である
少年院の種類については、少年院法に規定が置かれています。
12歳未満の少年が収容される可能性がある少年院は以下の2つです。
|
少年院の種類 |
収容する対象者 |
|---|---|
|
第一種少年院 |
保護処分の執行を受ける者のうち、心身に著しい障害がない、おおむね12歳以上23歳未満の者 |
|
第三種少年院 |
保護処分の執行を受ける者のうち、心身に著しい障害がある、おおむね12歳以上23歳未満の者 |
「心身に著しい障害がある」は、精神障害や薬物依存を患っているケースなどを指し、第三種少年院では専門的な治療がおこなわれる点が特徴といえるでしょう。
少年院に収容される少年の年齢の下限は、「おおむね12歳以上」という文言からも厳格に定められているわけではありません。
実務上は、10歳前後で少年院送致になる可能性があります。
12歳未満の少年が少年院に送致されるまでの流れ|4ステップ
次に、12歳未満の少年が犯罪となりうる行為に及んだあと、少年院に送致されるまでの手続きを解説します。
1.警察による触法調査がおこなわれる
被害届や告訴状が提出されたり、110番通報されたりすると、警察が当該事件についての捜査活動を開始します。
そして、捜査活動を進めるなかで、犯行に及んだ人物が12歳未満であることが判明すると、通常の捜査活動から「触法調査」へ切り替えられます。
触法調査の定義とは
触法調査とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年に対して、警察官が実施する調査活動のことです。
触法調査は、刑事訴訟法に基づく捜査活動とは異なり、警察が果たす行政活動のうちの「行政調査」に位置づけられます。
刑事手続きの範囲でおこなわれる捜査活動を実施したとしても、14歳未満の少年に刑事責任を問うことができないため、あくまでも行政活動のひとつとして触法調査が実施されます。
触法調査で実施される内容とは
触法調査を実施する必要性がある場合、警察官は、少年・保護者・参考人を呼び出して、質問することができます。
これらの呼び出しや質問は、あくまでも任意の範囲でおこなわれます。
また、触法調査では、事件の事実・原因・動機、当該少年の性格・行状・経歴・教育程度・環境・家庭の状況・交友関係などについて、以下のような配慮のもと調査が進められる点も特徴的です。
- 原則として少年の保護者やこれに代わるべき者へ連絡する
- 少年に無用の緊張や不安を与えることがないように言動に注意をする
- やむを得ない場合を除き、夜間の呼び出し・質問、長時間の質問、他人の耳目に触れるおそれがある場所における質問を避ける
- 事案の真相究明や効果的な指導育成のため、少年の保護者や少年の保護・監護の観点から適当と認められる者の立ち会いについて配慮する
ただし、警察官は、必要があると認められるときには、「押収、捜索、検証、鑑定の嘱託」ができるとされています。
押収や捜索などは強制処分として実施されるものである以上、令状が発付されると拒否することはできません。
2.児童相談所に送致されて職員から調査を受ける
触法調査を実施した結果、以下のいずれかに該当すると認められるときには、警察官は当該事件を児童相談所長へ「送致」しなければいけません。
- 故意の犯罪行為によって被疑者を死亡させた
- 死刑または無期もしくは短期2年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪に及んだ
- その他、事案の状況を総合的に考慮した結果、家庭裁判所の審判に付することが適当である
事件を引き継いだ児童相談所では、児童福祉司・児童心理士などの専門家が触法少年の性格、成育歴、家庭環境、学校での様子、交友関係、事件を起こした経緯などについて調査を実施します。
そのうえで、以下のいずれかの措置が決定されます。
- 児童相談所における福祉的な援助措置(訓戒または誓約書の提出、児童福祉司などによる指導、里親などへの委託、児童養護施設や児童自立支援施設などへの入所)
- 家庭裁判所への送致
また、児童相談所で一時保護されたのち、最終的な措置の検討がおこなわれることもあります。
基本的に、12歳未満という年齢を考慮すると、福祉的な介入の必要性が高いと判断される傾向が強いです。
ただし、家庭環境などの事情を総合的に踏まえた結果、12歳未満の触法少年であったとしても、家庭裁判所に送致される可能性はゼロではありません。
3.家庭裁判所に送致されて少年鑑別所に収容される
家庭裁判所に送致されると、24時間以内に「観護措置」となるかどうかが決定します。
観護措置が適切と判断された場合、少年は少年鑑別所に送致され、原則として2週間、最大8週間以内の範囲で身柄が拘束されます。
収容期間中は、心理検査や面接などが実施され、少年審判を下す際の証拠資料とされます。
少年鑑別所に送致されると、学校生活・社会生活から完全に隔離されるので、学習に遅れが生じたり、再び通学するときのハードルが高まったりします。
また、収容期間と受験などのイベントが重なったとしても、観護措置の一時取り消しなどの処分を獲得しない限り、参加することができません。
4.少年審判が開かれて少年院送致の決定が下される
家庭裁判所に送致されたあとは、少年審判において当該事件の審理がおこなわれます。
少年審判は完全非公開の形式でおこなわれ、事実関係に争いがない事案であれば、1時間程度で終了します。
少年審判では、少年・付添人の意見陳述や裁判官から少年・保護者に対する質問などのプロセスを経て、以下のような処分が下されます。
- 不処分:保護処分は必要ないとする判断を受ける
- 保護観察:施設に収容されずに一定期間、保護観察官・保護司の監督を受ける
- 少年院送致:少年院に収容され、矯正指導を受ける
不処分・保護観察処分が下された場合には、その時点で少年審判手続きが終了し、即日帰宅できるケースが多いです。
これに対して、少年院送致が下されると、いったん少年鑑別所に身柄が移されたうえで、後日少年院に収監されることになります。
なお、家庭裁判所が少年審判において少年院送致の決定を下すときには、以下のように、その収容期間についても勧告がおこなわれるのが一般的です。
- 特修短期処遇(4ヵ月以内)
- 一般短期処遇(原則6ヵ月以内)
- 長期処遇(原則2年以内)
少年院に収容されると、毎日集団で規則正しい生活を送りながら更生・社会復帰が目指します。
生活指導・教育指導・職業指導がおこなわれたり、運動会・成人式などのイベントも実施されたりします。
12歳未満の少年の少年院送致を回避するために弁護士に相談するメリット
12歳未満の少年が事件を起こしたケースでも、少年院送致される可能性はゼロではありません。
そのため、12歳未満の少年が事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士の力を借りて少年院送致の回避を目指すべきです。
ここでは、12歳未満の少年が事件を起こしたときに少年事件を得意とする弁護士の力を借りるメリットを紹介します。
1.被害者との示談交渉を進めてくれる
少年事件を得意とする弁護士に依頼をすれば、被害者との間で早期に示談交渉を開始してくれます。
示談とは、さまざまな紛争を当事者間の話し合いで解決するための手段のことです。
12歳未満の少年が事件を起こした場合、被害者との間で早期に示談交渉をおこなうことによって、以下のメリットを得られます。
- 「示談金を支払う代わりに捜査機関に被害申告をしない」という条件を付することによって、12歳未満の少年が起こした事件が警察に発覚すること自体を回避できる
- 示談成立によって「被害者が処罰感情をもっていないこと」「加害者側が反省の態度を有しており、これが被害者側に受け入れられたこと」を証明できる
- 家庭裁判所への送致、少年院送致などの重い判断を回避しやすくなる
- 仮に少年院送致の決定を免れることができなかったとしても、収容期間の短縮化を目指しやすくなる
もっとも、犯罪行為に及んだケースでは、被害者側が強い怒りを抱いていることが少なくありません。
そのような状況で直接示談交渉を求めたとしても、拒絶される可能性が高いといえます。
また、仮に話し合いには応じてくれたとしても、なかなか示談条件が折り合わず、示談交渉が長期化するおそれもあるでしょう。
少年事件や刑事事件を得意とする弁護士に依頼をすれば、豊富な知見・ノウハウを活かしながら、冷静に示談交渉を進めてくれます。
また、被害者側も弁護士が代理人として対応してくれたほうが安心感を得られるので、話し合いに応じてもらいやすくなるでしょう。
2.警察が実施する触法調査段階で丁寧な対応を期待できる
触法調査における丁寧な対応が期待できることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。
法律上、触法調査は少年が抱える事情などを配慮しながら進める必要があるとされています。
しかし、実際には誘導尋問で虚偽の自白を引き出したり、児童相談所に通告する際に警察署の留置施設を一時保護の委託先にするように打診して実質的な逮捕・勾留処分をおこなったりするケースもあります。
このような実態を踏まえて、少年事件を得意とする弁護士は、警察の捜査が適切におこなわれるように、呼び出しや質問の際に立ち会ったり、違法の疑いのある触法調査に対しては抗議してくれたりします。
3.児童相談所に働きかけて家庭裁判所への送致を回避してくれる
児童相談所に働きかけによって、家庭裁判所への送致を回避しやすくなる点も、弁護士に相談・依頼するメリットといえるでしょう。
家庭裁判所に送致するかどうかを決定するのは児童相談所です。
児童相談所が福祉的な援助措置による解決が望ましいと判断すれば、少年院に入れられることもありません。
少年事件が得意な弁護士であれば、少年の状態や事件の状況を客観的に分析し、家庭裁判所に送致する必要性がないことを論理的に訴えかけることができます。
4.家庭裁判所に働きかけて観護措置回避を目指してくれる
弁護士に依頼すれば、家庭裁判所に働きかけて観護措置回避を目指してくれます。
児童相談所が家庭裁判所への送致を決定した場合、身柄及び事件を受け取った家庭裁判所は、24時間以内に観護措置を下すか否かを判断します。
観護措置が下されると、触法少年の身柄は原則2週間は少年鑑別所に留められてしまいます。
最終的に少年院送致を回避できたとしても、一定期間学校生活・社会生活から隔離されるのは大きな負担になりかねません。
そこで、弁護士は家庭裁判所に意見書を提出したり、裁判官との面談機会を求めたりして、観護措置の必要性がないことをアピールしてくれます。
観護措置決定が下された場合には、家庭裁判所に対する異議申し立てを検討してもらうことも可能です。
5.家庭裁判所に働きかけて少年審判の不開始を求めてくれる
12歳未満の少年が起こした事件が家庭裁判所に送致され、少年審判手続きが開始されると、少年院送致のリスクが大きく高まります。
そこで、弁護士は家庭裁判所に働きかけて、少年審判を開始しない旨の決定を獲得するために尽力してくれます。
例えば、触法行為に及んだこと自体が間違いであるのならば、弁護士は当該触法少年が事件に関与していない証拠をそろえてくれるでしょう。
また、仮に触法行為に及んだ事実は確かなものであったとしても、被害が軽微であることや、被害者との間で示談が成立していること、保護者の監督方法が充実していることなどを主張して、少年審判にかける必要性がない旨をアピールしてくれます。
6.少年審判でできるだけ軽い処分を求めてくれる
弁護士に依頼すれば、少年審判でできるだけ軽い処分を求めてくれます。
少年審判では、最悪の場合、少年院送致の決定が下されることになるため、寛大な処分を求めるための働きかけが不可欠です。
少年審判では、付添人などの意見を陳述する機会が設けられます。
弁護士は触法少年の付添人として、以下のような寛大な処分を引き出すための主張を展開してくれるでしょう。
- 保護観察処分:施設への収容ではなく、実際の社会生活のなかで、定期的に保護観察所・保護司の指導監督を受けながら、更生を図る処分のこと
- 児童養護施設・児童自立支援施設送致:少年院とは違った開放的な環境で少年の自立更生を促す処分のこと
- 都道府県知事・児童相談所長送致処分:少年院送致などではなく児童福祉法の理念に沿った解決が適していると判断されたときに下される処分のこと
- 試験観察処分:最終的な保護処分を決定する前段階として、当該少年の生活態度を観察するための期間を設ける処分のこと
- 不処分決定:保護処分に付することができない場合や、保護処分に付する必要がない場合に下される処分のこと
7.少年院送致の決定が出た場合に抗告をしてくれる
少年院送致を含め、家庭裁判所の少年審判で下された決定に対して不満があるときには、家庭裁判所を所管する高等裁判所に抗告をして判断の見直しを求めることができます。
少年院送致の決定に対する抗告には、2週間の期間制限が設けられています。
少年事件や刑事事件を得意とする弁護士に依頼をすれば、少年院送致が不当であることを根拠付ける証拠を速やかに用意してくれるでしょう。
8.少年の更生・社会復帰をサポートしてくれる
少年事件に力を入れている弁護士に相談・依頼をすれば、軽い処分の獲得だけではなく、触法少年が本格的に社会復帰を目指すためのサポートも期待できます。
例えば、触法少年と何度も面談を重ねる過程で、本人がどのような気持ちでいるのか、家庭環境・学校生活・交友関係をどのように改善すればよいのかなど、問題点を洗い出してくれます。
警察などから厳しい質問をされている触法少年にとって、自分の味方になってくれる存在がいるだけで心強いはずです。
また、事件を起こしたことが学校などに知れ渡ってしまったときにも、復帰しやすい環境づくりについて、弁護士が学校側と丁寧に話し合いをおこなってくれます。
さらに、少年の構成に向けて、家族が取り組むべきことに関しても、個別具体的なアドバイスを提供してくれるでしょう。
さいごに|少年事件の支援が得意な弁護士はベンナビ刑事事件で探そう!
少年事件では、事件後の対応次第で処遇が大きく変わってきます。
何もせずにただ待っているだけでは、たとえ12歳未満でも少年院に送致される可能性があります。
そのため、事件が発生した段階でできるだけ早く弁護士に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。
ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
弁護士にはそれぞれ得意分野があるため、少年事件の支援が得意な弁護士を見つけることが問題解決の近い道になります。
ベンナビ刑事事件では、少年事件の解決実績が豊富な弁護士を多数掲載しています。
地域を絞って身近な弁護士を効率よく検索できるので、ぜひ活用してみてください。

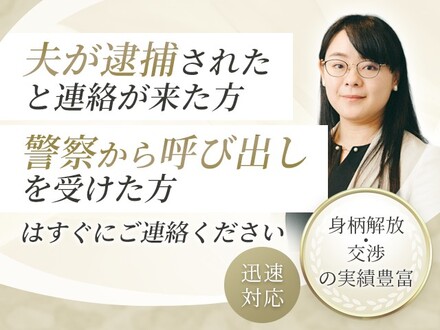
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る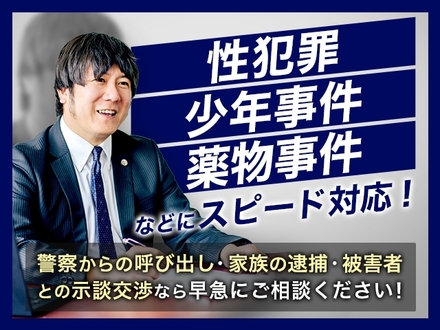
性犯罪/薬物事件/少年事件などに注力!刑事事件はスピード勝負です。逮捕直後および警察から連絡が来た時点からご相談ください。依頼者様がご納得できるよう、丁寧かつわかりやすい説明を心がけています。
事務所詳細を見る
検事の経験を持つ弁護士が窃盗・万引き/少年事件/性犯罪など幅広い刑事事件に対応◆『警察の呼び出しを受けている』『ご家族が逮捕された』はすぐご相談を◆フットワークの軽さを活かした迅速対応【即日接見も◎】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事処分の種類と内容に関する新着コラム
-
本記事では、「おはよう逮捕」と呼ばれる早朝逮捕の理由や、ほかの時間帯で逮捕されるケースについて、法律の観点からわかりやすく解説します。
-
未成年でも14歳以上は逮捕される可能性があります。本記事では逮捕後の流れや少年審判で受ける処分の内容、学校の退学処分、進学や就職への具体的な影響、今...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
窃盗罪で逮捕されると、罰金刑や拘禁刑といった刑事罰が科される可能性があります。本記事では、刑事処罰の1つである罰金刑を受ける場合の罰金額の相場・払え...
-
量刑判断では、被告人の反省の態度や再犯の可能性、被害者への影響など、さまざまな要素が考慮されます。本記事では、量刑がどのように決定されるのか、その基...
-
「控訴」と「上告」は、いずれも判決に不服がある場合におこなう手続きですが、何回目の裁判に対する申立てなのかが大きく異なります。そのほかにも共通点や相...
-
処断刑とは、法定刑を基準としながら、法律上または裁判における加重・減軽を考慮したうえで決定される刑罰のことを指します。処断刑と宣告刑の違いを理解する...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
刑事処分の種類と内容に関する人気コラム
-
執行猶予が得られると有罪判決を受けても刑の執行が猶予されます。懲役や禁錮を言い渡されても通勤や通学など日常の生活が可能となり、社会内で更生するチャン...
-
起訴と不起訴の違いは、有罪と無罪ほどの違いと言っても過言ではありません。この記事では不起訴処分になる条件の一例や、不起訴獲得のためにできること、弁護...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
無期懲役は期限のない懲役刑の事ですが、日本では死刑に次いで重い刑罰です。無期懲役は一生刑務所から出られないという認識がされますが、最も長い刑期の1....
-
「勾留」とは、刑事事件の被疑者・被告人を刑事施設に拘束することを指します。勾留されると拘束期間が長くなるため、仕事や生活に大きな影響が及びます。本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
微罪処分とは、軽い犯罪を起こしてしまい、逮捕されたとしても、その後、警察が微罪と判断し、身元引受人に被疑者を引き取ってもらうことで、刑事手続が終了す...
-
本記事では、拘留の法的な意味や「勾留」との違い、拘留が科されるケース、そしてそれを回避するためのポイントについて、弁護士が詳しく解説します。
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
刑事処分の種類と内容の関連コラム
-
本記事では、立ちションと罰金の関係が気になる方に向けて、立ちションだけなら罰金になる可能性はないこと、立ちションと一緒に成立する可能性がある犯罪4選...
-
略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対して被疑者への処罰を求める簡易的な手続きのことです。書面のみで審理がおこなわれ、被告人には罰金または科料が科せら...
-
実刑(じっけい)とは、執行猶予が付かずに懲役刑や禁錮刑で刑務所に収監されるという判決を受けてしまうことです。実刑判決を受けてしまうと、その後、数カ月...
-
刑事罰には「執行猶予」という猶予期間が設けられるケースがありますが、刑事罰の最高刑である死刑においても執行猶予が付くことはあるのでしょうか? 本記...
-
この記事では、起訴猶予と不起訴処分との違いや、前科の有無、起訴猶予のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。 起訴猶予になりやすい人...
-
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ...
-
精神鑑定の結果心神喪失状態にあると判定されると、無罪になる可能性があります。本記事では、刑事事件を 起こした人物が精神鑑定を経て無罪になる理由、無...
-
「前科は10年で消える」という情報がありますが、前科は一度ついてしまうと生涯消えることはありません。しかし、前科による不利益は時間とともに軽減されて...
-
前科一犯とは、過去に犯罪を起こし、前科が1回付いた人の事を指します。“一犯”とは、前科になった回数の事で、2回、3回と増えていけば、二犯、三犯とその...
-
処分保留とは、刑事手続きにおいて検察官が勾留期限内に起訴・不起訴を判断せず、一旦被疑者の身柄を解放することを指します。本記事では、処分保留の定義や不...
-
今回は、刑罰のなかでも禁錮刑について、どのような刑なのかや、自宅での受刑はあるのかなどを解説します。「禁錮刑と懲役刑の違いは?」「どちらがつらい?」...
刑事処分の種類と内容コラム一覧へ戻る






















































