詐欺加害者になったら弁護士に無料相談を。選び方・費用も解説

詐欺罪は、他人から金品を騙し取る重大な犯罪です。
詐欺罪を犯した方に対しては、基本的に厳しい刑事処分が予想されます。
しかし、被害額や情状によっては、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性もあります。
もし詐欺罪にあたる行為を犯してしまった場合は、速やかに弁護士へ相談して弁護活動を依頼してください。
弁護士を探す際は「刑事事件に注力しているか」「詐欺トラブルの解決実績は豊富か」などをチェックすることも大切です。
本記事では、詐欺事件で弁護士に依頼するメリットや探し方、弁護士費用の相場などを解説します。
詐欺罪で逮捕されたらすぐに弁護士に相談を
詐欺罪で逮捕されてしまった場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは、詐欺事件での刑事手続きの流れや、弁護士の必要性などを解説します。
弁護士への依頼は逮捕後72時間以内が勝負
詐欺などの刑事事件では、以下のような流れで刑事手続きが進行します。

手続きにはタイムリミットがあり、逮捕後72時間以内には勾留・釈放の判断が下されます。
勾留されると最大20日間の身柄拘束を受けることになり、会社員の方などは無断欠勤の状態が続いて解雇されるおそれもあります。
逮捕後速やかに弁護士に依頼すれば、勾留の回避に向けて捜査機関にはたらきかけてくれたりして、早期釈放につながる可能性があります。
詐欺事件を相談するなら私選弁護人がおすすめ
刑事事件を担当する弁護士は、以下のような3種類に分類されます。
| 当番弁護士 | 国選弁護人 | 私選弁護人 | |
|---|---|---|---|
| 呼べるタイミング | 逮捕後 | 勾留後・起訴後 | いつでも可 |
| 弁護士費用 | 無料 | 原則無料 (費用負担を求められる場合あり) | 有料 |
| 呼べる人 | 被疑者本人・家族・友人など | 被疑者・被告人 | 被疑者本人・家族など(誰でも可) |
| 対応・弁護活動 | 接見1回のみ | 起訴前・起訴後の弁護活動全般 | 起訴前・起訴後の弁護活動全般 |
| メリット | 無料で利用可 | 原則無料で利用可 費用負担が発生しても低額 | 自分で弁護士を選択できる 逮捕・勾留されていなくても依頼可 |
| デメリット | 自分で弁護士を選べない 継続的な弁護活動を依頼するには国選・私選への切り替えが必要 | 自分で弁護士を選べない 選任のタイミングが遅い | 弁護士費用が高額になりやすい |
上記のうち、私選弁護人については呼ぶタイミングの制限もなく、逮捕前の段階でも対応してもらえます。
当番弁護士や国選弁護人の場合、選任された弁護士が詐欺事件を得意としていないこともありますが、私選弁護人であれば自分で自由に選択することができます。
早期釈放や減刑獲得のために的確なサポートを受けたいのであれば、私選弁護人を選ぶことをおすすめします。
詐欺事件が得意な弁護士を探すならベンナビ刑事事件がおすすめ
詐欺事件での弁護活動を依頼したい場合は、当サイト「ベンナビ刑事事件」で探しましょう。
ベンナビ刑事事件は、詐欺などの刑事事件の加害者弁護が得意な全国の弁護士事務所を掲載しているポータルサイトです。
相談内容や都道府県などを選択するだけで対応可能な弁護士事務所を一括検索でき、各事務所の営業時間・解決事例・弁護士費用などの情報も掲載しています。
電話・メール・LINEなどでの相談にも対応しているので、まずは相談してみましょう。
詐欺に強い弁護士の選び方
詐欺事件で頼りになる弁護士に依頼したい場合、以下のようなポイントをチェックしましょう。
詐欺事件の弁護活動に力を入れている
「性犯罪事件が得意な弁護士」や「薬物事件に強い弁護士」など、一口に弁護士といってもそれぞれ力を入れている分野は異なります。
的確な弁護活動を受けるためにも、詐欺事件の解決に注力している弁護士を選びましょう。
注力分野などは各事務所ホームページにも記載されていますし、ベンナビ刑事事件でも確認することができます。
詐欺事件の解決実績が豊富
弁護士を選ぶ際は「これまでどれだけの事件を解決してきたのか」も判断材料のひとつとなります。
詐欺事件の場合、弁護士は被害者との示談交渉や刑事裁判に向けた証拠収集などをおこないます。
詐欺事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、これまでの知識やノウハウなどを活かして、依頼者側に有利な証拠の確保やスムーズな示談成立などが望めます。
詐欺事件でかかる弁護士費用の相場と内訳
刑事事件の加害者となった場合、弁護士に依頼せざるを得ないケースが大半ですが、弁護士費用が気になるという方も多いでしょう。
弁護士費用は各事務所が自由に決定しており、依頼する弁護士によっても差があります。
どの程度の金額が必要かは一概には言えませんが、大まかな目安を確認しておきましょう。
相談料
正式な依頼前の法律相談の際に相談料がかかるかどうかは、弁護士にもよります。
相談料が発生する場合、30分あたり5,000円程度が相場です。
一方、無料で法律相談を受け付けている弁護士もたくさんいます。
お金に余裕がない場合は、ひとまず相談料無料の弁護士に相談してみるとよいでしょう。
着手金
着手金は、弁護士に正式な依頼をする際に支払います。
刑事事件の場合、着手金は22万円~55万円程度が相場です。
複雑な事案の場合は、さらに高額となるケースもあります。
報酬金
報酬金は、弁護活動の結果として依頼者に何らかの利益が生じた場合に支払います。
刑事事件の場合、以下のようなケースで報酬金が発生することが多いです。
- 不起訴となった場合
- 略式命令がおこなわれた場合(正式起訴されなかった場合)
- 無罪となった場合
- 執行猶予付き判決が言い渡された場合
- 求刑よりも刑が軽減された場合 など
報酬金の仕組みや発生条件は、弁護士と協議のうえで決定します。
金額は22万円~55万円程度が相場ですが、着手金と同様に複雑な事案ではさらに高額になります。
その他費用
相談料・着手金・報酬金以外にも、以下のような費用が発生することもあります。
日当
日当は、公判期日への出席など、弁護士が出張する場合に発生します。
半日程度の出張であれば3万3,000円~5万5,000円程度、1日がかりの出張であれば5万5,000円~11万円程度が相場です。
接見費用
接見費用は、弁護士が身柄拘束されている被疑者・被告人と接見する際に、1回ごとに発生します。
多くの場合、日当と同じ仕組み・水準で請求されます。
実費
上記のほかにも、被害者に支払う示談金や、郵送費・交通費などの雑費が発生した場合は依頼者が負担します。
詐欺事件で弁護士に依頼する3つのメリット
詐欺の疑いで捜査機関に逮捕されたり、取り調べを受けることになったりした場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
被害者との示談交渉を進めてくれる
詐欺罪について厳しい刑事処分を免れるためには、被害者との示談を成立させることが大きなポイントになります。
示談によって被害者側の処罰感情が緩和され、かつ被害弁償がおこなわれたことが、被疑者・被告人にとって有利な情状となるためです。
弁護士は、被疑者・被告人に代わって被害者と示談交渉をおこない、早期に適正な水準で示談をまとめられるように尽力します。
取り調べの受け方についてアドバイスしてくれる
警察や検察による取り調べの内容は、刑事裁判において証拠として使われます。
取り調べで不用意な供述をしてしまうと、刑事裁判で不利な状況に追い込まれかねません。
弁護士に相談すれば、取り調べに臨む際の心構えや、言うべきこと・言ってはいけないことなどについてアドバイスを受けられます。
特に、逮捕された場合は逮捕直後から取り調べがおこなわれるため、早期に弁護士に相談することが大切です。
早期釈放・不起訴処分・執行猶予に向けた弁護活動を進めてくれる
弁護士は、被疑者・被告人を早期に刑事手続きから解放するため、以下のような弁護活動をおこないます。
- 勾留決定に対する準抗告
- 不起訴に向けた弁護活動(示談など)
- 保釈請求
- 公判手続きの準備、対応(良い情状に関する主張など)
特に、逮捕・勾留によって身柄を拘束されている場合、弁護士へ相談することが刑事手続きからの早期解放を目指すうえでは非常に重要です。
詐欺事件で弁護士がしてくれる弁護活動
詐欺事件における弁護活動の方針は、刑事手続きの段階や、被疑者・被告人の主張内容によって以下のように異なります。
不起訴処分の獲得を目指す場合
不起訴処分になれば、刑事罰を受けることなく、早期に刑事手続きから解放されます。
たとえ詐欺をおこなったことが事実であるとしても、主犯格ではない場合には「起訴猶予」という不起訴処分になる可能性もあります。
逮捕とそれに続く起訴前勾留の期間は、通算して最大23日間しかありません。
検察官は、その間に起訴・不起訴の判断をおこなうため、不起訴処分を目指す弁護活動ではスピードが重要です。
特に、被害者との示談交渉を逮捕直後から開始し、できる限り起訴前に示談をまとめることができれば、起訴猶予となる可能性が高まります。
実刑を回避して執行猶予判決を目指す場合
検察官によって詐欺罪で起訴されたとしても、公判手続き(刑事裁判)で執行猶予が付けば、ただちに刑務所に収監されずに済みます。
執行猶予付き判決は、被告人が十分に反省しており、社会における更生を促すほうが望ましいと考えられる場合に言い渡されます。
公判手続きでは、被告人質問に対して誠実に回答し、真摯な謝罪の姿勢を見せることが重要です。
また、被害者との示談を成立させることができれば、被告人にとって有利な情状となります。
詐欺が冤罪で無実を主張する場合
詐欺自体が冤罪であるとして犯罪事実を否定する場合、公判手続きでは長期戦を覚悟する必要があります。
刑事裁判における立証責任は、全て検察官にあります。
被告人としては、冤罪であることを一貫して主張し続ける、黙秘を貫くなど、否認の姿勢を明確に示すことが得策です。
詐欺を否認する場合、取り調べや公判手続きにどのような心構えで臨むのかについては、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
詐欺罪とは?
詐欺罪は、他人を騙して金品などの財物を交付させる行為をした場合に成立する犯罪です。
ここでは、詐欺罪の構成要件や量刑などの基礎知識を解説します。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
引用元:刑法第246条
詐欺行為の構成要件
詐欺罪の成立要件は、以下のとおりです。
1.人を欺く行為(欺罔行為)
人を欺く行為は「欺罔行為(ぎもうこうい)」とも呼ばれ、他人の事実認識を誤らせる(錯誤を惹起する)ような行為を意味します。
(例)
- 返す気がないのに「お金を貸してくれ」と頼む行為
- 本当は自分で使い込むつもりなのに「ファンドに投資して、儲かったら還元するから、お金を預けてください」と勧誘する行為 など
2.欺罔行為によって被害者が騙される(錯誤に陥る)
詐欺罪が成立するには、欺罔行為によって被害者が騙された(錯誤に陥った)ことが必要です。
もし欺罔行為をしたにもかかわらず、被害者が騙されなかった場合には、詐欺未遂罪が成立します(刑法250条)。
3.錯誤によって被害者が加害者に財物を引き渡す
さらに欺罔行為による錯誤に基づき、被害者が加害者に対して金品など(財物)を引き渡したことが、詐欺罪の成立要件とされています。
詐欺罪は、あくまでも被害者の誤った意思によって、財物を交付させる行為について成立する犯罪です。
これに対して、金品などを被害者が気づかないうちに盗む行為については、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
詐欺罪の刑罰
詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」です。
刑事裁判における詐欺罪の量刑は、法定刑の範囲内で決まりますが、上限いっぱいまで重い刑が科されることはまれです。
特に、初犯であり被害額もそれほど大きくない場合には、3年以下・執行猶予付きの判決となる傾向にあります。
詐欺罪にあたる行為の典型例としては「振り込め詐欺」「投資詐欺」「給付金詐欺」などがあり、それぞれの量刑の傾向としては以下のとおりです。
振り込め詐欺の量刑の傾向
「振り込め詐欺」は、被害者の身内に非常事態が発生したなどと嘘をつき、犯人の口座に金銭を振り込ませる詐欺行為です。
振り込め詐欺は単発ではなく、複数の被害者に対して連続しておこなわれる傾向にあります。
そのため、被害額は極めて高額になるケースが多いでしょう。
振り込め詐欺には、首謀者のほかに「かけ子(電話をかける役割)」「受け子(金銭を受け取る役割)」「出し子(ATMなどで金銭を引き出す役割)」「見張り役」などの補助者が関与しているケースが多いです。
振り込め詐欺の被害額が高額である場合、首謀者については、詐欺罪の上限に近い実刑判決(5年以上)が言い渡される可能性が高いと考えられます。
補助者として関与した者についても、詐欺の遂行に不可欠な役割を果たしていれば、実刑判決が言い渡される可能性が高いでしょう。
これに対して、詐欺の分け前をほとんど受け取っておらず、末端的な役割に留まる者については、不起訴または執行猶予となる可能性もあります。
投資詐欺の量刑の傾向
投資詐欺は、他人に対して架空または粗悪な金融商品への投資を勧誘し、金銭を騙し取る詐欺行為です。
振り込め詐欺と同様に、投資詐欺も複数の被害者に対して連続しておこなわれ、被害額が極めて高額になる傾向にあるのが特徴です。
したがって、首謀者および不可欠な役割を果たす補助者については、実刑判決を免れることは困難でしょう。
一方、首謀者に言われるがままに行動して分け前もほとんど受け取っていない者は、不起訴や執行猶予の余地があります。
給付金詐欺の量刑の傾向
給付金詐欺は、政府や自治体の給付金を、要件を満たしていないにもかかわらず申請して騙し取る詐欺行為です。
最近では、コロナ関連の給付金を騙し取る給付金詐欺が頻発して、社会問題となりました。
給付金詐欺は、つい出来心で1回限り犯してしまったというケースも多いところです。
その一方で、金額は数十万円~数百万円と高額になるケースも多いため、悪質な場合には実刑判決も想定されます。
なお、給付金詐欺で訴追される前に自主的に給付金を返還した場合には、不起訴となる可能性が高まるでしょう。
詐欺罪の時効
詐欺行為をした場合、詐欺罪で刑事訴追される可能性があるほか、被害者から不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求される可能性もあります。
刑事訴追については「公訴時効」、損害賠償請求については「消滅時効」により、それぞれ期限が設定されています。
刑事上の公訴時効
公訴時効とは、検察官が被疑者を起訴(公訴提起)できる期間を意味し、犯罪終了時から進行します。
詐欺罪の法定刑は長期10年(10年以下)の懲役であるため、公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。
民事上の損害賠償請求権の消滅時効
損害賠償請求権の消滅時効が完成すると、加害者は時効を援用することにより、被害者に対する損害賠償責任を免れます。
詐欺(不法行為)に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過した段階で完成します(民法724条)。
- 被害者が損害および加害者を知ったときから3年
- 詐欺の時点から20年
最後に|詐欺事件で逮捕されたら早急に弁護士へ相談
詐欺の疑いで捜査機関に逮捕された場合、長期間の身柄拘束に発展する可能性があります。
また、罪状によっては実刑判決を受け、刑務所に収監されてしまうことにもなりかねません。
詐欺を犯してしまった方が刑事手続きからの早期解放を目指すには、逮捕直後から弁護士に相談することが大切です。
その際は、ベンナビ刑事事件で詐欺事件を得意とする弁護士を選びましょう。
詐欺に手を染めてしまい、自責の念に駆られている方は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

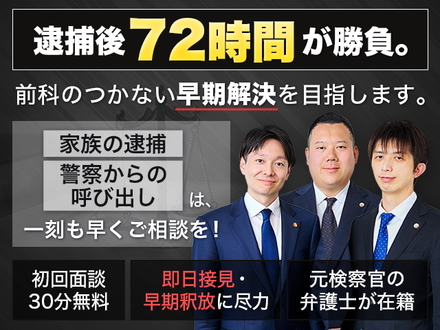
【初回面談30分無料】【元検事の弁護士が在籍】刑事事件の対応実績豊富な弁護士が、依頼者様に寄り添います。早期釈放を通じた社会復帰のことも考えた対応を大切に、最後までサポート。ぜひお早めにご相談ください。
事務所詳細を見る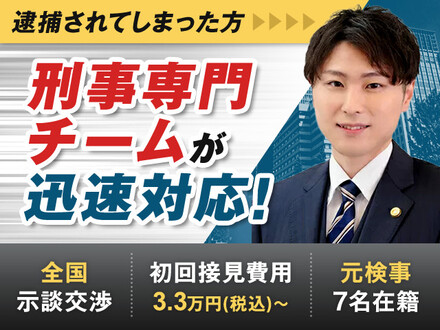
【銀座駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る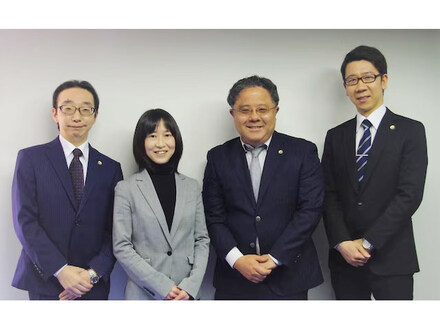
【警察から連絡がきた/被害届を出された方/刑事告訴を受けた方へ】痴漢・盗撮/万引き/人身事故・交通違反/暴行など幅広いお悩みに豊富な実績◆少年事件もお任せください◆迅速対応で刑事処分回避に向けてサポート【女性弁護士も在籍】東京・大阪に事務所あり
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



詐欺事件を起こしたらに関する新着コラム
-
詐欺罪の公訴時効は原則7年ですが、起算点や停止条件には注意が必要です。刑事責任を逃れても民事の損害賠償請求は残る場合があります。本記事では、時効の仕...
-
本記事では、闇バイトに関与してしまった場合に弁護士に相談すべき理由と、その具体的な対応方法について詳しく解説します。
-
結婚詐欺で逮捕されると、詐欺罪で10年以下の懲役刑になる可能性があります。この記事では、結婚詐欺で逮捕された後の流れや前科を回避する方法などを加害者...
-
給付金詐欺とは、一般的に国や自治体の支援金や補助金を嘘の申請によって不正に受け取る詐欺行為を指します。例えば、2020年は新型コロナウイルスの対策と...
-
保険金詐欺とは、保険金が受け取れる条件を満たすために虚偽の申し出をしたり、わざと事故などを起こしたりして不正に保険金をだまし取る詐欺行為のことです。
-
本記事では、詐欺の共犯が成立する条件や逮捕されたときの流れを解説します。
-
詐欺事件を起こしてしまったら早急に弁護士に相談しましょう。刑事手続きにはタイムリミットがあり、早期釈放や減刑獲得のためにはスピーディな対応が重要です...
-
詐欺罪はニュースなどでも頻繁に取り上げられ、身近に存在することを実感する犯罪のひとつです。詐欺の構成要件は4つに分類されますが、複雑なものではなく身...
-
詐欺罪の初犯は執行猶予がつくのか、初犯でも実刑となるのか。この記事では、詐欺罪の初犯について、量刑相場や、不起訴処分または執行猶予を獲得するためのポ...
-
本記事では、詐欺事件での示談のメリット・示談金の相場・示談の流れや方法・示談金が支払えない場合の対応・弁護士に依頼するメリットなどをわかりやすく解説...
詐欺事件を起こしたらに関する人気コラム
-
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑と定められています。詐欺事件では実刑となる可能性があるものの、なかには逮捕や実刑を回避できることもあります。本記事...
-
詐欺罪とは、人を騙して財物や利益などを不法に得た場合に成立する犯罪です。法定刑は10年以下の拘禁刑で、初犯でも実刑となる可能性があります。本記事では...
-
結婚詐欺は、男性・女性問わずたくさんの人が被害に遭っています。信じていた人が実は結婚詐欺師だったということもよくある事例ですので、ぜひこの記事をご覧...
-
詐欺の受け子で逮捕された場合、たとえ初犯でも実刑判決となる可能性があります。少しでも状況の改善を望む方は、早い段階で弁護活動を受けるのが有効でしょう...
-
偽証罪(ぎしょうざい)とは、法律のより宣誓した証人が虚偽の陳述を行うことに対する犯罪です。法定刑は、3ヶ月以上10年以下の懲役という重い罰則が設けら...
-
経歴詐称とは、一般的に学歴や職歴を偽ることです。簡単に言うと自分の経歴についてうそをつくことですが、場合によっては、うそでは済まされないこともありま...
-
詐欺罪の初犯は執行猶予がつくのか、初犯でも実刑となるのか。この記事では、詐欺罪の初犯について、量刑相場や、不起訴処分または執行猶予を獲得するためのポ...
-
サクラも詐欺罪で逮捕される場合があることをご存知ですか?サクラでも詐欺の共犯又は従犯と評価される可能性もあり、逮捕の可能性があります。今回はこのよう...
-
詐欺罪はニュースなどでも頻繁に取り上げられ、身近に存在することを実感する犯罪のひとつです。詐欺の構成要件は4つに分類されますが、複雑なものではなく身...
-
寸借詐欺(すんしゃくさぎ)とは、「財布を落とした」「交通費を忘れた」などとうそをつき、相手の善意に付け込んで、金銭をだまし取る行為のことをいいます。...
詐欺事件を起こしたらの関連コラム
-
詐欺罪とは、人を騙して財物や利益などを不法に得た場合に成立する犯罪です。法定刑は10年以下の拘禁刑で、初犯でも実刑となる可能性があります。本記事では...
-
詐欺罪の公訴時効は原則7年ですが、起算点や停止条件には注意が必要です。刑事責任を逃れても民事の損害賠償請求は残る場合があります。本記事では、時効の仕...
-
詐欺事件を起こしてしまったら早急に弁護士に相談しましょう。刑事手続きにはタイムリミットがあり、早期釈放や減刑獲得のためにはスピーディな対応が重要です...
-
保険金詐欺とは、保険金が受け取れる条件を満たすために虚偽の申し出をしたり、わざと事故などを起こしたりして不正に保険金をだまし取る詐欺行為のことです。
-
架空請求詐欺とは、架空の費目で金銭を要求する詐欺行為です。サイト運営者を装って、有料サイトの利用料金を架空請求する手口が代表的ですが、中には裁判所職...
-
結婚詐欺は、男性・女性問わずたくさんの人が被害に遭っています。信じていた人が実は結婚詐欺師だったということもよくある事例ですので、ぜひこの記事をご覧...
-
サクラも詐欺罪で逮捕される場合があることをご存知ですか?サクラでも詐欺の共犯又は従犯と評価される可能性もあり、逮捕の可能性があります。今回はこのよう...
-
本記事では、詐欺の共犯が成立する条件や逮捕されたときの流れを解説します。
-
詐欺罪はニュースなどでも頻繁に取り上げられ、身近に存在することを実感する犯罪のひとつです。詐欺の構成要件は4つに分類されますが、複雑なものではなく身...
-
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑と定められています。詐欺事件では実刑となる可能性があるものの、なかには逮捕や実刑を回避できることもあります。本記事...
-
給付金詐欺とは、一般的に国や自治体の支援金や補助金を嘘の申請によって不正に受け取る詐欺行為を指します。例えば、2020年は新型コロナウイルスの対策と...
-
寸借詐欺(すんしゃくさぎ)とは、「財布を落とした」「交通費を忘れた」などとうそをつき、相手の善意に付け込んで、金銭をだまし取る行為のことをいいます。...
詐欺事件を起こしたらコラム一覧へ戻る


















































