2010年に時効廃止になった犯罪の種類|殺人事件などで時効がなくなった経緯とは?


多くの犯罪には公訴時効が設けられており、時効が完成すると被疑者を起訴することはできなくなります。
しかし、2010年施行の改正刑事訴訟法により、殺人罪など一部の重大犯罪は公訴時効が廃止されました。
本記事では、刑事事件と時効廃止の関係を知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。
- 公訴時効が廃止された犯罪の条件
- 公訴時効が廃止された人を死亡させた罪で死刑がある犯罪の具体例
- 人を死亡させた罪ではあるものの公訴時効が廃止されていない犯罪
- 公訴時効の廃止を含む改正がされた2010年の刑事訴訟法の概要 など
本記事を参考に、どの犯罪の公訴時効が廃止されて、どの犯罪が廃止されていないのかを理解しましょう。
公訴時効が存在しない犯罪もある!時効が廃止された犯罪の条件は?
公訴時効が存在しない犯罪とは、人を死亡させたもので法定刑に死刑がある犯罪のことです。
- 人を死亡させた犯罪であること
- 法定刑の上限が死刑であること
たとえば、殺人罪、強盗致死罪、強盗・不同意性交等致死罪などの犯罪が該当するでしょう。
以前はこれらの犯罪にも公訴時効はありましたが、2010年に施行された改正刑事訴訟法によって撤廃されました。
なお、公訴時効と各犯罪の関係性については、以下のページで詳しく解説しています。
公訴時効が廃止された犯罪の例|人を死亡させた罪で死刑がある場合
現時点で公訴時効が廃止されている主な犯罪は、以下のとおりです。
- 殺人罪
- 強盗致死罪
- 強盗・不同意性交等致死罪 など
ここでは、公訴時効が廃止されている主な犯罪について解説します。
1.殺人罪
殺人罪は刑法第199条に規定されている、人を殺した場合に成立する犯罪のことです。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
殺人罪は「人を死亡させる犯罪」の典型例といえます。
そして、法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の懲役となっており、公訴時効廃止の条件を満たしています。
殺人罪の詳細については、以下のページで解説しています。
2.強盗致死罪
強盗致死罪は刑法第240条に規定されている、強盗の際に人を死亡させた場合に成立する犯罪のことです。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
一般的に強盗致死罪は、故意(殺意)が認められる「強盗殺人」と、故意がない「強盗致死」に分類されます。
しかし、法定刑は故意の有無に関係なく死刑または無期懲役であり、いずれも公訴時効廃止の対象となっています。
3.強盗・不同意性交等致死罪
強盗・不同意性交等罪は刑法第241条3項に規定されている、強盗現場で性交したうえで人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
(強盗・不同意性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
強盗・不同意性交等罪は、強盗のうえ性犯罪を働き、他人を死亡させる非常に悪質な犯罪となっています。
前述した強盗致死罪と同じく法定刑は死刑または無期懲役であり、公訴時効廃止の条件を満たしています。
公訴時効が廃止されていない犯罪の例|2つのパターンについて解説
公訴時効が廃止されていない犯罪には、以下のようなものがあります。
- 人を死亡させたが、死刑が設けられていない犯罪の場合
- 死刑が設けられているが、人を死亡させていない犯罪の場合
ここでは、公訴時効が廃止されていない犯罪について2つのパターンに分けて説明します。
1.人を死亡させたが、死刑が設けられていない犯罪の場合
殺人罪や強盗致死罪などのほかにも、人を死亡させた犯罪には以下のようなものがあります。
【人を死亡させた犯罪の例】
|
犯罪 |
法定刑 |
|
不同意性交等致死罪(刑法第181条2項) |
無期または6年以上の懲役 |
|
不同意わいせつ致死罪(刑法第181条1項) |
無期または3年以上の懲役 |
|
傷害致死罪(刑法第205条) |
3年以上の有期懲役 |
|
業務上過失致死罪(刑法第211条) |
5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金 |
|
危険運転致死罪(自動車運転死傷処罰法第2条) |
1年以上の有期懲役 |
|
過失運転致死罪(自動車運転死傷処罰法第5条) |
7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金 |
上記の犯罪も人を死亡させた犯罪に区分されます。
しかし、いずれの犯罪も法定刑に「死刑」がないため、公訴時効廃止の対象にはなっていません。
2.死刑が設けられているが、人を死亡させていない犯罪の場合
殺人罪や強盗致死罪などのほかにも、死刑が設けられている犯罪はいくつかあります。
【死刑が設けられている犯罪の例】
|
犯罪 |
法定刑 |
|
殺人未遂罪(刑法第203条) |
死刑または無期もしくは5年以上の懲役 |
|
現住建造物等放火罪(刑法第108条) |
死刑または無期もしくは5年以上の懲役 |
|
激発物破裂罪(刑法第117条) |
現住建造物等の場合:死刑または無期もしくは5年以上の懲役 |
|
内乱罪(刑法第77条) |
首謀者の場合:死刑または無期禁錮 |
|
外患誘致罪(刑法第81条) |
死刑 |
上記のような犯罪には死刑が設けられています。
しかし、人を死亡させた犯罪ではないため、公訴時効廃止の対象にはなっていません。
公訴時効の廃止を含む改正がされた2010年の刑事訴訟法の概要
最後に、公訴時効が廃止された2010年の改正刑事訴訟法について説明します。
1.遺族の方の声を反映させる形で公訴時効の見直しがされた
2010年に殺人罪などの公訴時効が廃止された背景には、被害者遺族の声が関係しているといいます。
- 2008年2月:全国犯罪被害者の会が、殺人事件における公訴時効廃止を要望する
- 2009年2月:殺人事件被害者遺族の会が、凶悪事件における公訴時効廃止を要望する
上記のような活動を受け、法務省は海外の制度や国民の意識動向などさまざまな調査をおこないます。
そして2010年3月12日に公訴時効期間を延長する法案が国会に提出され、同年4月27日に成立されました。
2.「人を死亡させた罪」の公訴時効が廃止または延長された
2010年の刑事訴訟法の改正では、人を死亡させた犯罪全般について公訴時効の見直しがおこなわれています。
【法定刑の内容別の改正前と改正後の公訴時効の違い】
|
犯罪の種類と法定刑の内容 |
改正前 |
改正後 |
|
法定刑の上限が死刑:殺人罪など |
25年 |
なし |
|
法定刑の上限が無期懲役・禁錮:不同意性交等致死罪など |
15年 |
30年 |
|
法定刑の上限が20年の懲役・禁錮:傷害致死罪など |
10年 |
20年 |
|
上記以外で法定刑の上限が懲役・禁錮:過失運転致死罪など |
3年/5年 |
10年 |
全体的に公訴時効が長くなったため、これまでは諦める必要があった犯罪でも、処罰できる可能性が高まりました。
3.法改正時に時効が完成していない犯罪には改正後の規定が適用される
改正前に起こした犯罪の公訴時効が成立していなかった場合は、改正後の公訴時効が適用されます。
たとえば、殺人をしてから逃亡し続けており、2010年4月1時点で24年11ヵ月捕まっていなかったとします。
この場合は同年4月27日に法改正がされたため、公訴時効が廃止されていつでも処罰できるようになっています。
なお、最高裁判所は2015年12月3日に「時効撤廃をさかのぼって適用することは合憲である」と判断しています。
さいごに|殺人罪や強盗殺人罪などの公訴時効は廃止されている
2010年以降、人を死亡させたもので法定刑に死刑がある犯罪は、公訴時効が廃止されています。
殺人罪、強盗殺人罪、強盗・不同意性交等致死罪などは、時効が廃止されていると覚えておきましょう。
もし刑事事件の時効のことで不安がある場合には、刑事事件が得意な弁護士に相談することをおすすめします。


【不同意性交・痴漢・盗撮などの性犯罪に注力】【初回相談0円|即日対応◎】『警察・被害者から連絡を受けている』方は当弁護士にご相談を!◆暴行・傷害なども対応◆依頼者の味方となり早期解決へのサポートを【即日接見・韓国語も対応可能】≫まずは写真をクリック≪
事務所詳細を見る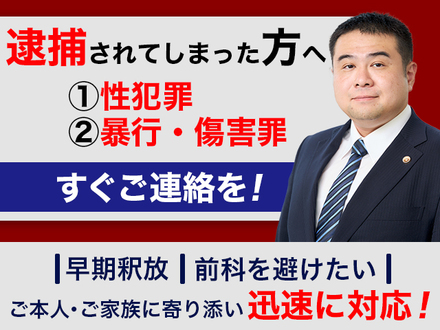
【性犯罪/暴行・傷害罪】当事務所は、原則として、都心での性犯罪および暴行・傷害罪のみ対応し、これらの刑事事件の不起訴処分を目指す事務所です。【渋谷駅徒歩5分】
事務所詳細を見る
【即日接見◎│初回面談0円】「警察から連絡が来た方」「ご家族が逮捕された方」はお早めにご連絡ください◆痴漢・盗撮・強制わいせつ/暴行・傷害など示談交渉は当事務所にお任せを◆早期解決に向けて全力でサポート!※匿名でのご相談はお受けできません。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
-
盗撮の冤罪にあいそうなときでも、対応を間違えると逆に状況が悪化する可能性があります。万が一のときに冷静に対応できるよう、正しい対処法と注意点をおさえ...
-
本記事では、廃棄物処理法違反について知りたい方向けに、廃棄物処理法違反に該当する代表的な行為、一般人・事業者それぞれの廃棄物処理法違反を防止するポイ...
-
家族が留置場に入れられた場合、留置場がどのような施設なのか当然気になるものです。本記事では、留置場の施設概要や一日の流れなどを解説しています。差し入...
-
「立件」という言葉はニュースなどで頻繁に用いられます。しかし、具体的にどのような状況を指すのか理解している人は少ないはずです。本記事では、立件の意味...
-
刑事事件を起こして刑事告訴されると、警察が捜査開始して逮捕や裁判となるおそれがあります。逮捕回避や減刑獲得に向けて迅速に動くためにも、手続きの流れを...
-
殺害された人が生前殺されることを承諾していた場合、犯行に及んだ人物は殺人罪ではなく、承諾殺人罪の容疑で刑事訴追されます。本記事では、承諾殺人の構成要...
-
単純逃走罪と加重逃走罪は、いずれも対象が勾留された被疑者や受刑者などとなり、一見して違いがわからないかもしれません。本記事では両者の概要や違い、共通...
-
検察庁からの呼び出しは、主に事件の取り調べや起訴・不起訴の判断のためです。呼び出しは任意ではあるものの、拒否すると逮捕のリスクがあります。本記事では...
-
道路交通法違反の時効と刑事罰に関する完全ガイドです。スピード違反から飲酒運転、あおり運転まで、各交通違反行為に適用される公訴時効を解説します。違反種...
-
刑事事件における時効とは、犯罪から一定期間経過すると加害者が起訴されなくなる制度です。罪を逃れられる制度がなぜ存在しているのか、疑問に感じている人も...
-
本記事では、心神喪失状態で起こした事件について、なぜ無罪になるのかについて詳しく解説します。 また、心神喪失で無罪になったあとの手続きの流れや、心...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る
























































