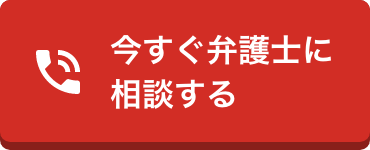【加害者限定】
【加害者限定】お急ぎの方へ

累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
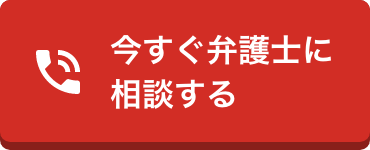
不正アクセス禁止法は、アクセス権限がないネットワークに侵入したり、パスワードを盗み取ったりすることなどを禁止する法律です。
SNSで他人のアカウントに勝手にログインする、ネットバンキングで勝手に送金する行為などがあてはまります。
総務省の統計によると、2016年~2020年の不正アクセス禁止法の認知件数はおおよそ1,000~3,000件の間で推移しており、2020年は2806件でした。不正アクセス後の行為としては「インターネットバンキングの不正送金」が最も多く、65,8%を占めています(※)。
ネットの普及により、今後ますます認知件数増加が予想される不正アクセス行為は、どのようなもので、どういった処罰が定められているのでしょうか。
この記事では、不正アクセス禁止法で規定されている行為やその罰則、万が一逮捕されてしまった後の流れ、逮捕後の対処などについて解説します。
不正アクセス禁止法の理解を深めたい人は参考にしてください。
(※参考)不正アクセス行為の発生状況|総務省
ご家族や自身が不正アクセス禁止法で逮捕された方へ
不正アクセス禁止法は、その行為によって懲役や罰金などが刑罰に定められています。
起訴され有罪になれば、前科がつき今後の人生に大きな影響を与えかねません。
ご家族や自身が逮捕された方は、弁護士への依頼がおすすめです。
それは次のようなサポートを受けられるからです。
- 取調べのアドバイスを受けられる
- 勾留取消請求や準抗告で早期釈放を目指せる
- 不起訴処分獲得のための弁護活動をしてもらえる
- 刑事裁判になっても執行猶予判決を得るための弁護活動をしてもらえる など
刑事事件は早い段階での弁護活動が重要です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|
不正アクセス禁止法で規制されている行為と罰則
早速、『不正アクセス禁止法』で規定されている禁止行為と罰則を確認していきましょう。
【関連記事】
▶サイバー犯罪に該当する罪名まとめ|防御策と対処法
▶ハッキングとは|手口やクラッキングとの違い・罰則を解説
不正アクセス行為自体の禁止|第3条(不正アクセス罪)
不正アクセスを行うこと自体を禁止する条文です。不正アクセスとは、本来アクセス権限を持たない人が、サーバーやSNS、情報システムの内部へ侵入する行為を指します。
第3条の罰則は、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第3条
具体例
他人のLINEに無断でログインする行為。
他人のパスワードなどの不正取得の禁止|第4条(不正取得罪)
他人のパスワードを正当な理由なく取得することを禁止する条文です。
第4条の罰則は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第4条
具体例
システム管理者のふりをして電話をかけ、パスワードを聞き出す行為。
正当な理由がないパスワード伝達の禁止|第5条(不正助長罪)
他人のパスワードを知っている人が本来知る権利のない人へパスワードを伝達することは、不正アクセス行為を助長することになります。
不正アクセス禁止法第5条は、こうした行為を禁止する条文です。
第5条の罰則は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第5条
具体例
友達のTwitterのパスワードを他人に教える行為。
不正アクセスのためのパスワード保管の禁止|第6条(不正保管罪)
他人のパスワードなどを不正に保管しておくことを禁止する法律です。
第6条の罰則は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第6条
具体例
不正アクセスする目的で、入手したパスワードを保管しておく行為。
不正なパスワードの入力要求の禁止|第7条(不正入力要求罪)
不正にパスワードなどの入力を要求することを禁止する法律です。
第7条の罰則は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為
二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為
引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第7条
具体例
公式サイトになりすまして、他人にパスワードを入力させる行為。
アクセス管理者の義務|第8条
不正アクセス禁止法では、サーバー管理者やサイト管理人などアクセス管理者は、以下の措置を講じる義務があるとされています。
- パスワードなどを適切に管理する措置
- アクセス制限機能を適切に管理・強化する措置
- その他の不正アクセス行為を防ぐ措置
なお、第8条はアクセス管理者に課せられた義務についての記載で、罰則はありません。
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第8条
不正アクセス禁止法違反で逮捕された後の流れ
冒頭でもお伝えしましたように、不正アクセス禁止法違反で逮捕された人は多数存在します。ここでは、逮捕されるとどのような流れになるか確認しておきましょう。

逮捕後48時間以内|逮捕期間ー警察からの捜査~送検
不正アクセス禁止法違反で逮捕された場合、警察からの捜査を受けることになります。ただ、この捜査は逮捕から48時間以内と決まっており、捜査後、被疑者の身柄は警察から検察へと移されます(送検)。
逮捕されたとき、誰でも『当番弁護士制度』の利用が可能です。1度だけ弁護士と面会できアドバイスをもらえるのがメリットです。
ただし、次に紹介するような「勾留」以降も続けてサポートを得るには、私選弁護士に相談しなければなりません。
早期釈放や不起訴を獲得するには私選弁護士への依頼が有効です。逮捕直後から私選弁護士に依頼するのがベストです。
送検後24時間以内|逮捕期間ー勾留請求
証拠隠滅や逃走を防ぐために、被疑者の身柄を拘束する場合があり、これを勾留と言います。勾留が必要だと判断された場合は、検察によって送検後24時間以内に手続きがなされます。
ただし、私選弁護士に依頼しておくと、勾留をしておく必要がない旨の主張・立証などの弁護活動ををしてもらえ、早期の釈放が目指せます。
勾留開始最大20日間|勾留期間・起訴・不起訴処分決定期間
勾留期間は原則10日間で、この間に検察官は起訴か不起訴かを決めなくてはいけません。しかし、さらなる捜査などが必要と判断された場合、勾留の期間を最大10日間延長できます。
ちなみに、起訴とは検察が被疑者に対して裁判所に訴訟を起こすことです。起訴された場合の有罪率は、99.9%です。逆に不起訴で終わった場合は、前科がつくことなくただちに釈放されます。
勾留が決定しても、私選弁護士に依頼すると、勾留取消請求や準抗告などによって、早期の釈放が目指せます。
逮捕後約1~2ヶ月|刑事裁判
起訴を受けると、『被疑者』から『被告人』へと呼び方が代わり、原則的には起訴後も身柄を拘束され続けます。刑事裁判までは約1ヶ月と長期間の拘束になってしまいます。
私選弁護士に依頼しておけば、保釈請求によって起訴後であっても身体解放を目指せます。また、刑事裁判では執行猶予付き判決など軽い処分を目指すための弁護活動もしてもらえるのがメリットです。
不正アクセス禁止法違反で逮捕された後の対処法
不正アクセス禁止法違反で逮捕されてしまったら、どうしたらよいのでしょうか。ここでは、身に覚えがある場合とない場合、それぞれの対処法をお伝えします。
身に覚えがない場合(否認する場合)
あなたが不正アクセスをしていなくても、他人にパソコンを遠隔操作され、不正アクセスに悪用されるおそれもあります。まったく身に覚えがない場合は、遠隔操作の可能性も考え、弁護士に相談するようにしましょう。
そして、取調べ中は黙秘権を行使して罪を認めないようにしましょう。万が一、取調べ中に自白に近い供述をした後に、裁判時の主張と食い違ってしまうと、発言の信頼性が損なわれてしまいます。
心当たりがある場合(認める場合)
不正アクセスを実際に行って逮捕された場合には、ただちに弁護士に依頼してください。弁護士のサポートがなければ、起訴されそのまま有罪判決を受ける可能性も否定できません。
逮捕された後の72時間は家族との面会も許されていません。その間に面会できるのは弁護士に限られています。
弁護士に依頼すると、まずは取調べのアドバイスをします。24時間監視下に置かれ厳しい取調べを受けると、不本意な発言をして不利な供述調書が作成される可能性もあるでしょう。弁護士が面会することで精神的な支えになり、適切なアドバイスをすることで、不利な供述調書が作成されるのを防ぎます。
また、弁護士に依頼すれば勾留取消請求や準抗告、さらに保釈請求などによって早期の身体解放を目指せるのもメリットです。最大で23日間拘束されると、実社会からの隔離によって、有形無形の不利益を被る可能性もありますのが、そういった事態も防げます。
さらに、被害者との示談や反省文の作成、そのた被疑者に有利な証拠の収集などによって、不起訴や執行猶予処分なども目指します。起訴されると99%が有罪になるといわれているので、早期からの弁護士への依頼はとても重要です。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事トラブルに注力する弁護士を探せるサイトです。相談料無料・土日対応可・即日対応可の事務所も掲載しています。刑事事件はスピードが命ですから、万が一逮捕されたら早急に弁護士へ依頼しましょう。
家族が不正アクセスで逮捕された場合の対処法
ここでは、万が一家族が不正アクセス禁止法で逮捕された場合の対処法をお伝えします。
弁護士に依頼して被疑者と接見してもらう
被疑者は逮捕されて呆然としていて、何をしていいのかわからない場合が多いでしょう。実は起訴・不起訴判断は逮捕後23日以内、そして裁判は目安として逮捕後1~2ヶ月以内に行われます。
そのため、刑事事件において処分の軽減を目指すならばスピードが命です。今後の流れや、取調べの対処法などについて知っておくことが、処分の軽減を目指すために重要です。
接見時、これらについて弁護士が被疑者へ伝えてくれます。
弁護士と共に示談交渉の準備を進める
示談交渉において被疑者(加害者)が被害者に直接会うことは避けるべきでしょう。なぜなら、被疑者が直接被害者と会うことによって、事件時のつらい記憶や恐怖などの被害者感情を煽ることになり、被害者の混乱や怒りにつながって事態が悪化する可能性があるからです。
弁護士に間に入ってもらい示談交渉を進めてもらうことが重要になってきます。また、示談に要する時間のことを考えなくてはいけません。
- 被害者が示談を受けるか否かを決定する時間
- 示談場所・時間を決定するための時間
- 1回で示談が成立しなかった場合の日程調整の時間
などを考えると、示談は時間を必要とすることがわかります。
先ほどもお伝えしたように、刑事事件はスピードが命です。被害者感情と時間を鑑みて、家族が弁護士に早く相談し、示談の準備を進めていくことが推奨されます。
不正アクセス禁止法の裁判例
最後に、不正アクセス禁止法違反で逮捕された事例をご紹介します。
インターネットバンキングなりすまし
刑罰
懲役8年
未決勾留日数中700日をその刑に算入
押収してある無線接続機器1式(平成28年押第25号符号1)を没収
以上の刑罰になった理由等
以下のような不正アクセスを多数働いた。
- 不正アクセス行為目的でインターネットバンキングサービスになりすまして、相手の顧客番号、ログインパスワード、インターネット用暗証番号等の識別符号を同サイトに入力させた。
- そしてそのパスワードを用いて、不正アクセス行為をはたらいた。
| 参考:東京地裁 平成29年4月27日(Westlaw Japan 文献番号 2017WLJPCA04279011) |
社内権限を使用した不正アクセス
刑罰
被告人を懲役1年6ヶ月
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予
以上の刑罰になった理由等
- 被告人は以下の事実に関わった。
- 総務課人事労務担当主査として職員の健康診断に関する事務に従事していた。
- 性的好奇心を満たすために女性職員の健康診断結果に関する個人情報を入手しようと考えた。
- 11人の健康診断結果に関する情報を被告人方に設置されたパーソナルコンピューターに転送した。
- 後日、同様の手口で女性職員の電話番号を手に入れた。
|
参考:横浜地裁 平成28年4月26日(Westlaw Japan 文献番号 2016WLJPCA04266005)
|
まとめ
不正アクセス禁止法では、さまざまな行為が禁止されています。それぞれの行為に罰則が規定されていますが、ほとんどが懲役刑を含んでおり、起訴されると正式裁判になる可能性もはらんでいます。
もし、不正アクセス禁止法に該当してしまったら、ただちに弁護士へ相談しましょう。
刑事事件は逮捕後の72時間までに弁護士からのサポートを受けられるかがカギといっても過言ではありません。
逮捕直後の取調べの段階からサポートを受けることで、早期釈放の可能性を高め、不起訴処分や執行猶予判決など軽い刑事処分も目指せます。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事トラブルに注力している弁護士を探せるサイトです。相談料無料・土日対応可の事務所も多数あるので、ご家族が逮捕された・これから逮捕される可能性がある人は、早急に依頼するようにしてください。
ご家族や自身が不正アクセス禁止法で逮捕された方へ
不正アクセス禁止法は、その行為によって懲役や罰金などが刑罰に定められています。
起訴され有罪になれば、前科がつき今後の人生に大きな影響を与えかねません。
ご家族や自身が逮捕された方は、弁護士への依頼がおすすめです。
それは次のようなサポートを受けられるからです。
- 取調べのアドバイスを受けられる
- 勾留取消請求や準抗告で早期釈放を目指せる
- 不起訴処分獲得のための弁護活動をしてもらえる
- 刑事裁判になっても執行猶予判決を得るための弁護活動をしてもらえる など
刑事事件は早い段階での弁護活動が重要です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|