不起訴処分が前科に与える影響|正しく理解し対処するための基礎知識

- 「不起訴になっても前科はつくのか」
- 「どうすれば不起訴を勝ち取ることができるのか」
逮捕されてしまった場合、なんとかして不起訴になりたいと考えるのは当然のことです。
しかし、不起訴を勝ち取ったとしても、私生活になんらかの不利益が生じるのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、不起訴処分となった際に前科がつくのかどうかを解説します。
不起訴処分となる条件や、逮捕後に不起訴処分を獲得するためのポイントなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

Q1 あなたは事件の…
不起訴処分でも前科はつくの?前科はつかないが前歴は残る
まず、不起訴処分でも前科はつくのかどうかを解説します。
不起訴なら前科はつかない
逮捕されたとしても、不起訴であれば前科はつきません。
前科がつくのは、起訴されて有罪判決を受けたときだけです。
そのため、不起訴となり釈放されたあとは普段どおりの生活を取り戻すことができます。
不起訴であっても前歴は残る
不起訴になると前科はつきませんが、前歴は残る点に注意しておきましょう。
前歴とは、捜査機関の捜査対象になったものの、有罪判決には至らなかった経歴のことです。
前歴は消すことができず、本人が死亡するまで残り続けます。
しかし、前歴があるからといって、私生活への影響を心配する必要はありません。
海外旅行にいったり、ローンを組んだり、国家資格を取得したりすることもできます。
前歴の有無は照会をかけて調べられるものではなく、自ら申告する義務もないので、就職活動などで不利になることもないでしょう。
ただし、再犯の際に前歴があることで不利になる可能性はあります。
刑事事件において不起訴処分以外で前科がつかない2つのケース
不起訴を獲得する以外にも、前科を避けられる方法は存在します。
ここでは、刑事事件において不起訴処分以外で前科がつかない2つのケースを詳しく見ていきましょう。
1.微罪処分|一定の犯罪について警察限りで終結させる手続きのこと
微罪処分が下された場合は、前科がつきません。
微罪処分とは、比較的軽い犯罪の捜査を警察限りで終結させる手続きのことです。
検察官に事件が引き継がれる前に捜査が終了するので、その時点で前科は確実に避けられます。
微罪処分となる犯罪の種類は自治体ごとに異なりますが、窃盗罪・詐欺罪・賭博罪・暴行罪・傷害罪などが一般的です。
もちろん、事件の規模や前科の有無などによっては検察に送致され、起訴される可能性も十分あり得ます。
2.無罪判決|刑事裁判において被告人が刑に処されない判決のこと
不起訴処分以外で前科がつかないケースのひとつが、無罪判決を受けた場合です。
無罪判決とは、刑事裁判において被告人が刑に処されない判決のことを指します。
検察官が起訴を決定すると裁判が開かれ、裁判官が有罪・無罪の判決を下すことになりますが、無罪判決を勝ち取ればいかなる処罰も受けません。
とはいえ、日本の刑事事件における有罪率は99%を超えます。
起訴されてしまった段階で有罪となり、前科がつくことはほぼ確実といえるでしょう。
刑事事件を起こした場合に前科がつくことになる3つのケース
次に、刑事事件を起こした場合に前科がつくケースを紹介します。
実刑判決・執行猶予付き判決・略式命令の3種類があるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.実刑判決|被告人に対する執行猶予を設けない有罪判決のこと
刑事事件を起こし、実刑判決が下された場合は前科がつきます。
実刑判決とは、被告人に対する執行猶予を設けない有罪判決のことです。
実刑には懲役・禁錮・罰金などがありますが、いずれにしても前科はついてしまいます。
2.執行猶予付き判決|被告人に対して執行猶予を設ける有罪判決のこと
執行猶予付き判決を受けた場合も前科はつきます。
執行猶予付き判決とは、被告人に対して執行猶予を設ける有罪判決のことです。
執行猶予期間中は普段どおりの生活を送ることができ、犯罪を起こさなければ刑が免除されるため、執行猶予がつくかどうかはその後の人生を左右する分かれ道となります。
しかし、執行猶予付き判決であっても有罪であることに変わりなく、前科がついてしまう点には注意しておきましょう。
3.略式命令|略式手続で簡易裁判所から出される罰金・科料の命令のこと
刑事事件を起こした場合に前科がつくケースのひとつが、略式命令が出された場合です。
略式命令とは、略式手続で簡易裁判所から出される罰金・科料の命令のことを指します。
略式命令に懲役などの刑罰はなく、命じられるのは罰金・科料の支払いだけです。
しかし、正式な裁判手続きが省かれているにすぎず、略式命令が確定した場合は有罪判決と同じ効力が生じます。
そのため、不服申し立てをおこなわない限りは有罪が確定し、前科がついてしまうのです。

Q1 あなたは事件の…
刑事事件を起こして逮捕されても不起訴処分となるケース
刑事事件を起こして逮捕されても、不起訴処分となれば前科がつくことを避けられます。
ここでは、逮捕後に不起訴処分となるケースを詳しく見ていきましょう。
1.嫌疑なし|被疑者が犯人でないことや証拠がないことが明白な場合
逮捕後に「嫌疑なし」となった場合は、不起訴処分となります。
嫌疑なしとは、被疑者が犯人でないことが明白な場合や、証拠が見つからない場合におこなわれる判断です。
たとえば、真犯人がほかに見つかったときなどは嫌疑なしで不起訴となり、当然前科がつくこともありません。
2.嫌疑不十分|犯罪の成立を認定するのに必要な証拠が不十分な場合
「嫌疑不十分」とされた場合も、不起訴処分となります。
嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定するために必要な証拠が不足している場合におこなわれる判断です。
被告人を裁判で有罪にするには、一般人が合理的疑いを抱かない程度の立証が求められます。
そのため、被疑者にアリバイがあり、明白な証拠が見つかっていないときなどは、裁判官も起訴することができません。
確証をもてない限りは、嫌疑不十分として不起訴とせざるを得なくなるわけです。
3.起訴猶予|犯罪は明白であるが、一定の事情を考慮して訴追しない場合
刑事事件を起こして逮捕されても、不起訴処分となるケースのひとつが「起訴猶予」です。
起訴猶予とは、犯罪をおこなったことは明白であるものの、一定の事情を考慮して訴追しない判断のことを指します。
実際、起訴猶予を理由に不起訴となるケースが最も多く、その数は半数以上にのぼります。
なお、検察官は以下のような点を考慮したうえで、起訴猶予とするかどうかを判断するケースが一般的です。
- 犯人の年齢・性格・境遇
- 犯罪の軽重・動機・様態
- 示談の有無
- 反省の程度
たとえば、万引きなどの軽微な犯罪を犯した場合に、初犯かつ示談も成立しているようであれば、起訴猶予となる可能性は高いといえるでしょう。
不起訴処分を獲得し前科をつけないための3つのポイント
不起訴処分を獲得できるかどうかで、その後の人生は大きく変わります。
ここでは、不起訴処分を獲得し、前科をつけないためのポイントを解説するので参考にしてみてください。
1.犯罪について深く反省をする
まずは、犯罪を犯したことについて深く反省することが大切です。
十分な反省が見られ、再犯の可能性が低いと判断された場合には不起訴になる可能性があります。
反省の意は、目に見える形で示さなければなりません。
検察庁に反省文を提出したり、被害者に謝罪文を送付したりといった対応が考えられるでしょう。
2.被害者との示談を成立させる
被害者との示談を成立させることも、不起訴処分を獲得し、前科をつけないための方法のひとつです。
示談の成立は、被害者が加害者を許し、処罰を求めない意向があることを意味します。
そのため、検察官からも刑罰を科す必要性は低いと判断され、不起訴を獲得できる可能性が高まるのです。
また、早急に示談を成立させ、被害届を取り下げさせることができれば、その時点で警察の捜査自体が終了する可能性もあります。
3.できる限り早く弁護士に相談する
不起訴処分を獲得したいのであれば、できる限り早く弁護士に相談しましょう。
法律の知識と実務経験に基づいた弁護活動をおこなってもらうことで、不起訴処分を勝ち取れる可能性があります。
たとえば、被害者との示談交渉や警察・検察へのはたらきかけなどを円滑に進めてもらえるはずです。
自力で事態を収集することは難しいので、逮捕された場合には刑事事件が得意な弁護士を早急に探すようにしてください。

Q1 あなたは事件の…
不起訴処分と前科に関するよくある質問
最後に、不起訴処分と前科に関するよくある質問に回答します。
Q.不起訴処分になる割合はどれくらいですか?
検察に送致されたあとで、不起訴処分になる割合は6~7割程度です。
多くの場合、起訴猶予を理由に不起訴処分となっています。
Q.不起訴になるかどうかはいつわかりますか?
逮捕・勾留によって身柄が拘束される身柄事件の場合は、逮捕後23日以内に不起訴かどうかが判断されます。
通常どおりの生活を送りながら捜査が進められる在宅事件の場合は、起訴か不起訴の判断がいつになるかは不明です。
被疑者本人が処分の見込みを尋ねても、検察から回答してもらえることはほとんどありません。
Q.示談が成立すれば必ず不起訴になりますか?
示談が成立したからといって、必ずしも不起訴になるとは限りません。
前科があったり、事件の内容が深刻だったりすると起訴されることがあります。
反対に、軽犯罪で初犯であるような場合には、示談の成立を理由に不起訴となる可能性が高いといえるでしょう。
不起訴によって前科がつかないメリットは何ですか?
不起訴によって前科がつかないメリットには、以下のような点が挙げられます。
- 就職活動時の不利益を避けられる
- 資格の取得制限を受けずに済む
- 自由に渡航できる
起訴されて有罪となった場合は、就職希望先に提出する履歴書に前科を記載しなければなりません。
犯罪を犯した経歴を知られてしまうため、就職活動に支障が生じる可能性は高いと考えられます。
また、前科の内容によっては医師や教員などの資格取得を制限されるほか、パスポート・ビザが発行できないケースもあります。
このように、不起訴になるかどうかで、その後の人生が大きく変わることを覚えておきましょう。
さいごに|前科をつけないためにも早めに弁護士に相談を!
逮捕されてしまった場合は、前科をつけないためにも早めに弁護士に相談してください。
迅速に弁護活動や示談交渉を進めてもらうことによって、不起訴処分を勝ち取れるかもしれません。
前科を回避できれば不利益を受けることもなく、普段通りの生活を取り戻せます。
弁護士を探す際は、できるだけ刑事事件が得意な弁護士に依頼することを心掛けましょう。
豊富な知識と経験のある弁護士であれば、被害者の心情を汲み取りながら示談交渉を進めたり、検察官に直接不起訴処分を訴えたりすることができます。
初回の相談であれば無料で対応している弁護士も多いので、まずは気軽に問い合わせてみることが大切です。

Q1 あなたは事件の…

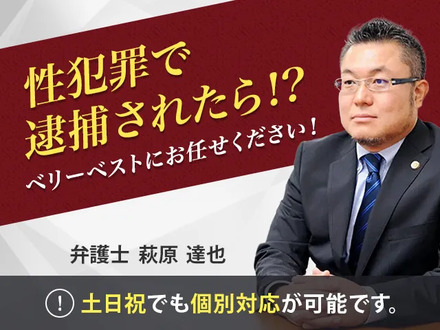
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る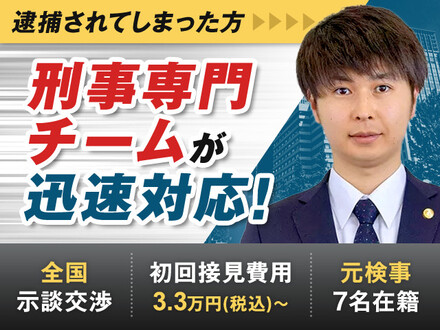
【町田駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る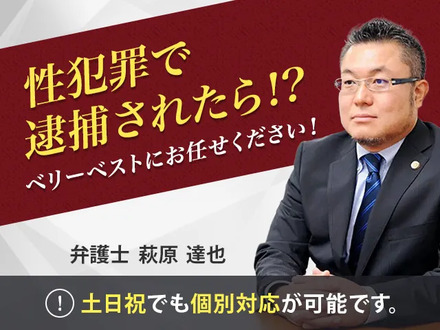
【六本木一丁目駅近】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
出頭要請(出頭命令)とは、警察や検察から受ける呼び出しのことを指します。任意ではあるものの、拒否すると逮捕されたりする可能性があります。本記事では、...
-
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮のような明確な性犯罪行為に加えて、卑猥な言動を処罰対象にしていることが多いです。本記事では、迷惑防止条例に規定される卑猥...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
本記事では、身元引受人になれる条件や具体的な役割、そして身元引受人が見つからない場合の対処法まで、分かりやすく解説します。
-
無免許運転で逮捕された高校生は、長期間の身体拘束や退学処分を受ける可能性があります。早期の身柄解放や退学処分の回避、家庭裁判所・学校と連携を図るため...
-
業務をしているとき、過失によって事故を起こしてしまったら、業務上過失致死傷罪に問われます。業務上過失致死傷罪に該当するのは、どのような事故のときなの...
-
本記事では、刑事裁判における上告と控訴の違い、上訴を検討しているときに刑事裁判を得意とする弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します...
-
「少年センター」とはどのような施設なのか、具体的な活動内容・対象年齢・利用条件などについて解説します。
-
日本の司法取引制度は、2018年6月に施行されたばかりであり、事件解決に向けて重要な供述を得るための活用が期待されています。本記事では、日本の司法取...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る

























































