【加害者向け】警察は証拠がないと動かない?刑事事件を起こした場合にとるべき対応

罪を犯してしまったものの、証拠がないから大丈夫だろうと安心している方もいるかもしれません。
しかし、警察は証拠がなくても動くことがあります。
事件性があれば捜査が開始され、その過程で証拠が見つかれば逮捕される可能性もあるのです。
本記事では、警察がどのような状況で動くのか、証拠の種類や重要性、そして逮捕される前に取るべき行動について詳しく解説します。
何らかの事件の加害者になってしまった方は、本記事を参考にしつつ、弁護士に相談することも検討しましょう。
警察は証拠がないと動かないのか?事件性があれば動く可能性はある
実は、証拠がなくても事件性があれば警察は動きます。
刑事訴訟法第317条では刑事裁判にて事実認定をする際には証拠によることが定められています。
事件があった際に捜査を通じて証拠を収集し、犯罪事実を裁判で証明するのが捜査機関の仕事です。
そのため、事件が発生した時点では証拠が乏しかったとしても、警察が動くことはあります。
警察が動くのは非親告罪または被害届が提出された場合です。
非親告罪は親告罪ではないものであり、親告罪とは被害者やその関係者などからの告訴がなければ検察が起訴できない犯罪のことを指します。
刑法で規定されている多くの犯罪は非親告罪であるため、ほとんどの場合、事件性があれば警察は動くと考えてよいでしょう。
警察官が捜査活動の際に守るべき心構えや捜査方法などについて定めた犯罪捜査規範第67条柱書においては、告訴または告発を受けたら特にすみやかに捜査をおこなう努力をすることが規定されています。
告訴状・告発状が提出された場合、警察は捜査をするよう努めるのが通常だといえるでしょう。
なお、証拠がなかったとしても現行犯であれば逮捕が可能です。
現行犯逮捕とは、犯罪をしている最中や犯罪の直後に逮捕されることを指します。
現行犯逮捕ができるのは、警察官に限りません。被害者本人や犯行現場に居合わせた方が取り押さえることも現行犯逮捕に含まれます。
このような場合は警察官や検察官に身柄を引き渡すことになるでしょう。
警察が動く可能性が高まる証拠の例|物証と人証の違い
証拠がなかったとしても警察が動く可能性はありますが、証拠がある場合はなおさら迅速に捜査が開始されるでしょう。
警察が動く可能性が高まる証拠として、物証と人証があります。
それぞれの違いについて、以下で詳しくみてみましょう。
1.物証|犯行に使われた凶器など
物証とは、ものの存在や状態自体が証拠となるものです。
犯行に使用された凶器のほか、録音された音声や録画された映像も物証にあたります。
物証は、客観的に事実を証明するものとして「客観証拠」とも呼ばれます。
傷害事件におけるナイフなどの特定物だけでなく、窃盗事件が起こった際に家を荒らされた状態を写真に収めたものも物証として取り扱われます。
客観証拠は、証明力が高い証拠であると考えられています。
2.人証|被害者や目撃者の証言など
人証とは、被害者や目撃者などが口頭で発言した内容が証拠となるものです。
証人の発言のほか、供述調書・陳述書などの書面となったものも人証にあたります。
被害者や目撃者だけでなく、被告人の親族や鑑定人などの専門家の発言も、証拠能力があれば人証となります。
人証は人の主観的な認識であるため、客観証拠ではありません。
しかし、人証だけで告訴できるケースも存在します。
なぜなら、痴漢をはじめとする性犯罪など、そもそも客観証拠が残りにくい犯罪も少なくないからです。
犯行現場の周囲に監視カメラなどの物証が見当たらなかったとしても、人証をきっかけに物証にたどり着くこともあります。
たとえば、窃盗したものを持って走り去る姿を見た人物がいたしたことから犯人の足取りを掴むことができ、離れた場所にあった監視カメラに映っていたというようなケースです。
証拠がないと思った事件で警察が動いた場合に起こりうる4つのこと
何らかの事件を起こしてしまった場合、証拠が見つからないだろうと思っても安心してはいけません。
ここまで見てきたように、証拠がなくても警察は動きます。
警察が動くとどのようなことが起こるのか、以下で解説します。
1.捜査される
捜査とは、捜査機関が犯罪が起こったと考えられる際に、犯人を発見したり、証拠を収集・保全したりする手続きのことです。
警察は事件を捜査した後、ほとんどの事件を検察に送致します。検察は、送致された事件を起訴するかどうかを決めます。
つまり、犯人を刑事裁判にかけるかどうかを決めるのです。
そのため警察は、検察に報告しやすいように捜査をおこないます。
主に、目撃者がいないかや監視カメラの映像に怪しい人物が映っていないか、現場に証拠が残っていないかなどを調べます。
また、近隣への聞き込みも警察がおこなう主な捜査方法です。
2.逮捕される
被疑者が特定され、被疑者に逮捕の理由及び必要性が認められる場合には、警察は被疑者を逮捕します。
逮捕とは、被疑者の身柄を拘束することです。
逮捕せずに警察署などへの出頭を求めて捜査する「任意捜査」がおこなわれる場合もあります。
逮捕するには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。
- 逃亡のおそれがある
- 証拠隠滅のおそれがある
つまり、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕はされず、任意捜査が進められます。
逮捕されると、警察署の留置施設に留置されます。
逮捕されたあとは48時間以内に検察官へ送致されるかどうかが決まります。
送致されず、そのまま釈放されるのは、次のようなケースです。
- 犯罪をしていないことが明らかであるとき
- 軽微な罪であるとき
- 被害が小さく、すでに被害が回復しているとき
3.送検される
逮捕されてから48時間以内に、事件が検察庁に送られるかどうかが決まります。
検察庁に事件が送られることを「送致」といいます。
なお、送致されてから24時間以内(ただし逮捕後72時間を超えない)に検察官が被疑者を勾留するか検討し、検察官が勾留の理由及び必要性ありと判断した場合には裁判官に勾留請求をします。
裁判官がこれを認めると、被疑者は引き続き身柄拘束をされることになります。
勾留期間は基本的には10日以内とされていますが、やむを得ない事由(防犯カメラのデータが膨大であり解析に時間がかかる等)がある場合には、検察官から裁判官へ請求することで最長20日まで延長されます。
逮捕のときと同様、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には勾留され得ます。
勾留の理由並びに必要性及び勾留延長のやむを得ない事由がなければ釈放されます。
勾留の途中で交流の理由・必要性が変化した場合に、勾留が取り消された場合も同様に釈放されます。
例えば、逮捕されたとしてもその後身元引受人となる家族が監督を誓約して逃亡のおそれが低下したり、被害者と示談が成立して証拠隠滅のおそれが低下したりしたときに勾留が取り消され、釈放されます。
この時に捜査が完了していなければ、在宅(任意)捜査となり、捜査が完了している場合には事件が終了することもあります。
4.微罪処分になる
通常、刑事事件は犯罪が発生したあとに警察が被疑者を捜査し、検察官への送致を経て、検察官が起訴するか不起訴とするかを決めます。
起訴されると裁判がおこなわれて判決にて刑罰が決まるというのが大まかな流れです。
しかし、捜査の間に証拠がまったく見つからなかった場合は、送致されずに微罪処分として処理される可能性が高いでしょう。
微罪処分とは、刑事事件の捜査を警察段階で終える手続きのことです。
微罪処分が決まった時点で警察がその事件の捜査を終了するため、それ以上は捜査や取り調べはおこなわれません。
なかなか証拠が出ない場合は、送致しても起訴される可能性は低く、起訴をしても有罪にすることができません。
そのため、証拠が見つからなければ事件は終わる可能性があるのです。
なお、証拠が見つからない場合以外に、次のような条件に当てはまるときも微罪処分になる可能性があります。
- 加害者が初犯である
- 加害者に保護者などの監督者がいる
- 被害が軽微である
- 被害が弁償されている
- 被害者との示談が済んでいる
- 被害者が処罰を望んでいない
微罪処分になれば前科がつくことはありません。
しかし、被疑者として捜査の対象になった履歴である前歴はつきます。
警察が動くかどうかにかかわらず犯罪をした場合にとるべき3つの対応
もしも犯罪行為をしてしまったら、警察が動いているかどうかにかかわらず加害者がとるべき行動があります。
それぞれの行動について、以下で詳しく解説します。
1.逮捕前なら自首する
証拠を残さずに犯行を終えられたと思っていても、気づいていないだけで監視カメラに写っていたり目撃者がいたりする可能性もあります。
犯人を示す証拠が残っているかもしれない場合は、いっそう逮捕される可能性は高まるでしょう。
そのため、逮捕前の自首を検討してください。
自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、犯人が自発的に警察署などに出頭し、罪を申告することをいいます。
自首した場合、逮捕される可能性は格段に低くなります。
なぜなら、自分から犯罪を行ったという申告をしているため逃亡のおそれがないとみなされるからです。
さらに、反省が見られるとして刑の減軽などの効果が期待できます。
犯人が特定されてしまったあとになって出頭しても、自首は成立しません。
そのため、自首が成立した場合の減軽は受けられません。
しかし、自首が成立しなかったとしても、自発的に出頭して反省しているとみなされることには変わりありません。
少しでも軽い処分で済むよう、どの段階であっても自首することは重要です。
2.被害者がいる場合は示談交渉をする
被害者がいる犯罪を起こしてしまった場合は、いち早く被害者と示談しましょう。
示談が成立し、被害者が加害者に対して処罰を求めていない場合は、不起訴となる可能性が高くなります。
とくに、初犯や悪質性が低い事件である場合は、より不起訴処分となる可能性は高まるでしょう。
日本における刑事裁判では、起訴されると有罪判決が下される割合が99%以上です。
つまり、検察官に起訴されてしまうと、基本的に有罪となるのです。有罪になれば刑罰を受けなければなりません。
前科がつくことで社会生活に不利益が生じることもあるでしょう。
仕事を辞めなければならなくなったり、近隣の方々からの視線に悩まされたりすることになるかもしれません。
示談交渉をおこない、示談を成立させることで不起訴処分を目指すのが賢明でしょう。
3.刑事事件が得意な弁護士に相談する
自首をする際も、示談交渉する際も、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
自首をすると取り調べがおこなわれ、聞かれたことや答えた内容が調書として文書に記録されます。
反省を示すことは重要ですが、一人で取り調べに臨んだ場合、捜査機関の取り調べで暴言があったり、調書の内容と自身が話したことが違っていたりしても、どのように対応したらよいか分からないことも多いです。
そのため弁護士に相談し、どのように取り調べを受ければよいのかアドバイスをもらいましょう。
また、示談交渉は弁護士に依頼するのが一番です。
なぜなら被害者がいる事件の場合、被害者は加害者に会いたいとは思わないからです。
どれだけ心から謝罪をしたいと思っても、相手の不快感や被害意識を強めてしまうと逆効果です。
そのため、示談は代理人として弁護士がおこなうのがベストなのです。
弁護士であれば、豊富な経験から、被害者の心情に寄り添いつつ適切な交渉をしてくれます。
また、弁護士から検察官や裁判官へ働きかけることによって、不起訴処分を獲得したり、有罪となった場合であってもなるべく罪を軽くしたりと、弁護士に依頼するのとしないのとでは、結果は大きく異なるでしょう。
さいごに|刑事事件が得意な弁護士はベンナビ刑事事件で探せる!
警察が動くかどうかは証拠の有無だけで決まるわけではありません。
証拠がない場合でも警察は捜査を開始し、すぐではなくとも逮捕される可能性があります。
少しでも刑罰を軽くするためには、逮捕される前に自首や示談交渉をおこなうことも検討してください。
自首の方法や示談交渉の進め方については、刑事事件に強い弁護士への相談が有効です。
刑事事件における加害者の弁護を得意とする経験豊富な弁護士を見つけたいなら「ベンナビ刑事事件」を活用してください。
「初回無料相談に応じている」、「近くの地域にある」など条件を絞って法律事務所を探すことができます。
刑事事件の加害者弁護においては、特に迅速な対応が大切です。
なるべく早く相談しましょう。

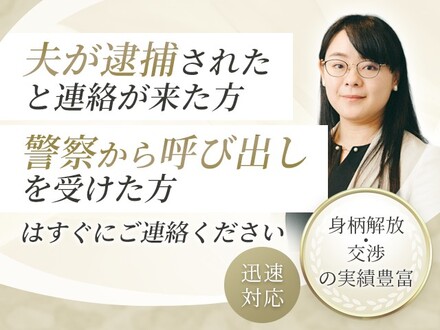
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る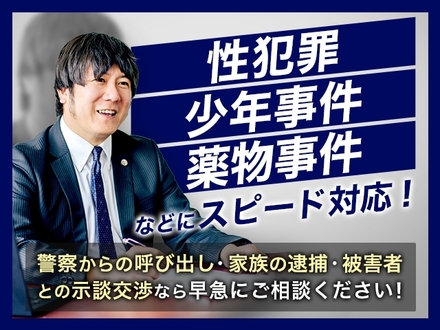
性犯罪/薬物事件/少年事件などに注力!刑事事件はスピード勝負です。逮捕直後および警察から連絡が来た時点からご相談ください。依頼者様がご納得できるよう、丁寧かつわかりやすい説明を心がけています。
事務所詳細を見る
検事の経験を持つ弁護士が窃盗・万引き/少年事件/性犯罪など幅広い刑事事件に対応◆『警察の呼び出しを受けている』『ご家族が逮捕された』はすぐご相談を◆フットワークの軽さを活かした迅速対応【即日接見も◎】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
盗撮の冤罪にあいそうなときでも、対応を間違えると逆に状況が悪化する可能性があります。万が一のときに冷静に対応できるよう、正しい対処法と注意点をおさえ...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
緊急避難とは、刑法で定められた違法性阻却事由の一つです。正当防衛も違法性阻却事由という点では同じですが、緊急避難と正当防衛は成立要件が異なります。具...
-
いじめは犯罪だと聞いたことがあるかもしれません。自分の子どもが逮捕されてしまうのか、犯罪者になってしまうのか、と不安に感じる方もいるでしょう。本記事...
-
「少年センター」とはどのような施設なのか、具体的な活動内容・対象年齢・利用条件などについて解説します。
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
保釈金は問題なく裁判が進めば返金(還付)されるお金ですが、裁判が終わった後に直接手渡されるわけではなく弁護士の口座などを通してあなたに返金されます。...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
本記事では、犯罪歴が日常生活に及ぼす悪影響、犯罪歴がバレるリスク、犯罪歴が残らないようにするためのポイントなどについてわかりやすく解説します。
-
犯罪をしてしまったときはもちろん、罪を犯していなくても指紋が警察のデータベースに登録されるケースがあります。 本記事では、警察に採取・登録された指...
-
実名報道されてしまうことのデメリットは多く、一度報道されてしまうと日常生活に大きな影響を及ぼします。この記事では、実名報道されることによるデメリット...
-
ものを盗む行為は強盗や窃盗にあたり、どちらも逮捕される可能性が高い犯罪です。 例をあげながら強盗と窃盗の内容や法定刑について解説します。また、強盗...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る
























































