承諾殺人とは?構成要件や法定刑、殺人罪になるかどうかなどの違いを解説

近年では、介護疲れが原因となり家族内で無理心中を図る事件も少なくありません。
仮に、殺害された人(被殺者)が生前殺されることを承諾していた場合、犯行に及んだ人物は殺人罪ではなく、承諾殺人罪の容疑で刑事訴追されます。
本記事では、承諾殺人の構成要件や法定刑について、詳しく解説します。
普段聞きなれない「承諾殺人」について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
承諾殺人とは?被害者から同意を得て殺害した場合に成立する犯罪
承諾殺人とは、刑法に規定されている「同意殺人」の一種のことです。
そして、承諾殺人罪は「被害者の承諾を得たうえで、当該人物を殺したとき」に成立します。
まずは、承諾殺人罪の構成要件や法定刑、未遂処罰などの基本的な知識について解説します。
なお、刑法第202条では、前段で「自殺関与罪」、後段で「同意殺人罪」について規定しており、後段の「同意殺人罪」は、加害者の行為類型によって「嘱託殺人罪」「承諾殺人罪」に区分されています。
承諾殺人の構成要件|加害者が申込みをし、被害者の同意を得て殺害すること
承諾殺人罪は、「人をその承諾を得て殺したとき」に成立する犯罪類型のことです。
承諾殺人罪の構成要件としては、以下の4つが挙げられます。
- 承諾:加害者が「殺させてくれ」と申し込みをしたときに被害者本人がこれに同意をすること
- 人を殺す:加害者が被害者を殺害すること
- 因果関係:嘱託または承諾と被害者死亡との間に相当因果関係があること
- 故意:加害者が①~④を認識・認容していること
たとえば、高齢の母親を介護している息子が、母親に「介護生活に疲れたから殺させてくれ」と頼み、息子の心情を理解をしたうえで殺害の申し込みに承諾したケースが挙げられます。
一方、母親が再婚相手の連れ子に対して「お前が死ねば生活が楽になる。自分で死ねないなら殺させてくれ」という言葉を投げかけたあと、思い悩んだ子どもが自殺をしたようなケースでは、母親の言動と子どもの死亡との間の因果関係が認められず、承諾殺人罪は成立しません。
承諾殺人の法定刑|6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮を科される
承諾殺人罪の法定刑は、「6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮」です。
殺人罪とは異なり、承諾殺人罪では、被殺者自身が自分の生命が侵害されることに同意をしています。
そのため、見方を変えれば殺人をした人が罪に問われるのはおかしいと思う方もいるでしょう。
しかし、命が奪われたことに代わりはなく、重い刑事罰が定められているのです。
ただし、承諾殺人の法定刑においても執行猶予が付く可能性はあります。
そのため、執行猶予付きの判決を勝ち取るためには、情状酌量や自首減刑を目指して防御活動をおこなう必要があるでしょう。
未遂罪の有無|承諾殺人は未遂であっても処罰される
承諾殺人罪は未遂犯も処罰されます。
未遂犯が処罰されるのは、「既遂発生の具体的危険性が生じたとき」と理解するのが一般的です。
つまり、「殺人行為に着手して、被害者の生命侵害の具体的危険が発生したとき」に未遂罪が成立すると考えられます。
承諾殺人が成立しない3つのケース|殺人罪になる可能性が高い
承諾殺人は「被殺者から殺害の承諾を得ていること」が要件ですが、このうち「承諾」という点を満たせなければ、殺人罪に問われる可能性があります。
そして、「承諾の有無」は、形式的に判断されるわけではありません。
承諾が被殺者の真意に基づいてなされたものでなければ、承諾があったとは認められないおそれがあるのです。
ここでは、承諾殺人罪が問題になりうる事例において、「承諾が被殺者の真意に基づいたものではない」と判断される可能性が高い3つのケースについて解説します。
1.被害者が十分な精神能力を有していない場合
殺害されることへの承諾が被殺者の真意に基づいたものであるためには、被殺者が死ぬことの意味を理解し得るだけの精神能力を有していること必要です。
そのため、自殺や殺されることの意味を理解できない幼児や、意思能力を欠いた精神障害者などが、形式的には承諾をしたように見える言動をしたとしても、有効な承諾があったとは認められません。
2.暴行や脅迫により任意の同意がおこなわれていない場合
殺害されることについて無理やり承諾させていた場合も、承諾殺人罪ではなく、殺人罪として問われることになります。
たとえば、暴行・脅迫・強制などによって被殺者の意思が抑圧された結果、承諾に至ったとしても、有効な承諾がなされたとは考えにくいでしょう。
3.具体的な死の認識・受容の意思がなかった場合
承諾殺人罪が成立するには、被殺者が承諾をする時点で、具体的な死の認識・受容をしていることが必要です。
たとえば、一時的に仮死状態になるものの蘇生すると勘違いしていた事例や、殺害行為自体に対しては承諾したものの、当該行為の結果自分が死亡するに至るとは思っていなかった事例などでは、有効な承諾があったとは認められません。
4.欺罔により真意に基づく同意がおこなわれていない場合
欺罔によって被殺者に被殺意思を生じさせた場合、有効な承諾がないことを理由に承諾殺人罪が成立しない可能性があります。
たとえば、追死する意思が存在しないのに追死するものと誤信をさせて、毒薬を飲ませて被殺者を中毒死させた偽装心中事件について、最高裁判所は真意に添わない重大な瑕疵ある意思によって承諾行為がなされたと判断し、承諾殺人罪ではなく殺人罪が成立すると判示しました。
そのため、欺罔がなければ承諾しなかったであろうケースでは、有効な承諾はあったとは認められないでしょう。
承諾殺人として逮捕・起訴された事例2選
ここからは、実際に承諾殺人罪で刑事訴追された事案を紹介します。
1.息子の介護に疲れた父親が殺害に至ったケース
本件は、82歳の会社役員が自宅において50歳の長男を殺害した事案です。
事件当日の早朝、被疑者は自宅で長男の頭に袋をかぶせて首を圧迫して殺害をしました。
当初警察は、殺人罪の容疑で捜査を進めていましたが、逮捕後の取り調べのなかで、殺害について長男の承諾があったことが判明します。
息子の介護に疲れた父親が心中しようとしたという経緯がありました。
結果として、本件の被疑者は承諾殺人罪の容疑で送検されました。
2.介護中の父親の承諾を得て殺害に至ったケース
本件は、自宅で介護中の父親(87歳)の同意を得て首を絞めて殺害した息子(58歳)が、承諾殺人罪の容疑で逮捕・起訴された事案です。
息子は強固な殺意を抱いていましたが、犯行当時、重度のうつ病が原因で心神耗弱の状態にあったことが認定されています。
また、本件被告人は自首をし、それ以降の取り調べでは一貫して反省の態度を示していました。
その結果、検察官は懲役2年6ヵ月を求刑しましたが、執行猶予3年の判決が下されました。
承諾殺人と類似する犯罪との違い
ここでは、承諾殺人罪と類似するその他の犯罪類型との違いについて解説します。
1.殺人罪との違い
殺人罪とは、「人を殺したとき」に成立する犯罪類型のことです。
殺人罪の法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」であり、承諾殺人罪の「6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮」に比べると、非常に重い刑罰が定められています。
殺人罪と承諾殺人罪は、「被害者を殺害する」という部分で共通しています。
反面、殺人罪は被害者が自分自身の生命侵害について同意をしていないのに対して、承諾殺人罪では被害者本人が自分が殺されることについて同意をしています。
つまり、「本人の承諾の有無」が殺人罪と承諾殺人罪の違いであり、法定刑に大きな差がある理由だといえるでしょう。
2.嘱託殺人との違い
刑法第202条では、同意殺人罪として「嘱託殺人罪」と「承諾殺人罪」の2類型を定めています。
嘱託殺人罪とは、「人をその嘱託を受けて殺したとき」に成立する犯罪類型のことです。
被殺者本人から殺害の依頼がある点で、承諾殺人罪よりも殺害されることに対して被殺者本人の積極性があると考えられます。
なお、「刑法202条では、嘱託殺人罪・承諾殺人罪の双方に対して同一の法定刑を定めていることを踏まえると、嘱託殺人罪と承諾殺人罪の違いを議論する実益は乏しい」と主張する人も少なくありません。
しかし、実際の刑事手続きや刑事裁判では、どのような経緯で被疑者・被告人が犯行に至ったのか、犯行の動機ややむを得ない事情の有無などの諸般の事情を総合的に考慮した結果、刑事処分や判決の内容が決定されます。
つまり、「被殺者側から殺害についての働きかけがあったのかどうか」という点は、刑事処分や判決内容の軽重を決定する際に重要な要素になるのです。
その意味では、承諾殺人罪よりも嘱託殺人罪のほうが執行猶予付き判決のような軽い司法判断を獲得しやすい犯罪類型だといえるでしょう。
3.自殺教唆・自殺幇助(自殺関与罪)との違い
刑法第202条では、同意殺人罪と並んで自殺関与罪についての規定も置いています。
自殺関与罪とは、「人を教唆しもしくは幇助して自殺させたとき」に成立する犯罪類型のことです。
自殺関与罪の法定刑は、同意殺人罪と同じく「6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮」と定められています。
教唆とは、自殺を実行する決意をしていない人に決断をさせるために唆す行為のことです。
また、幇助はすでに自殺を実行する決意をしている人に、その実行を容易にするための手助けをする行為を指します。
自殺関与罪と同意殺人罪は、自殺者・被殺者の意思に合致した生命侵害に対して教唆的・幇助的関与をしたのか、共同正犯的関与をしたのか、という点に違いがあります。
ただし、たとえば毒入りの水が入ったコップを自殺者・被殺者の口に運んでこれを飲ませて死に至らしめたケースのように、自殺関与罪と同意殺人罪の区別が難しい事例も少なくありません。
とはいえ、両罪の間に法定刑の違いはないため、この2つの犯罪を厳密に区別する実益は乏しいといえるでしょう。
なお、実務的には、実際に「殺害」行為に及んだ承諾殺人罪・嘱託殺人罪に比べて、「自殺行為への関与」に過ぎない自殺関与罪で刑事訴追されたほうが、軽い刑事処分・判決を獲得しやすいと考えられています。
承諾殺人で家族が逮捕されたときに弁護士に相談するメリット
身内が家族を殺害して逮捕された場合、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談してください。
刑事事件を得意とする弁護士の力を借りることで、以下のようなメリットを得られます。
- 事案の状況に即した証拠をそろえて「被殺者の真意に基づく承諾があった」ことを証明してくれる
- 身柄拘束中の被疑者とこまめに接見機会を設けて捜査の進捗状況を踏まえたアドバイスを提供してくれる
- 少しでも軽い刑事処分(起訴猶予、執行猶予付き判決)獲得を目指してくれる
- 可能な限り逮捕・勾留を阻止して在宅事件扱いを目指してくれる
- 前科によるデメリットを軽減しながら社会復帰するためのポイントについてアドバイスをしてくれる
- 実名報道が原因でさまざまなトラブルが生じても粛々と対応してくれる
当番弁護士や国選弁護人に相談・依頼をしても一定の効果を得られますが、刑事事件の実績がある私選弁護人に相談・依頼をしたほうが効果的な防御活動を期待できるでしょう。
さいごに|承諾殺人は被害者から同意を得て殺害した場合に成立する
承諾殺人罪は、被殺者の承諾があるために殺人罪より刑罰が軽減されていますが、人の死亡結果がある以上、重い犯罪類型に位置づけられています。
承諾殺人罪の容疑で刑事訴追されると、逮捕・勾留によって数週間身柄拘束されたり、有罪判決が下されて実刑判決が下されて前科がついたりするなどのリスクに晒されます。
また、事案の内容・経緯次第では、殺人罪として非常に重い刑事罰を科されかねません。
これらのデメリット・リスクを回避・軽減するには、早期に刑事事件を得意とする弁護士に相談し、適切な防御活動を展開してもらうべきでしょう。
ベンナビ刑事事件では、承諾殺人罪などの受任経験がある弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から希望に合致する専門家を検索できるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。

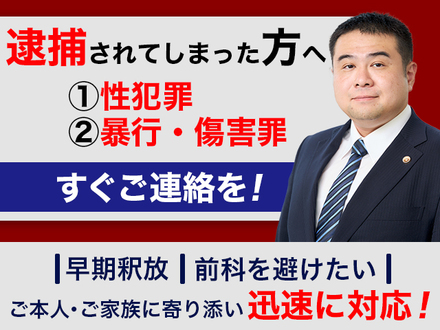
【性犯罪/暴行・傷害罪】当事務所は、原則として、都心での性犯罪および暴行・傷害罪のみ対応し、これらの刑事事件の不起訴処分を目指す事務所です。【渋谷駅徒歩5分】
事務所詳細を見る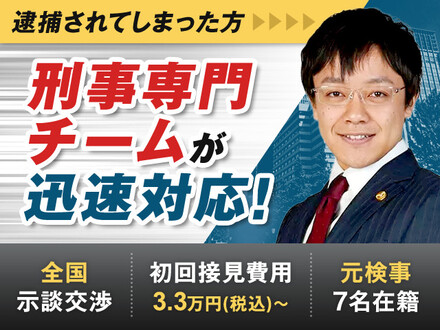
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る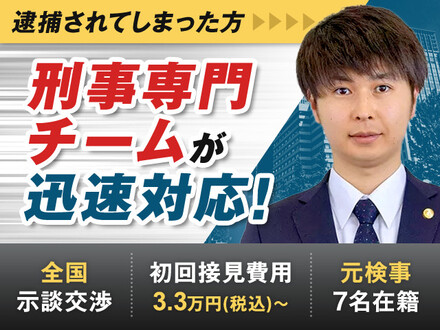
【町田駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
本記事では執行猶予期間中の方に向けて、執行猶予の取り消しについての定義・意味、執行猶予が取り消しになる2つのパターン、再犯をして執行猶予が取り消しに...
-
本記事では、心神喪失状態で起こした事件について、なぜ無罪になるのかについて詳しく解説します。 また、心神喪失で無罪になったあとの手続きの流れや、心...
-
痴漢・万引き・盗撮・横領など、やってもいないのに犯人だと疑われてしまうケースは少なからず存在します。 どうすれば疑いを晴らせるのか悩んでいる方もい...
-
家宅捜索によって証拠品が押収されると逮捕・取調べ・捜査を経て懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。この記事では①家宅捜索が行われる時間②どこまで...
-
盗撮は現行犯だけでなく後日逮捕されるケースも少なくありません。防犯カメラの普及やデジタル証拠の残存性から「時効まで逃げ切る」ことは極めて困難です。本...
-
本記事では、どのようなときに緊急逮捕されるのか、緊急逮捕をされるとどうなるのかなどについて、通常逮捕や現行犯逮捕との比較を交えながら解説していきます...
-
刑法第39条には『刑事責任能力のない人は処罰の対象外とする、または、処罰を軽減する』という記述がされています。刑法第39条とは具体的にどういうものな...
-
今回は、刑罰のなかでも禁錮刑について、どのような刑なのかや、自宅での受刑はあるのかなどを解説します。「禁錮刑と懲役刑の違いは?」「どちらがつらい?」...
-
詐欺未遂罪とは、詐欺罪の未遂犯のことです。本記事では、詐欺未遂罪に該当するかもしれない行為に手を染めてしまった人のために、詐欺未遂罪の構成要件、刑事...
-
この記事では、現行犯逮捕についてくわしく解説しています。現行犯逮捕とは「目の前で犯行に及んでいる犯人を逮捕すること」です。現行犯逮捕できる要件や、一...
-
公訴時効とは、刑事上の時効の概念で、犯罪が終わってから一定期間が過ぎると、公訴の提起(起訴)ができなくなることです。
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る


























































