上告と控訴の違いとは?刑事事件における不服申立ての仕組みや手続きを解説

- 「控訴と上告って何が違うの?」
- 「上告で必要な手続きは?」
刑事裁判の結果について納得がいかず、控訴・上告を検討している方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
控訴と上告は、どちらも判決への不服申立てという点では同じですが、必要な手続きや要件が異なります。
本記事では、刑事裁判における上告と控訴の違い、上訴を検討しているときに刑事裁判を得意とする弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
上告と控訴の違い|どの判決に対する不服申立てなのかが異なる
上告と控訴は、どちらも判決に対する不服申立ての手続きを指します。
まずは、刑事訴訟における控訴・上告について、それぞれの内容を見ていきましょう。
控訴とは|第一審判決に対する不服申立てのこと
控訴とは、第一審の裁判所が下した判決に対しておこなう不服申立てのことです。
刑事裁判では、地方裁判所または簡易裁判所が第一審裁判所の役割を担います。
そのため、刑事裁判における控訴は、第一審である地方裁判所または簡易裁判所が下した判決に対する不服申立てを意味します。
なお、控訴の裁判権を有するのは高等裁判所です。
高等裁判所の管轄は、第一審裁判所の所在地によって決まるので、「裁判所の管轄区域|裁判所HP」で確認をしておきましょう。
上告とは|第二審判決に対する不服申立てのこと
上告とは、高等裁判所の判決に対しておこなう不服申立てのことです。
一般的な裁判においては、控訴後に高等裁判所で裁判をおこない、それでも納得がいかないときに上告をすることになります。
なお、上告には以下のような条件が設けられており、控訴に比べると申立てをできる事項が大幅に制限されています。
第三章 上告
第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
上告と控訴の違いを詳しく理解するための3つの基礎知識
上告と控訴の違いを理解するには、日本の刑事裁判の仕組みを知っておく必要があります。
ここでは、日本の刑事裁判の仕組みについて重要な3つのポイントを解説します。
1.日本の裁判では三審制の仕組みがとられている
日本の刑事裁判では「三審制」の審級制度が採用されています。
三審制とは、「公正かつ真実に合致した裁判を実現するために、当事者が希望した場合には、原則として3回まで裁判所で反復審理を受けることができる」という裁判制度のことです。
なお、内乱罪、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪が公訴事実になっている刑事裁判については、例外的に二審制が採用されています。
2.控訴と上告をまとめて「上訴」と呼ぶこともある
上訴とは、下級裁判所の裁判内容に不満があると考える当事者が、確定前に上級裁判所に対して不服を申し立てることです。
上訴のうち、第一審裁判所の判決に不満があり、第二審裁判所に不服申立てをするケースが「控訴」、第二審の判決に不満があり第三審裁判所に不服申立てをするパターンが「上告」と分類されます。
つまり、控訴・上告は上訴の一種であるといえるでしょう。
なお、上訴には、控訴・上告のほかに「抗告」があります。
抗告は、裁判所がした「決定」に対する不服申立てのことです。
3.第一審、第二審(控訴審)、第三審(上告審)の順におこなわれる
原則として三審制が採用されている日本の刑事裁判では、第一審、第二審(控訴審)、第三審(上告審)の順番で審理がおこなわれます。
第一審裁判所の判決に不服があるときには、第二審裁判所に控訴できます。
そして、第二審裁判所の判決に不服があれば、さらに第三審裁判所に上告するという流れです。
そもそも、個々の裁判所はそれぞれ独立して裁判権を有するため、下級裁判所が裁判を進めるときに上級裁判所の指揮監督を受けることはありません。
ただし、下級裁判所の判決内容に不服があるとして控訴・上告がおこなわれたときには、上級裁判所が下級裁判所の判決を審査します。
そして、控訴・上告がされた事件については、上級裁判所の判断が下級裁判所の判断より優先されることになります。
上告と控訴の違い|要件や手続きなどを表で比較してみよう
ここからは、上告と控訴の違いについて詳しく解説します。
以下の表は、上告と控訴の違いをまとめたものです。
【控訴と上告の主な違い】
| 項目 | 控訴 | 上告 |
| 要件 |
・絶対的控訴理由 ・相対的控訴理由 |
・憲法違反 ・憲法解釈の誤り ・過去の判例との判断が違う など |
| 必要な手続き | 1.控訴の申立て
2.控訴趣意書などの提出 3.審理 4.判決 |
1.上告の申立て
2.上告趣意書などの提出 3.審理 4.判決 |
| 審査する内容 | 控訴申立書・控訴趣意書 | 上告申立書・上告趣意書 |
| 判決の種類 | ・控訴棄却判決
・控訴棄却決定 ・破棄自判 ・破棄差戻し ・破棄移送 |
・上告棄却判決
・上告棄却決定 ・破棄自判 ・破棄差戻し ・破棄移送 |
項目ごとに、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
1.要件の違い
控訴と上告それぞれについて審理できる事項・要件は厳格に定められています。
控訴理由
まず、刑事裁判の控訴理由は「絶対的控訴理由」「相対的控訴理由」に区別され、それぞれ以下のように定められています。
【刑事裁判の絶対的控訴理由】
| 条文 | 項目 |
| 刑事訴訟法第377条 | ・法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと
・法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと ・審判の公開に関する規定に違反したこと |
| 刑事訴訟法第378条 | ・不法に管轄、または、管轄違いを認めたこと
・不法に公訴を受理し、または、これを棄却したこと ・審判の請求を受けた事件について判決をせず、または、審判の請求を受けない事件について判決をしたこと ・判決に理由を附せず、または、理由に食い違いがあること |
【刑事裁判の相対的控訴理由】
| 条文 | 項目 |
| 刑事訴訟法第379条 | 刑事訴訟法第378条、第379条の場合を除いて、訴訟手続きに法令違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであること |
| 刑事訴訟法第380条 | 法令の適用に誤りがあってその誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであること |
| 刑事訴訟法第381条 | 刑の量定が不当であること |
| 刑事訴訟法第382条 | 事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであること |
| 刑事訴訟法第383条 | ・再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること
・判決があった後に刑の廃止もしくは変更または大赦があったこと |
上告理由
一方で、刑事裁判における上告理由は以下のように定められています。
控訴理由と比較すると、相当限定されているといえるでしょう。
- 憲法違反があること、または、憲法の解釈に誤りがあること
- 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと
- 最高裁判所の判例がない場合に、大審院もしくは上告裁判所たる高等裁判所の判例、または、現行の刑事訴訟法施行後の控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと
なお、最高裁判所は上記に当てはまらない場合でも、法令解釈に関する重要な事項を含む事件については、判決確定前に限り自らが上告審としてその事件を受理できます。
2.必要な手続きの違い
次に、控訴と上告の手続きについて解説します。
控訴の手続き
控訴をするには、第一審裁判所を管轄する高等裁判所に申立て手続きをする必要があります。
また、控訴の申立て手続きは、第一審判決言い渡し日の翌日から14日以内におこなわなければなりません。
申立て手続きの際は、控訴申立書を作成して第一審裁判所に提出しましょう。
控訴申立書が受理されると、控訴裁判所側から、控訴の理由などを簡潔に記載した「控訴趣意書」の提出を求められます。
控訴趣意書の提出期限は事案によって異なりますが、21日~1ヵ月程度の日数が指定されることが多いです。
なお、控訴趣意書を提出する際には、必要な証拠等を提出する必要があります。
控訴が認められると審判の日程が通達されます。
控訴審の公判期日の回数・期間は事案によって異なりますが、控訴審は控訴趣意書を中心に書面審理をするだけなので、審理自体は1回で終わることが多いです。
上告の手続き
控訴審の判決内容に不満がある場合には、最高裁判所に上告をすることが可能です。
上告の申立ては、控訴審判決言い渡し日の翌日から14日以内に、上告申立書を最高裁判所に提出することでおこなえます。
最高裁判所からの求めに応じて、上告趣意書やその他の書類も提出しましょう。
なお、上告審は「法律審」なので、事実認定に関する手続きは全て省略されます。
ただし、あくまでも裁判であることから、公判期日自体は設けられています。
また、上告審では公判期日に被告人を召喚することを要しないとされています。
さらに、上告趣意書やその他の書類によって上告申立ての理由がないことが明らかだと認められるときには、上告棄却の判決を下される可能性もあるでしょう。
上告の申立てがあってから最高裁判所に事件が係属するまでには約1ヵ月、最高裁判所に係属してから判決・決定が下されるまでには約3ヵ月~4ヵ月程度の期間がかかります。
そして、上告審の裁判における法律問題などについて審理が終了すると、判決が下されます。
さらに、上告審の判決の宣告があった日から訂正の申立てがなく10日が経過したとき、または、訂正の申立てがおこなわれた場合において、訂正の判決もしくは訂正の申立てを棄却する決定があったときに、上告審の判決内容が確定します。
3.審査する内容の違い
控訴審では、控訴申立書・控訴趣意書、上告審では上告申立書・上告趣意書について、それぞれ審査がおこなわれます。
ただし、控訴趣意書に記載されていない事項についても、控訴理由に該当する事由に関しては、控訴裁判所による職権調査が認められています。
4.判決の種類の違い
控訴審と上告審で下される判決の種類は、以下のとおりです。
- 控訴棄却判決:控訴理由が認められることなく、第一審判決の内容がそのまま維持される。
- 控訴棄却決定:形式的不備などを理由に、実質的な審理なく、第一審判決の内容がそのまま維持される。
- 破棄自判:第一審の判決の内容を破棄して、控訴裁判所が自ら判決を下す。
- 破棄差戻し:第一審の判決内容を破棄して、第一審裁判所に差し戻す。
- 破棄移送:第一審の判決内容を破棄して、正しい管轄を有する裁判所に差し戻す。
- 上告棄却判決:上告理由が認められることなく、控訴審判決の内容がそのまま維持される。
- 上告棄却決定:形式的不備などを理由に、控訴審判決の内容がそのまま維持される。
- 破棄自判:控訴審判決を破棄して、最高裁判所が自ら判決を下す。
- 破棄差戻し:控訴審判決を破棄して、第一審または控訴審に差し戻す。
- 破棄移送:控訴審判決を破棄して、正しい管轄を有する第一審または控訴審裁判所に差し戻す。
それぞれ名称は異なりますが、実質的な判決内容として大きく違いはないと思ってよいでしょう。
上告と控訴に関するよくある質問
さいごに、上告や控訴についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
Q.上訴によって刑罰が重くなることはあるか?
被告人が上訴した場合、上訴によって刑罰が重くなることはありません。
なぜなら、刑事裁判では「不利益変更禁止の原則」が定められているからです。
不利益変更の禁止の原則とは、刑事裁判において被告人が控訴をした場合、原判決よりも被告人にとって不利な判決・重い刑事罰を科すことはできないというルールのことです。
原判決よりも重い判決になっているかどうかについては、上級審と下級審の判決を比べて実質的に被告人にとって不利益になっているかを、刑の種類、執行猶予の有無などの諸事情から総合的に判断するものとされています。
たとえば、「原判決が懲役2年、控訴審判決が懲役3年、執行猶予4年」のケースでは、懲役部分は控訴審判決のほうが重くなっていますが、執行猶予が付されている点で控訴審判決のほうが被告人にとって有利になっているといえるでしょう。
なお、不利益変更禁止の原則が適用されるのは、被告人だけが上訴をしたときだけです。
検察官が上訴をした場合には、上級審で重い判決が下されるリスクがあるので注意しましょう。
Q.控訴について民事裁判と刑事裁判で違いはあるか?
民事裁判と刑事裁判は、どちらも三審制が採用されている点では共通していますが、各裁判制度における控訴の方法・内容については以下のような違いがあります。
| 項目 | 民事裁判 | 刑事裁判 |
| 控訴理由 | 制限なし | 制限あり |
| 控訴審の裁判所 | 高等裁判所か地方裁判所 | 高等裁判所 |
| 控訴期間 | 判決書等の送達日の翌日から2週間 | 判決言い渡し日の翌日から14日 |
| 付帯控訴・和解 | あり | なし |
| 弁論ができる人 | 紛争当事者及び弁護士 | 検察官と弁護人だけ |
Q.上告や控訴について弁護士に相談したほうがいいのか?
刑事裁判で控訴や上告を考えているときには、刑事裁判実務に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。
第一審判決の内容に不満があるときに別の弁護士に意見を求めることで、以下のメリットを得られるでしょう。
- 事案の状況を総合的に考慮したうえで、そもそも上訴をするべきか否かを判断してくれる
- 第一審判決の内容を覆すための防御方針を構築してくれたり新しい証拠の収集に尽力してくれる
- 14日間という限られた期間内に第一審判決の内容や証拠類を精査してくれる
第一審裁判が終わったあと、上訴するタイミングで弁護士を変更するケースは少なくありません。
少しでも有利な判決を獲得し、今後の社会生活への支障を軽減するために、速やかに弁護士の力を借りてください。
さいごに|上訴を検討中なら今すぐ弁護士へ相談を!
刑事裁判にかけられたとき、全ての被告人には、3回まで裁判所の審理を受ける権利が与えられています。
そのため、第一審判決の内容に不満があったとしても、控訴審・上告審で争う余地は残されているといえるでしょう。
ただし、控訴審・上告審で第一審よりも有利な判決を獲得するには、限られた上訴期間のうちに、今後の方針を抜本的に見直さなければいけません。
また、刑事裁判の控訴審・上告審ではさまざまな制約・ルールが設けられているので、第一審よりも厳しい防御活動を強いられる可能性が高い点にも注意が必要です。
これらを踏まえると、上訴を検討している場合は速やかに弁護士へ相談し、適切に対処してもらう必要があるでしょう。
ベンナビ刑事事件では、刑事裁判に力を入れている弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から、24時間無料で専門家を検索できるので、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。

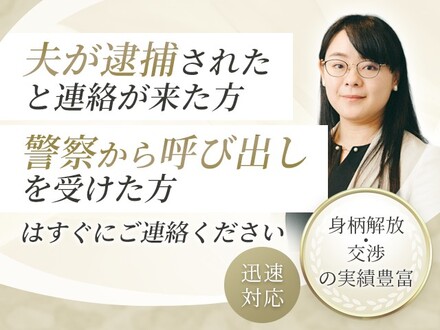
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る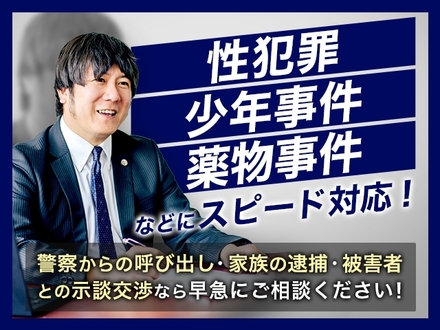
性犯罪/薬物事件/少年事件などに注力!刑事事件はスピード勝負です。逮捕直後および警察から連絡が来た時点からご相談ください。依頼者様がご納得できるよう、丁寧かつわかりやすい説明を心がけています。
事務所詳細を見る
検事の経験を持つ弁護士が窃盗・万引き/少年事件/性犯罪など幅広い刑事事件に対応◆『警察の呼び出しを受けている』『ご家族が逮捕された』はすぐご相談を◆フットワークの軽さを活かした迅速対応【即日接見も◎】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
刑事事件における時効とは、犯罪から一定期間経過すると加害者が起訴されなくなる制度です。罪を逃れられる制度がなぜ存在しているのか、疑問に感じている人も...
-
罪を犯してしまったものの、証拠がないから大丈夫だろうと安心している方もいるかもしれません。本記事では、警察がどのような状況で動くのか、証拠の種類や重...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
任意同行(にんいどうこう)とは、犯罪容疑のある人物が警察などの捜査期間から任意的に捜査に同行してもらうことです。
-
略式命令は簡易な刑事裁判手続です。100万円以下の罰金刑である犯罪で、被疑者の同意がある場合に選択されます。この記事では略式命令の概要や、略式命令に...
-
自分が逮捕されるかもしれない、あるいは家族や友人が逮捕されてしまったというとき、相談の時間や経済的な余裕がない場合は、まずは無料のメール相談を活用す...
-
正当な理由なく他人の建物に侵入すると建造物侵入罪にあたります。住居侵入罪との違い、構成要件、「侵入」や「正当な理由」の定義、刑罰、逮捕後の流れ、弁護...
-
本記事では告発とは何かや、告発が必ずしも受理されるとは限らない理由、告発と告訴・被害届や内部告発との違い、告発された場合に起こることを解説します。
-
どのような行為が強制執行妨害罪に該当するのか、もしも強制執行妨害罪にあたりそうな行為をしてしまったらどんな刑罰が科せられるのかなど、強制執行妨害罪に...
-
事件を起こし警察に検挙・逮捕された場合は、不起訴処分の獲得を目指すのが一般的です。本記事では、不起訴処分とは何かや無罪との違い、不起訴処分を獲得する...
-
本記事では、どのようなときに緊急逮捕されるのか、緊急逮捕をされるとどうなるのかなどについて、通常逮捕や現行犯逮捕との比較を交えながら解説していきます...
-
どのようなときに後日逮捕されるのでしょうか?どのくらいの確率で警察が犯行に気付き逮捕しに来るのでしょうか?この記事では、後日逮捕の概要をお伝えしたう...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る


























































