鑑別所とは?少年院との違い・収容の流れ・送致を回避する方法を解説

鑑別所(かんべつしょ)とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、罪を犯した未成年の少年を一時的に収容し、少年審判での処分を決定するための資料を集めたり、調査をおこなったりする場所です。
具体的には、事件を起こした動機や少年の性格、更生のするために必要な支援などについて、医学・心理学・社会学・教育学・人間科学などの専門的な観点から観察・調査をおこないます。
少年院について知っている方は多いと思いますが、少年鑑別所の存在については、あまり知られていないかもしれません。
本記事では、少年鑑別所とはどのような施設なのか、少年院との違い、少年鑑別所の役割や収容された少年がそこでどのような生活を送るのか、そして最終的に少年審判でどのような処分が下されるのかについて解説します。
お子さんが逮捕された方は弁護士に依頼しましょう
お子さんが捕まった後にすぐに面会できるのは弁護士だけです。
弁護士に依頼することでお子さんの現状を把握できます。
また、弁護士ならば、土日祝日でも制限なく面会できたり、示談交渉して減刑されるように尽力してくれます。
当サイト「ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)」は下記の特徴をもつ、刑事問題に特化した弁護士相談のポータルサイトです。
- 刑事問題を得意とする経験豊富な弁護士を検索可能
- 24時間対応の法律事務所も掲載
まずは下記からお近くの弁護士を探して相談してみてください。
少年鑑別所とは?
少年鑑別所とは、法務省が管轄する「少年鑑別所法」に基づいて設置された施設で、罪を犯した少年に対する処分を決定するための調査をおこなう場所です。
全国に52ヵ所設置されており、少年の精神面や生活環境などについて、専門的な観点から調査しています。
少年鑑別所の役割
少年鑑別所には、大きく分けて以下の3つの役割があります。
- 専門的な知識や技術に基づいて「鑑別」を実施すること
- 収容された少年の特性に応じた「観護措置」をおこなうこと
- 地域社会における非行や犯罪の防止に関する支援をおこなうこと
具体的には、収容された少年に対して心理検査や面接などを通じた鑑別をおこなって、それぞれに応じた観護措置や育成支援を提供します。
また、少年の非行の背景にある家庭環境や教育上の問題についても、専門家が関与するかたちで相談対応やカウンセリングなどの援助を実施しています。
少年鑑別所に入る理由
少年が鑑別所に入る主な理由は、後におこなわれる「少年審判」に必要な資料を作成するためです。
家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は鑑別所に収容され、そこでの生活や行動が観察されます。
また、専門のスタッフによる面接や心理テストを通じて、非行の原因や更生に必要な支援内容などを分析し、どのような処分が適切なのかを判断します。
これらの調査結果と意見は「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に提出され、最終的な処分を決定するための重要な判断材料となるのです。
少年鑑別所の収容期間
少年鑑別所に収容される際には、家庭裁判所によって「観護措置」という手続きが取られます。
観護措置とは、原則として少年を鑑別所に送致し、少年審判に必要な調査をおこなうための措置です。
観護措置による収容期間は、原則として最大2週間と定められています。
ただし、1回に限り延長が可能で、その場合は最長で4週間まで収容することができます。
実務上は、この更新がおこなわれることが多く、実質的には4週間が一般的な収容期間です。
また、一定の事情がある場合には、さらに2回までの「特別更新」が認められています。
特別更新が適用される条件は、以下のようなケースです。
- 少年が死刑、懲役または禁錮に当たる罪を犯したとされる場合
- 非行事実の認定にあたり、証人尋問、精神鑑定、検証などが必要であると判断された場合
- 少年を引き続き収容しなければ、審判手続きに著しい支障が生じるおそれがあると認められる場合
このような事情が認められると、観護措置の期間がさらに延長されることがあるでしょう。
少年鑑別所と少年院との違い
少年鑑別所とよく似た言葉に「少年院」があります。
どちらも少年を収容する施設という点では共通していますが、両者はまったく異なる目的を持つ施設です。
少年鑑別所とは、前述のとおり、少年審判で処分を決定する前に、少年の性格や非行の背景を調査するための施設です。
少年の処分はまだ決定しておらず、あくまでも調査と収容中に健全な育成を支援することが目的です。
そのため、少年は比較的自由な環境で過ごすことができます。
一方、少年院は、少年審判により「矯正教育が必要」と判断された場合に、少年を収容する施設です。
少年審判で少年院送致が決定されると、少年は少年院で一定期間生活し、社会復帰を目指して矯正教育を受けることになります。
このように、少年鑑別所は「調査のための施設」であり、少年院は「矯正教育をおこなう施設」であるという明確な違いがあるのです。
何をしたら鑑別所に収容されるのか?入る基準
少年鑑別所に収容されるのは、家庭裁判所が「観護措置」を決定した場合です。
実務上では、以下のような条件のいずれかに該当する場合、観護措置が決定され、鑑別所への収容がおこなわれる可能性があります。
- 少年が非行を犯したと疑うに足りる相当な理由があること
- 少年審判をおこなう必要があると判断されること
- 非行の程度が深刻であること
- 逃亡や証拠隠蔽のおそれがあること
- 少年の身に危険があり、一時的な保護する必要があること
- 精神的または発達上の問題があり、専門的な調査が必要とされること など
これらの事情のいずれかに当てはまると判断された場合、家庭裁判所は観護措置を決定し、少年は少年鑑別所に収容されることになります。
なお、観護措置については、少年法第17条で定められています。
少年鑑別所に収容されるまでの流れ
少年が逮捕されてから少年鑑別所に収容されるまでの流れは、以下のとおりです。

1.逮捕・検察に送致
14歳以上の少年が罪を犯すと、逮捕されることがあります。
逮捕後は、48時間以内に警察から検察へ身柄が送致されます。
その後、検察官による取調べがおこなわれます。
検察官は取調べの結果を踏まえ、さらに24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断するのです。
2.勾留に代わる観護処置
取調べの結果、身柄の拘束が必要と判断された場合には、勾留がおこなわれます。
勾留期間は原則10日間ですが、延長が認められた場合には最長20日間まで延長されることがあります。
ただし、少年事件の場合には、やむを得ない事情がなければ勾留は認められないとされています。そのため、実際に勾留がおこなわれるのは、鑑別所の収容能力に問題があるなど、特別な事情がある場合に限られることが多いです。
勾留に代わる措置として観護措置が取られた場合には、少年は少年鑑別所に10日間収容されることになります。
3.家庭裁判所に送致
勾留、または勾留に代わる観護措置の後、少年事件は家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、観護措置が必要かどうかを判断します。
観護措置が必要と判断された場合、少年は審判までの間、少年鑑別所に収容されることになります。
4.鑑別所に収容または在宅観護
裁判官との面接の結果、観護措置が必要と判断された場合、少年は少年鑑別所に収容されます。
前述のとおり、収容期間は原則として2週間ですが、継続の必要があると判断された場合には、1回に限り更新が可能です。
多くの場合、この更新がおこなわれるため、実質的には4週間の収容となるケースが一般的です。
さらに、事件の内容や進行状況によっては、「特別更新」により、最大8週間まで観護措置が延長されることもあります。
一方で、裁判官の判断によっては、少年を鑑別所に収容せず、在宅のまま家庭裁判所の調査官による指導・観護を受けるケースもあります。
5.少年審判
観護措置、または観護の後、家庭裁判所が少年審判の開始を決定すると、少年審判がおこなわれることになります。
これは、成人における「裁判」に相当し、少年に対する処分を決定するための手続きです。
成人の裁判は原則として公開でおこなわれますが、少年審判は少年のプライバシー保護の観点から、原則非公開で実施されます。
審判の結果として下される処分には、以下のような種類があります。
- 保護処分(保護観察、少年院送致)
- 検察官送致(逆送)
- 不処分決定
また、直ちに処分を決めることが困難な場合には、試験観察という中間的な措置が取られることもあります。
これは、一定期間少年を自宅に帰宅させて、その生活状況などを観察したうえで、最終的な処分を判断するための制度です。
少年鑑別所での生活
少年鑑別所に収容された少年は、どのような生活を送ることになるのでしょうか。
ここでは、少年鑑別所での一日の過ごし方や、面会のルールについて詳しく見ていきます。
少年鑑別所での過ごし方
少年鑑別所は、あくまでも少年審判の要否を判断するための鑑別をおこなう施設であり、少年院のように厳しい指導がおこなわれる場所ではありません。
そのため、基本的には、定められたスケジュールに沿った規則正しい生活を送ることになります。
一日の基本的な流れは、以下のとおりです。
7:00 起床・洗面
7:30 朝食・点呼
9:00 運動
10:00 面接・心理検査
12:00 昼食
13:00 学習支援・講和
14:30 面会
15:30 診察・入浴
17:00 夕食・点呼
18:00 日記記入・自由時間
21:00 就寝
引用元:少年鑑別所のしおり
収容中に、鑑別技官による面接や、集団・個別の心理検査、知能テストなどを受けながら、読書や学習に取り組んで過ごすことになります。
また、学校に通っている少年の場合は、授業に遅れないように、教科書や問題集を使って自習する時間も設けられています。
少年鑑別所での面会
少年が少年鑑別所に収容されている場合でも、一定の条件のもとで面会は認められています。
ただし、面会が許されるのは、両親・兄弟姉妹・祖父母などの三親等以内の親族や、在学中の学校の教師、弁護士などの付添人に限られます。
そのため、交際相手や友人など、親族ではない人物については、面会が認められないことがあります。
また、面会は、鑑別所の開所時間内である平日の日中に限られ、1回あたりの面会時間はおおむね15分程度と定められています。
ただし、弁護士などの付添人については、鑑別所の閉所時間であっても、事前に申し出ることで面会が認められることがあります。
なお、面会するだけではなく、差し入れも可能となっています。
現金や下着、靴下などの衣類、書類、手紙などを届けられるでしょう。
鑑別所送致(観護措置)になるのを回避する方法
観護措置は、「審判をおこなうために必要があるとき」に限って取られるものです。
具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。
- 少年が非行を犯したと疑うに足りる事情があること
- 審判をおこなう蓋然性があること
- 観護措置の必要性があること
このうち、観護処置の必要性とは、以下のいずれかに該当することを指します。
- 身体拘束の必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれがある、または住所不定の場合)
- 緊急保護の必要性(自殺や自傷行為のおそれがある場合)
- 心身鑑別の必要性(社会から一時的に隔離して、継続的な行動観察や心理的鑑別をおこなう必要がある場合)
観護措置決定を回避するためには、これらの必要性が認められないことを主張し、裁判所に納得してもらう必要があります。
捜査段階で弁護士に依頼をする
観護措置の必要性がないことを具体的に主張するためには、弁護士のサポートが不可欠です。
特に少年事件において裁判所が重視するポイントのひとつが「少年の要保護性」であるため、事件が家庭裁判所に送致される前の段階で、適切な弁護活動をおこなうことが重要です。
弁護士は、少年の要保護性を軽減するための証拠や資料を整え、「観護処置を取る必要はない」と主張していきます。
なお、要保護性とは、事件を起こした少年が将来的に再び事件を起こしてしまう可能性を意味します。
この要保護性が低いと判断されれば、観護措置を回避できる可能性が高まります。
観護措置になってからできること
仮に観護措置の決定がなされ、少年が少年鑑別所に収容された場合でも、決定に対して争うことは可能です。
具体的には、以下のふたつの手続きがあります。
- 異議申立て
- 観護措置取消申立て
これらの方法を通じて、観護措置の必要性がないことを裁判所に主張し、収容の解除を求めることができます。
異議を申し立てる
観護措置決定が、前述したような要件を満たしていないにもかかわらずおこなわれていた場合には、「異議申立て」によって争うことができます。
この手続きでは、観護措置を決定した裁判官とは別の裁判官によって構成される合議体(複数の裁判官による審理で判断)が、異議が認められるかどうかを判断します。
取消しを申し立てる
「少年審判規則」第21条には、以下のように定められています。
観護の措置は、その必要がなくなったときは、速やかに取り消さなければならない。
引用元:少年審判規則 第21条
この規定に基づき、観護措置の決定後に事件の内容や調査結果などを踏まえて「観護措置の必要がなくなった」と判断された場合には、観護措置決定取消申立てをおこなうことが可能です。
この申立てにより、速やかな釈放を求めることができます。
実際の運用状況
現実には、逮捕・勾留された後に家庭裁判所へ送致された少年事件の多くにおいて、観護措置決定がなされるのが一般的です。
また、前述のような異議申立てや取消申立てといった手段がとられても、実際に認められるケースは限られています。
しかし、全ての事案がそのとおりになるわけではありません。
弁護士による迅速かつ適切な弁護活動によって、観護措置の決定が回避されたり、決定後に異議申立てなどが認められて釈放に至ったケースもあります。
そのため、できるだけ早い段階から弁護士に相談・依頼することが非常に重要です。
特に捜査段階での対応が、その後の処分や生活に大きな影響を与える可能性があります。
少年鑑別所に関するよくある質問
最後に、少年鑑別所に関するよくある質問を紹介します。
鑑別所と少年院の違いは何ですか?
鑑別所と少年院の違いは、収容される目的にあります。
鑑別所は、少年の性格や非行の背景を調査することを目的とした施設です。
これに対して少年院は、非行に対して矯正教育をおこなうことを目的とした施設となります。
そのため、鑑別所は少年審判で処分が決定する前に一時的に収容される施設であり、少年院は審判で処分が決定した後に、教育的措置として収容される施設となります。
鑑別所に入ると履歴として残りますか?
鑑別所に入ると、観護措置として収容されたという履歴が残ります。
しかし、この規則は非公開情報であるため、日常生活や就職活動などで他人に知られたり、不利益を受けたりすることは基本的にありません。
これは、鑑別所への収容が「前科」に当たらないためです。
ただし、将来再び非行を犯した場合には、家庭裁判所の審理などで過去の履歴が考慮される場合があります。
少年鑑別所は何をするところですか?
少年鑑別所は、家庭裁判所の観護措置によって収容された少年に対して、性格や行動傾向、非行の背景などを専門的に調査・観察する施設です。
その目的は、少年審判において適切な処分を決定するための資料を作成することにあります。
施設内では、専門のスタッフによる面接や心理検査などがおこなわれ、その少年にどのような処分や支援が適切かを判断する材料として活用されます。
少年鑑別所では何がおこなわれますか?
少年鑑別所では、収容された少年に対して、少年審判の判断に必要な資料を作成するために、専門的な調査や観察がおこなわれます。
主におこなわれる内容は、以下のとおりです。
- 心理検査・知能検査
- 心理専門職による面接・カウンセリング
- 日常生活における行動観察
- 家庭環境や交友関係に関する調査 など
これらの調査・観察を通じて得られる情報は、少年審判において、その少年にどのような処分や支援が適切かを判断するための資料として活用されます。
まとめ
少年の更生のために、鑑別所で非行の原因を調査することが必要な場合もあります。
しかし、少年が学生であったり、すでに就労している場合には、身柄拘束による影響が非常に大きなものとなることもあります。
そうした不利益をできる限り回避するためには、家族によるサポートや、弁護士による迅速な弁護活動が欠かせません。
もし、あなたのお子さんが逮捕されてしまった場合には、少年事件に強い弁護士に早めに相談されることをおすすめします。
まずは、「ベンナビ刑事事件」から無料相談を活用し、弁護士に相談してみましょう。

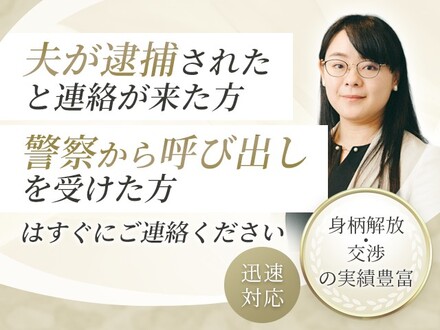
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る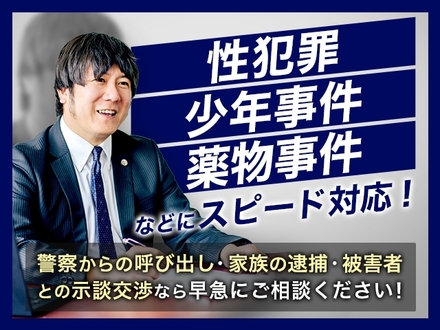
性犯罪/薬物事件/少年事件などに注力!刑事事件はスピード勝負です。逮捕直後および警察から連絡が来た時点からご相談ください。依頼者様がご納得できるよう、丁寧かつわかりやすい説明を心がけています。
事務所詳細を見る
【早期釈放/不起訴実績多数】加害者側・被害者側双方で、示談交渉対応多数◆痴漢・盗撮/暴行傷害/事故/窃盗など迷う前に電話◆早めの相談で選択肢を広げることが可能◎◆【即日接見で安心をお届け】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
盗撮の冤罪にあいそうなときでも、対応を間違えると逆に状況が悪化する可能性があります。万が一のときに冷静に対応できるよう、正しい対処法と注意点をおさえ...
-
犯罪を犯して起訴された場合は、通常、刑事裁判に移行します。刑事裁判は有罪・無罪や刑罰が決定する重要な場になるので、先を見据えてしっかりと準備しておく...
-
本記事では、犯罪歴が日常生活に及ぼす悪影響、犯罪歴がバレるリスク、犯罪歴が残らないようにするためのポイントなどについてわかりやすく解説します。
-
2023年5月の法改正により逃走罪の対象が拡大され、刑罰も厳格化されました。そのほか、GPS装着制度や刑の時効停止に関する規定が新設されるなど、逃走...
-
どのようなときに後日逮捕されるのでしょうか?どのくらいの確率で警察が犯行に気付き逮捕しに来るのでしょうか?この記事では、後日逮捕の概要をお伝えしたう...
-
殺害された人が生前殺されることを承諾していた場合、犯行に及んだ人物は殺人罪ではなく、承諾殺人罪の容疑で刑事訴追されます。本記事では、承諾殺人の構成要...
-
本記事では、刑事罰の役割や刑法で規定されている6つの刑事罰について解説します。2025年6月に運用が始まった拘禁刑の詳細や、刑事罰の種類・重さの一般...
-
家族が留置場に入れられた場合、留置場がどのような施設なのか当然気になるものです。本記事では、留置場の施設概要や一日の流れなどを解説しています。差し入...
-
緊急避難とは、刑法で定められた違法性阻却事由の一つです。正当防衛も違法性阻却事由という点では同じですが、緊急避難と正当防衛は成立要件が異なります。具...
-
この記事では、現行犯逮捕についてくわしく解説しています。現行犯逮捕とは「目の前で犯行に及んでいる犯人を逮捕すること」です。現行犯逮捕できる要件や、一...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る
























































