▶日本版司法取引制度とは|2018年6月施行の背景と運用リスク
▶プロレス・K-1などの格闘技はなぜ決闘罪にはならないのか?
特定犯罪とは|日本版司法取引制度に適用された罪の概要


2018年6月1日、刑事裁判手続きに1つの制度が導入されました。それが『日本版司法取引制度(協議・合意制度)』です。
この制度の導入により、捜査に協力すればあなたの罪も軽くなるかもしれません。この記事では、日本版司法取引制度の対象や、対象となる犯罪(特定取引)について説明していきます。
日本版司法取引制度における特定犯罪とは
すべての犯罪に関し、被疑者・被告人と検察の間で司法取引ができるわけではありません。司法取引の対象は、『特定犯罪』であるとされています。
では、特定犯罪とはいったい何を指すのでしょうか。この点、特定犯罪については刑事訴訟法第350条の2第2項に規定されています。
2 前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たるものを除く。)をいう。
一 刑法第九十六条から第九十六条の六まで若しくは第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第百五十七条の罪、同法第百五十八条の罪(同法第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第百五十七条第一項若しくは第二項の罪に係るものに限る。)又は同法第百五十九条から第百六十三条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで、第百九十八条、第二百四十六条から第二百五十条まで若しくは第二百五十二条から第二百五十四条までの罪
二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第一号から第四号まで、第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪、同項第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂罪又は組織的犯罪処罰法第十条若しくは第十一条の罪
三 前二号に掲げるもののほか、租税に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
四 次に掲げる法律の罪
イ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)
ロ 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
ハ 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
ニ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
ホ 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
ヘ あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
ト 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
チ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
刑法第百三条、第百四条若しくは第百五条の二の罪又は組織的犯罪処罰法第七条の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)若しくは組織的犯罪処罰法第七条の二の罪(いずれも前各号に掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)
引用元:刑事訴訟法 第350条の2
まず、1号では刑法犯について規定しています。これは、たとえば以下のような犯罪になります。
公務の作用を妨害する罪
強制執行妨害目的損壊(刑法第96条の2)、強制執行妨害(刑法第96条の3)など
文書偽造の罪
公文書偽造等(刑法第155条)、偽造公文書行使(刑法第158条)、私文書偽造等(刑法第159条) など
汚職の罪
贈収賄(刑法第197条〜197条の4、刑法第198条) など
財産犯罪
詐欺(刑法第256条)、電子計算機使用詐欺(刑法第246条の2)、背任(刑法第247条)、業務上横領罪(刑法第253条)など
2号では『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』に関し、封印等破棄(刑法第96条)、強制執行妨害目的財産損壊(刑法第96条の2)などを対象としています。3号では、租税に関する法律や独禁法違反のほか、『その他の財政経済関係犯罪』を対象としていますが、これは会社法違反、出資法違反、著作権法違反など、広く税法違反や経済犯罪を含む趣旨であると考えられます。
最後に4号では、覚せい剤取締法や銃刀法違反など、被害者がいないために証拠が残りにくい犯罪がまとめられています。
司法取引の基礎知識
日本版司法取引制度(協議・合意制度)とは何か
日本版司法取引制度とは、簡単に言えば『被疑者や被告人が刑事事件の捜査等に協力するのと引き換えに、自分の事件を不起訴にしてもらったり、軽い罪にしてもらったりすること』です。刑事訴訟法の改正により、2018年6月1日から導入されました。
導入の理由
では、なぜこのような制度が導入されるに至ったのでしょうか。ここで、近年問題になっているオレオレ詐欺を例に考えてみましょう。
オレオレ詐欺では、計画を首謀する人の他に、お金の受け渡しをする『受け子』と呼ばれる役割の人がいます。実際に逮捕されるのは、首謀者よりも、お金を取りに来た受け子であることの方が多いのですが、受け子はあくまで犯罪組織の末端に過ぎません。
首謀者を捕まえなければ、オレオレ詐欺の撲滅にはつながりませんよね。そこで、捕まった受け子に対し、「首謀者の情報を教えてくれれば、罪を軽くするよ」と持ちかけ、首謀者の逮捕・起訴へつなげるのです。
このように、日本版司法取引制度は、組織的犯罪に対処するための一手段として導入されました。
制度の内容
では、日本版司法取引制度とは具体的にどのような内容の制度なのでしょうか。新設された刑事訴訟法第350条の2第1項を確認してみましょう。
第三百五十条の二
検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
一.次に掲げる行為
イ 第百九十八条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること。
ロ 証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
ハ 検察官、検察事務官又は司法警察職員による証拠の収集に関し、証拠の提出その他の必要な協力をすること(イ及びロに掲げるものを除く。)。
一.次に掲げる行為
イ 公訴を提起しないこと。
ロ 公訴を取り消すこと。
ハ 特定の訴因及び罰条により公訴を提起し、又はこれを維持すること。
ニ 特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。
ホ 第二百九十三条第一項の規定による意見の陳述において、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
ヘ 即決裁判手続の申立てをすること。
ト 略式命令の請求をすること。
引用元:刑事訴訟法 第350条の2
長い条文ではありますが、まとめると、
・被疑者や被告人が、他人の刑事事件について、取調べにおいて真実の供述をしたり、証拠を出す代わりに
・検察は起訴しない、起訴をやめる、刑を軽くする
という約束ができる
という内容になっています。
関連記事:日本版司法取引制度とは|2018年6月施行の背景と運用リスク
司法取引の流れ
仮にあなたが被疑者・被告人として司法取引をする場合、どのような手続きの流れを踏むのでしょうか。
司法取引は、検察と被疑者・被告人(または弁護士)のいずれかが「司法取引をしたいです」といった協議を申し入れ、相手方が承諾することから始まります。協議の結果、取引内容に納得し、司法取引が成立すると、合意内容書面が作成されます。
ただし、被疑者・被告人であるあなたが合意をするためには、弁護人が同意しなければなりません(刑事訴訟法第350条の3第1項)。
合意内容書面を作成したら、実際に取引内容を実行します。つまり、あなたは証拠を提出したり、取調べに応じ、一方で検察官は不起訴にしたり、求刑を軽くしたりするのです。
万が一、どちらかが約束を破った場合には『合意からの離脱』(刑事訴訟法第350条の10第1項)をします。これにより、司法取引前の状態に戻り、あなたは捜査に協力する義務がなくなります。
司法取引は始まったばかりの制度であり、どのように運用されて行くのか未知数なところがあります。もしもあなたが司法取引にかかわることがあれば、まずは刑事事件を得意とする弁護士に相談しましょう。


【初回相談料1時間1.1万円(逮捕されている場合等は無料)|弁護士直通TEL|夜間・休日◎】無罪を獲得した実績◎早期の身柄釈放を第一に!性犯罪/痴漢・盗撮/暴行傷害事件など元検事の弁護士に相談が◎今何をすべきか明確にご提示します
事務所詳細を見る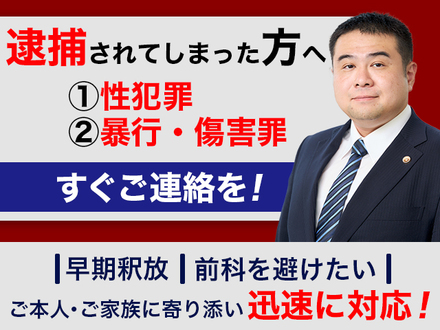
【性犯罪/暴行・傷害罪】当事務所は、原則として、都心での性犯罪および暴行・傷害罪のみ対応し、これらの刑事事件の不起訴処分を目指す事務所です。【渋谷駅徒歩5分】
事務所詳細を見る
≫被害者の方との示談交渉ならお任せください≪【初回のご相談0円!】会社や学校に知られる前に解決を目指しましょう●不起訴獲得・前科回避に自信あり【LINE歓迎!弁護士と直接やりとり◎】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
風営法に違反すると、経営者・従業員が逮捕される可能性も十分あります。そのため、風営法の規定を正しく理解したうえで、事業を営むことが重要です。本記事で...
-
ニュースでよく聞く「検挙」という言葉の正確な意味を理解している人は、実はそこまで多くはありません。検挙という言葉がよく使われるシーンや、似た用語との...
-
刑事事件を起こして刑事告訴されると、警察が捜査開始して逮捕や裁判となるおそれがあります。逮捕回避や減刑獲得に向けて迅速に動くためにも、手続きの流れを...
-
2023年5月の法改正により逃走罪の対象が拡大され、刑罰も厳格化されました。そのほか、GPS装着制度や刑の時効停止に関する規定が新設されるなど、逃走...
-
刑事事件でよく聞く被疑者という言葉ですが、「容疑者」や「被告人」とはどういった違いがあるのでしょうか。そしてもしも自分が被疑者になってしまった場合、...
-
本記事では執行猶予期間中の方に向けて、執行猶予の取り消しについての定義・意味、執行猶予が取り消しになる2つのパターン、再犯をして執行猶予が取り消しに...
-
ナンパをしたことで通報され、警察に逮捕された事例はいくつもあります。本記事では、ナンパで問われる可能性がある罪にはどのようなものがあるのか、どこまで...
-
保釈金は問題なく裁判が進めば返金(還付)されるお金ですが、裁判が終わった後に直接手渡されるわけではなく弁護士の口座などを通してあなたに返金されます。...
-
事件を起こし警察に検挙・逮捕された場合は、不起訴処分の獲得を目指すのが一般的です。本記事では、不起訴処分とは何かや無罪との違い、不起訴処分を獲得する...
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る






















































