執行猶予が取り消しされるケースとは?取り消しを回避したいなら弁護士に相談を!


刑事裁判には実刑判決と執行猶予付き判決があり、執行猶予が付くとすぐに刑罰が実施されることはありません。
しかし、執行猶予期間中に再犯し、実刑判決となった場合には、この執行猶予が取り消される可能性があります。
そのため、取り消しを防ぐためには、再犯をしないことはもちろん、不起訴処分などを獲得することも重要です。
本記事では、執行猶予期間中の方に向けて、以下の内容について説明します。
- 執行猶予の取り消しとは何か?
- 執行猶予が取り消しになる2つのパターン
- 再犯をして執行猶予が取り消しになるまでの大まかな流れ
- 取り消しを回避したい方が弁護士に相談・依頼するメリット など
本記事を参考に、執行猶予を取り消されないために何をすればよいのかについて理解しましょう。
執行猶予の取り消しとは?猶予されていた刑罰が実施されること
執行猶予の取り消しとは、猶予されていた刑罰(懲役刑、禁錮刑、罰金刑)が実施されることを指します。
そもそも執行猶予とは、刑事事件において有罪判決となった場合に一定期間刑の執行が先送りされる制度です。
先送りされているだけなので、以下のいずれかに当てはまる場合には刑罰が実施される可能性があるでしょう。
- 必要的取り消し:禁錮刑以上の犯罪をするなど必ず取り消しになるケース
- 裁量的取り消し:罰金刑の犯罪をするなど裁判所が任意に取り消すケース
上記に当てはまり、猶予されていた刑罰が実施されることを、一般的に執行猶予の取り消しなどと言います。
執行猶予を取り消しされた場合の刑の内容
執行猶予を取り消された場合は、猶予されていた刑罰と新しく有罪判決になった刑罰の両方が科されます。
たとえば「懲役3年・執行猶予5年」の最中に犯罪を起こして「懲役2年」の実刑判決を受けたとしましょう。
この場合は5年分(猶予されていた懲役3年+新しく有罪判決になった懲役2年)の懲役を受けることになります。
執行猶予が取り消しになる2つのパターン
執行猶予の取り消しには、以下の2パターンがあります。
- 必要的取り消し
- 裁量的取り消し
ここでは、執行猶予が取り消しになる2つのパターンについてそれぞれ説明します。
1.必要的取り消し|執行猶予が必ず取り消しになる場合
必要的取り消しとは、執行猶予が必ず取り消されるケースのことです。
執行猶予期間中に犯罪をして、禁固刑以上の実刑判決が下された場合には取り消しされます。
また、以下のようなケースに該当する場合も、執行猶予は取り消されることになるでしょう。
- 猶予の言い渡しの前にした犯罪について、禁錮刑以上の実刑判決が下された場合
- 猶予の言い渡しの前にした犯罪について、すでに禁錮刑以上の実刑判決が下されていた場合
基本的には「執行猶予期間中に犯罪をし、禁固刑以上になると取り消される」と理解しておけばよいでしょう。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
2.裁量的取り消し|裁判所の裁量によって執行猶予が取り消される場合
裁量的取り消しでは、裁判所の裁量によって執行猶予が取り消されます。
執行猶予期間中に犯罪をして、罰金刑の実刑判決が下された場合に取り消される可能性があります。
また、以下のようなケースに当てはまる場合にも、裁判所に執行猶予が取り消される可能性があるでしょう。
- 保護観察つきの執行猶予期間中に重大な遵守事項違反があった場合
- 猶予の言い渡しの前にした犯罪について、禁錮刑以上で執行猶予付きの判決が下されていた場合
なお、裁判所が執行猶予を取り消すかどうかは、犯罪の内容や種類などを個別具体的に判断して決定されます。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
引用元:法令検索
再犯をして有罪判決となり執行猶予が取り消しになるまでの大まかな流れ
再犯をして有罪判決となった場合に執行猶予が取り消しされるまでの流れは、以下のとおりです。
- 執行猶予の取り消し事由が生じる
- 検察官が執行猶予取り消しの請求をする
- 裁判所が執行猶予の取り消しを決定する
ここでは、再犯をして有罪判決となった場合に執行猶予が取り消しされるまでの大まかな流れについて説明します。
1.執行猶予の取り消し事由が生じる
執行猶予の取り消される事由とは、必要的取り消しまたは裁量的取り消しのことです。
取り消し事由として最も多いのは、再犯をして実刑判決が確定したケースとされています。
2.検察官が執行猶予取り消しの請求をする
検察官が裁判所に対して、執行猶予取り消しの請求をおこないます。
検察官の請求によって手続きが開始することは、刑事訴訟法第349条1項に規定されています。
3.裁判所が執行猶予の取り消しを決定する
執行猶予の取り消し請求がされると、裁判所で本人または代理人に対する意見の聴取がおこなわれます。
禁錮刑以上の場合(必要的取り消しの場合)は、意見の内容にかかわらず執行猶予は取り消されるでしょう。
一方、罰金刑の場合(裁量的取り消しの場合)は、裁判所に執行猶予が取り消されない可能性は残されています。
もっとも実務上は検察が取り消しの請求しているため、罰金刑の場合でも取り消されることが多いといいます。
執行猶予の取り消しを回避できる3つのケース
執行猶予の取り消しを回避できる主なケースは、以下のとおりです。
- 不起訴処分や無罪を獲得した場合
- 有罪でも「再度の執行猶予」を獲得した場合
- 執行猶予満了後に取り消し事由が生じた場合
ここでは、執行猶予の取り消しを回避できる3つのケースについて説明します。
1.不起訴処分や無罪を獲得した場合
執行猶予の取り消し事由の多くは、懲役刑や罰金刑などの実刑判決が確定するというものです。
そのため、再犯をしても不起訴処分や無罪を獲得できた場合には取り消し事由が発生しないというわけです。
起訴された場合に無罪を獲得するのは非常に困難であるため、不起訴処分の獲得を目指すのが望ましいでしょう。
2.有罪でも「再度の執行猶予」を獲得した場合
再犯で有罪判決になったとしても、再度、執行猶予を獲得できれば取り消しを回避できる可能性があります。
ただし、再度の執行猶予を獲得するには、刑法第25条2項に規定された条件を全て満たす必要があるでしょう。
- 初犯の刑罰が全て猶予されていること
- 再犯の刑罰が1年以下の懲役刑または禁錮刑であること
- 犯罪の経緯などについて特に酌量すべき情状があること
- 初犯の執行猶予期間中に保護観察がついていないこと
もっとも反省していないと判断される可能性が高く、再度の執行猶予を獲得するのは非常に難しいとされています。
3.執行猶予満了後に取り消し事由が生じた場合
執行猶予満了後に再犯の有罪判決が確定した場合も、初犯の執行猶予の取り消しを避けられます。
- 再犯をして警察に逮捕される
- 捜査期間中に初犯の執行猶予期間が満了する
- 再犯に関する裁判がおこなわれて有罪判決が確定する
上記のような場合では「2.捜査期間中に初犯の執行猶予期間が満了する」の時点で初犯の刑罰は免除されます。
そのため、そもそも刑罰を科すことができなくなるため、執行猶予の取り消しがおこなわれることもありません。
ただし、再犯で有罪判決になった際に執行猶予を獲得できる可能性は低くなるでしょう。
執行猶予の取り消しを回避したい方が弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士に相談・依頼すれば、執行猶予の取り消しを回避するために以下のような対応をしてくれるでしょう。
- 被害者との示談交渉を進めてくれる
- 再犯防止プランを検討・実行してくれる
- 検察官に対しての働きかけをしてくれる
ここでは、執行猶予の取り消しを回避したい方が弁護士に相談・依頼する3つのメリットについて説明します。
1.被害者との示談交渉を進めてくれる
弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉を進めてくれます。
被害者に対して十分謝罪し示談が成立した場合には、通常、検察に被害感情が和らいだと判断してもらえます。
そのため、不起訴処分になる可能性が高まり、執行猶予の取り消し事由の回避につなげることができるのです。
また、裁判になった場合でも情状が考慮されて、再度の執行猶予の獲得を目指せる可能性があるでしょう。
ただし、加害者が被害者と示談をすることは困難なので、弁護士に依頼し対応してもらう必要があります。
2.再犯防止プランを検討・実行してくれる
弁護士に依頼することで、再発防止プランを検討・実行してくれることも多いです。
犯罪の内容によって異なりますが、主な再発防止策には以下のようなものが考えられます。
- 家族に協力を求める
- 不良グループと距離を取る
- 医療機関でサポートを受ける など
再発防止プランの検討・実行も、不起訴処分や再度の執行猶予の獲得などに役立つことが多いです。
また、再発防止プランへの取り組み状況を証拠化し、検察や裁判官などを説得してくれるでしょう。
3.検察官に対しての働きかけをしてくれる
弁護士は、検察官に対して以下のような働きかけをしてくれます。
- 勾留請求をしないように求める
- 不起訴処分になるように求める
- より軽い罪で起訴するよう求める など
示談交渉の結果や再発防止プランの内容などを提示しつつ、働きかけをしてくれることが多いです。
これにより不起訴処分を獲得できたり、再度の執行猶予を獲得できる条件を満たせたりする可能性があります。
さいごに|刑事事件が得意な弁護士はベンナビ刑事事件で探そう
執行猶予を取り消されないためには、再犯をしないことが何よりも重要です。
執行猶予期間中に再犯して、実刑判決が確定した場合には、執行猶予は取り消されてしまうでしょう。
もし執行猶予期間中に再犯をした場合には、できる限り早く弁護士に相談し不起訴処分の獲得を目指すべきです。
その際「ベンナビ刑事事件」を使うことで、刑事事件や再犯の弁護活動が得意な弁護士を効率よく見つけられます。
最寄りの刑事事件が得意な弁護士を探して相談し、執行猶予の取り消しを回避するためのサポートを受けましょう。


【初回相談無料】家族が逮捕された方・警察から連絡が来た等はすぐにご連絡を!◆「早期釈放してほしい」「周囲にバレずに解決したい」などあなたのニーズに合わせてスピード対応!【土日祝も対応可能◎】
事務所詳細を見る
【新宿駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る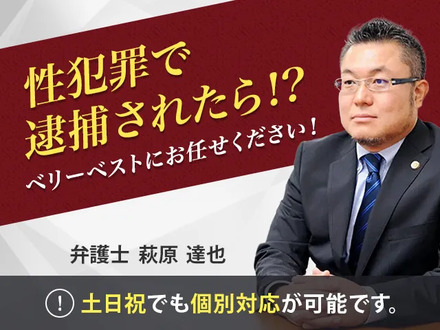
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
-
この記事では、痴漢で解雇されるシチュエーションや、解雇するかどうかを判断するときに考慮されるポイント、弁護士に早期相談・依頼するメリットなどについて...
-
ニュースでよく聞く「検挙」という言葉の正確な意味を理解している人は、実はそこまで多くはありません。検挙という言葉がよく使われるシーンや、似た用語との...
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
名誉毀損の可能性がある行為をしてしまったら、刑法第230条を理解することが非常に重要です。 本記事では、刑法第230条について、どのようなときに名...
-
殺害された人が生前殺されることを承諾していた場合、犯行に及んだ人物は殺人罪ではなく、承諾殺人罪の容疑で刑事訴追されます。本記事では、承諾殺人の構成要...
-
刑事事件における時効とは、犯罪から一定期間経過すると加害者が起訴されなくなる制度です。罪を逃れられる制度がなぜ存在しているのか、疑問に感じている人も...
-
本記事では、心神喪失状態で起こした事件について、なぜ無罪になるのかについて詳しく解説します。 また、心神喪失で無罪になったあとの手続きの流れや、心...
-
略式命令は簡易な刑事裁判手続です。100万円以下の罰金刑である犯罪で、被疑者の同意がある場合に選択されます。この記事では略式命令の概要や、略式命令に...
-
道路交通法違反の時効と刑事罰に関する完全ガイドです。スピード違反から飲酒運転、あおり運転まで、各交通違反行為に適用される公訴時効を解説します。違反種...
-
日本の刑事事件で起訴された場合の有罪率は約99.9%と言われています。刑事裁判の有罪率は高く、多くのケースで有罪となり前科が付くことになります。本記...
-
本記事では執行猶予期間中の方に向けて、執行猶予の取り消しについての定義・意味、執行猶予が取り消しになる2つのパターン、再犯をして執行猶予が取り消しに...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
風営法に違反すると、経営者・従業員が逮捕される可能性も十分あります。そのため、風営法の規定を正しく理解したうえで、事業を営むことが重要です。本記事で...
-
家族が留置場に入れられた場合、留置場がどのような施設なのか当然気になるものです。本記事では、留置場の施設概要や一日の流れなどを解説しています。差し入...
-
刑事事件を起こして刑事告訴されると、警察が捜査開始して逮捕や裁判となるおそれがあります。逮捕回避や減刑獲得に向けて迅速に動くためにも、手続きの流れを...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る
























































