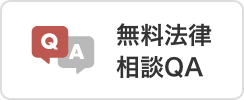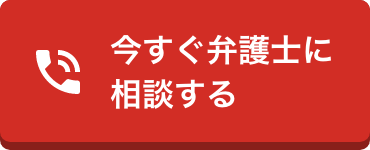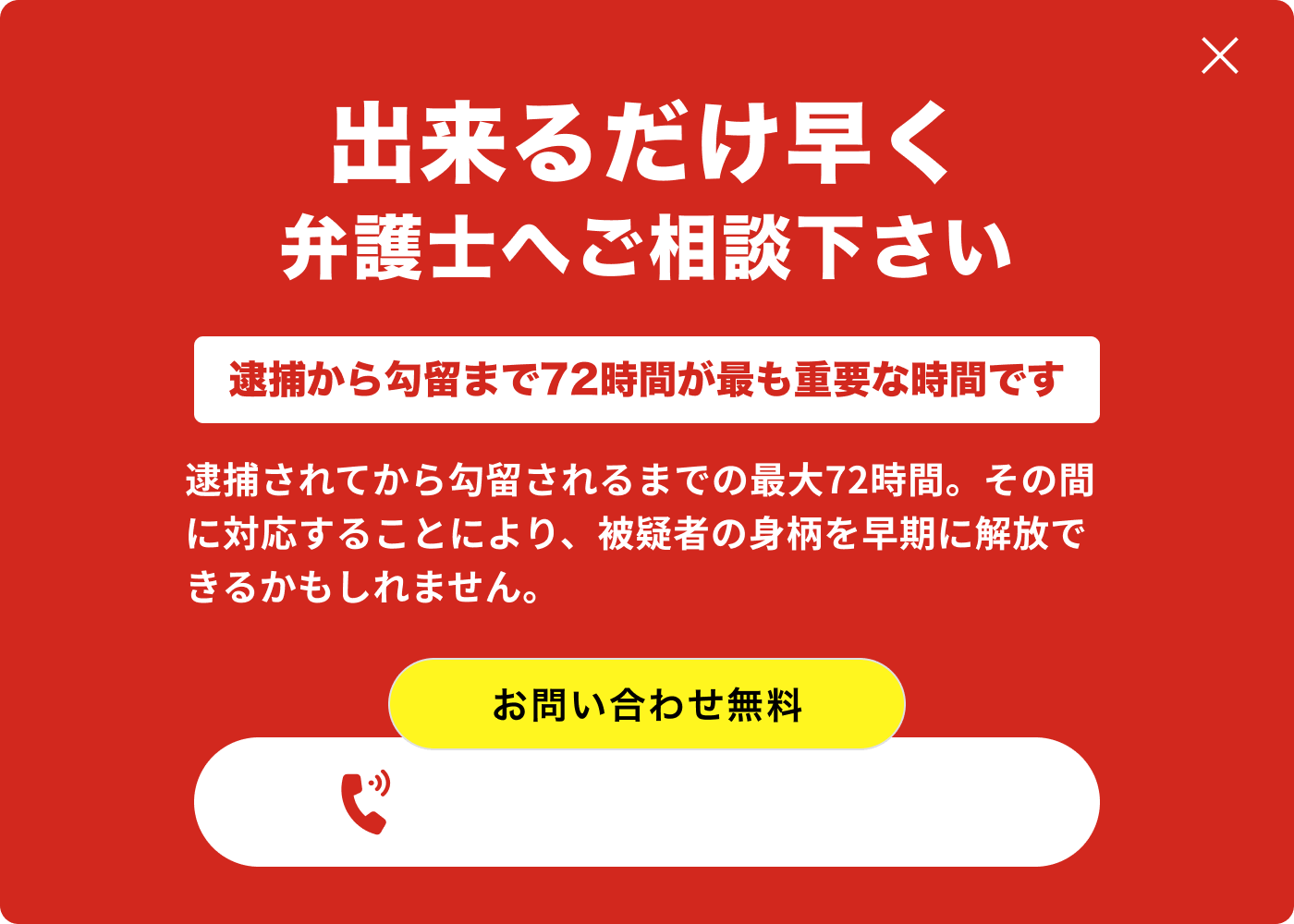略式命令とは?罰金や前科などのデメリット・早期釈放のメリットを解説


略式命令(りゃくしきめいれい)とは、簡易な刑事裁判手続です。
検察官は、100万円以下の罰金刑である軽微な犯罪について、被疑者の同意を条件として「略式手続」を選択することができます。
略式手続では、公判が開かれず簡単な手続で処理されますが、実際略式命令にしてもらう方が良いものでしょうか?
以下では略式命令とはどのような処分なのか、また略式命令になる流れやメリットデメリットなどを解説していきます。
略式命令とは

略式命令について詳しく説明します。
前提知識|略式手続と公判手続の違い
刑事裁判には「略式手続」と「公判手続」の2種類があります。
原則的な手続きは「公判手続」です。公判手続になると法廷で裁判が開かれ、被告人は裁判官の面前で検察官によって追及されます。最終的に裁判官が被告人に判決を宣告します。
判決内容は、有罪であれば死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑などが宣告され、無罪であれば無罪である旨宣告されます。
一方略式手続になると法廷で審理が開かれることはなく、書類審査で刑罰が決定されます。
略式手続で無罪になることはなく、有罪となって罰金刑となります。宣告されるのは罰金刑のみです。
略式手続が採用される目的は、裁判の手間を省くことです。軽微な事件についていちいち公判を開いていたら、裁判所のリソースも足りなくなりますし被告人にも大きな負担となります。
そこで書類上で簡単な審理方法としての略式手続を認め、裁判所と被告人双方の利益を図っているのです。
このように、略式手続は事実関係が明らかな軽微な事件について簡易的な処罰を決めるための手続であるため、仮に無罪主張をしたいのであれば、略式手続に同意しないで正式裁判を求めるべきでしょう。
略式命令は正式裁判を経ずに出される罰金支払い命令
略式命令とは、略式手続における「判決」です。略式手続が採用されたときに裁判所が被告人に対して下す罰金や科料の命令を「略式命令」と言います。
略式命令で命じられるのは100万円以下の「罰金」や「科料」の支払いのみです。拘留や懲役刑、禁固刑などの身柄拘束の刑罰は選択されませんし、死刑も選択されません。
略式命令の条件
刑事事件の中でも略式手続きを選択できるのは、以下の要件を満たすケースです。
100万円以下の罰金または科料に処す場合
略式命令では、被告人に科される刑罰は「100万円以下の罰金または科料」のみです。拘留、懲役刑、禁固刑、死刑のような刑罰を略式手続で科すことはできません。
被疑者に異議がない場合
略式手続は、被疑者(被告人)に異議がないケースにしか適用されません。被疑者や被告人が略式裁判を拒絶する場合には、必ず公判手続が採用されます。
略式命令までの流れ
被疑者が逮捕されて略式命令が出るまでの流れは、以下の通りです。
逮捕後勾留された場合
逮捕後勾留されて身柄拘束が続いた場合には、以下の通りです。
1.逮捕される
まず、万引きや暴行などの罪で逮捕されるところから刑事手続が始まります。
2.48時間以内に検察官のもとに送られる
逮捕されると、48時間以内に検察官のもとに身柄を送られます。
3.24時間以内に勾留される
検察官が引き続いて身柄拘束を必要と判断したら、裁判所へ勾留請求されます。裁判所で勾留決定が出たら、引き続いて警察の留置場で身柄拘束を受けます。
4.検察官から略式起訴として良いか確認される
勾留期間は延長も含めれば最大20日です。その間に検察官から「略式起訴にしても良いか」と聞かれます。被疑者が納得して署名をすれば略式起訴が選択されます。
5.勾留満期までに略式起訴される
勾留期間が満期になるまでに略式起訴されます。
6.略式命令が出て罰金を支払い、解放される
略式起訴されたら被疑者の身柄は即時に解放されます。罰金を払い、すべての刑事手続が終了します。
逮捕後勾留されなかった場合
1.逮捕される
2.48時間以内に検察官のもとに送られる
逮捕されて48時間以内に検察官に送られるまでは身柄拘束されるケースと同様です。
3.釈放される
検察官が身柄拘束を不要と判断したら、勾留請求されずに釈放されます。その後も捜査は継続します。
4.検察官から呼び出しを受けて検事調べを受ける
捜査が終了すると、検察官は被疑者を検察庁に呼び出して検事調べを行います。
5.検察官から略式起訴として良いか確認される
検事調べの際、検察官は被疑者に「略式起訴にして良いか?」と確認します。被疑者が納得すれば書面に署名押印します。
6.略式起訴される
その後、検察官は被疑者を略式起訴します。
自宅に起訴状と罰金の納付書が届き、罰金を支払う
しばらくすると被疑者の自宅に起訴状と罰金の納付書が届くのでそれを使って罰金を支払い、すべての刑事手続が終了します。
勾留されずに在宅捜査となった場合には、20日などの期間制限はなく、任意のタイミングで検察庁に呼ばれます。
略式起訴するには必ず本人の同意が必要なので、起訴前に検察官から略式起訴として良いかどうか尋ねられます。被疑者が納得すれば略式手続きによって起訴されます。
略式命令のメリット

略式命令にはどのようなメリットがあるのか、裁判所や検察官の目線と被告人(被疑者)目線の両方から検討します。
裁判所と検察官:効率的に事件をさばける
裁判所や検察官にとっての略式手続のメリットは「効率的に事件を裁けること」です。
公判請求をして正式裁判を開く場合、検察官は毎回法廷に出頭して立証活動をしなければなりませんし、裁判官も時間を割いて法廷に出席し、最終的に被告人を裁く判決を書かねばなりません。
審理は何度も開かれるので、そのたびに時間と労力を割かれます。
略式命令ならば書類上の審査と簡単な書面作成だけで済むので、両者にとっては非常に楽です。
被疑者被告人:早期に社会復帰しやすい
被疑者被告人サイドにとっても、略式命令は大きなメリットがあります。
略式になると裁判所に出廷しなくて良いので時間も労力もかかりません。検察官から罪を追及されたり裁判官から判決を宣告されたりすることもないので、精神的にも楽です。
また略式請求になると身柄を解放されるので、通常通りの生活に戻れます。会社にも行けて解雇などの不安も減りますし、家族に余計な心配や負担をかけることもありません。
社会復帰しやすいことが大きなメリットとなります。
略式手続きのデメリット
略式手続きにはデメリットもあります。それは「必ず有罪になること」です。
略式手続きは、被疑者被告人が自身の主張をする機会がありません。
そのため、被疑者・被告人が事実を争うということは想定されておらず、有罪となって罰金の刑罰が下されます。これらは刑事罰であるため、「前科」がつきます。
「略式裁判」「略式命令」は前科にならないというのは誤解です。略式手続で有罪となれば前科がつくのです。そして前科がつけば検察庁のデータベースで一生保管されます。
検察官から「略式で良いですか?」と聞かれたとき、もしこれから無罪を主張したいのであれば「良いです」と言ったり書類にサインしたりしてはいけません。
もっとも、略式命令で出た判決に異議を申し立てることは可能ですので、略式命令後に正式裁判で争うという途もなくはありません。
略式手続に応じてよいのか、よく考えるべき

検察官から略式手続を打診されたら、以下のようなことを考えてしっかり検討すべきです。
早く釈放されるが前科はつく
勾留されている事案で略式起訴にしてもらったら、身柄は即時に解放されます。在宅のケースでもいちいち裁判所に出頭する手間や時間を省けます。
しかし略式でも前科がつきますし、1回ついた前科は死ぬまで消してもらえません。
次に犯罪を犯した場合に、前科が考慮されて重い処分を受ける可能性も否定できません。
そのようなことを考えると、安易に略式命令を受け入れるのは全くリスクがないというわけではありません。
冤罪の場合は正式裁判も検討するべき
逮捕されても、実際には犯罪を犯していないケースもあるかもしれません。たとえば痴漢などで犯人と間違われる場合が典型例です。
そのような「冤罪」のケースでは略式裁判は推奨されません。略式手続では被疑者・被告人の主張を提出することができないためです。
このような場合は正式裁判で事実を争うべきでしょう。
略式命令に納得いかない場合は正式裁判をする
いったんは略式手続に同意してしまっても、下された略式命令に納得できなければ、異議を申し立てて正式裁判を求めることが可能です。
ただし略式命令を受けてから2週間以内に異議申立をする必要があります。
期間を過ぎると略式命令が確定してしまうので、不満があるなら早急に手続きしましょう。
まとめ
略式命令は、一般的に「刑事裁判」の判決と異なり「軽い印象」を持たれている例が多々あります。
その印象はある意味正しいですが、略式命令も刑事裁判の判決の1種であり、確定すれば前科がつきます。
略式命令を受け入れるかどうか悩んだら、一度弁護士に相談してアドバイスをもらうと安心です。刑事事件に慣れた弁護士を探して、あなたのおかれた状況を話してみましょう。



【年間相談件数1000件以上】【24時間・365日予約対応可能】刑事事件の実績豊富な弁護士がサポート◆性犯罪(盗撮・不同意わいせつなど)で逮捕されたらすぐにお問い合わせを!【即日接見・オンライン対応可】
事務所詳細を見る
【新宿区(高田馬場)◆早期釈放/不起訴実績多数】加害者側・被害者側双方で、毎年数多くの示談交渉を行っており、解決に自信あり◆出会う弁護士によって、その後の人生は大きく変わります◆】
事務所詳細を見る
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等で警察の取り調べを受けた方・捜査されている方へ|元検事率いる刑事弁護チームが迅速サポート!今後の人生を守るため、すぐにご連絡を【バレずに解決】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
受刑者は、どのように1日を過ごすのでしょうか。なぜ、刑務所での生活は辛いといわれるのでしょうか。本記事では、刑務所生活が辛いといわれる理由を紹介し、...
-
罪を犯してしまったものの、証拠がないから大丈夫だろうと安心している方もいるかもしれません。本記事では、警察がどのような状況で動くのか、証拠の種類や重...
-
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ...
-
名誉毀損の可能性がある行為をしてしまったら、刑法第230条を理解することが非常に重要です。 本記事では、刑法第230条について、どのようなときに名...
-
犯罪をしてしまったときはもちろん、罪を犯していなくても指紋が警察のデータベースに登録されるケースがあります。 本記事では、警察に採取・登録された指...
-
ニュースやドラマでよく聞く「検察」について、警察との違いを知りたいけれどよくわからないという方は少なくありません。 本記事では、逮捕前後の流れを含...
-
どのような行為が強制執行妨害罪に該当するのか、もしも強制執行妨害罪にあたりそうな行為をしてしまったらどんな刑罰が科せられるのかなど、強制執行妨害罪に...
-
痴漢・万引き・盗撮・横領など、やってもいないのに犯人だと疑われてしまうケースは少なからず存在します。 どうすれば疑いを晴らせるのか悩んでいる方もい...
-
もしも自分や家族が刑事告訴され、警察から連絡があったら、逮捕後の流れや、各段階でやるべきことを確認しておく必要があります。本記事を参考に、早めに弁護...
-
本記事では、どのようなときに緊急逮捕されるのか、緊急逮捕をされるとどうなるのかなどについて、通常逮捕や現行犯逮捕との比較を交えながら解説していきます...
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
【弁護士監修】書類送検を徹底解説!書類送検とは被疑者を逮捕せず、書類のみ(証拠を含む)を検察官に送る手続きです。この記事では、そもそも送検とはどうい...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所(かんべつしょ)とは、正式名称は少年鑑別所と呼ばれ、家庭裁判所の少年審判を開くために犯罪を犯した未成年の少年を収容し、少年審判で処分を決めるた...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
出頭に関する知識として、自首との違いや正しい使い方、出頭するメリットデメリットについてご紹介します。
-
いじめは犯罪だと聞いたことがあるかもしれません。自分の子どもが逮捕されてしまうのか、犯罪者になってしまうのか、と不安に感じる方もいるでしょう。本記事...
-
鑑別所(かんべつしょ)とは、正式名称は少年鑑別所と呼ばれ、家庭裁判所の少年審判を開くために犯罪を犯した未成年の少年を収容し、少年審判で処分を決めるた...
-
【弁護士監修】書類送検を徹底解説!書類送検とは被疑者を逮捕せず、書類のみ(証拠を含む)を検察官に送る手続きです。この記事では、そもそも送検とはどうい...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
在宅事件とは、被疑者が勾留による身柄拘束をされないまま捜査が進められる刑事事件です。この記事では、在宅事件とはどのようなもので、どういったケースで選...
-
「少年センター」とはどのような施設なのか、具体的な活動内容・対象年齢・利用条件などについて解説します。
-
公訴時効とは、刑事上の時効の概念で、犯罪が終わってから一定期間が過ぎると、公訴の提起(起訴)ができなくなることです。
-
余罪があることを自覚している場合、余罪捜査がどこまで進められるのか、大きな不安を抱えながら毎日を過ごすことになります。本記事では、余罪が発覚しやすい...
-
名誉毀損の可能性がある行為をしてしまったら、刑法第230条を理解することが非常に重要です。 本記事では、刑法第230条について、どのようなときに名...
-
逮捕された場合、不起訴を期待するのは当然のことです。しかし、不起訴を勝ち取ったとしても、なんらかの不利益が生じるのではないかと不安に感じている方もい...
-
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る