公務執行妨害とは?逮捕後の流れ・罰則・成立する3つの要件を解説


- 「自分の言動が公務執行妨害にあたるのではないか…」
- 「家族が公務執行妨害で逮捕されてしまったが、今後どうなるのか…」
このような突然の事態に強い不安を感じていませんか。
公務執行妨害とは、公務員が職務を執行している際に、暴行や脅迫を用いてその職務を妨害する行為です。
警察官とのトラブルだけでなく、市役所の窓口や学校など、日常生活に近い場面でも発生する可能性があります。
もしあなたやご家族が公務執行妨害の容疑をかけられてしまった場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
今回の記事では、公務執行妨害罪の成立要件や罰則といった基本から、逮捕後の具体的な刑事手続きの流れ、不起訴処分や減刑を目指すために何をすべきかまで解説します。
公務執行妨害とは|公務員の職務を妨害することで成立する罪
公務執行妨害とは、公務員が職務を執行している際に、暴行や脅迫を用いてその職務を妨害する行為のことです。
(刑法第95条)
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
公務執行妨害は、公務員個人を守るためだけでなく、国や地方公共団体の重要な業務、つまり「公務」そのものが円滑におこなわれることを保護する目的があります。
そのため、実際に職務の遂行が妨害されたかどうかに関わらず、妨害する危険性のある行為があった時点で成立する可能性があります。
具体的には、以下のようなケースが公務執行妨害にあたる可能性があります。
- 警察官の職務質問を拒否し、腕を振り払う、または胸ぐらを掴む
- 市役所の窓口で納得できず、職員の机を強く叩いたり、大声で「殺すぞ」などと恫喝する
- 学校で教員の指導に激昂し、暴力をふるう
- 救急隊員の活動を妨げるように暴言を吐く
このように、警察官だけでなく、市役所職員や教員、救急隊員など、さまざまな公務員に対する妨害行為が対象となります。
公務執行妨害の刑罰|3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
公務執行妨害罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められています(刑法第95条)。
なお、2022年6月に刑法が改正され、2025年6月1日よりこれまであった「懲役刑」と「禁錮刑」が「拘禁刑」に一本化されました。
拘禁刑は、刑事施設に収容し、改善更生に必要な作業を命じたり、指導をおこなったりする刑罰です。
初犯で行為が悪質でない場合は罰金刑となることも多いですが、前科がある場合や、行為の態様が悪質な場合には、正式な裁判を経て拘禁刑が科される可能性も十分にあります。
公務執行妨害の時効は3年
公務執行妨害罪の公訴時効(検察官が起訴できる期間)は、犯罪行為が終わった時から起算して3年です。
時効が完成すると、検察官は事件を起訴することができなくなり、逮捕されることも、刑罰を受けることもなくなります。
ただし、公務執行妨害は、その性質上、職務執行中の公務員に対しておこなわれるため、その場で現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
そのため、犯人が特定されずに逃亡を続け、時効が成立するというケースは極めてまれであると言えるでしょう。
公務執行妨害罪が成立する3つの構成要件
どのような場合に公務執行妨害罪が成立するのでしょうか。
公務執行妨害罪が成立するためには、法律で定められた3つの条件(構成要件)を満たす必要があります。
具体的には、「誰に対して」「どのような状況で」「何をしたか」が重要なポイントとなります。
以下で、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
①行為の対象は「公務員」であること(警察官以外も対象)
公務執行妨害罪の対象となるのは、警察官や消防士といった特定の職種に限りません。
国または地方公共団体の職員、その他法令に基づき公務に従事するすべての「公務員」が対象となります(刑法第7条)。
- 市役所や区役所の職員
- 公立学校の教員
- 税務署員
- 労働基準監督官
- 市長や議員 など
したがって、「警察官ではないから大丈夫だろう」という安易な考えは通用しません。
公的な職務に従事している人に対する妨害行為は、広くこの罪の対象となる可能性があることを理解しておく必要があります。
②「公務の執行に際し」おこなわれること
公務執行妨害罪が成立するためには、その行為が公務員が「職務を執行している最中」におこなわれる必要があります。
つまり、公務員であればいつでも対象になるわけではなく、休憩時間中や通勤中、あるいは私的な時間におこなわれた暴行や脅迫は、原則としてこの罪にはあたりません。
その場合は、別途暴行罪や傷害罪、脅迫罪などが成立する可能性があります。
また、おこなわれている公務が「適法」であることも重要な要件です。
例えば、違法な逮捕や令状のない家宅捜索など、法律の手続きを無視した職務に対して抵抗したとしても、公務執行妨害罪は成立しないとされています。
③「暴行または脅迫」を加えること
公務執行妨害罪が成立する最後の要件は、公務員に対して「暴行または脅迫」を加えることです。
ここでいう「暴行」は、一般的にイメージされる殴る・蹴るといった直接的な暴力行為に限りません。
人の身体に向けられていなくても成立する「間接的な暴行」も含まれます。
「脅迫」とは、相手を怖がらせるような害悪を伝えることを指します。
相手が実際に恐怖を感じたかどうかは関係なく、一般の人が聞いた場合に恐怖を感じるような内容であれば成立します。
- 直接的な暴行: 警察官の胸ぐらを掴む、腕を振り払う、体当たりする
- 間接的な暴行: パトカーを蹴る、取り押さえられた証拠品を破壊する、書類を破り捨てる
- 脅迫:「殺すぞ」 「家族に危害を加えるぞ」「夜道に気をつけろ」などと告げる
公務執行妨害で逮捕された後の刑事手続きの流れ

もし公務執行妨害の容疑で逮捕されてしまった場合、その後はどのような手続きが進められていくのでしょうか。
ここでは、逮捕後の一般的な刑事手続きの流れを解説します。
①逮捕~勾留請求(最大72時間)
逮捕後の72時間は、その後の手続きを左右する重要な時間です。
公務執行妨害で逮捕されると、まず警察署に連行され取調べを受けます。
警察は48時間以内に事件を検察へ送致するか、あるいは釈放するかを決定しなければなりません。
送致された場合、検察官が取調べをおこない、さらに24時間以内に逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すれば、裁判官に勾留を請求します。
こうした手続きを経て、身柄拘束が続くかどうかが決まります。
この間、弁護士以外の面会は原則認められず、被疑者は孤立した状況で取調べに臨むことになります。
逮捕直後の供述は今後の処分に大きく影響するため、できるだけ早く弁護士に接見を依頼し、適切な助言を受けることが重要です。
②勾留(最大20日間)
裁判官が検察官の請求を認め、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断すると、被疑者は原則10日間、警察署の留置場などで勾留されます。
この間、検察官は起訴の可否を決めるために捜査を進め、被疑者は警察や検察の取調べに応じることになります。
さらに「やむを得ない事由」があると検察官が判断し、裁判官が許可すれば、勾留は追加で最大10日間延長され、合計で最長20日間続く可能性があります。
この勾留期間は、検察官が最終的に起訴・不起訴を判断するうえで重要です。
被疑者にとっても、弁護士を通じて被害者への謝罪や反省の姿勢を示す活動をおこなうことが、後の処分を軽減するために大切な対応となります。
③起訴・不起訴の決定
最大20日間の勾留期間が満了するまでに、検察官は集めた証拠や供述内容、被疑者の反省態度などを踏まえて、起訴するか不起訴にするかを最終的に判断します。
不起訴処分には、「罪を犯した疑いがない(嫌疑なし)」「証拠が不十分(嫌疑不十分)」「罪は認めるが、今回は起訴を見送る(起訴猶予)」があります。
不起訴となれば裁判は開かれず、前科も付かずに身柄も解放されます。
一方、起訴と判断された場合には刑事裁判にかけられます。
起訴には、公開の法廷で審理がおこなわれる「正式起訴(公判請求)」と、書面のやり取りのみで罰金刑を科す「略式起訴」の二つの手続きに分かれます。
いずれにしても、この決定が事件の行方を大きく左右する重要な局面となります。
④略式起訴または正式起訴
検察官に起訴されると、事件は刑事裁判へと進みます。
起訴には「略式起訴」と「正式起訴」の二種類があり、どちらが選択されるかで手続きは大きく異なります。
略式起訴は、100万円以下の罰金や科料に相当する比較的軽い事件で、本人が事実を認めている場合に用いられます。
この場合、公開の裁判はおこなわれず、書面審理のみで罰金額を決定する略式命令が出されます。
罰金を納めれば手続きは終了し身柄も解放されますが、有罪判決となるため前科が残ります。
一方、正式起訴は、略式起訴によることができない事件で用いられ、公開の法廷で裁判官が証拠を検討し判決を下します。
初犯で反省や示談成立といった事情があれば、実刑ではなく執行猶予が付される可能性もあります。
公務執行妨害の被害者は「国家」のため示談が難しい
刑事事件において、被害者との示談は、その後の処分を決定する上で重要な要素です。
しかし、公務執行妨害罪の場合、被害者は「国家」とされるため、示談を成立させることは容易ではありません。
つまり、この罪の被害者は暴行や脅迫を受けた公務員個人ではなく、公務そのものを妨げられた国家機関と解釈されます。
そのため、仮に警察官本人が「許す」と述べたとしても、事件が解決するわけではなく、組織として示談に応じることはほとんどありません。
しかし、諦める必要はありません。
示談が成立しなくても、弁護士を通じて謝罪の気持ちを伝え、反省文や贖罪寄付などを通じて真摯な反省の態度を示すことは、検察官や裁判官の心証を良くし、不起訴処分や刑の減軽につながる可能性があります。
公務執行妨害で逮捕された直後に取るべき3つの行動
逮捕直後の行動は、その後の人生を大きく左右する可能性があります。
特に逮捕後の72時間は、その後の身柄拘束の期間や最終的な処分に大きな影響を与える極めて重要な時間です。
ここでは、公務執行妨害で逮捕された直後に取るべき行動を解説します。
①弁護士に連絡する
公務執行妨害で逮捕された直後に最も重要なのは、速やかに弁護士へ連絡することです。
逮捕された人には弁護士を呼ぶ権利(接見交通権)が認められていますが、逮捕後72時間は家族であっても面会が制限されるのが通常です。
その孤立した状況で取り調べに一人で臨むのは大きなリスクとなります。
弁護士はこの期間でも自由に接見でき、供述調書で不利にならないよう助言し、精神的な支えにもなります。
また、勾留を避けるために裁判官へ働きかけ、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張して早期の解放を目指します。
当番弁護士や国選弁護人制度もありますが、刑事事件に精通した私選弁護人に依頼する方が、より良い結果につながる可能性が高いといえます。
②深い反省の意思を示す
公務執行妨害罪で処分を軽くするためには、自らの行為を真摯に反省していることを示すことが重要です。
特に示談が難しい公務執行妨害では、反省の態度が処分に大きく影響します。
具体的には、弁護士を通じて被害を受けた公務員に謝罪文を届け、誠意ある謝罪の気持ちを伝えることが有効です。
また、なぜその行為に至ったのか、社会にどのような影響を与えたのかを冷静に振り返り、再発防止の誓約を盛り込んだ反省文を作成して提出することも大切です。
逆に、「相手が悪かった」「酒のせいで覚えていない」といった言い訳や、事実を否認する態度は、反省がないと判断され処分が重くなるおそれがあります。
どのように振る舞うべきかは、必ず弁護士のアドバイスを受け、慎重に対応することが賢明です。
③嘆願書や身元引受書を提出する
反省の意思を示すだけでなく、被疑者が釈放後に家族や職場などの支えを受けながら更生できる環境にあることを示すことも重要です。
その有効な手段が「嘆願書」と「身元引受書」の提出です。
嘆願書は、家族や勤務先の上司・同僚などが「更生を支えていくので寛大な処分をお願いしたい」と訴える文書で、社会的な支えの存在を客観的に示せます。
一方、身元引受書は、配偶者や親族が「身元引受人として今後の生活を監督する」と誓約する書面です。
これにより、逃亡や再犯の可能性が低いことを裁判所や検察官に示せ、早期の釈放や不起訴処分、さらには執行猶予付き判決につながる可能性を高めることができます。
公務執行妨害に強い弁護士を探すなら「ベンナビ刑事事件」
「ベンナビ刑事事件」は、刑事事件に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。
法律事務所を自分で探す際には、弁護士の専門分野や料金の比較など意外と面倒な点が多いもの。
「ベンナビ刑事事件」では、以下の条件で絞り込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なくすぐに見つけられます。
- オンライン面談や電話相談・出張相談の対応
- 土日祝日・夜間の相談が可能
- 刑事事件の解決実績や具体的な解決事例
- 弁護士の費用や経験年数
初回相談が無料で、分割払いに対応している弁護士も多く、費用面での負担を軽減できるのもおすすめポイント。
夜間や休日に相談できる事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。
刑事事件では、初期対応が非常に重要です。
早期の弁護活動により、不起訴処分や軽い処分を得られる可能性が大幅に向上します。
一人で悩まず、まずは専門家に相談することから始めましょう。
ベンナビ刑事事件なら、経験豊富な弁護士があなたの不安を解消し、最適な解決策を提案します。
公務執行妨害に関するよくある質問
最後に、公務執行妨害に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。
Q1. 初犯の場合、刑務所に入る可能性はありますか?
初犯であれば、多くの場合、略式起訴による罰金刑や、不起訴処分(特に起訴猶予)となる可能性が高いです。
しかし、初犯であっても、犯行の態様が悪質、例えば凶器を使用した場合や、公務員に重大なけがを負わせた場合などには、正式な裁判が開かれ拘禁刑の実刑判決が下される可能性もゼロではありません。
「初犯だから大丈夫」と安易に考えず、まずは弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。
Q2. 相手がけがをした場合、傷害罪にも問われますか?
はい、公務執行妨害の行為によって公務員がけがをした場合、公務執行妨害罪に加えて傷害罪にも問われる可能性があります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」であり、公務執行妨害罪よりも重い刑罰が定められています。
このように、一つの行為が複数の罪名に該当する場合、法律ではより重い方の刑罰が適用される原則があります。
そのため、相手にけがを負わせてしまった場合は、傷害罪の刑罰(最大で懲役15年)の範囲内で処分が決定されることになり、事態はより深刻になります。
Q3. 業務妨害とは何が違うのですか?
公務執行妨害罪と業務妨害罪(威力業務妨害・偽計業務妨害)は、いずれも「業務を妨害する」点で共通しますが、決定的な違いは妨害の手段と対象となる業務にあります。
公務執行妨害罪が成立するのは、公務員に対して暴行や脅迫を用いた場合に限られます。
一方、業務妨害罪では手段がより広く、大音量を流す・多数の無言電話をかける・虚偽の情報を流すなども含まれます。
また対象となる業務も公務に限られず、企業や個人の業務も含まれます。
そのため、例えば警察署にしつこくいたずら電話をかけた場合は、公務執行妨害ではなく業務妨害罪が適用される可能性があります。
どちらに当たるかは事案ごとに判断されるため、迷う場合は弁護士に相談することが重要です。
Q4. 酔っていて覚えていない場合でも公務執行妨害は成立しますか?
結論から言うと、「酔っていて覚えていない」という主張が認められ、罪に問われなくなるケースは、ほとんどありません。
法律上、自分で酒を飲んで酔った状態(自招酩酊)で犯罪行為に及んだ場合、原則として責任能力はあったと判断されます。
これは、飲酒すれば判断能力が低下することを予見できたはずだと考えられるためです。
ただし、極度の酩酊状態で、完全に善悪の判断がつかない「心神喪失」の状態であったと医学的に証明されるような例外的なケースでは、無罪になる可能性もゼロではありません。
しかし、現実的にはその証明は非常に困難であり、「酔っていた」という言い分だけで罪を免れることは難しいと考えるべきでしょう。
まとめ
この記事では、公務執行妨害罪の成立要件から、逮捕後の手続き、そして逮捕された場合に取るべき行動について詳しく解説しました。
公務執行妨害は、警察官だけでなく、市役所職員や教員など、あらゆる公務員が対象となる身近な犯罪です。
カッとなった一瞬の行動が、逮捕や前科といった深刻な結果を招く可能性があります。
もしあなたやご家族がこの罪の疑いをかけられてしまった場合、最も重要なのは、決して一人で抱え込まず、できる限り早く弁護士に相談することです。
逮捕直後の迅速な対応が、その後の人生を大きく左右します。
この記事が、公務執行妨害という罪について正しく理解し、万が一の際に冷静な一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

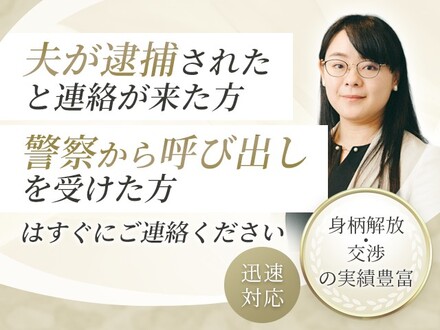
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る
【初回相談無料】「前科を回避したい」「示談交渉をして欲しい」などのお悩みにスピード対応!風俗店トラブルや性犯罪、窃盗など、刑事事件の加害者になった方はすぐにご相談を。依頼者さまの利益最大化に向けて、徹底的にサポートいたします。
事務所詳細を見る
「逮捕」や「取調べ」という緊急事態に、立ち止まっている時間はありません。即日の接見(面会)から具体的な防御策の立案まで一気通貫でサポート。釈放・減刑・示談成立に向けた「効果的な行動」をすぐさま起こします。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



その他の犯罪を起こしたらに関する新着コラム
-
本記事では、ミスティーノの違法性や問われる可能性がある罪、万が一利用してしまった場合の対処法について解説します。
-
本記事では、住居侵入罪において初犯でも逮捕・起訴されるかどうか、実際に起訴を回避するためにできる対応策について、わかりやすく解説します。
-
テレグラムでのやり取りが警察にバレる可能性について詳しく解説します。テレグラムの特徴や関連する犯罪事例、警察のデータ解析能力などを具体的に説明します...
-
本記事では、オンラインカジノが違法となっている理由や、近年の取り締まり強化の流れ、時効などについて詳しく解説します。オンラインカジノを利用してしまっ...
-
本記事では、一般人でもオンラインカジノ利用によって逮捕されることはあるのか、逮捕された場合のデメリットなどを解説します。また、実際に逮捕されてしまっ...
-
本記事では、迷惑防止条例違反について知りたい方に向けて、迷惑防止条例違反の定義や意味、迷惑防止条例違反に該当する主な犯罪、迷惑防止条例に規定されてい...
-
本記事では、オンラインカジノの利用を検討している方に向けて、オンカジ関連で成立する可能性がある3つの犯罪、日本国内でオンカジの利用や勧誘をして逮捕さ...
-
逃走罪とは、法令によって拘禁されている状態からの逃走を罰する犯罪です。2023年の法改正により対象が拡大され、厳罰化が進んでいます。逃走罪の種類や法...
-
本記事では、正当な権利行使と脅迫罪の成否、脅迫罪に問われかねない発信をしたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
前科は海外渡航の大きな障壁となることがあります。パスポートの発給制限やビザの取得、入国審査など、前科による渡航制限の具体的内容をわかりやすく解説しま...
その他の犯罪を起こしたらに関する人気コラム
-
違法ダウンロード(いほうだうんろーど)とは、インターネット上に違法にアップロードされたコンテンツ(画像や動画等)をダウンロードする行為のことです。こ...
-
迷惑電話や執拗なクレームは、威力業務妨害に問われる危険があります。自分では正当な理由があると思っていても、刑罰が科せられる可能性があります。この記事...
-
脅迫罪とは被害者に害悪の告知をする犯罪で、【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金】の法定刑が定められています。脅迫に聞こえるような脅し文句や言葉...
-
映画や小説などのフィクションでよく見るサイコパスは、現実に存在します。この記事では、犯罪心理学者にサイコパスの特徴や、その基準を伺いました。イメージ...
-
本記事では、名誉毀損が成立する条件、名誉毀損が成立する具体例、トラブルに発展した時の対処法について解説します。
-
本記事では、住居侵入罪の具体的な定義や刑罰、そして構成要件を詳しく解説。「初犯でも懲役刑になるのか」「正当な理由ってどこまで?」といった疑問にも回答...
-
公文書偽造(こうぶんしょぎぞう)とは、国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪です。【法定刑は1年以上10年以下】と意...
-
不法投棄(ふほうとうき)とは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた処分場以外に、廃棄物を投棄することです。
-
死刑になる犯罪は全部で18種類あり、殺人罪などのイメージしやすいものから、海賊行為を規定したイメージしにくいものまで多くあります。裁判で死刑が下され...
-
護身目的でもナイフなどを携帯できないことをご存知ですか?この記事では銃刀法違反で逮捕されかねないケースと銃刀法違反の罰則、逮捕されてしまったときにと...
その他の犯罪を起こしたらの関連コラム
-
外患誘致罪(がいかんゆうちざい)の法定刑は死刑しかなく、刑法で最も重い罪と言えるでしょう。この記事では、外患誘致罪の定義や、類似する罪との違い、適用...
-
落書きは逮捕されます。この記事では落書きで逮捕されるケースやシチュエーション、実際に落書きで逮捕された事例、落書きで問われる罪と罰則、落書きで逮捕さ...
-
本記事では、住居侵入罪の具体的な定義や刑罰、そして構成要件を詳しく解説。「初犯でも懲役刑になるのか」「正当な理由ってどこまで?」といった疑問にも回答...
-
脅迫罪とは被害者に害悪の告知をする犯罪で、【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金】の法定刑が定められています。脅迫に聞こえるような脅し文句や言葉...
-
故意に他人のものを壊せば、器物損壊罪に問われます。本記事では、器物損壊罪に該当する具体的な行為や罰則、時効などを幅広く解説。逮捕後の流れや前科回避の...
-
美人局(つつもたせ)とは、夫婦などが共謀して行う犯罪のことです。今回は、美人局が該当する罪に関して説明をした上で、逮捕されるとどうなるのかということ...
-
本記事では、オンラインカジノの利用を検討している方に向けて、オンカジ関連で成立する可能性がある3つの犯罪、日本国内でオンカジの利用や勧誘をして逮捕さ...
-
無銭飲食は詐欺罪に該当する可能性があります。この記事では、無銭飲食で逮捕されてしまった場合の罰則と対処法を詳しく解説します。
-
死刑になる犯罪は全部で18種類あり、殺人罪などのイメージしやすいものから、海賊行為を規定したイメージしにくいものまで多くあります。裁判で死刑が下され...
-
本記事では、YouTube違法アップロードに関する逮捕事例などを交えながら、問われる罪や視聴者側の対処法などを解説します。
-
死体遺棄とは、死体を埋葬せずに捨て置く犯罪行為で、犯した場合は死体遺棄罪で罰せられます。遺骨の遺棄は罰則対象となりますが、散骨については明確に罰する...
-
脅迫事件を含む刑事事件では逮捕・勾留・起訴までの時間が限られているため、できる限り早く弁護士に相談するのが重要です。そこで、弁護士を選ぶ際のポイント...
その他の犯罪を起こしたらコラム一覧へ戻る




















































