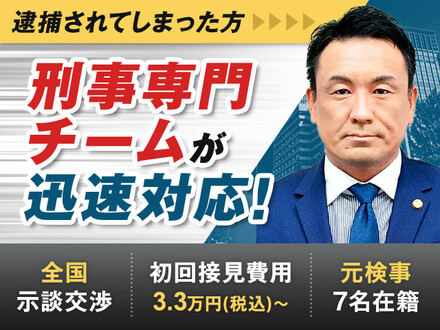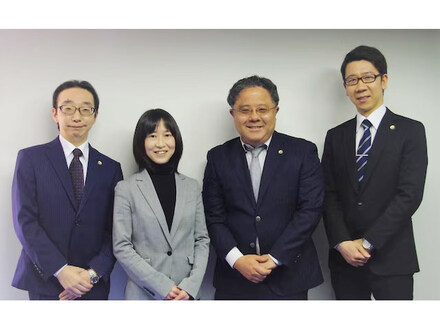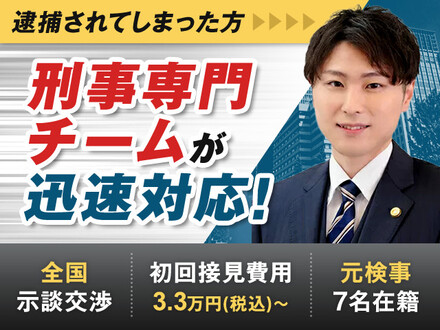強要罪とは、「暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことをおこなわせる犯罪」です。
脅迫罪や傷害罪などと比べて馴染みのない罪名かもしれませんが、身近に起こり得る犯罪で、刑罰は懲役3年以下の懲役刑しかありません。
また、未遂についても規定があるため、相手が目的の行為をしなかったケースでも罰せられる可能性があります。
特に最近では、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された地域において、スーパーやコンビニなどの食料品店で従業員に対して大声でクレームをいう行為が見受けられます。
こうした行為について、消費者庁は強要罪や恐喝罪に該当する可能性があると指摘しています。
本記事では、強要罪とはどのような罪なのか、成立するための要件や類似犯罪との違い、逮捕されてしまった場合の対処法について解説します。
自分やご家族が強要罪で逮捕されてしまった方へ
強要罪とは、「暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことをおこなわせる犯罪」です。
身近でも起こり得る犯罪で、刑罰は懲役3年以下の懲役刑しかありません。
ご家族や自身が刑事事件の当事者になった場合、弁護士に依頼する事をおすすめします。
弁護士であれば、次のような弁護活動を効果的におこなえます。
- 被害者と示談して処分の軽減を目指せる
- 取調べの受け方についてアドバイスがもらえる
- 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決などが望める
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)では、刑事事件に注力している弁護士を掲載しています。
無料相談ができる法律事務所もありますので、お気軽にご相談ください。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第三者に開示されることはありません。
安心して相談いただけます。
引用元:弁護士職務基本規程第23条
|
強要罪とは
強要罪とは、暴力や脅迫などを用いて、本来おこなう義務のないことを相手に強要させた場合に成立する犯罪です。
以下で詳しく見ていきましょう。
刑法第223条で定められた犯罪
強要罪については、刑法第223条において、以下のように定められています。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
引用元:刑法第223条|e-Gov
このように、本人または親族の「生命・身体・自由・名誉・財産」に対して害を加える旨を告知し、脅迫によって義務のない行為を強制した場合には、強要罪が成立します。
たとえば、男性客が店員に対して「土下座しなければ殴る」と怒鳴り、土下座を強要した場合、土下座は本来義務のない行為であるため、強要罪が成立します。
また、「土下座しなければ店長を殴る」といった脅迫については、店長が店員本人やその親族ではないため、条文上では対象外と考えられます。
しかし、店員がその発言によって心理的に圧迫され、義務のない行為を強いられた場合には、間接的に本人に対する脅迫と評価され、強要罪が成立する可能性もあります。
このように、誰に対して害を加える旨を告知したのかだけでなく、その脅迫が被害者にどのような影響を与えたのかも、強要罪の成立において重要なポイントとなります。
なお、脅迫によって目的の行為を実現できなかった場合でも、強要未遂罪として処罰されることもありますので、十分な注意が必要です。
強要罪の刑罰
強要罪の刑罰は、3年以下の懲役刑のみと定められています。
また、被害者が強要された行為を実際におこなわなかった場合でも、強要未遂罪が成立し、同様に3年以下の懲役刑が科されることになります。
このように、強要罪には罰金刑が規定されておらず、懲役刑のみとなるため、比較的重い刑罰といえます。
ただし、前科や前歴が考慮されることに加え、3年以下の懲役刑には執行猶予が付される可能性もあります。
そのため、初犯で強要罪のみで起訴された場合には、執行猶予付きの判決が下される可能性が高いといえるでしょう。
強要罪の成立要件
強要罪は日常生活でも発生しやすい犯罪のひとつであり、次のような場合に成立要件を満たす可能性があります。
- 生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知する
- 脅迫・暴行を用いる
- 相手に義務のない行為をさせる、または正当な権利の行使を妨害する
これらの要件について、以下で詳しく解説します。
生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知する
生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知すると、強要罪の成立要件を満たすことになります。
具体的には、次のような脅迫的な言動が該当します。
- 生命に対するもの:「殺すぞ」「突き落とすぞ」などと脅す
- 身体に対するもの:「殴るぞ」「蹴るぞ」などと暴行を加えるそぶりを見せる
- 自由に対するもの:「この部屋から出なさい」などと強制的に行動を制限する
- 名誉に対するもの:「職場にバラしてやる」などと社会的評価を下げる内容で脅す
- 財産に対するもの:「家に火をつけるぞ」などと財産への損害を示唆する
このような言葉や態度で相手を脅した場合、強要罪が成立する可能性があります。
日常のやり取りでも感情的になった際などには、不注意な発言をしてしまわないように、注意しましょう。
脅迫・暴行を用いる
実際に脅迫や暴行を用いた場合、強要罪が成立します。
たとえば、次のような行為は、強要罪における「脅迫」または「暴行」に該当する可能性があります。
- 脅迫の例:「上司に報告するぞ」「家族にばらすぞ」「訴えてやる」などと告げて、相手に精神的な圧力をかける
- 暴行の例:相手を何度も殴り続ける、胸ぐらをつかむ、机を叩いて威嚇するなど、直接的な暴力や威圧的な行動を取る
加害者がこれらの脅迫や暴行を用いて危害を加える意思を示して、相手に対して物理的・精神的な圧力を与えると、強要罪が成立することになります。
義務のない行為をさせる、権利行使を妨害する
上記の内容を踏まえて、「土下座しろ」「借金をチャラにしろ」といったように、暴行や脅迫を用いて被害者に義務のないことを強制したり、正当な権利の行使を妨げたりした場合には、強要罪が成立します。
強要罪の要件を満たす事例
強要罪の成立要件は、日常生活の中でも十分に発生し得るものであり、特別な場面に限った話ではありません。
たとえば、以下のような行為は、強要罪に問われる可能性があります。
- 土下座での謝罪要求:衣料品店の店員に対してクレームをつけ、「土下座で謝れ」と要求したうえで、その様子を撮影してSNSに投稿する。
- パワーハラスメント(パワハラ):職場の上司が部下に対して、「今月中にこの売上を達成できなかったら、地方に左遷するぞ」と脅して、達成困難なノルマや休日出勤を強要する。
- セクシャルハラスメント(セクハラ):職場の上司が部下に「付き合わなかったら昇進させない」と脅し、性的な関係やわいせつな行為を強要する。
- 酒類の強要によるハラスメント(酒ハラ):飲み会の場で、上司や先輩が「一気に飲め」「残すな」といった発言を繰り返し、部下や後輩に飲酒を強制する。
このように、強要罪の要件を満たす行為は、身近なシーンに潜んでいます。
加害者自身が「犯罪になるとは思っていなかった」と主張しても、行為の内容が強要罪の成立要件に該当すれば、処罰の対象となる点に注意しましょう。
強要罪と類似する犯罪との違い
強要罪が成立する場面では、場合によってはほかの犯罪も同時に成立することがあります。
ここでは、強要罪に類似する犯罪として「脅迫罪」や「恐喝罪」などと比較し、それぞれの違いについて解説します。
脅迫罪との違い
強要罪と合わせて言及されることの多い犯罪に「脅迫罪」があります。
刑法では、脅迫罪について以下のように規定されています。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用元:刑法第222条|e-Gov
脅迫罪も「相手に害を加えることを告げる」点では強要罪と共通していますが、それによって相手に義務のないことを無理させたかどうかが、両者の大きな違いです。
脅迫罪は、行為を強要しなくても、脅した時点で成立します。
また、脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」であり、強要罪に比べて刑罰は、比較的軽くなっています。
恐喝罪との違い
脅迫や暴行を用いて金品を要求した場合は、恐喝罪に該当する可能性があります。
刑法では、恐喝罪について以下のように規定されています。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法第249条|e-Gov
恐喝罪も「脅迫や暴行を用いて要求する」点では、強要罪と共通していますが、金品の提供を目的としているかどうかが両者の大きな違いです。
つまり、恐喝罪は、相手に害を加える旨を告げたうえで、金銭などを要求し、実際にそれを得ようとした場合に成立する犯罪です。
なお、恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」となっており、強要罪に比べて重い刑罰が科される可能性があります。
関連する犯罪との違い
脅迫罪や恐喝罪のほかにも、強要罪に関連する犯罪はいくつか存在します。
具体的には、以下のような犯罪です。
- 暴行罪
- 不同意性交等罪または不同意わいせつ罪
- 威力業務妨害罪
暴行罪とは、暴行を加えたものの、人を傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪です。
暴行を用いても、相手に義務のないことを無理やりさせなかった場合には、強要罪ではなく暴行罪が成立する可能性が高いでしょう。
また、脅迫や暴行を用いて、相手の同意なく性交やわいせつな行為をした場合は、不同意性交等罪または不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
このような性的な行為に関する強制は、強要罪とは異なり、より重い犯罪として独立して処罰されます。
そのほかにも、暴行や脅迫などの威力を用いて、店舗や企業などの業務を妨げた場合には、強要罪ではなく、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
これは、個人に対して義務のない行為を強制するのではなく、業務自体を妨げることを目的としている点が特徴です。
このように、犯行の内容や目的によっては、強要罪ではなく、関連したほかの犯罪が適用されることがあります。
場合によっては、強要罪よりも重い刑罰が科される可能性があるため、注意しましょう。
強要罪で逮捕される可能性
強要罪で逮捕される可能性は十分にあります。
ここでは、どのようなケースで逮捕に至るのか、そして逮捕された後にどのような手続きが進むのかについて詳しく見ていきましょう。
強要罪で逮捕されるケース
強要罪で現行犯逮捕されるケースは、実はそれほど多くありません。
多くの場合、以下のような状況に該当する場合に、後日逮捕される可能性が高くなります。
- 強要行為に悪質性がある場合
- 被疑者に前科・前歴がある場合
- ほかの犯罪(暴行罪や脅迫罪など)が同時に成立している場合
これらのケースでは、その場で現行犯逮捕されることは少なく、被害者が被害届を提出したことをきっかけに、後日逮捕に至るのが一般的です。
強要罪で逮捕された後の傾向
それでは、強要罪で逮捕された場合、その後どのような流れになるのでしょうか。
起訴率と量刑の傾向について解説します。
起訴率
検察統計(被疑事件の罪名別起訴人員および起訴率の累年比較)によると、令和元年の強要罪(脅迫罪をまとめた統計)における起訴率は、38.1%となっています。
この数値からわかるように、全体の約6割は不起訴となっており、近年は起訴率が低下傾向にあるようです。
引用元:被疑事件の罪名別起訴人員および起訴率の累年比較
量刑の傾向
強要罪は懲役刑のみが規定されており、罰金刑の選択肢はありません。
しかし、初犯で反省の態度がある場合や示談が成立している場合など、多くのケースでは執行猶予付きの判決が言い渡されます。
一方で、執行猶予中の再犯や、被害の重大性、悪質性が高い場合には、実刑判決となる可能性があります。
そのため、自身のケースでどのような量刑が見込まれるのかについては、早めに弁護士に相談し、調べてもらうほうが安心でしょう。
強要罪の時効
強要罪の公訴時効は3年と定められています(刑事訴訟法第250条)。
つまり、犯罪行為がおこなわれた時点から3年以内であれば、刑事事件として逮捕・起訴される可能性があるということです。
また、3年が経過して強要罪の時効が成立しても、民事事件としての時効は成立しているわけではありません。
そのため、刑事責任を問われなくても、被害者から損害賠償請求を受ける可能性が残っている点に注意しましょう。
強要罪で逮捕されてしまった場合の対処法
強要罪で逮捕されてしまった場合、刑事処分を軽くしたり、早期の釈放を目指すためには、どのように対処すべきでしょうか。
基本的には、次の3つの対処を取ることが効果的です。
- 弁護士に相談・依頼する
- 被害者と示談交渉を成立させる
- 反省の姿勢を示す
以下で、それぞれの対処法について詳しく解説します。
弁護士に相談・依頼する
強要罪で逮捕されてしまった場合、できるだけ早く弁護士に相談するのがおすすめです。
早い段階で弁護士に相談・依頼すれば、不起訴を獲得するための弁護活動を迅速におこなってもらえるからです。
実際、令和元年の統計によると、強要罪・脅迫罪の起訴率は約38%となっており、残りの約62%は、不起訴処分となっています。
弁護士に相談・依頼することで、不起訴による早期釈放の可能性を高めることができるでしょう。
被害者と示談を成立させる
強要罪で逮捕された場合、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。
示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まるほか、仮に起訴された場合でも、減刑が期待できるからです。
これは、示談を通じて被害者に謝罪の意を伝えることで、被害者の心情が和らぐことが多いためです。
ただし、逮捕されてしまうと、加害者本人が直接示談交渉をおこなうのは困難になります。
したがって、できるだけ早く弁護士に依頼し、代理人として示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
反省の姿勢を示す
強要罪で逮捕されてしまった場合は、反省の姿勢を示すことが大切です。
なぜなら、反省の有無は勾留期間やその後の刑罰に大きく影響するためです。
そのため、取調べ中に身に覚えのないことを問いただされた場合でも、「反省していない」と受け取られないように、反論の仕方には十分に注意しなければなりません。
なお、反省の姿勢をどう示せばよいか不安がある場合は、「当番弁護士制度」の活用をおすすめします。
この制度では、取調べ前に一度だけ無料で弁護士を呼ぶことができ、取調べへの対応などについてアドバイスを受けることが可能です。
まとめ
強要罪は、一見すると自分には関係のないような犯罪に思えますが、日常のちょっとした言動でも成立し得る身近な犯罪です。
自分にそのつもりがなくても、相手の受け取り方によっては加害者となる可能性もあるため、注意しましょう。
また、強要罪の法定刑は懲役刑のみとされており、罰金刑が規定されていない点でも、比較的重い処罰が科される犯罪といえます。
もっとも、被害者との示談が成立している場合には、早期の釈放や不起訴処分となる可能性も高まります。
万が一、強要罪で逮捕されてしまった場合は、「ベンナビ刑事事件」を活用し、できる限り早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、適切な弁護活動を受けることが重要です。