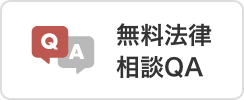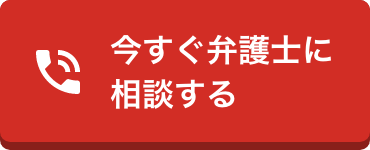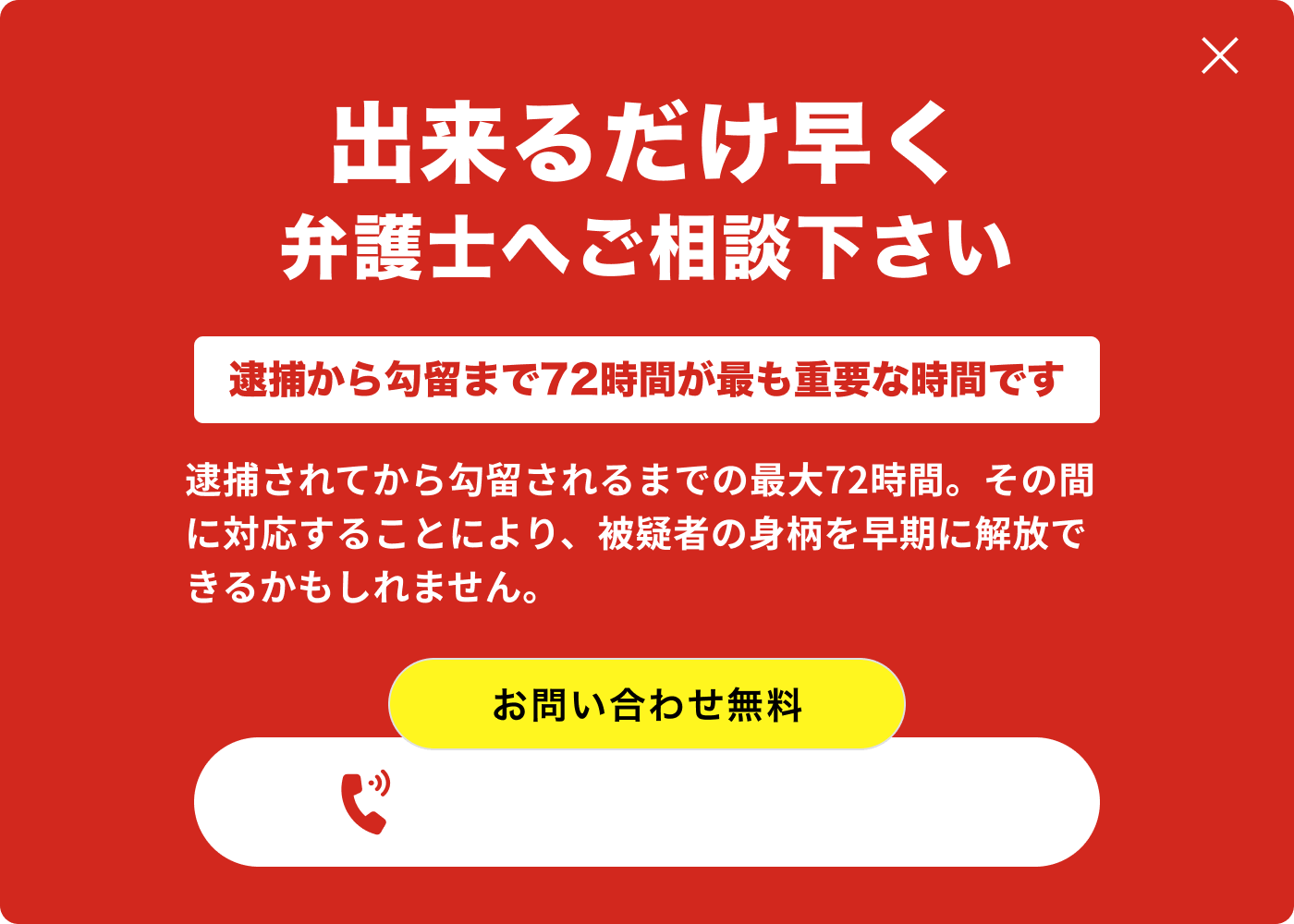【加害者限定】
【加害者限定】お急ぎの方へ

累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
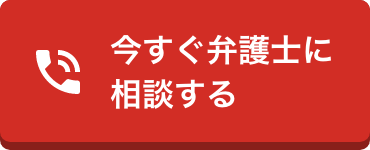
暴行罪とは、他人に暴力を振るった場合などに成立する犯罪です。しかし、なかには「傷害罪とは何が違うのか」「自分の場合はどちらが適用されるのか」など、詳しく知らないという人もいるでしょう。
暴行罪と傷害罪は似ている部分があるものの、成立する条件や罰則などは異なります。それぞれの違いを知っておくことで、自分の場合はどのような罰則が科されるのか把握でき、減刑獲得に向けて具体的なスケジュールを立てることができます。
暴行罪と傷害罪はどのような犯罪なのか、どのようなケースで適用されるのか、刑事処分を軽くするにはどうすればよいのかなど、この記事で暴行罪のポイントを押さえておきましょう。
ご家族が暴力事件を起こしてしまった方へ
逮捕され何も対策しないと、社会生活から長期間隔離されて、精神的な苦痛を味わうだけでなく、社会的信用を失い、経済的な損失を被る可能性があります。
家族が喧嘩で逮捕された方は、弁護士への依頼がおすすめです。
次のようなメリットがあります。
- 取り調べのアドバイスをうけ不利な供述調書の作成を防げる
- 勾留を防ぐなどして早期釈放を目指せる
- 被害者との示談交渉を任せられる
- 不起訴処分や執行猶予など軽い刑事処分を目指せる など
刑事事件は逮捕後72時間以内の対応が重要です。
逮捕後72時以内に、本人と会えるのは弁護士だけです。
初回相談が無料の弁護士事務所もあるので、まずは下記からお気軽にご相談ください。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|
暴行罪と傷害罪の違いとは?成立要件と罰則を確認
まずは、暴行罪・傷害罪のそれぞれについて、成立要件と罰則を確認しておきましょう。
暴行罪とは?成立要件と罰則
暴行罪は、他人に対して暴行を加えた場合に成立する犯罪です。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。
【引用】刑法第208条
暴行とは、他人に対する物理力の行使を意味します。例えば、殴る・蹴る・叩くといった暴力行為が典型例です。
さらに音・光・熱・冷気などを用いた物理力の行使も、暴行に当たり得ます。
ほかにも、裁判では以下のような行為についても暴行に当たると判断されています。
- 衣服を掴んで引っ張る行為
(大審院昭和8年4月15日判決|Westlaw Japan 文献番号1933WLJPCA04156004)
- 太鼓を連打して意識朦朧とした気分を与える、息を詰まらせる行為
(最高裁昭和29年8月20日判決|Westlaw Japan 文献番号1954WLJPCA08200009)
- 塩を振りかける行為
(福岡高裁昭和46年10月11日判決|Westlaw Japan 文献番号1971WLJPCA10110006)
- 驚かす目的で、数歩手前を狙って投石する行為
(東京高裁昭和25年6月10日判決|Westlaw Japan 文献番号1950WLJPCA06100004)
- 脅かす目的で、狭い室内で日本刀を振り回す行為
(最高裁昭和28年2月19日決定|Westlaw Japan 文献番号1953WLJPCA02190007)
条文上にも明記されているように、暴行罪は「暴行によって怪我を負わなかった場合」に限って成立します。被害者が怪我を負った場合には、次に解説する傷害罪が成立します。
なお、懲役刑や罰金刑などの刑事処分は、被害者との示談交渉を成立させることで軽くなる可能性があります。しかし、暴力事件の場合、被害者が怒りや恐怖を感じており、直接交渉に応じてくれないということもあります。
弁護士であれば、示談交渉の代行を依頼することが可能です。被害者も、第三者である弁護士が相手であれば交渉に応じてくれることもあり、少しでも示談成立の可能性を高めたいのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。
傷害罪とは?成立要件と罰則
傷害罪とは、他人の身体に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、極めて重い犯罪となっています。
(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【引用】刑法第204条
判例・通説では、傷害とは「他人の生理的機能を侵害する行為」であると解されています(大審院明治45年6月20日判決等)。例えば、殴る・蹴る・叩くなどの暴力により相手にケガをさせる行為が典型例です。
ほかにも、裁判では以下のような行為も該当すると判断されています。
- 嫌がらせ電話によって不安感を与え、精神を衰弱させる行為
(東京地裁昭和54年8月10日判決|Westlaw Japan 文献番号1979WLJPCA08100008)
- 騒音によって精神的ストレスを与え、睡眠障害に陥れる行為
(最高裁平成17年3月29日決定|Westlaw Japan 文献番号2005WLJPCA03290003)
- 性病であることを秘して性交渉等を行い、性病に感染させる行為
(最高裁昭和27年6月6日判決|Westlaw Japan 文献番号1952WLJPCA06060006)
ケガがない場合でも暴力罪は成立する?暴行罪と傷害罪の違い
暴行罪と傷害罪は、いずれも「他人の身体に対して不法に何らかのアクション(物理力の行使)をする」という内容の犯罪です。法定刑については、暴行罪よりも傷害罪の方が重たい内容になっています。
ここでは、暴行罪と傷害罪がどのような基準で区別されるのかについて、解説します。
ケガなどがなければ暴行罪、あれば傷害罪
暴行罪と傷害罪の違いは、被害者の生理的機能に対する侵害の有無です。
つまり、他人に対して不法に物理力を行使した結果、その人がケガをしたり病気に罹ったりした場合には傷害罪が成立します。
これに対して、被害者がケガをしたり病気に罹ったりしなかった場合には、暴行罪が成立します。
傷害罪の法定刑が暴行罪よりも重く定められている背景には、ケガや病気などの重大な結果を引き起こしたことについて、加害者を強く非難すべきという価値判断が存在するためと考えられます。
他人の髪を勝手に切ったら暴行罪?傷害罪?
暴行罪と傷害罪の境目に当たる事例としてよく挙げられるのが、「他人の髪を勝手に切った」というケースです。
他人の髪を勝手に切った場合、不法な物理力の行使があったことは明らかなので、暴行が認められることには異論がありません。
問題は、髪を切られたことが傷害に当たるのか当たらないのかという点です。
「傷害とは他人の生理的機能を侵害する行為」と解釈している判例・通説の立場からすると、髪を切られたことは傷害に該当しないという結論になります(大審院明治45年6月20日判決|Westlaw Japan 文献番号1912WLJPCA06206002)。
なぜなら、髪を切られたことによって、被害者がケガをしたり病気になったりするわけではないからです。つまり、他人の髪を勝手に切った場合、傷害罪ではなく暴行罪が成立します。
これに対して、「傷害とは身体の完全性の侵害である」と捉える学説も、一部では存在します。
この考え方によると、「他人の髪を勝手に切る行為は、被害者の身体の完全性を侵害する傷害に当たる」という結論になります。
暴行の故意しかなくても、傷害罪が成立し得る
犯罪の成立には、原則として、犯罪行為および結果についての故意(認識・認容)が必要となります(刑法38条1項)。
つまり暴行罪であれば「他人に対して暴行をすること」、傷害罪であれば「他人を傷害すること」について、故意が要求されるのが原則です。
しかし傷害罪については、傷害の故意犯だけでなく、暴行罪の結果的加重犯も含むと解されています。
結果的加重犯とは、犯人が意図していたものよりも重い犯罪結果が発生した場合に、重い結果についても処罰する犯罪類型を意味します。
つまり、被害者がケガをしたり病気に罹ったりした場合、犯人には暴行の故意しかなかったとしても傷害罪が成立するのです。
もちろん、わざとケガをさせた場合と、意図せずケガをさせてしまった場合では、前者の方がより悪質です。
そのため、実際の量刑には前者と後者で差が出ることが予想されますが、後者でも傷害罪が成立し得るということを理解しておきましょう。
暴行罪と傷害罪、逮捕される可能性の違いは?
暴行罪と傷害罪では、犯罪結果の重大性が異なりますので、当然逮捕される可能性にも差が生じます。
逮捕の一般的な要件
捜査機関が被疑者を逮捕するためには、原則として、裁判官が発行する逮捕令状が必要になります。
逮捕令状は、以下の2つの要件を満たす場合に発行されます。
-
逮捕の理由
「罪を犯した」と疑うに足りるだけの理由が必要です(刑事訴訟法199条1項)。
犯罪の嫌疑について、ある程度以上の段階まで確度が高まっていることが要求されます。
-
逮捕の必要性
「明らかに逮捕の必要がない」と認められる場合には、逮捕令状の請求は却下されます(刑事訴訟規則143条の3)。
逮捕の必要性は、「被疑者に逃亡または罪証隠滅のおそれがないか」という観点から主に審査が行われます。
その際、被疑者の年齢・境遇や、犯罪の軽重・態様などの事情が考慮されます。
また、裁判官による令状審査以前に、捜査機関が逮捕令状を請求するかどうかを判断する段階があります。
犯罪の内容が軽微なものであれば、そもそも逮捕令状の請求が行われない可能性が高くなります。
傷害罪は逮捕される可能性が高い
傷害罪は、理不尽にも被害者にケガや病気による苦痛を強いる重大な犯罪です。
法定刑も最長15年の懲役が認められており、窃盗や詐欺などの財産犯に比べても、重い犯罪として位置づけられます。
したがって、捜査機関が傷害罪の逮捕令状の発行を請求する可能性は、かなり高いと言うべきでしょう。
また、犯人性(真犯人かどうか)や暴行と傷害の因果関係などを裏付けるため、一定の証拠を収集することが必要です。
そのため、捜査が完了するまでは罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕令状の発行が認められる可能性も高いと言えます。
暴行罪でも逮捕されることがある
暴行罪は、被害者にケガや病気が発生していない分、傷害罪よりは訴追・処罰の必要性が低いと言えます。
法定刑は最長でも2年の懲役であり、刑法全体で見ても軽いものとなっています。
また、傷害の結果が発生していないことにより、どのような暴行があったのかを立証することが難しいのも特徴です。
そのため捜査機関としては、犯罪の嫌疑を固めるに至らず、逮捕令状の請求を行わないケースも想定されます。
ただし、暴行罪で逮捕されるケースがないわけでは決してありません。
特に、暴行現場での目撃者が複数存在する場合には、逮捕されてしまう可能性は大いにあると考えられます。
暴行罪・傷害罪の量刑はどのように決まる?
実際の刑事裁判の判決で言い渡される量刑は、犯罪の重大性や情状などを総合的に考慮して決定されます。
暴行罪や傷害罪の場合、以下のポイントが重点的に考慮されます。
- (傷害罪の場合)傷害の程度
- 暴行等の態様、悪質性
- 被害者の人数
- 犯行の動機、計画性
- 被害弁償(示談)の有無
- 前科の有無
- 反省の様子 など
未成年が暴力事件を起こした場合でも逮捕される?刑罰はどうなる?
未成年者が暴力事件を起こした場合、成人とは異なる手続きによって審理が行われるのが原則です。
しかし、特に悪質な事案では、未成年者が成人と同じ刑事裁判にかけられるケースもあります。
未成年者は少年審判による処分が原則
未成年者は、刑事手続きにおいては「少年※」と呼ばれています。
※2022年4月1日、民法上の成人年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、18歳・19歳の者は少年法上新たに「特定少年」として位置づけられ、成人と少年の中間的な取扱いが行われています。
少年が犯罪行為をした場合、まず家庭裁判所が少年の処分を審査します(少年審判)。
家庭裁判所の少年に対する処分のパターンは、以下のとおりです。
-
不処分・審判不開始
訓戒・指導・講習などを行うにとどめ、少年に対する処分を行わないという判断です。
-
保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督の下、社会の中で更生を促す処分です。
-
少年院送致
少年院に収容したうえで、矯正教育を行う処分です。
再非行・再犯のおそれが高い少年について、少年院送致が行われる傾向にあります。
-
児童自立支援施設送致
少年院よりも開放的な児童自立支援施設に収容したうえで、矯正教育を行う処分です。
少年が比較的低年齢の場合に、児童自立支援施設送致が選択される傾向にあります。
-
検察官送致
検察官に事件を戻し、少年を刑事裁判にかける処分です。
なお、少年が14歳未満の場合、検察官送致が行われることはありません。
検察官送致以外は、家庭裁判所において少年に対する処分が完結し、前科が付くこともありません。
少年は人格的な変化の余地が大きいため、教育的な見地から更生を促すべきという考え方により、少年審判による処分が原則となっているのです。
悪質なケースでは刑事裁判に付されることもある
禁錮以上の刑に当たる罪の事件については、少年を刑事裁判にかける「検察官送致」が選択されるケースもあります。
家庭裁判所は以下の事情を考慮したうえで、刑事裁判による裁きを受けさせるのが相当と判断された場合には、検察官送致を行います(少年法20条)。
特に傷害罪に当たる事案で、被害者に深刻な傷害を負わせたケース・連続犯罪のケースなどでは、検察官送致が選択される可能性が高いでしょう。
刑事裁判では、少年には「不定期刑」が科される
刑事裁判で少年に対して有期懲役・禁錮刑が言い渡される際には、不定期刑とする旨が定められています(少年法52条)。
成人の場合、「懲役3年」などと、確定した期間の刑が言い渡されます(定期刑)。
これに対して少年の場合、「懲役2年から3年」などのように、期間の範囲を定めて刑が言い渡されるのです(不定期刑)。
不定期刑の目的は、少年の人格的更生の状況を踏まえて、教育的見地から社会へ出すタイミングを見極められるようにする点にあります。
暴力事件の加害者になってしまったら示談成立を目指そう
暴行罪や傷害罪に当たる犯罪行為をしてしまった場合、重い刑事処分を受けてしまう可能性があります。
できる限り刑事処分を軽く済ませるためには、被害者との示談を成立させることが重要なポイントです。
被害者との示談が重要である理由
被害者との示談が成立したことは、検察官による起訴判断や裁判官による量刑判断において、被疑者・被告人に有利な情状として働きます。
示談に伴う金銭弁償によって一応の被害回復が図られたと見ることができますし、被害者の処罰感情も、示談によってある程度緩和されたと評価し得るからです。
示談するためには弁護士に依頼すべき
しかし被害者は、暴行・傷害の加害者との間で、直接示談交渉をすることを拒否することが多いです。
拒否する理由としては、理不尽な暴行・傷害について強い憤りを覚えている、被害当時の恐怖がフラッシュバックするなどが挙げられます。
また、そもそも加害者が逮捕・勾留されている場合には、被害者との間で自ら示談交渉を行うことはできません。
上記の理由から、暴行・傷害事件の示談交渉は、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
暴力事件の示談金はどのように決まる?相場は?
暴行・傷害事件の示談金額は、加害者・被害者間の協議(交渉)によって決まります。
基本的には、被害者に生じた客観的な損害額が、示談金額の目安となることが多いです。
暴行罪にとどまる場合、被害者はケガや病気をしていないので、精神的な損害を補填する慰謝料が中心となります。
金額的には、数十万円~100万円程度が相場です。
これに対して傷害罪の場合、治療費や後遺症に対する賠償が発生します。
示談金額はケースバイケースですが、数百万円~数千万円に及ぶこともあります。
最終的に示談がまとまるかどうかは、加害者が提示する示談金について、被害者がある程度納得できるかどうかにかかっています。
弁護士を通じて、真摯な謝罪を行いながら粘り強く交渉し、示談の成立を目指しましょう。
暴力事件の弁護士費用相場
暴行・傷害事件の弁護士費用(私選の場合)は、各弁護士が自由に設定しているため、弁護士によって異なります。
そのため一概には言えませんが、着手金20万円~50万円程度、報酬金20万円~50万円程度が相場と考えられます。
なお、国選弁護人を選任する場合、原則として費用負担は発生しません。
資産状況等によっては費用負担を求められるケースもありますが、私選の場合よりもかなり安くなるのが一般的です(被疑者国選:15~20万円程度、被告人国選:8万円程度)。
最後に|暴力事件を起こしてしまったら早めに弁護士へ相談を
基本的に、他人に暴力を振るった場合には暴行罪、暴力などにより他人が怪我を負った場合には傷害罪が成立します。いずれも懲役刑や罰金刑などが定められており、少しでも処分を軽くするためには被害者との示談成立が重要です。
しかし、暴力事件の場合、被害者が直接交渉に応じてくれないケースもあり、加害者が自ら交渉に臨んでも徒労に終わる恐れがあります。
少しでも示談成立の可能性を高めたいのであれば、弁護士に依頼しましょう。弁護士は依頼者の代理人として示談交渉でき、被害者としても、第三者である弁護士が相手であれば交渉に応じてくれることもあります。
初回相談無料の事務所も多くありますので、まずは一度詳しい話を聞いてみましょう。
ご家族が暴力事件を起こしてしまった方へ
逮捕され何も対策しないと、社会生活から長期間隔離されて、精神的な苦痛を味わうだけでなく、社会的信用を失い、経済的な損失を被る可能性があります。
家族が喧嘩で逮捕された方は、弁護士への依頼がおすすめです。
次のようなメリットがあります。
- 取り調べのアドバイスをうけ不利な供述調書の作成を防げる
- 勾留を防ぐなどして早期釈放を目指せる
- 被害者との示談交渉を任せられる
- 不起訴処分や執行猶予など軽い刑事処分を目指せる など
刑事事件は逮捕後72時間以内の対応が重要です。
逮捕後72時以内に、本人と会えるのは弁護士だけです。
初回相談が無料の弁護士事務所もあるので、まずは下記からお気軽にご相談ください。
|
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|