少年審判の当日の流れ|審理内容や事前準備のコツなどについても詳しく解説

- 「自分の子どもが事件を起こして少年審判がおこなわれることになった」
- 「少年審判とその後の流れについて詳しく知りたい」
自分の子どもが少年事件を起こし、このような悩みを抱えていませんか?
少年審判では、子どもが起こした事件についての処分が下されますが、対応を間違えると少年院送致などの重い処分が下される可能性もあります。
そのため、少年審判がおこなわれることがわかったら、できるだけ軽い処分を獲得するために準備を進めなければなりません。
そこで本記事では、少年審判や少年事件の流れ、少年事件を起こしたときに弁護士に早期相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
少年審判当日の流れ|処分を言い渡されるまでの8ステップ
まずは、少年事件について家庭裁判所で審判がおこなわれる流れを解説します。
1.人定質問|本人かどうか確認される
少年審判では、冒頭に人定質問が実施されます。
人定質問とは、事件を起こした嫌疑をかけられている人物と実際に審判に出頭した少年が同一人物であるかを確かめる手続きのことです。
人定質問では、氏名・生年月日・住所・本籍地などが確認されます。
2.黙秘権の告知|話さなくてよい権利について伝えられる
次に、事件を起こした少年に対して黙秘権の告知がおこなわれます。
黙秘権とは、自分にとって不利益な供述を強要されないという憲法上保障された権利のことです。
話したくないことは話さなくてもよいですし、黙秘権を行使して沈黙をしたとしても、その沈黙を理由に不利益を被ることはありません。
3.非行事実の告知|非行の内容に間違いがないか確認される
人定質問が終了して黙秘権が告知されると、裁判官から非行事実の告知がおこなわれます。
これは、何について少年審判が開かれているのかを明示するためです。
4.少年による意見陳述|少年から非行事実に関する意見を聞く
非行事実の告知がおこなわれたタイミングで、裁判官から少年に対して、非行事実の内容に間違いがないか確認されます。
認める・認めない、黙秘権を行使するなど、どのような返答をすることも可能です。
ただし、認否の方向性が保護処分などの内容に影響を与える点に注意しましょう。
5.付添人による意見陳述|付添人から非行事実に関する意見を聞く
次に、少年の付添人に対して非行事実に関する意見を聞きます。
少年審判の付添人は、少年の人権を擁護して更生をサポートする役割を担いながら、少年の代弁者として意見を発信します。
付添人は、少年・保護者が直接選任する「私選付添人」、裁判所が職権で選ぶ「国選付添人」に区分されます。
付添人の資格に制限はありませんが、保護者や法定代理人などが付添人になるには裁判所の許可が必要です。
そのため、付添人には裁判所の許可なく就任できる弁護士が就くことが多いです。
6.少年・保護者に対する質問|裁判官、調査官、付添人が質問をする
裁判官、調査官、付添人から、少年とその保護者に対して質問がおこなわれます。
少年や保護者に対する質問では、少年が事件のことをどの程度反省しているのか、更生に向けた意欲はあるのか、少年の社会復帰を支える環境は整っているのか、などの事情について聴取されます。
7.少年による最終陳述|最後に言っておきたいことについて聞かれる
処分の言い渡しの前に、少年による最終陳述がおこなわれます。
最終陳述のタイミングが、少年が処分が下される前に最後に発言できる機会です。
8.最終的な処分の言い渡し|裁判官からどの処分になるか伝えられる
最終陳述が終わると、最終的に裁判官から処分内容が言い渡されます。
少年審判で言い渡される処分の種類や少年審判に関連して下される処分としては、以下のものが挙げられます。
| 処分の種類 | 処分の概要 |
|---|---|
| 審判不開始決定 | 少年事件の態様が軽微で、教育的な働きかけだけで再非行のおそれがないと判断される場合に、少年審判を開かずに当該事件を終結させる決定。 |
| 不処分決定 | 少年審判を経た結果、さまざまな教育的な働きかけによって再非行のおそれがないと判断された場合や、少年が事件を起こしたとは認められない場合に、処分をせずに当該事件を終結させる決定。 |
| 保護観察決定 | 非行を働いた少年を施設に入所させずに通常の社会生活を送らせながら、保護観察所(保護観察官・保護司)の指導監督を受けて改善・更生・社会復帰を目指す決定。 |
| 少年院送致決定 | 審判の結果、再非行に及ぶ危険性が高く、通常の社会生活を送りながらの更生が難しいと判断される場合に、当該少年を少年院に収容して矯正教育を受けさせる決定。 |
| 児童自立支援施設送致決定・児童養護施設送致決定 | 非行を働いた少年が比較的低年齢の事案で、少年院送致をするほどの悪質性が認められない場合に、少年院よりも解放的な福祉施設(児童自立支援施設・児童養護施設)で生活指導を受けさせる決定。 |
| 知事又は児童相談所長送致決定 | 少年院などの施設に送致をして更生改善を目指すのではなく、児童福祉法の理念にしたがって児童福祉機関の指導に委ねる。 |
| 試験観察 | 少年審判で最終的な処分内容を決定する前に、一定期間、少年の行動や生活の様子を観察するための中間処分のこと。民間施設に身柄を預けて補導・指導させることもある。 |
| 検察官送致決定 | 少年審判の結果、事件の内容、少年の心身の成熟度、性格、非行歴、家庭環境などの諸般の事情を総合的に考慮したうえで、保護処分ではなく刑事処分が適当だと判断される場合に、刑事裁判を受けさせる目的で検察官に事件を送致する決定。 |
※保護観察決定、少年院送致決定、児童自立支援施設送致決定、児童養護施設送致決定は、まとめて「保護処分」と呼ばれます。
なお、家庭裁判所は必要に応じて、少年の保護者に対して非行を防止するための措置を取ることがあります。
また、少年審判で言い渡された処分については、重大な事実誤認や著しく不当な処分であることを理由に2週間以内に抗告することが可能です。
少年審判の流れの中で審理されることになる主な内容
少年審判における審理事項は、以下の2点です。
- 非行事実
- 要保護性
わかりやすく表現すると、非行事実の要件は「刑事事件における構成要件該当性」、要保護性の要件は「刑事裁判における情状要素」に位置づけられます。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1.非行事実|非行の有無や内容などについて審理される
少年に対して保護処分などを下すためには、「少年が非行に及んだ」という客観的事実が存在しなければいけません。
そのため、少年審判でもさまざまな証拠に基づき、非行事実の有無・内容について審理がおこなわれます。
たとえば、事実認定について必要があれば検察官が出席することもあります。
また、裁判所は、保護事件の性質に反しない限り、証人尋問・鑑定・通訳・翻訳・検証・押収・捜索を実施可能です。
2.要保護性|再非行を防止する必要性について審理される
少年審判では、要保護性の審理もおこなわれます。
要保護性とは、当該少年の再犯可能性のことです。
再犯するリスクが高いほど、要保護性があると判断されやすくなります。
要保護性の有無は、以下3つの要素から判断されます。
- 犯罪的危険性:生活、環境などが原因で、当該少年が再犯に及ぶリスクがあるか否か
- 矯正可能性:保護処分による矯正教育によって犯罪的危険性を除去できるか否か
- 保護相当性:他の決定に比べて、当該少年の改善更生にとって保護処分が適当か否か
たとえば、非行事実が悪質な内容であったとしても、被害者との間で示談が成立しており、少年本人自身が非常に反省をしている、かつ、更生・社会復帰に向けた家族の手厚いサポート体制が整っているのなら、要保護性は低いと判断されやすいでしょう。
その結果として、少年院送致のような重い保護処分ではなく、保護観察決定や不処分決定などを獲得しやすくなる可能性もあります。
一方、非行事実自体は軽微な内容であったとしても、少年を取り巻く生活環境に問題があり、反省の態度も全く見えないなら、要保護性が高いと判断されて、重い保護処分が下されかねません。
少年審判当日の流れをできる限り有利に進めるための3つのポイント
少年事件は刑事事件と比べて教育的・福祉的な観点が重視されますが、少年院送致などの重い保護処分が下される可能性があります。
少年院送致などの重い保護処分が下されると、学校生活や社会生活から隔離されるので、社会復帰しにくくなってしまいます。
そのため、少年審判にかけられた場合には、可能な限り軽い処分・決定を獲得するための防御活動が不可欠です。
ここでは、少年審判でできるだけ有利な結果を得るためのポイントを3つ解説します。
1.少年は非行内容について深く反省する
少年審判における審理対象のひとつである「要保護性」の要件では、少年が非行事実に対して真摯に反省をしているかがチェックされます。
反省をしているのなら再犯可能性が低いですし、反省をしていなければ再犯可能性が高いからです。
反省の態度を示すのは、少年審判当日だけでは足りません。
少年審判当日に至るまでの段階で、非行事件の被害者側に対して謝罪の旨を伝えたり、示談交渉を成立させて示談金を差し入れたりするなど、事前準備が必要です。
また、自分の交友関係を見直したり、生活スタイルを改善したりすることで、更生の意欲があることをアピールできるでしょう。
2.保護者も十分質問の対策をしておく
少年審判では、裁判官・調査官・付添人から少年の保護者に対して質問が実施されます。
保護者に対して質問が実施されるのは、保護者の関わり方・考え方が少年の更生にとって大きな影響を与えるからです。
保護者が熱心に少年の更生を支援できる状況だとアピールできれば、少年審判で有利な判断を引き出せるでしょう。
たとえば、少年審判では保護者に対して以下のような質問がされます。
- 保護者から見た少年の性格、家庭や学校での過ごし方、交友関係
- 保護者自身は少年がなぜ今回の非行に及んだと考えているか
- 少年の再犯を防止して更生を図るために親として何ができると考えているか
少年審判の場面でいきなり質問に回答するのは簡単ではありません。
少年審判で裁判官から納得を引き出すには、裁判官からの質問を想定して、事前に回答の練習をしておくべきでしょう。
3.少年事件が得意な弁護士に依頼する
少年審判にかけられるときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をすることを強くおすすめします。
刑事事件や少年事件を得意とする弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得ることができます。
- 裁判官から何を質問されるのかなどを予測して、質疑応答の事前練習ができる
- 保護処分などを回避するために役立つ供述方針を決定してくれる
- 被害者との間で早期に示談交渉を進めてくれる
- 観護措置などの身柄拘束処分の回避や期間短縮を目指してくれる
- 納得できない保護処分に対しては速やかに抗告などの措置をとってくれる
- 少年本人が本当の意味で更生できるような環境を構築するサポートをしてくれる
ベンナビ刑事事件では、少年審判の経験が豊富な弁護士を多数紹介中です。
事前準備に着手するタイミングが早いほど有利な解決結果を得やすくなります。
少年が事件を起こしたときには、速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。
少年審判の流れに関するよくある質問
さいごに、少年審判の流れについてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
Q.事件発生から少年審判当日までの流れは?
少年が非行を働いた場合、原則として以下のような流れで手続きが進みます。
- 通報などをきっかけに警察が捜査活動を開始する
- 刑事未成年であることが判明したタイミングで児童相談所に通告される
- 児童相談所から家庭裁判所に送致される
- 家庭裁判所が観護措置を下す
- 家庭裁判所で少年審判が開かれる
- 家庭裁判所の少年審判で最終的な判断が下される
- 検察官送致された場合には、刑事裁判手続きに移行する
ただし、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の種別や、犯した罪の重さ・内容次第で手続きの流れは異なります。
適切な防御活動をおこなうには、警察が捜査活動を開始したタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
Q.事件発生から少年審判が始まるまでの期間はどれくらいか?
少年が事件を起こしてから少年審判が始まるまでの期間は、ケースごとに異なります。
たとえば、先行して警察に逮捕・勾留された場合には、逮捕段階で72時間以内、勾留段階で10日間~最長20日間の身柄拘束期間が発生します。
逮捕されない事案でも、在宅事件として一定期間捜査活動に対応しなければいけません。
また、家庭裁判所に少年事件が送致されたあと、観護措置が下されたときには、少年審判が開始するまで、約4週間程度のあいだ少年鑑別所に収容されます。
事件の内容次第ですが、少年事件が発覚してから少年審判が開始するまでには数週間以上の期間を要することが多いでしょう。
Q.少年審判の回数や当日の審理にかかる時間はどれくらいか?
少年審判当日は、1時間程度で審理が終了するのが一般的です。
また、否認事件でない限り少年審判は1回で終了します。
さいごに|少年事件・少年審判が得意な弁護士はベンナビ刑事事件で探そう
少年が非行に及んだり事件を起こしたりしたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談をしてください。
未成年が事件を起こしたとしても、事件の深刻さや少年を取り巻く環境や態度次第では、一定期間身柄拘束をされたうえで少年院送致などの重い処分を科されかねないからです。
早期に弁護士へ相談すれば、被害者との示談交渉をスピーディーに進められるうえ、軽い処分内容を獲得できる可能性が高まります。
ベンナビ刑事事件では、刑事事件や少年事件などを得意とする弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、子どもが何かしらの事件を起こしたときには、ぜひ一度お問い合わせください。

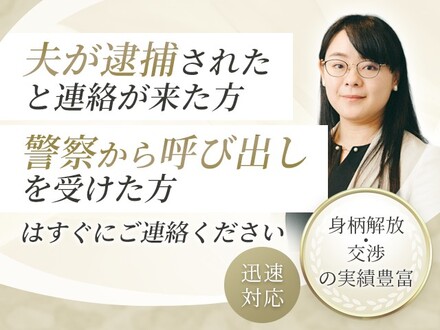
【ご家族が突然逮捕されてしまった方はすぐにご相談ください】仕事への影響を最小限にしたい/職場に知られずに解決したいなど迅速な身柄解放に向けてきめ細やかにサポートします【初回相談料30分:5500円】
事務所詳細を見る
【即日対応!弁護士直通!】【初回相談0円】逮捕されたり警察の呼び出しを受けたりしたらすぐ相談ください!◆性犯罪(不同意わいせつ・盗撮・痴漢など)/暴行・傷害/児童ポルノなど、解決実績の豊富な弁護士がスピード対応します!《当日すぐに面談できます!》
事務所詳細を見る
【早期釈放/不起訴実績多数】加害者側・被害者側双方で、示談交渉対応多数◆痴漢・盗撮/暴行傷害/事故/窃盗など迷う前に電話◆早めの相談で選択肢を広げることが可能◎◆【即日接見で安心をお届け】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
日本の司法取引制度は、2018年6月に施行されたばかりであり、事件解決に向けて重要な供述を得るための活用が期待されています。本記事では、日本の司法取...
-
窃盗事件を起こした場合は、いつか逮捕されるのではないかと不安になるものです。そのなかで、時効の完成まで逃げ切ろうと考えている人もいるのではないでしょ...
-
犯罪を犯して起訴された場合は、通常、刑事裁判に移行します。刑事裁判は有罪・無罪や刑罰が決定する重要な場になるので、先を見据えてしっかりと準備しておく...
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
歩いていたら突然声をかけられて、職務質問をされたことがある方も多いでしょう。本記事では、職務質問を拒否できるか否か、職務質問をスムーズに終わらせる方...
-
正当な理由なく他人の建物に侵入すると建造物侵入罪にあたります。住居侵入罪との違い、構成要件、「侵入」や「正当な理由」の定義、刑罰、逮捕後の流れ、弁護...
-
刑法の多くの罪に罰金刑が定められており、犯罪を起こして刑事罰を受けることになると有罪判決のうち約80%以上が罰金刑です。判決を受ける可能性が高い刑事...
-
自首(じしゅ)とは、犯罪が起きた事や犯人が分かっていない段階で、犯人自らが捜査機関(おもに警察官)に犯罪事実を申告し、処分を求めることを言います。
-
本記事では、心神喪失状態で起こした事件について、なぜ無罪になるのかについて詳しく解説します。 また、心神喪失で無罪になったあとの手続きの流れや、心...
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る























































