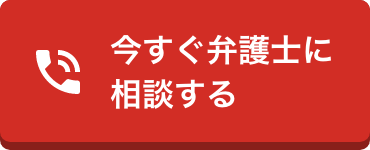任意同行とは?強制?拒否するリスクや求められたときの対処法とは


任意同行(にんいどうこう)とは、警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある人物を取調べるため、捜査官に同行して警察署などへ出頭させることをいいます。
刑事訴訟法198条では、取り調べについて
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
とあり、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を求められても拒否をすることが可能ですので、任意の取調べとなります。
今回は犯罪の嫌疑をかけれている人物に対して行われる、任意同行についてご説明していきます。
|
刑事事件はスピードが命です! |
任意同行とは|逮捕や事情聴取との違い
それでは、さっそくですが任意同行についてご説明していきたいと思います。
任意同行の経緯は2種類
任意同行については、上記で述べた刑事訴訟法198条と、警察官職務執行法第2条に明記されています。
すでに犯罪の嫌疑のある人物に対する任意同行
刑事訴訟法198条では、
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
とあり、逮捕・勾留されていない被疑者に関しては出頭を拒み、出頭しても取り調べを退去することができます。つまり、出頭は任意である事から任意同行と言われています。
警察などの捜査期間が捜査を進めていくうえで、被疑者の特定がなされた後に任意同行が行われますが、逮捕・勾留されていない時点での取調べには応じなくてもいいのです。
職務質問からの任意同行
また、警察官職務執行法にも任意同行についての記載があります。警察官職務執行法2条2項には、
その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
とあります。
警察による職務質問が行われその場で職務質問をすることが本人の利益を害したり交通の妨げになるような場合は、近くの警察署や派出所等に同行を求めることができるとありますが、こちらも任意同行となります。職務質問については後述します。
任意同行は拒否ができる
このように、任意同行は“任意”であることから、拒否することも可能です。本人の意思を制圧して警察署に連行することは逮捕と同等になりますが、警察が被疑者を逮捕するにはいくつかの条件や手順を踏む必要があります。
ただ、後述しますが、任意同行はすでに逮捕の直前の段階で行われていることも多く、任意同行を拒否したことにより、「逃亡・証拠隠滅の恐れあり」と評価されて、逮捕されてしまうという事態にもなる場合も少なからずあります。
【関連記事】
▶「逮捕に関する全て|逮捕の種類と逮捕後の流れと問題点」
逮捕・勾留後の取り調べ
逮捕・勾留後に取調べを受けることがありますが、こちらは身柄を拘束されている身であるため、退去することはできません。実質強制的な取調べになりますが、容疑を否認したり、黙秘権を使うことは可能です。
ただ、容疑の否認や黙秘をしていることにより、勾留期間は長引くことになるでしょうし、むやみやたらに否認をしていると、犯行に対して反省していないとも捉えられますので、逮捕後の取り調べには、きちんと計画的に応じていく必要があります。
【関連記事】
▶「取り調べの実態と有効に進めていくための3つの方法」
▶「黙秘権とは|利用する際の注意点と知っておくべきデメリット」
事情聴取との違い
任意同行・取調べと似た内容に「事情聴取」という言葉も聞いたことがあるでしょう。事情聴取は主に犯罪の被害者や告発者、目撃者などに行なう取調べの事で、出頭も任意です。
ただ、厳密には事情聴取という用語は使われず、刑事訴訟法ではこの事情聴取のことも取調べとなります。
職務質問との違い
職務質問は、犯罪を起こしたか又は起こし得ると疑うだけの相当の理由がある人物を呼び止め質問を行なうことです。職務質問に応じることも任意ですので、拒否することは可能です。
しかし、実際として拒否しようとすればするほど、犯罪の疑いが高まり、警察官もしつこく追及してなかなか解放されません。
任意同行は逮捕間近が多い|任意同行が行われる理由
お伝えしたように、任意同行とは逮捕・勾留されていない時点での任意の取調べです。拒否することができるとは法律上はなっていますが、実際のところ任意同行はどのように行なわれているのでしょうか。
逮捕直前の任意同行が多い
まず、任意同行を求められるということは、実際すでにその被疑者の容疑が固まっており、逮捕直前であることが多いです。逮捕前に任意同行が行われる理由としては以下の内容が考えられます。
任意同行が行われる理由
逮捕をスムーズに行うため
お伝えのように、逮捕直前で任意同行が行われることが多いのですが、その理由としては、警察が逮捕をスムーズに行う為に任意同行を行なっていることが考えられます。
逮捕と言えば、逮捕状をもって被疑者の自宅や職場などに向かうことを思い浮かべますが、当然警察が向かった時に本人がいないということもあるでしょう。
事前に任意同行によって警察署に被疑者を呼び出しておくことで、逮捕をスムーズに行います。
また、通常逮捕の場合、事前に逮捕状が必要になりますが、任意同行で被疑者を呼び出している間に逮捕の手続きを警察が進めていることもあります。
被疑者への配慮の為
また、被疑者に対しての配慮もあると言われています。
逮捕を行なう際は、自宅や職場に警察官が駆け付けることが多いのですが、そこで逮捕することで家族や職場の人、近隣の人などに逮捕される場面を見られないような配慮があるとも言われています。
任意同行で警察署に呼び、そこで改めて被疑者を逮捕するのです。
任意同行を拒否するとどうなるのか?|任意同行への対処法
このように、任意同行は任意であるため、拒否することはできるのですが、実際に任意同行を拒否した場合はどのようになっていくのでしょうか。
状況にはよるでしょうが、任意同行を拒んだ場合と、任意同行を求められた時の対処法についてご説明していきます。
拒否することで逮捕されることも
お伝えのように、任意同行が行われる時点ですでに逮捕の直前に来ていることが多いです。犯罪を起こした自覚がある状態で任意同行を求められているのであれば、拒否することにより逮捕される可能性もあります。
また、任意同行を拒んだことにより、自宅や職場などに警察が訪れることや、警察の印象が悪くなるなどの事も考えられます。任意ではありますが、基本的には任意同行には応じるようにして下さい。
弁護士を同行させることも可能
そうはいっても、逮捕されるかもしれない状態で自分一人で警察署などに出頭し、取調べに応じることも不安でしょう。事件や警察の判断によっては拒否されることもありますが、弁護士に同行してもらうことも可能です。
任意同行によって今後どうなるかは、状況による部分もありますし、弁護士に同行してもらうにもお金がかかってしまいます。もしも任意同行を求められているようでしたらまずは弁護士に個別に相談してみて、具体的な対処法を聞いてみましょう。
以下のリンクからお近くの刑事事件が得意な弁護士を探すことができますし、事務所によっては無料相談が可能な弁護士もいます。弁護士探しにお役立ていただければと思います。
まとめ
任意同行はあくまでも任意ですが、実際には逮捕が直前に迫っていることも考えられます。
任意同行を求められたのであれば、早い段階で弁護士に相談してみることをおすすめします。


【弁護士直通ダイアル|夜間・休日対応可】早期の身柄釈放へ迅速対応!◆痴漢・盗撮・性犯罪はすぐにご相談を!取り調べ/逮捕から1~2日での対応が重要です!万引き/窃盗/薬物/詐欺/オーバーステイなどの外国人事件も取り扱い多数
事務所詳細を見る
【初回相談無料|オンライン面談対応可】外国人事件の実績豊富≪中国籍の方歓迎|可提供中文服务≫/日本での生活を守るためにも早めにご相談を/入管法に知見のある弁護士が刑事弁護と在留資格の両面からサポート【無罪獲得実績あり】
事務所詳細を見る
◤逮捕直後の行動が今後を左右します ◢24時間対応で即日接見可能!殺人・裁判員裁判などの複雑な問題も対応可能◎解決実績200件以上・身柄事件を中心に在宅事件も迅速に対応いたします
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡



刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
立ちんぼ行為は、売る側・買う側の双方に法的リスクがあります。売春自体に罰則はなくても、勧誘や客待ちは法令違反となるおそれがあります。相手が未成年なら...
-
たとえ犯行から3ヵ月が経過していても、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕される可能性は十分にあります。逮...
-
エアドロ痴漢は、AirDropを悪用して卑わいな画像や動画を送り付ける重大な犯罪です。迷惑防止条例違反や刑法175条に問われ、実際に逮捕事例も報告さ...
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
余罪があることを自覚している場合、余罪捜査がどこまで進められるのか、大きな不安を抱えながら毎日を過ごすことになります。本記事では、余罪が発覚しやすい...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
ベンナビ刑事事件では、24時間盗撮事件に強い弁護士に無料で電話相談ができます。47都道府県全国からの相談に対応。盗撮事件に強い弁護士に無料相談する方...
-
刑法第39条には『刑事責任能力のない人は処罰の対象外とする、または、処罰を軽減する』という記述がされています。刑法第39条とは具体的にどういうものな...
-
手頃な費用でいざというとき頼れる弁護士費用保険ですが、実は犯罪に巻き込まれてしまった(刑事事件の被害者となってしまった)場合も役立ちます。弁護士費用...
-
本記事では、どのようなときに緊急逮捕されるのか、緊急逮捕をされるとどうなるのかなどについて、通常逮捕や現行犯逮捕との比較を交えながら解説していきます...
-
逮捕された場合、不起訴を期待するのは当然のことです。しかし、不起訴を勝ち取ったとしても、なんらかの不利益が生じるのではないかと不安に感じている方もい...
-
緊急避難とは、刑法で定められた違法性阻却事由の一つです。正当防衛も違法性阻却事由という点では同じですが、緊急避難と正当防衛は成立要件が異なります。具...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
ナンパをしたことで通報され、警察に逮捕された事例はいくつもあります。本記事では、ナンパで問われる可能性がある罪にはどのようなものがあるのか、どこまで...
-
在宅事件とは、被疑者が勾留による身柄拘束をされないまま捜査が進められる刑事事件です。この記事では、在宅事件とはどのようなもので、どういったケースで選...
-
本記事では執行猶予期間中の方に向けて、執行猶予の取り消しについての定義・意味、執行猶予が取り消しになる2つのパターン、再犯をして執行猶予が取り消しに...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る