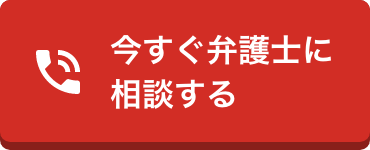少年事件は弁護士に相談を|つけないリスク、弁護士費用を解決

20歳未満の少年が起こした事件についても、弁護士に依頼することは可能です。
しかし、少年事件において、弁護士(付添人)が選任されるケースは、下記のとおり、まだまだ少ないのが現状となっています。
※少年審判では、刑事裁判のような「弁護人」という制度はなく、少年の権利を擁護する役割を担う「付添人」を選任できることになっています。少年法では、付添人は弁護士に限定されていませんが、実際はその大半が弁護士です。
また、少年事件で逮捕・勾留されてしまうと、成人とは異なる手続きを経て処分されます。
このとき、少年は未熟であるがゆえに、不利な状況に追い込まれることも少なくありません。
そのため、少年事件は成人の刑事事件以上に、弁護士の支援が求められます。
本記事では、少年事件において弁護士をつけるべき理由や、弁護士費用の目安などについて解説します。
少年事件で弁護士をつけるかどうか検討している方は、ぜひ参考にしてください。
少年事件とは
少年事件とは、少年法の対象となる非行少年が起こした犯罪や非行などの事件を指します。
ここでいう非行少年とは、以下のいずれかの少年が対象です。
- 犯罪少年:14歳以上で刑法に違反する行為をした少年
- 触法少年:14歳未満で刑法に違反する行為をした少年
- ぐ犯少年:18歳未満で将来的に罪を犯すおそれのある行動をする少年
少年事件では14歳に満たない少年の行為は処罰されず、保護的な処置に留まります。
一方で、14歳以上の少年については、成人事件と同じく警察や検察官による捜査のあと、家庭裁判所に送致されるのが、通常です。
なお、2022年4月の少年法改正により、18歳・19歳の少年は「特定少年」として区別され、17歳以下の少年とは異なる特例が設けられました。
特定少年は民法上は成人ですが、刑事事件においては「特定少年」として少年法が適用されます。
特定少年が事件を起こした場合は、処分が厳しくなるとともに、原則的に検察官に送致する必要がある「原則逆送対象事件」の範囲も拡大されています。
少年事件に弁護士が必要な6つの理由
少年は未熟である一方で、将来性が高いため、成人以上に弁護士からのサポートを受けることが重要です。
ここでは、少年事件に弁護士をつけるべき6つの理由について解説します。
1.取調べ対応のアドバイスをおこなう
弁護士をつけることで、取調べに対する不安を和らげ、不利な供述が取られるのを防げます。
特に少年は、精神的に未熟であり、知識や判断能力も十分とはいえません。
そのため、捜査機関がその未熟さにつけ込み、都合のよい供述調書を作成しようとする可能性があります。
その結果、成人よりも不利な供述調書が作成されやすくなり、処分が重くなったり、保釈の時期が遅れたりするリスクが高まります。
少年にとって不利な調書を作成させないためにも、弁護士が少年と接見し、取調べにどのように対応すべきかアドバイスすることで不安を軽減し、適切な対応ができるようにサポートします。
2.早期釈放の可能性を高める
弁護士をつけることで、早期に釈放される可能性を高められます。
少年事件においても、14歳以上の少年は警察に逮捕され、勾留される可能性があります。
検察官が勾留を請求し、それを裁判官に認められると、最長で20日間にわたり身柄が拘束されます。
この長期の拘束は、学校の退学処分や会社からの解雇につながり、少年の将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
弁護士をつけることで、少年の勾留を阻止するために、検察官や裁判官に意見書を提出し、釈放を求めるための説得をおこなえます。
また裁判所に対して勾留決定の取消しを求める準抗告をおこなうことで、早期の釈放を目指します。
3.被害者と示談交渉を進める
弁護士をつけることで、被害者との示談交渉を早期に進めることができ、重大な処分を防ぐ可能性が高まります。
通常、加害者であるその少年やその家族が直接被害者に連絡することはできません。
しかし、弁護士を通じて検察に示談を申し入れることで、被害者の連絡先を教示される可能性があります。
その結果、被害者への謝罪や示談交渉を進めることが可能です。
ただし、成人の刑事事件とは異なり、少年事件では示談が成立したとしても、検察官が少年に嫌疑があると判断した場合、全件が家庭裁判所に送致されます。
これは、少年の未熟さや将来性を考慮し、今後の少年の健全な育成のためにどのような保護処分が必要であるかを家庭裁判所が調査・判断する必要があるためです。
4.家庭裁判所調査官に働きかける
弁護士は、家庭裁判所調査官に対しても積極的に働きかけることができます。
家庭裁判所調査官の役割は、少年が立ち直るのに必要な方策を検討し、その内容を「社会記録」としてまとめることです。
この社会記録には、「少年をどのような処分にするべきか」も記載されるため、弁護士は少年院送致を防ぐための提案や交渉、説得をおこないます。
また、弁護士は少年審判で付添人(つきそいにん)として弁護活動をおこなうことも可能です。
事実関係を認めている事件では、通常、審判までに少年の生活環境を整えたり、監督者を確保したりすることで、少年が少年院に入所しなくても更生できることを裁判官に説明します。
一方で、事実関係を争う事件では、少年に非行事実が認められないことを裁判官に主張します。
また、証人尋問や、少年への質問を通じて、少年に有利な証拠を示す弁護活動をおこないます。
5.退学処分の回避をサポートする
弁護士をつけることで、少年が退学処分を回避できるようにサポートします。
少年事件を起こしたことが学校に知られると、早期の自主退学が求められたり、退学処分となる可能性があります。
これにより、少年の将来に大きな影響を与えるおそれがあります。
弁護士は、少年が退学処分を回避できるように、警察や家庭裁判所の調査官に対して、現在通っている学校へ連絡しないように申し入れてくれます。
また、事件がすでに学校に知られている場合は、弁護士が学校の関係者と面談し、退学処分を避けるために働きかけてくれます。
6.更生のための環境を整備する
弁護士は、少年が更生できるよう環境の整備もおこないます。
少年事件で不起訴処分や保護観察処分を受けるためには、再非行の可能性が低いことを裁判官に示す必要があります。
そのため、弁護士は職場や学校に対して、不当な扱いを受けないよう働きかけるほか、親子関係がこじれている場合には、その関係を修復するための支援をおこないます。
また、交友関係に問題がある場合には、電話番号の変更などの対応を通じて、不良グループと距離を置くように助言します。
少年の更生環境を整えて、将来性があることを示すためにも、弁護士の支援が不可欠です。
少年事件の大まかな流れ
少年事件では「全件送致主義」といって、原則として全ての事件が家庭裁判所に送致されます。
また、捜査段階では、基本的に成人と同様の刑事手続(逮捕・勾留など)がとられますが、家庭裁判所に移った後は、少年法に則って審判などがおこなわれます。
少年事件の発生から審判までの大まかな流れについて見ていきましょう。
1.事件発生・捜査開始
事件が発生すると、警察や検察は捜査を開始します。
少年が犯罪を起こした場合でも、成人の刑事事件と同様に、証拠の収集や事情聴取がおこなわれます。
2.逮捕・勾留(必要な場合)
事件の状況からやむを得ない場合には、少年であっても逮捕されることがあります。
逮捕後、警察は48時間以内に検察官に身体拘束をしたまま事件を送致するかを判断します。
そして、事件の送致を受けた検察は24時間以内に、裁判所に対して勾留請求するかどうかを判断します。
この逮捕から勾留までの流れは、成人の刑事事件と大きく変わりません。
勾留請求のあとは、裁判官が少年に話を聞く「勾留質問」をおこなって、少年を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が少年の勾留を決定すると、最長20日間にわたり勾留されます。
そして、この間にも、警察や検察による捜査が継続されます。
3.家庭裁判所への送致(全件送致)
捜査の結果、検察官が少年に嫌疑があると判断した場合は、すべての事件が家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。
法務省が発表した「令和3年版 犯罪白書」を見ると、少年犯罪の新規受理数4万5,436人のうち、家裁送致数が4万3,015人で、送致率は94.7%と高い確率で送致されていることがわかります。
家庭裁判所へ送致されると、まず裁判官が観護措置をとるかどうかの判断をします。
観護措置がとられた場合には,通常は、その日のうちに少年(鑑別対象者)の鑑別などを専門におこなう少年鑑別所に収容されることが多く、原則として2週間・例外的に4週間(最長8週間)にわたり、少年鑑別所に収容されます(実務上は4週間弱の期間となることが多いです)。
その間に少年は、鑑別や観護処遇などを受けます。
4.観護処置(少年鑑別所での鑑別)
少年鑑別所でおこなわれる鑑別(収容審判鑑別)とは、非行に影響を与えた要因を明らかにして、その要因の改善に寄与する処遇の指針を立てるための手続きです。
具体的には、担当技官による鑑別面接や心理検査などのほかに、少年の行動を確認するための行動観察や意図的な行動観察などが実施されます。
5.家庭裁判所調査官による調査
家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所で取り扱う家事事件や少年事件などの調査の専門家です。
少年事件では、非行に至った動機や原因などを調査するために、少年やその保護者などと面会したり、少年の資質や性格を把握するために心理テストを実施したりします。
また、少年鑑別所や児童相談所などとも連携しながら、少年が立ち直るための方策を検討し、それを社会記録という形でまとめて裁判官に報告します。
6.少年審判
少年審判は、原則として非公開でおこなわれます。
少年審判の目的は、少年に自分自身の過ちを自覚させて、更生させることにあります。
事案によっては少年が本当に非行をしたかどうかという、非行事実を争うこともあります。
そのうえで、家庭裁判所の裁判官は、その少年に必要な処分を言い渡します。
少年鑑別所に収容されている場合は、収容期間中におこなわれるのが一般的です。
少年事件における5つの処分
少年事件では「保護主義」という考え方のもとで、少年の性格や環境を改善するための処分が言い渡されます。
その主な処分内容には、不処分、保護観察処分、少年院送致、検察官送致の4つがあります。
ここでは、少年審判で言い渡される可能性がある処分について解説します。
1. 不処分
不処分とは、少年を処分しないという決定のことです。
非行事実が認められない場合だけでなく、非行事実が認められても、再非行のおそれがなく処分が必要ないと判断されたような場合、不処分となります。
なお、場合によってはそもそも審判を開くことなく、処分を受けない(審判不開始)場合があります。
2. 保護観察処分
保護観察処分とは、少年院などの施設に入所させることなく、社会の中で少年の更生を目指す決定のことです。
保護観察処分が決定された場合、少年は定期的に保護司と面接して近況を報告したり、指導監督を受けたりする必要があります。
なお、保護観察期間は20歳になるまで、または保護観察が解除されるまでとなっています。
3. 少年院送致
少年院送致とは、少年院で適切な矯正教育を受けさせるための決定のことです。
再非行の可能性が高く、社会の中で更生を目指すのが難しい場合には、少年院送致の処分を受けることがあります。
少年院では少年が社会に復帰するために、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別支援指導といった矯正教育を受けることになります。
4. 検察官送致
検察官送致とは、少年を検察に送致(いわゆる逆送)するという決定のことです。
少年が起こした事件や内容、心身の成熟度、性格、非行性などを考慮し、保護処分ではなく、刑事処分が相当と判断された場合に決定されます。
検察官は少年を起訴するかどうかを判断し、起訴されると成人と同じ刑事裁判を受けることになります。
結論、少年事件は「私選弁護人」を選ぶのがおすすめ
少年事件では、私選弁護人を選ぶことをおすすめします。
なぜなら、私選弁護人であれば、少年本人やその家族が自由に弁護士を選ぶことができるためです。
特に、少年事件に強い弁護士を選ぶことで、適切な対応が可能になります。
また、逮捕直後から、取調べが始まる前に私選弁護人を呼べるため、取調べへの対応について適切なアドバイスを受けられるというメリットもあります。
弁護士費用は高額ではありますが、前科を回避することや、少年の未来を守るためには、できるだけ早く、私選弁護士を呼ぶほうがいいでしょう。
少年事件で依頼できる弁護士の種類
少年事件で依頼できる弁護士は、国が選ぶ国選弁護人や国選付添人と、少年本人やその家族が選ぶ私選弁護人(私選付添人)に分けられます。
ここでは、それぞれの弁護士に依頼できるタイミングについて解説します。
1.国選弁護人
国選弁護人とは、国選弁護制度を利用して選任される弁護士のことです。
国選弁護人として活動することができるのは、捜査段階であり、主に取調べのアドバイスや早期釈放のサポートなどをおこないます。
また、並行して、必要となる環境調整などもおこないます。
国選弁護人が選任されるタイミング
国選弁護人が選任されるタイミングは、勾留決定後になります。
国選弁護人の依頼方法
国選弁護人を依頼したい場合、裁判官に対して「国選弁護人を選任したい」と伝えます。
通常は、裁判官の勾留質問時に「国選弁護人を選任するかどうか」の確認がされますので、そこで国選弁護人を選任したい旨を伝えれば、問題ありません。
その後は、裁判所から法テラスに連絡が入り、国選弁護人が選出されます。
2.国選付添人
付添人のうち、国が選んだ付添人のことを「国選付添人」といいます。
国選付添人は、少年が家庭裁判所に送致されてから少年審判までを担当し、主に少年鑑別所に収容されている少年と面会したり、少年の環境などを調整したりします。
また、捜査段階で国選弁護人を担当した弁護士が、そのまま家庭裁判所で国選付添人に選任されることもあります。
国選付添人が選任されるタイミング
国選付添人が選任されるタイミングは、家庭裁判所に送致された後からとなっています。
なお、国選弁護人に引き続き依頼したい場合は、同じ弁護士を「国選付添人」として選任し直す必要があります。
国選付添人を利用できる条件
国選付添人制度を利用できる少年事件は、以下の3つのケースに限られています。
- 検察官関与決定に伴うもの(少年法第22条の3第1項)
- 被害者等の審判傍聴に伴うもの(少年法第22条の5第2項)
- 家庭裁判所の裁量によるもの(少年法第22条の3第2項)
このうち1と2のケースは、必要的国選付添人と呼ばれていて、必ず国選付添人を選任しなければなりません。
一方、3のケースでは裁量的国選付添人と呼ばれていて、裁判所の裁量によって選任されるかどうかが決まります。
なお、3は「死刑、無期懲役、長期3年を超える懲役・禁錮にあたる事件」が該当します。
3.私選弁護人・私選付添人
私選弁護人とは、少年本人やその保護者が選んだ弁護士のことです。
国選弁護人とは異なり、どのような事件でも自由に選任することができます。
私選弁護人は勾留決定される前から依頼できるため、勾留前からの取調べに関するアドバイスや勾留請求をさせないための働きかけなども任せられます。
また、家庭裁判所送致後には「私選付添人」として、少年審判に向けた働きかけやサポートなどもしてくれます。
私選弁護人・私選付添人に依頼できるタイミング
私選弁護人・私選付添人の場合は、少年が非行を犯してから裁判所に処分が言い渡されるまで間であれば、いつでも依頼することが可能です。
また、国選付添人のような利用条件もないため、どのような少年事件でもサポートしてもらえます。
早めに弁護士に支援してもらうことで、早期釈放なども目指せるでしょう。
少年事件にかかる弁護士費用の目安
では、少年事件について弁護士に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
ここでは、国が選ぶ国選弁護士・国選付添人と、少年本人やその家族が選ぶ私選弁護士のそれぞれの弁護士費用について解説します。
国選弁護人・国選付添人にかかる費用
国選弁護人や国選付添人は、私選弁護士の弁護士費用を支払うことが難しい方のために、国が選任する弁護士です。
そのため、原則として弁護士費用はかからず、無料で利用できます。
私選弁護人にかかる費用
私選弁護人にかかる費用の目安は、おおむね60万円〜150万円程度です。
少年事件を私選弁護人に依頼する場合、相談料、着手金、報酬金(成功報酬)などの費用が必要となります。
また、それ以外に日当や実費が発生することもあるため、料金体系については事前に確認することが大切です。
少年事件の場合、原則として全件、家庭裁判所に送致されます。
そのため、弁護士による長期的な支援が必要となる分、成人の刑事事件よりも弁護士費用は高くなる傾向にあります。
少年事件の弁護士費用を節約する方法
少年事件では弁護士に依頼するのが重要ですが、経済的な事情などから弁護士に依頼することが難しいケースもあるでしょう。
そのような場合は、弁護士費用の負担が軽減される「少年保護事件付添援助制度」や、無料相談窓口を活用することをおすすめします。
少年保護事件付添援助制度を活用する
「少年保護事件付添援助制度」とは、日本弁護士連合会(日弁連)が運営している、少年が付添人の費用の援助を受けられる制度です。
これは、日弁連の特別会費として徴収された「少年・刑事財政基金」を財源とする援助事業です。
本制度を利用することで、経済的な事情で弁護士に依頼できない少年でも、弁護士による支援を受けることができます。
なお、弁護士白書の統計情報によると、2020年の本制度の利用件数は1,292件となっています。
「少年保護事件付添援助制度」を利用したい場合には、都道府県の弁護士会もしくは法テラスに連絡します。
あるいは、担当している国選弁護人に相談することも可能です。
また、少年の保護者が反対している場合でも、少年自身が希望する場合には利用できます。
無料相談できる弁護士を選ぶ
弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、中には無料相談を受け付けている事務所もあります。
そのため、大手や中小にかかわらず、無料相談ができる事務所を選ぶことで、弁護士費用を抑えられます。
「ベンナビ刑事事件」では、少年事件に強い弁護士の中から無料相談を受け付けている法律事務所を絞り込んで、比較することができます。
弁護士に依頼したいものの、費用面で不安がある方は、こうした無料相談を活用するのがおすすめでしょう。
少年事件の弁護士についてよくある質問
最後に、少年事件の弁護士についてよくある質問について見ていきましょう。
未成年者でも弁護士に依頼できますか?
はい、可能です。
ただし、弁護士に依頼するには通常、保護者の同意が必要です。
一方で、弁護士への相談については、未成年者のみでも可能です。
保護者に知られずに相談することはできますが、正式に依頼するとなると制約が生じることに注意しましょう。
少年事件の弁護士費用の相場はどれくらいですか?
少年事件の弁護士費用の相場は、おおよそ60万円〜150万円程度です。
ただし、具体的な弁護士費用は、法律事務所によってまちまちです。
費用を抑えたい場合は、大手や中小を問わず、弁護士費用の安さで法律事務所を選ぶのもひとつの方法です。
いずれにしろ、少年事件の弁護士費用は、成人の刑事事件よりも高くなる傾向にあります。
少年事件で弁護人は選任されますか?
少年事件では、原則として「弁護人」は選任されません。
その代わりに「付添人」が選任される制度になっています。
そのため、弁護士が少年事件に関与する場合、「弁護人」ではなく「付添人」として活動し、少年の権利を擁護、および更生を支援する役割を担います。
最後に|少年事件はスピードが命!早期に弁護士に相談しよう
弁護士に相談すると、えん罪から守ってくれたり、取り調べで不利にならないようアドバイスを受けられたりします。
また、早期釈放を目指したり、少年院送致などを回避したりするために働きかけもおこなってくれます。
そのような弁護士には、国の制度などを利用して依頼する国選弁護人(国選付添人)と、少年やその家族が任意で依頼する私選弁護人(私選付添人)がいます。
それぞれにメリットがあるため、現在のご状況に合わせて利用しましょう。
また、弁護士に相談したからといって、必ずしも依頼をしなければならないというわけではありません。
お子さんが少年事件を起こしてしまったり、疑いをかけられてしまったら、まずは早期に弁護士にご相談ください。

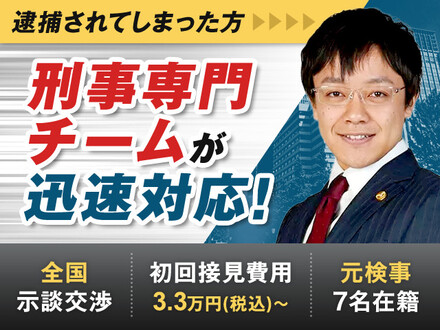
【立川駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る
【初回相談無料】家族が逮捕された方・警察から連絡が来た等はすぐにご連絡を!◆「早期釈放してほしい」「周囲にバレずに解決したい」などあなたのニーズに合わせてスピード対応!【土日祝も対応可能◎】
事務所詳細を見る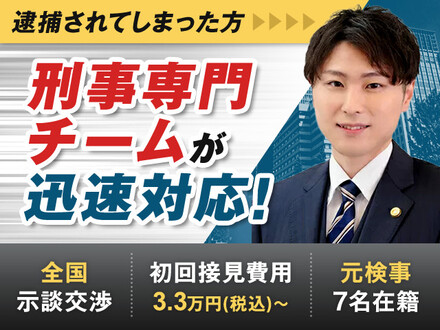
【銀座駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡


ご家族が少年事件を起こしお困りの方は弁護士へご相談ください
ご説明の通り、少年事件の対応によっては
少年本人の今後の人生にも大きく影響してきます。
少年自身のためにも、ご家族が早期対応、早期解決をサポートしてあげてください。
専門的な知識も必要になるため、お困りの方は早急に弁護士へご相談ください。

逮捕された場合の対処法に関する新着コラム
-
逮捕され混乱する状況で頼りになる弁護士の種類と呼び方、費用、依頼するメリットを解説。早期釈放、不利な状況の回避、職場への影響軽減のため、弁護士への早...
-
本記事では、逮捕されると何が起こるのか、どんな流れで逮捕から裁判までがおこなわれるのか、どの段階で釈放される可能性があるのかなど、刑事事件の逮捕後の...
-
身近な人に鑑定留置処分が下されてしまった場合、「留置所でどんな生活を送ることになるの?」など、不安に感じることも多いでしょう。 そこで本記事では、...
-
本記事では、勾留延長の連絡に関する実務の状況、勾留延長されたかどうかを確認する方法を解説します。 また、勾留延長の阻止に向けて弁護士がやってくれる...
-
無免許運転で逮捕された高校生は、長期間の身体拘束や退学処分を受ける可能性があります。早期の身柄解放や退学処分の回避、家庭裁判所・学校と連携を図るため...
-
無免許運転は常習犯の場合、初犯よりも重い処分が下される可能性が高いです。本記事では、無免許運転の常習犯として逮捕された場合に考えられる刑罰の内容や、...
-
これから拘置所での生活が控えている方々にとって、不安や疑問は尽きないでしょう。本記事では拘置所でのスマートフォンや携帯電話の取り扱いについて詳しく解...
-
本記事では、誤認逮捕の被害者が利用できる補償・賠償制度について解説します。 誤認逮捕されてしまった方や、罪を犯していないのに警察から疑われている方...
-
痴漢・万引き・盗撮・横領など、やってもいないのに犯人だと疑われてしまうケースは少なからず存在します。 どうすれば疑いを晴らせるのか悩んでいる方もい...
-
刑事事件を起こして刑事告訴されると、警察が捜査開始して逮捕や裁判となるおそれがあります。逮捕回避や減刑獲得に向けて迅速に動くためにも、手続きの流れを...
逮捕された場合の対処法に関する人気コラム
-
保釈は、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄を解放させる制度です。ここでは釈放との違いや保釈金の相場...
-
家族が逮捕されたら、学校や会社への対応や、被害者との示談交渉など、やるべきことがいくつか出てきます。留置場に拘束された本人をサポートするために、ご家...
-
未成年が逮捕された場合と成人が逮捕された場合とでは、その後の手続きが異なる部分があります。この記事では、未成年が逮捕された後の手続きの流れと対処法に...
-
再逮捕(さいたいほ)とは、既に逮捕され勾留状態にある人物を釈放直後、又は勾留中に再び逮捕をすることです。
-
黙秘権とは、刑事事件の捜査で行なわれる取り調べの際に自分にとって不利益な供述にならないために、終始沈黙し、陳述を拒むことができる権利です。黙秘権は刑...
-
逮捕とは、捜査機関や私人(一般人)が被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために一時的に身柄を強制的に拘束することを言います。逮捕された後の流れはどうなってい...
-
「拘置所に入れられた身内と面会したい。」身内が逮捕され、拘置所に入れられてしまうと誰しもが思うことです。例え刑事事件を起こして逮捕されてしまった人で...
-
供述調書は、警察官や検察官が被疑者・参考人の供述を記した公式文書です。本記事では、供述調書の役割や作成までの流れ、署名・押印する際の注意点などを解説...
-
取り調べとは、被疑者や参考人に出頭を求めて、事件に関する内容の事情を聴取することです。取り調べに強制力はありませんが、逮捕・勾留されている被疑者は退...
-
誤認逮捕とは、警察などの捜査機関が無実の人物を逮捕してしまうことです。
逮捕された場合の対処法の関連コラム
-
黙秘権とは、刑事事件の捜査で行なわれる取り調べの際に自分にとって不利益な供述にならないために、終始沈黙し、陳述を拒むことができる権利です。黙秘権は刑...
-
「拘置所に入れられた身内と面会したい。」身内が逮捕され、拘置所に入れられてしまうと誰しもが思うことです。例え刑事事件を起こして逮捕されてしまった人で...
-
罪を犯してしまった人は、逮捕や刑事罰などによって罰則を受けなくてはなりません。ただ、『犯罪を起こした=逮捕』ではないことは知っておいてください。軽微...
-
少年事件で逮捕・勾留されてしまうと、成人とは異なる手続きを経て処分されます。少年は成人の刑事事件よりも弁護士の支援が必要です。本記事では、少年事件で...
-
身近な人に鑑定留置処分が下されてしまった場合、「留置所でどんな生活を送ることになるの?」など、不安に感じることも多いでしょう。 そこで本記事では、...
-
娘が逮捕されてしまった場合はすぐに弁護士に相談しましょう。この記事では、あなたがすべき5つのことから、弁護士の呼び方、弁護士費用の相場、逮捕後の流れ...
-
誤認逮捕とは、警察などの捜査機関が無実の人物を逮捕してしまうことです。
-
刑事事件を起こして刑事告訴されると、警察が捜査開始して逮捕や裁判となるおそれがあります。逮捕回避や減刑獲得に向けて迅速に動くためにも、手続きの流れを...
-
保釈は、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄を解放させる制度です。ここでは釈放との違いや保釈金の相場...
-
本記事では、逮捕されると何が起こるのか、どんな流れで逮捕から裁判までがおこなわれるのか、どの段階で釈放される可能性があるのかなど、刑事事件の逮捕後の...
-
逮捕された家族と面会したいと考えていたところ、接見という言葉を知り、気になっている方もいるでしょう。この記事では、接見の意味や方法、弁護士への接見の...
-
医師が逮捕された場合、実名報道や医師免許の取消などの不利益に直面します。この記事では、医師が逮捕された場合の対処法から、逮捕された場合のその後、どう...
逮捕された場合の対処法コラム一覧へ戻る